業務負担軽減のためにやるべきこととは?人手不足でも取り組める軽減方法
最終更新日:2025年8月29日
多くの企業が直面している人手不足の問題。限られた人員で従来以上の業務をこなさなければならず、従業員の負担は日々増加するばかりです。「人を雇いたくても良い人材が見つからない」「既存の従業員が疲弊している」といった悩みを抱える経営者や管理職の方も多いのではないでしょうか。
しかし、新しい人材の確保を待つだけでは、問題の根本的な解決にはなりません。重要なのは、現在の体制でも実践できる業務負担軽減の方法を見つけ、組織全体の効率性を高めることです。
本記事では、人手不足の状況下でも取り組める具体的な業務負担軽減の方法から、その実践によって得られるメリット、さらには人手不足が起こる背景まで体系的に解説していきます。これらの知識を活用することで、従業員の働きやすさを高めながら、企業の生産性向上も同時に実現できるでしょう。
【この記事を読んでわかること】
- 人手不足でも実践できる5つの業務負担軽減方法
- 業務負担軽減がもたらす4つの重要なメリット
- 業務負担が増加する3つの根本原因と対策
- 人手不足の構造的背景と今後の対応戦略
目次
人手不足でも取り組める業務負担軽減方法
人手不足が深刻化する中、限られた人員で業務を回さなければならない状況に頭を悩ませている経営者や管理職の方は多いのではないでしょうか。帝国データバンクの調査(2025年1月※)では、企業の半数以上(53.4%)が正社員の不足を感じていると回答しました。特にIT業界では7割を超えるなど、この問題は多くの業界で待ったなしの課題となっています。
※:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2025年1月)」(2025年2月21日)
このような状況下では、新たな人材確保を待つのではなく、現在の体制でも実践できる業務負担軽減策を講じることが重要です。業務負担の軽減は、従業員の心身の健康を守るだけでなく、生産性向上や離職率低下にもつながる重要な経営課題といえるでしょう。
ここからは、予算や人員に制約がある中でも取り組める以下の5つの業務負担軽減方法について、具体的な実践手順とともに詳しく解説していきます。
- 業務の自動化やAI導入で業務負担を軽くする
- 雇用のミスマッチをなくす
- 属人化をなくす
- 業務の無駄を省き効率的に人員を運用する
- 従業員のスキルアップ施策を実施する
それぞれの方法は単独でも効果的ですが、組み合わせることでより大きな成果を期待できます。まずは自社の状況に最も適した方法から始めて、段階的に取り組みを拡大していく方法をおすすめします。それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。
業務の自動化やAI導入で業務負担を軽くする
近年、RPA(Robotic Process Automation)やAI技術の普及により、これまで人手に頼っていた多くの業務を自動化できるようになりました。特にデータ入力や帳票作成、定型的なメール送信といった反復作業は、自動化による業務負担軽減の効果が最も現れやすい領域です。
例えば、従来は月末に丸一日かけていた売上データの集計作業が、RPAツールを導入することで30分程度に短縮されるケースも珍しくありません。また、AIを活用したチャットボットを導入すれば、顧客からの基本的な問い合わせ対応を24時間自動化でき、担当者の負担を大幅に軽減可能です。
重要なのは、いきなり大規模な自動化を目指すのではなく、最もルーチン化された業務から段階的に取り組むことです。まずは1つの業務を選んで小さく始め、効果を実感してから適用範囲を広げていくアプローチが成功のカギとなります。
現在では中小企業でも導入しやすい低コストなツールが数多く提供されており、月額数万円程度から始められるソリューションも豊富にあります。自動化により人員を削減するのではなく、より付加価値の高い業務に人的リソースを集中させれば、全体的な業務負担軽減と生産性向上の両立が可能になります。
まずは、あなたのチームで最も時間がかかっている定型作業は何か、リストアップしてみることから始めてはいかがでしょうか? その中から、小さな自動化の第一歩が見つかるかもしれません。
雇用のミスマッチをなくす
雇用のミスマッチは、企業と求職者の間で期待と現実にギャップが生じる状況を指します。このミスマッチが発生すると、せっかく採用した人材が業務に適応できず、早期離職や周囲への業務負担増加につながってしまいます。
ミスマッチの主な原因は、採用段階での相互理解不足にあります。企業側は求める人材像や業務内容を明確に伝えきれておらず、求職者側も企業の実態を十分に把握できていないケースが多く見られます。
この問題を解決するためには、適性検査やアセスメントツール(客観的な評価ツール)の導入が効果的です。これらのツールを活用することで候補者の特性を把握し、自社の風土やチームとの相性を判断できるため、採用の精度の向上が見込めます。また、職務記述書を作成して業務内容や求められるスキルを明確化することも重要です。
適切な人材を採用できれば、業務効率の向上はもちろん、教育期間の短縮や他の従業員への負担軽減にもつながります。人手不足だからといって妥協するのではなく、長期的な視点で自社にマッチした人材確保を目指すことが、持続的な業務負担軽減の実現につながるでしょう。
まずは、直近の採用活動を振り返り、『期待と現実のギャップはどこにあったか?』をチームで話し合ってみましょう。そこから、採用プロセスの具体的な改善点が見えてくるはずです。
属人化をなくす
「あの人がいないと仕事が回らない」という状況は、多くの職場で起こりがちな「属人化」の典型です。特定の従業員にしかできない業務があると、その人に負担が集中し、急な休みや退職の際に業務が滞る原因となります。
属人化を解消するには、業務の標準化と多能工化が有効です。作業手順をマニュアルにまとめて共有すれば、誰でも一定の品質で業務をこなせるようになり、特定の人への依存を減らせます。また、従業員が複数の業務をこなせるようになると、業務量の偏りを是正して負担を軽減したり、繁忙期にチームで柔軟に対応できたりと、多くのメリットが生まれます。
管理者は、日頃から従業員の業務量を把握し、負担が偏らないよう配慮することが大切です。例えば、定期的にメンバーのタスク状況や負荷を確認する時間を設けることで、業務が滞る前に問題を発見し、対策を打つことができます。
属人化の解消は、単にマニュアルを作成するだけでなく、組織全体の知識(ナレッジ)を体系的に管理し、活用するナレッジマネジメントの考え方が不可欠です。従業員が持つ暗黙知を形式知に変え、誰もがアクセスできる状態にすることで、組織全体の業務遂行能力が向上します。
あなたのチームで、『あの人がいないと進まない業務』はありませんか? まずは1つ、その業務の手順を誰でもわかるように書き出してみることから、属人化解消の第一歩を踏み出しましょう。
業務の無駄を省き効率的に人員を運用する
限られた人員で最大の成果を上げるためには、まずは、現在行っている全ての業務を洗い出し、それらが本当に価値を生んでいるのかを一つひとつ吟味する作業が不可欠です。多くの職場では「これまでのやり方だから」という理由で、実際には必要性の低い業務が継続されているケースが少なくありません。
業務を洗い出す際の視点として、ECRS(イクルス)の原則が役立ちます。これは、以下の4つの観点から業務を見直すことで、効果的に無駄を発見するフレームワークです。
- Eliminate(排除できないか?)
- Combine(他の業務と結合・集約できないか?)
- Rearrange(手順・順序・場所を変更できないか?)
- Simplify(もっと単純化・簡素化できないか?)
これらの頭文字を取ってECRS(イクルス)と呼ばれています。
業務改善は、担当者1人に任せるのではなく、チームで取り組むことが成功のカギです。客観的な視点が加われば、個人では気づけなかった課題や改善の糸口が見つかります。その際は、「そもそも、この仕事なくせないか?」「もっと楽な方法はないか?」といったゼロベースの視点で議論すると良いでしょう。例えば、必要性の低い会議の削減、重複する報告書の統合、承認フローの簡素化などにより、大幅な時間短縮が期待できます。
また、外注や業務委託の活用も効果的な選択肢です。かつてノンコア業務の代行が中心だった業務委託は、現在、マーケティングのような専門領域にまで及び、その選択肢は多様化しています。特にBPO(Business Process Outsourcing)は、業務プロセスごと専門企業に委ねることで、社内の貴重な人材を利益に直結するコア業務へとシフトさせる有効な経営戦略です。
自社で多くの工数を要する業務は、外部の知見やノウハウを借りることで、費用対効果を高め、事業のスピードアップにもつながるでしょう。
今週、あなたのチームで行われる定例会議を1つ選び、『この会議は本当に必要か?目的は何か?』と自問してみてください。そこから、業務の無駄を見直す良いきっかけが得られるかもしれません。
従業員のスキルアップ施策を実施する
従業員のスキルアップは、業務負担軽減と企業全体のレベルアップを同時に実現する重要な施策です。スキルが向上することで作業処理速度が上がり、同じ業務量でも短時間で完了できるようになります。
具体的なスキルアップ方法として、社内研修、OJT(On-the-Job Training)、外部講師によるセミナーなどが挙げられます。特に、Excelの高度な操作、プログラミングスキル、生成AIツールの習得は、データ処理や定型業務の効率化に直結し、大幅な時間短縮効果が期待できます。
公的機関でもリスキリングやスキルアップの機会を提供しています。こういった施策も検討してみると良いでしょう。
また、スキルアップ施策は従業員のモチベーション向上にも効果的です。新しい知識や技術を身につけることで仕事に対するやりがいが高まり、結果として生産性の向上につながります。企業側にとっても、従業員の能力向上は組織全体の競争力強化となり、長期的な成長基盤の構築に寄与します。
重要なのは、従業員一人ひとりの現在のスキルレベルを把握し、個別の成長計画を立てることです。組織全体でスキルアップに取り組めば、より効果的な業務負担軽減が実現できるでしょう。
まずは、チームメンバー一人ひとりに『今後どんなスキルを身につけたいか、それによって今の業務負担をどう軽減できそうか』をヒアリングしてみることから、具体的なスキルアップ計画の糸口を見つけてみてはいかがでしょうか。
業務負担軽減によるメリット

業務負担軽減に取り組むことで得られる効果は、単に従業員の疲労を減らすだけにとどまりません。組織全体に次のような多面的なメリットをもたらし、企業の持続的な成長につながる重要な経営施策といえるでしょう。
- 社員のモチベーション向上
- 離職率の低下
- ワークライフバランスの改善
- 新規事業や事業拡大のきっかけに
業務負担が軽減されることで、まず従業員の心身の健康が改善され、働きやすい環境が整います。これにより従業員満足度が向上し、モチベーションの高い状態で業務に取り組めるようになります。その結果、生産性の向上や品質の改善が期待でき、企業全体のパフォーマンス向上につながります。
さらに、働きやすい環境は離職率の低下をもたらし、採用・教育にかかるコストの削減効果も生まれます。また、ワークライフバランスに配慮した企業として外部からの評価も高まり、優秀な人材の確保がしやすくなるという好循環が生まれます。
これらのメリットは相互に影響し合いながら、企業の競争力強化と持続的成長の基盤となります。以下、主要なメリットについて詳しく見ていきましょう。
社員のモチベーション向上
業務負担が軽減されれば、従業員のメンタル面での負担やプレッシャーも大幅に軽くなります。過度な業務量によるストレスから解放されることで、従業員は本来の能力を十分に発揮できる状態になり、仕事に対する前向きな姿勢を取り戻せます。
適切な業務量になることで、一つひとつの仕事に集中して取り組めるようになり、成功体験を積み重ねる機会が増えます。結果として自信とやりがいが生まれ、さらなる成果向上への意欲が高まります。まず、時間内に仕事を終える文化が定着すれば、社員は心身の健康を保ち、翌日のパフォーマンス向上につながります。
次に、こうした「働きがい」のある環境は社員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を育み、組織全体の活力を増大させます。最終的に、社員を大切にする企業姿勢は採用市場における強力なブランドとなり、自社の理念に共感する才能豊かな人材を引き寄せる、という持続的な成長サイクルが生まれるのです。
モチベーションの高い従業員は、創造性や提案力も向上するため、企業の革新や成長にも大きく貢献することが期待できるでしょう。
離職率の低下
社員間で業務量に大きな偏りが生じている状況では、長時間労働や休日出勤が常態化し、従業員のワークライフバランスが大きく崩れてしまいます。このような労働環境への不満が蓄積されると、優秀な人材ほど他社への転職を検討するようになり、結果として離職率の高い組織になってしまいます。
チーム全体でタスクを分担する体制を築き、特定の個人に負荷が集中する状況を解消することで、組織的な長時間労働の是正が図れます。社員一人ひとりが健全な労働環境で能力を発揮できるようになれば、組織へのエンゲージメントが高まり、貴重な人材の定着、すなわちリテンション(従業員定着率)の向上に直結します。
離職率の低下は、企業にとって大きな経済的メリットをもたらします。中途採用には一人当たり数十万円から数百万円のコストがかかるため、人材定着によるコスト削減効果は非常に大きいものです。また、経験豊富な従業員が組織に残ることで、培われたノウハウや顧客との関係が継続され、安定した事業運営が可能になります。
人材が定着する組織では、チームワークが向上し、さらなる生産性向上と業務負担軽減の好循環が生まれるでしょう。
ワークライフバランスの改善
業務負担が軽減されれば、従業員の労働時間が適正化され、残業時間や休日出勤を大幅に減らすことが可能になります。従業員はプライベートの時間を十分に確保でき、家族との団らんや趣味の充実、自己啓発への取り組みなど、仕事以外の活動に時間を割けるようになるのです。
適切な休息と私生活の充実は、翌日の仕事に対する集中力と創造性を高める効果をもたらします。心身ともにリフレッシュした状態で業務に取り組むことで、より高いパフォーマンスを発揮できるようになり、結果として生産性の向上につながる好循環が生まれます。
働く価値観が多様化する現代において、リモートワークやフレックスなど、企業には「時間や場所に縛られない柔軟な勤務形態」の導入が求められています。働きがいのある環境を整備することは、採用市場における競争優位性を確立し、優れた才能を引き寄せるための重要な経営投資です。
個々のパフォーマンスを最大化し、多様な働き方を許容する組織文化を醸成することこそ、変化の激しい時代を勝ち抜くレジリエントな(しなやかで強い)組織づくりに他なりません。
新規事業や事業拡大のきっかけに
業務負担が軽減され組織に余裕が生まれると、これまで日常業務に追われて手が回らなかった新しい取り組みにチャレンジできるようになります。効率化によって創出された人的リソースを新規事業の立ち上げや既存事業の拡大に振り向けることで、企業の成長機会を大幅に広げられます。
特に、専門性の高い業務が属人化していた状況を改善し、マニュアル化や標準化を進めることで、経験豊富な従業員が新しい業務領域にも挑戦しやすい環境が整います。この環境は、従業員全体のスキル向上が促進されるとともに、仕事に対するモチベーションアップにもつながります。
また、業務負担軽減により時間的・精神的余裕が生まれることで、従業員の創造性や企画力が向上し、新しいアイデアやビジネスチャンスの発見にもつながります。市場環境の変化に対して迅速かつ柔軟に対応可能な組織体制が構築され、競合他社に対する優位性も確保できるでしょう。
このように、業務負担軽減は単なるコスト削減ではなく、企業の成長戦略を支える重要な基盤となるのです。
業務負担が増えてしまう原因とは
業務負担軽減を効果的に進めるためには、まず負担が増加している根本的な原因を正確に把握することが重要です。多くの組織では複数の要因が絡み合って業務負担の増大を招いており、表面的な対策だけでは根本的な解決に至らないケースが少なくありません。
業務負担増加の主な原因は、大きく分けて次の3つに分類できます。
- 人手が不足している
- 業務量に偏りがある
- 作業効率が悪い
これらの要因は相互に影響し合うことが多く、例えば人手不足により一部の従業員に業務が集中し、さらに効率的な作業方法を検討する余裕もなくなるという悪循環が生じるケースがあります。
現代では少子高齢化による労働力不足が深刻化する一方で、顧客ニーズの多様化や業務の高度化により、従来以上に多くの時間と労力が必要な業務が増加しています。これらの社会的背景も業務負担増加の一因となっています。
次からは、これらの原因について具体的に解説し、それぞれに対する効果的な対策のヒントを提供します。
人手が不足している
業務の総量と、それを担う人員との間にアンバランスが生じているのが「人手不足」の本質です。結果として、現場のチームは常にキャパシティ以上のタスクを処理せざるを得ず、個々の負荷は過重なものとなります。
この状況では、一人ひとりが担当する業務の範囲と量が適正水準を大幅に超えてしまい、長時間労働や休日出勤が常態化してしまいます。さらに深刻なのは、過度な負担により疲労が蓄積し、作業効率が低下することで、同じ業務により多くの時間が必要になるという悪循環が生じるケースです。
人手不足による業務負担増加は、単に忙しくなるというだけではなく、従業員の心身の健康に深刻な影響を与える可能性があります。適切な休息を取れない状態が続くと、判断力の低下やミスの増加を招き、結果として業務品質の悪化や顧客満足度の低下につながるリスクもあります。
適切な人材の確保はもちろん重要ですが、既存の人員でも効率的に業務を進められるよう、チーム全体で業務量を見直し、負担の分散を図ることが急務といえるでしょう。
業務量に偏りがある
組織内で業務量に大きな偏りが生じている状況も、業務負担増加の主要な原因の1つです。マネジメントが機能せず、チーム内のタスク管理が適切に行われないと、特定のメンバーにばかり負荷がかかり、チーム内に深刻な不公平感が生まれる原因となります。
この偏りが生じる背景には、「有能な人に任せておけば安心」という管理者の安易な判断や、特定の業務を行える人材が限られているという組織的な問題があります。また、各従業員が現在どのような業務をどの程度抱えているかを管理者が正確に把握できていないことも、偏りを生む大きな要因となっています。
一部のメンバーに過度な負担を強いる状況は、個人の疲弊を招くだけでなく、チーム全体の協力体制を蝕み、結果としてパフォーマンスの低下を引き起こします。負担の重い従業員は疲労やストレスにより効率が低下し、一方で業務量の少ない従業員は達成感や成長機会を得られず、組織全体のモチベーション低下を招きます。
この状況を打開するには、マネージャーがチームのタスク状況を常に「見える化」し、定期的な対話を通じて負荷を調整していくことが求められます。
個々の従業員が効率的に業務を進めるためには、タスクの優先順位付けも重要です。例えば、アイゼンハワー・マトリクス(緊急度と重要度でタスクを4象限に分類し、取り組むべき順序を判断する手法)などを活用し、本当に重要な業務に集中できる環境を作りましょう。
作業効率が悪い
非効率な働き方は、単に個人の生産性が低いという問題ではありません。同じ成果を出すのに倍の時間を費やすなど、組織全体のリソースを浪費してしまいます。その根底には、「形骸化した定例会議」、「部門間の連携不足による手戻り」、「何重にも及ぶ承認プロセス」といった、組織的な「ムダ」が潜んでいることが少なくありません。
多くの組織で見られるのは、「昔からそうしているから」という理由で続けられている非効率な業務プロセスです。例えば、本来であればデジタル化できる単純作業を人力で行い続けていたり、必要以上に複雑な報告書を作成していたりするケースがあります。また、上司の確認待ちで次の作業に進めない状況や、目的が不明確な会議に多くの時間を費やしているケースも散見されます。
このような非効率性を放置すると、本来30分で終わる作業に2時間かかったり、1日で完了可能な業務が数日にわたったりと、大幅な時間ロスが発生します。組織的な生産性を向上させるには、まず業務プロセス全体を俯瞰し、非効率な部分を徹底的に洗い出す必要があります。その上で、テクノロジーを活用して定型業務を自動化し、社員はより付加価値の高い仕事に集中できる環境を整えることが肝要です。
例えば、形骸化した会議を減らすためには、①会議の目的とゴールを明確にする、②事前にアジェンダを共有する、③参加者を必要最小限に絞る、④時間を厳守する、といった基本的なルールを徹底することが効果的です。
働き方改革は業務負担軽減につながる

働き方改革が目指すのは、「短い時間で、より賢く働き、大きな成果を出す」ということです。それによって社員一人ひとりが心身ともに健康で、いきいきと活躍できる職場を実現しようとする取り組みと言えるでしょう。単に労働時間を短縮するだけでなく、従業員の意欲を高めて生産性向上につなげるのが本来の狙いです。
働き方改革関連法により、残業時間の上限規制や有給休暇取得の義務化、労働時間把握の義務化などが実施されています。これらの施策により、従業員は適切な休息を取りながら集中して業務に取り組めるようになり、結果として業務効率が向上します。これからのマネジメント層には、組織の生産性をデザインする役割が課せられます。業務の標準化や、柔軟な勤務体系の整備などが急務となっています。
こうした仕組み作りにより、従業員はより付加価値の高い仕事にリソースを注力でき、時間的・精神的なゆとりが生まれます。これはダイバーシティ&インクルージョンの基盤となり、エンゲージメント向上や人材定着は、企業の競争力に結びつくのです。
働き方改革は業務負担軽減と企業成長を両立させる重要な経営戦略といえるでしょう。
人手不足が起こっている背景
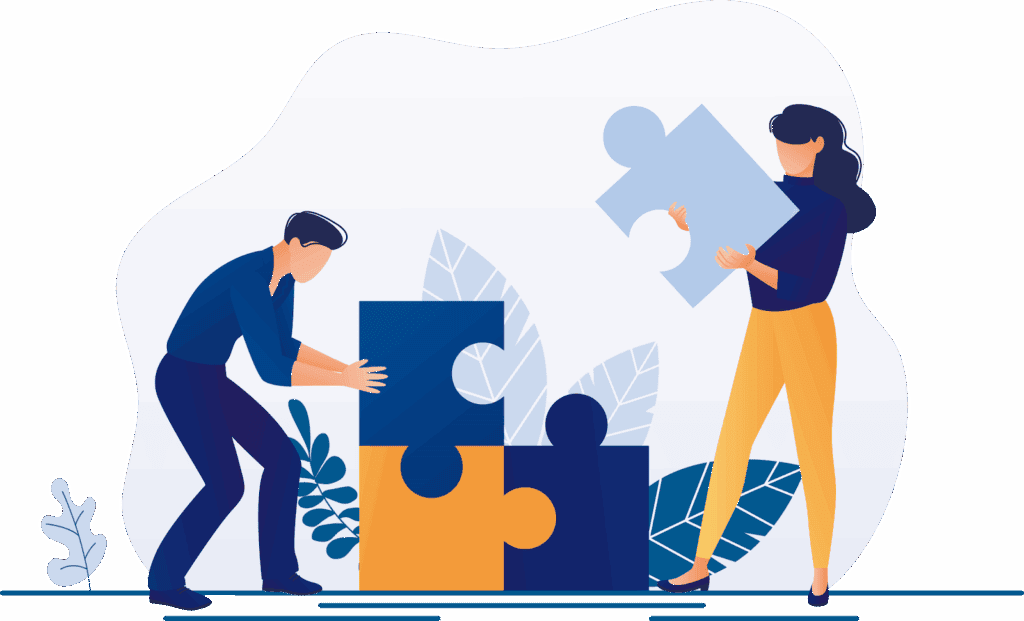
現在多くの企業が直面している人手不足は、一時的な労働市場の変動ではなく、日本社会全体の構造的な変化に起因する深刻な問題です。この問題を効果的に解決するためには、表面的な対症療法だけでなく、根本的な背景を正しく理解した上で、長期的な視点に立った対策を講じることが重要になります。
人手不足の背景には、主に次のような要因が複雑に絡み合っています。
- 出生率低下によって労働者が減少している
- 人材の確保と維持が難しくなってきた
これらの要因は相互に影響し合いながら、従来の人材確保・定着の手法では対応困難な状況を作り出しています。
特に重要なのは、これらの背景要因の多くが一朝一夕には解決できない構造的な問題であるということです。そのため、企業は従来の採用手法や労働環境に固執するのではなく、新しい時代に適応した柔軟な対応策を検討する必要があります。
以下では、人手不足の主要な背景要因について詳しく解説し、それぞれの対応策について考察していきます。
出生率低下によって労働者が減少している
日本の深刻な人手不足は、長期的な出生率の低迷にその端を発しています。少子高齢化が長期間にわたって進行した結果、子どもの数が少ないということは、そのまま将来の労働人口減少を意味します。
総務省統計局『人口推計(2024年(令和6年)4月1日現在確定値/PDF)によると、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年の8,726万人(総人口比69.5%)を頂点に減少をたどり、2023年11月時点では約7,397万人(総人口の約61.07%)に減少しています。2012年頃からの団塊世代の大量退職が引き金となり、この傾向は加速しました。社会の中核を担う若年層の先細りが、経済成長の足かせとなっているのです。
1995年

2025年

また、国立社会保障・人口問題研究所の最新の将来推計(2023年公表※)はさらに厳しい未来を描いており、生産年齢人口は2070年には4,535万人まで落ち込むと予測されています。これは2020年時点から約4割も縮小することを意味し、労働力の供給制約は避けられない見通しです。こうした人口動態の変化は、日本が世界でも類を見ないスピードで少子高齢社会へと突き進んでいる現実を浮き彫りにしています。
この構造的な労働力減少は、一時的な景気変動とは異なり、短期間での回復が困難な問題です。企業にとっては、従来の人材確保手法だけでは対応できない新たな経営課題として、長期的な視点での対策が求められています。
人材の確保と維持が難しくなってきた
労働力不足が社会問題となる一方、採用市場では求職者の応募先に著しい偏在が見られます。一握りの人気企業には、採用倍率が数千倍に達することも珍しくないほどの競争が生まれる半面、その他大多数の中小企業は採用候補者を集めること自体に苦心しているのが現状です。
この背景には、企業側の情報発信不足があります。多くの中小企業では、自社の魅力や実際の業務内容、職場環境について求職者に十分な情報を提供できておらず、結果として大企業志向の求職者を呼び込めない状況が生まれています。
終身雇用を前提としない価値観が広がり、若年層にとってキャリアアップのための転職はもはや当たり前の選択肢です。彼らは常に自身の市場価値を意識し、今の職場が自己実現やスキル向上の場としてふさわしいかを冷静に見定めています。これは企業にとって、採用後も従業員のエンゲージメントを高め続けなければ、人材は容易に流出するという厳しい現実を意味します。
企業は求職者と従業員の双方のニーズを理解し、継続的に労働環境の改善に取り組む必要があるでしょう。
人手不足は今後も続くと考えられる
人手不足という複合的な問題の要因は、労働供給力の構造的な縮小と、採用市場における人材獲得競争の偏在という2点に集約されます。これらは一朝一夕には解消し得ない構造的な課題であり、日本の労働力不足は今後、慢性化すると見られています。
事実、帝国データバンクの調査(2025年1月※)でも、企業の半数以上(53.4%)が正社員の人手不足を訴えており、事態の好転は見込めません。とりわけ、社会インフラを支えるIT、建設、介護などの分野では需要と供給のミスマッチが深刻です。高齢化で需要が増す一方、担い手の確保は一層困難を極めるでしょう。
※:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2025年1月)」(2025年2月21日)
このような状況下では、新たな人材確保を待つのではなく、現在の人員体制でも効率的に業務を進められる仕組みづくりが急務となります。業務負担軽減に向けた対策を早急に実施すれば、限られた人材を最大限に活用し、競合他社との差別化を図ることが可能になります。
自社の現状を改めて見つめ直し、どのような対策が最も効果的かを検討して、即座に改善に取り組むことが、今後の企業存続と成長のカギを握っているといえるでしょう。
業務の効率化と業務負担軽減にはDocBaseがおすすめ
人手不足による業務負担増加は、多くの企業が直面する深刻な課題ですが、適切な対策を講じることで確実に改善可能な問題でもあります。業務の自動化やAI導入、雇用のミスマッチ解消、属人化の排除、無駄な業務の削減、従業員のスキルアップなど、今すぐ実践できる方法は数多く存在し、これらの取り組みにより多面的なメリットを得られます。
中でも、効率的なツールの活用は即効性の高い改善策として注目されています。DocBaseは、直感的な操作で初心者でも安心して使える情報共有プラットフォームです。複雑な設定や専門知識は必要なく、導入したその日から業務効率化を実感できます。
特に属人化の解消において、DocBaseは大きな効果を発揮します。業務ノウハウをマニュアル化して共有することで、特定の人にしかできない作業を標準化し、チーム全体で業務分担する体制を構築可能です。また、検索機能により必要な情報を瞬時に見つけられるため、「あの人に聞かないと分からない」という状況を大幅に減らせます。
人手不足は今後も継続する構造的な問題だからこそ、早期の対策が競争優位の源泉となります。DocBaseなら無料トライアルで実際の操作感や効果を体験できます。従業員が働きやすく、企業が持続的な成長を見込める環境づくりを、今日から始めてみませんか。
業務負担軽減を目的としたDocBaseの活用事例

DocBaseは、さまざまな企業で業務負担の軽減に貢献しています。ここでは実際の事例をご紹介します。
- 情報共有・検索にかかる手間と時間の削減
- 新人教育・オンボーディングの効率化
- 会議・コミュニケーションの効率化と削減
- 業務の属人化解消と品質向上
- 問題解決の迅速化
- ドキュメント作成・更新の効率化と促進
これらの活用事例から、DocBaseが情報共有の障壁を取り除き、組織全体の業務効率を向上させることで、様々な企業で業務負担の軽減につながっていることがわかります。
情報共有・検索にかかる手間と時間の削減
GitHub WikiやGoogle Docsなどの情報共有ツールでは情報が分散していたり、メールやSlack、 Chatwork、Teamsなどのチャットでは情報が流れてしまい、後から見つけにくいという課題がありました。DocBaseの導入により、情報がDocBaseに一本化され、欲しい情報にすぐたどり着けるようになり、情報を探す手間と時間が大幅に減りました。
情報がフラットに並んでおり、フォルダ階層がないため、どこに格納するか悩むことなく気軽にメモを作成・共有できるようになったことも、書くハードルを下げる要因となっています。タグや検索機能で容易に情報を見つけられるようになります。
オイシックス・ラ・大地様では、よく使う情報のリンク集として「ここみて」というメモを作成し、組織図や各種依頼書などをまとめており、「ここに行かないと情報が得られない」という認識が浸透しています。大和財託でも社内ルールなどのリンク集をDocBaseに集約し、チャットで送られていたファイルをDocBaseのリンクから確認できるようにしました。
事例を読む 会議のペーパーレス化が進んで、とても楽になりましたオイシックス・ラ・大地株式会社様
新人教育・オンボーディングの効率化
新人が入社した際に、業務内容や社内ルールを口頭でいちいち説明するコストが大幅に削減されました。DocBaseにマニュアルや過去の情報をまとめておくことで、新人は自ら情報を参照できるようになり、教育にかかる時間が短縮され、無駄も減っています。
例えば、伊藤忠テクノソリューションズ様では、新人の開発環境構築に以前は1〜2日かかっていたところが、DocBaseの手順書を読んでもらうことで2〜3時間で済むようになりました。
大和財託様でも、バラバラだったシステム環境構築マニュアルをDocBaseに統一したことで、今後人が増えても安心できるようになったと述べています。
Housmar様では、DocBaseのAPIを活用して旧サービスからのデータ移行を半日程度で完了させることができ、新人が入った際にDocBaseのメモを提示するだけで大幅な時間節約につながっています。
事例を読む
暗黙知や経験則をドキュメント化する文化が根付き、手戻りや新人教育の時間が激減
いつ自分がいなくなっても大丈夫なチームへ。暗黙知をマニュアル化し業務を効率化 | DocBase ナレッジ共有・情報共有ツール
【事例】気にせず人を増やせるので、「いいじゃん!」となりました | DocBase ナレッジ共有・情報共有ツール
会議・コミュニケーションの効率化と削減
DocBaseに会議の議事録や関連情報を共有することで、定例ミーティングの時間が短縮された事例があります。モバイルファクトリー様では、画像共有を積極的に行うことで会議の数が減ったと報告しています。
サイバード様では、DocBaseで日報を毎日見るようになったことで、週に1回行っていた仕事内容を報告するミーティングがなくなったと報告されています。
オイシックス・ラ・大地様では、会議資料を印刷する手間がなくなり、会議のペーパーレス化が進みました。情報共有ツールに迷ったら共有する文化が根付くことで、立ち話のような気軽な会話でもDocBaseに記録を残すようになり、情報が流れてしまう問題が解決されています。
事例を読む
【事例】困っていることを気軽に吐き出せる場所 | DocBase ナレッジ共有・情報共有ツール
会議のペーパーレス化が進んで、とても楽になりましたオイシックス・ラ・大地株式会社様
業務の属人化解消と品質向上
特定の個人しか知らなかった情報やノウハウがDocBaseに共有されることで、「この人しか知らない」という状態が減り、属人化が解消されました。
GameWith様では、エンジニアが自身の持つ情報をDocBaseに吐き出すことで、エンジニア全員が日々の重要な作業を行えるようになりました。アールキューブでは、会場に関するノウハウがDocBaseに集約されたことで、誰もが同じクオリティのサービスを提供できるようになりました。
大垣ケーブルテレビ様では、経験者のノウハウをDocBaseで共有することで、新人でも不具合に素早く対応できるようになり、顧客サポートにかかる時間が短縮されました。
双日様では、年に1回の業務など、スポットの出来事やイシューもDocBaseに残す習慣ができ、引き継ぎの難しさが改良されたと評価されています。
事例を読む
エンジニア全員が日々の重要な作業を行えるようになりました株式会社GameWith様
属人化していたノウハウを全社で共有し、誰でも顧客サポートができるチームへ大垣ケーブルテレビ様
情報をDocBaseに残していくカルチャーができました双日株式会社様
問題解決の迅速化
サイバード様では、日報で「困ったこと」を共有する欄を設けたところ、それを見た他のメンバーがコメントで助言をするようになり、問題解決が早くなったと報告されています。
大和財託様では、よくある質問とその対処法をQ&A形式でDocBaseにまとめることで、問い合わせ対応の効率が大幅に向上し、DocBaseのURLを送るだけで済むようになりました。
事例を読む
【事例】困っていることを気軽に吐き出せる場所 | DocBase ナレッジ共有・情報共有ツール
いつ自分がいなくなっても大丈夫なチームへ。暗黙知をマニュアル化し業務を効率化 | DocBase ナレッジ共有・情報共有ツール
ドキュメント作成・更新の効率化と促進
DocBaseはMarkdown記法に対応しており、エンジニア以外のメンバーでもMarkdownの便利さに気づき、簡単に書けて見出しも付けやすいと評価されています。Markdownのヘルパーボタンがあることで、非エンジニアでも抵抗なく使えるという声もあります。
WordやGoogle Docsのように体裁を意識する必要がなく、気軽にメモを書ける雰囲気があるため、投稿数が増加しました。
モバイルファクトリー様ではWikiに比べて投稿数が4倍に増加しました。
画像のドラッグ&ドロップでの挿入が簡単な点も、会議数の削減や手順書の作成に貢献しています。Excelからテーブルをコピー&ペーストするとMarkdown形式のテーブルが自動生成される機能も好評です。
差し込みメモ機能は、関連する情報を紐付けたり、議事録や手順書のテンプレートを作成することで、効率的な文書化を促進しています。
事例を読む 【事例】Wikiを使っていた時より投稿数が4倍に増えました | DocBase ナレッジ共有・情報共有ツール





