組織の業務は電子マニュアルで管理しよう|おすすめツールを紹介
最終更新日:2025年4月4日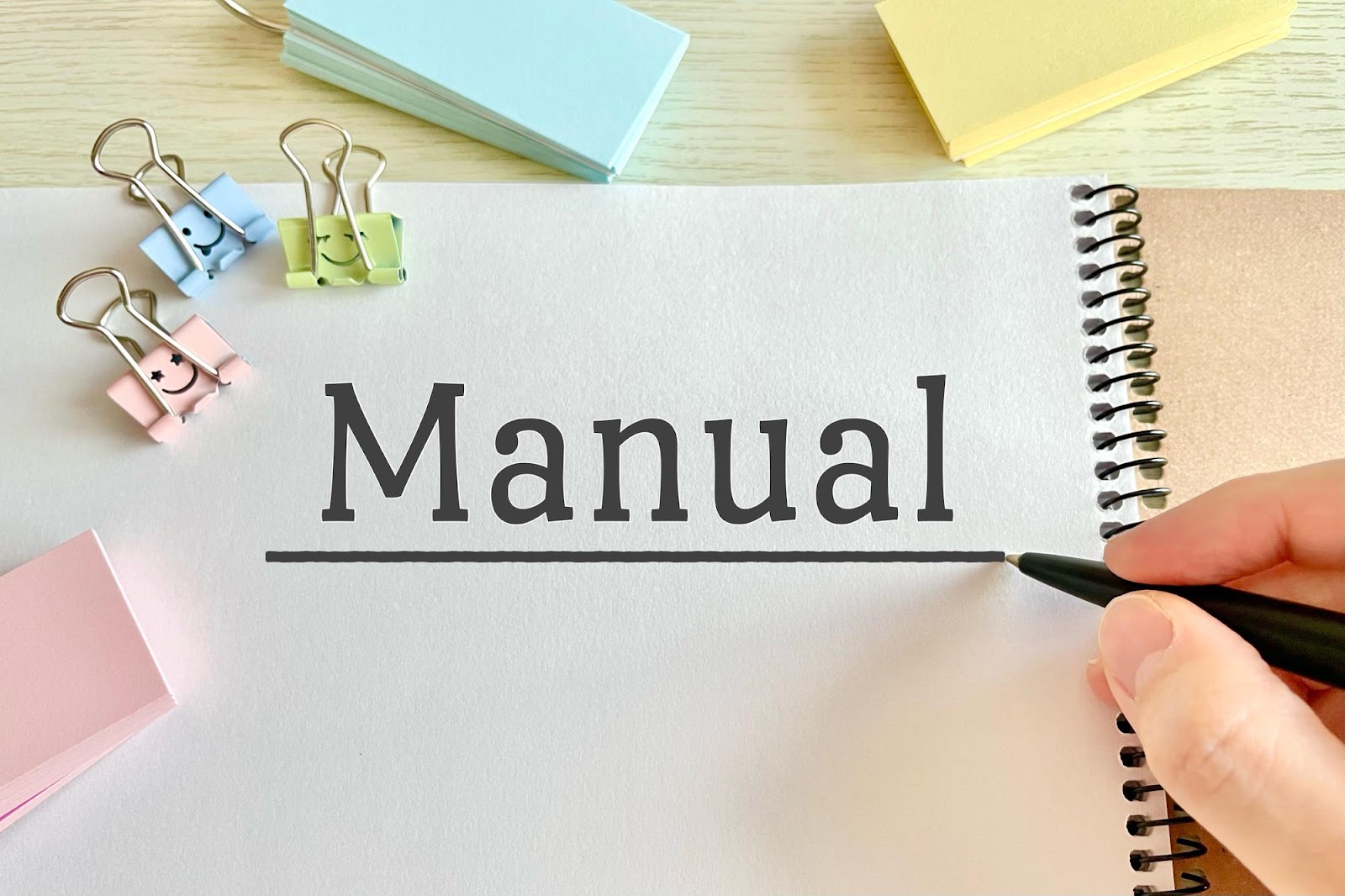
業務のDX化のための一手として、電子マニュアルを検討されている方も多いのではないでしょうか。従来の紙のマニュアルと比べ、素早い更新や検索のしやすさ、場所を選ばない閲覧など、電子マニュアルには多くの利点があります。
しかし、「どのツールを選べばいいの?」「効果的な作り方は?」など、電子マニュアルの導入にあたってはさまざまな疑問が浮かぶことでしょう。本記事では、電子マニュアルの基本的な考え方から、作成時のポイント、おすすめのツールまで、実践的な情報をお届けします。
マニュアル作りの経験が浅い方でも、この記事を読めば電子マニュアルの作成から運用までのイメージが掴めます。業務のデジタル化や標準化、効率化を目指す方は、ぜひ参考にしてください。
【この記事を読んでわかること】
- 電子マニュアル/紙のマニュアルのメリット・デメリット
- 効果的な電子マニュアルの作り方と運用方法
- 目的に応じた電子マニュアル作成ツールの選び方
目次
マニュアルを作る目的

みなさんは、日々の業務でマニュアルをどのように活用していますか?
マニュアルを作る大きな目的は、業務手順を標準化することです。特に以下のような課題を抱える企業では、マニュアル作成が効果的な解決策となります。
- マニュアルがないことで担当者によりサービスの質に差が生じてしまう
- 新入社員の教育や研修に時間がかかる
- 各部署からの問い合わせ対応に追われて、管理部の負担が大きい
- 新しい業務プロセスの導入時に手順がなかなか定着しない
これらの課題に対してマニュアルは有効なツールとなるのですが、紙のマニュアルでは改定や共有に手間がかかり、うまく運用できないことがあります。そこで注目されているのが電子マニュアルなのです。
電子マニュアルとは

電子マニュアルは、実際どのようなものなのでしょうか? 簡単にいえば、従来の紙のマニュアルをデジタル化したものです。でも、それだけではありません。
一番の特徴は、ネットワーク上で運用できること。インターネットにつながっていれば、いつでもどこでもマニュアルにアクセス可能です。
使う端末は、会社のパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットでもOK。マニュアルの内容を見るだけでなく、作成や編集まで、すべての作業をデジタル上で完結できます。時代とともに変化する業務のスピードに、柔軟に対応できるこの特徴は、効率的な業務の実現につながります。
従来の紙のマニュアルのあり方を大きく変える、新しい形の情報共有ツールともいえる電子マニュアル。これからの時代、ますます重要になってくるでしょう。
電子マニュアルのメリット3つ

電子マニュアルの導入を検討している方に、まず押さえておいてほしいのが、そのメリットです。従来の紙のマニュアルにはない、業務効率を大きく向上させる3つのメリットがあります。
- 編集がしやすい
- 検索がしやすい
- 端末があれば、どこからでも閲覧できる
この3つのメリットについて、具体的に見ていきましょう。
編集がしやすい
電子マニュアルの最大の魅力は、なんといっても編集のしやすさです。紙のマニュアルと違い、すべての作業がデータ上で完結するため、手間を大きく軽減することができます。
例えば、手順の変更があった場合。紙のマニュアルなら、該当ページを作り直して印刷し、古いページと差し替える必要がありました。でも、電子マニュアルなら、データを直接修正するだけでOK。改定作業がとてもスムーズです。
さらに、写真や動画を使った説明も簡単に追加できます。「この部分をもっとわかりやすく」という要望にも、迅速な対応が可能。画像の差し替えや、手順の並び替えなども、数クリックで完了します。
このように、電子マニュアルは細かな改定にも柔軟に対応できます。日々変化する業務の実態に合わせて、マニュアルを進化させていけるのです。
検索がしやすい
「新しいシステムの操作方法、どこに書いてあったっけ…」と、分厚いマニュアルを何度も見返す。締め切りが迫っているのに、情報探しに時間がかかり、残業が増えてしまう… そんな経験はありませんか?電子マニュアルなら、この悩みを簡単に解決できます。
最も便利なのが、キーワード検索機能です。探したい内容に関連する言葉を入力するだけで、該当するページがすぐに表示されます。厚い冊子の目次から該当ページを探す手間がなくなるのです。あいまい検索や全文検索にも対応しているため、具体的な表記が思い出せない場合でも、目的の情報が見つけやすくなっています。
特に、マニュアルのボリュームが多い場合に、検索機能は大きな効果を発揮します。数百ページもあるような業務マニュアルでも、必要な情報にピンポイントでたどり着けます。
「あの手順ってどこに書いてあったっけ?」といったストレスから解放され、業務効率が大きく向上し、残業時間の削減、社員満足度の向上にも貢献します。
端末があれば、どこからでも閲覧できる
電子マニュアルの大きな特徴として、場所を選ばない利便性もあげられます。パソコンやスマートフォン、タブレットなど、普段使っている端末があれば、いつでもどこでも必要な情報を確認できるのです。
例えば、在宅ワーク中に業務の手順を確認したいとき。わざわざ出社する必要はありません。自宅のパソコンやスマートフォンから、すぐにマニュアルを開けます。
外出先での商談中に、お客様からの専門的な質問にも、タブレットで最新情報を確認し、的確に回答できます。データはサーバーで管理されているため、いつでも最新の情報が閲覧できます。法改正や製品仕様の変更があっても、常に正確な情報が提供されます。バージョン管理機能も搭載されているので、過去の情報を参照することも可能です。
電子マニュアルは、場所や時間といった制約を解放し、リモートワークやフレックスなど、より柔軟な働き方を支援します。現代の多様な働き方をサポートするツールであるともいえるでしょう。
電子マニュアルのデメリット3つ

電子マニュアルには、たくさんのメリットがありますが、同時にいくつかの課題もあります。
- デバイスがないと閲覧できない
- 見にくいと感じる人もいる
- 同時に複数のページを見るのが難しい
ただし、これらのデメリットは、適切な準備と工夫によって、ほとんどの場合解決できます。むしろ、事前に課題を把握しておくことで、より効果的な導入が可能になるのです。電子マニュアルの主な3つのデメリットについて、具体的に見ていきましょう。
デバイスがないと閲覧できない
電子マニュアルを利用するうえで、避けて通れないのがデバイスの問題です。いくら便利な機能があっても、それを閲覧するための端末がなければ始まりません。
特に注意が必要なのは、全従業員が適切なデバイスを持っているとは限らないということ。パソコンやタブレットを新たに用意する必要がある場合、それなりの初期投資が必要になります。
また、端末の性能によっては、スムーズな閲覧ができない可能性もあります。特に画像や動画が多用されているマニュアルの場合は要注意です。
ただし、最近では個人所有のスマートフォンでの閲覧に対応したシステムも増えています。導入時には、従業員の端末保有状況をしっかり確認し、最適な運用方法を検討することが大切です。
見にくいと感じる人もいる
デジタル機器が当たり前になった今でも、「画面よりも紙の方が読みやすい」という声は少なくありません。電子マニュアルの導入時には、この「見やすさ」の問題も考慮する必要があります。
特に、長時間にわたって画面を見続ける必要がある場合、目の疲れを訴える人も出てくるでしょう。液晶画面からの光が苦手な人や、紙の文字の方が頭に入りやすいという人もいます。
これは世代による違いだけでなく、個人の特性による部分も大きいものです。全員が同じように快適に使えるとは限らないことを、理解しておく必要があります。
ただし、文字サイズの変更や画面の明るさ調整といった機能を活用することで、大幅な改善が期待できます。個々の利用者に合わせたカスタマイズが可能な点は、電子マニュアルならではの利点といえるでしょう。
同時に複数のページを見るのが難しい
電子マニュアルを実際に使用していると、意外と困るのが複数ページの同時確認です。紙のマニュアルなら、複数のページを同時に見たり行き来したりできますが、データではそうはいきません。
特に困るのが、基本の作業手順と応用的な内容を並行して確認したい場合です。例えば、「作業Aと作業Bの工程を見比べたい」「基本手順を確認しながら、注意事項も参照したい」といった状況です。画面の切り替えが必要になるため、作業の流れが途切れてしまうこともあるはずです。
パソコンであれば、複数のウィンドウを開いて並べることで対応できますが、スマートフォンやタブレットではそれも難しいでしょう。画面サイズの制約もあり、快適な閲覧環境を作るのは容易ではありません。
ただし、目次やリンクの工夫、関連内容のまとめ、ポップアップウィンドウの活用など、さまざまな対策方法があります。導入時には、実際の使用シーンを想定した設計が大切です。
紙のマニュアルを使うメリット3つ

電子マニュアルが注目を集める中、あえて紙のマニュアルを選ぶ企業も少なくありません。実は、従来の紙のマニュアルには、デジタルでは代替しにくい3つのメリットがあります。
- 印刷すればどこでも見られる
- 自由に書き込める
- ページの行き来がしやすい
印刷すればどこでも見られる
紙のマニュアルの最大の魅力は、その手軽さにあります。印刷されたマニュアルがあれば、すぐに利用可能。電源やネットワーク環境、特別なデバイスは一切不要です。この「シンプルさ」が、実は大きな価値を持っているのです。
例えば、工事現場や倉庫など、電源の確保が難しい環境での作業確認。あるいは、システムトラブル時の対応手順の確認など、デジタル機器が使えない状況でも、紙のマニュアルなら即座に参照できます。
一方で、マニュアルのボリュームが数百ページを超える場合、このメリットが十分に発揮されないことも。持ち運びの負担が大きくなり、かえって不便になってしまう可能性があります。
マニュアルの内容やページ数、使用する場面などを考慮しながら、紙のマニュアルの活用シーンを見極めることが大切です。
自由に書き込める
紙のマニュアルならではの特徴として、自由な書き込みができる点が挙げられます。気づいたことをその場でメモしたり、重要な箇所にマーカーを引いたり、付箋を貼ったりと、使う人の創意工夫を存分に活かせるのです。
特に研修や教育の場面では、この特徴が大きな価値を発揮します。例えば、講師の補足説明をマニュアルに書き込んだり、自分なりの解釈や注意点を余白にメモしたり。これらの行為が、内容の理解と記憶を助けてくれます。
また、経験を重ねる中で気づいた「コツ」や「ポイント」も、その場でマニュアルに反映できます。この積み重ねが、より実践的で使いやすいマニュアルへと進化させていくのです。
このように、紙のマニュアルは単なる情報伝達ツールではなく、個人の学習や成長をサポートする「生きた教材」としても機能します。
ページの行き来がしやすい
紙のマニュアルの優れた点として、複数のページを同時に参照できる使いやすさがあります。例えば、基本手順のページを開いたまま、関連する注意事項のページをぱらぱらとめくって確認することもできますし、付箋を活用すれば、よく参照するページへの素早いアクセスも可能です。
この「ページの行き来のしやすさ」は、作業効率に大きく影響します。画面の切り替えが必要な電子マニュアルと比べ、作業の流れを途切れさせることなく、必要な情報にアクセスできるのです。
このように、紙のマニュアルは、人間の自然な動作や認知特性に合った使いやすさを備えています。デジタルツールでは完全には代替できない価値があるといえるでしょう。
紙のマニュアルを使うデメリット3つ

紙のマニュアルには、電子マニュアルにはない優れた特徴がありますが、実際の運用ではさまざまな問題に直面することもあります。特に大規模な組織での活用時には、次のような課題がより顕著になってきます。
- 印刷するコストがかかる
- アップデートの手間がかかる
- 検索がしにくい
紙のマニュアルの3つのデメリットについて、具体的に見ていきましょう。
印刷するコストがかかる
紙のマニュアルを運用する際、最も頭を悩ませるのが印刷にかかるコストの問題です。特に、分厚いマニュアルを大量に印刷する必要がある場合、その負担は無視できないものとなります。
例えば、100ページのマニュアルを100人の社員に配布する場合。用紙代、インク代、印刷機の維持費など、さまざまなコストが発生します。さらに、マニュアルの改訂のたびに、これらのコストが繰り返し発生するのです。
コスト削減のために、部署で1冊を共有使用する方法も考えられます。しかし、それでは紙のマニュアルの利点である「書き込みのしやすさ」や「いつでも確認できる」といったメリットが失われてしまいます。
このように、印刷コストの問題は、マニュアルの効果的な活用と相反する関係にあることが多いのです。紙のマニュアルは、コストと利便性のバランスが、運用上の大きな課題となります。
アップデートの手間がかかる
紙のマニュアルの大きな課題として、内容の更新にかかる手間とコストの問題があります。業務内容が変更されるたび、すべてのマニュアルを刷り直して配布し直す必要があるのです。
例えば、ちょっとした手順の変更があった場合。該当ページを作り直し、印刷して、全社員分のマニュアルの該当ページを差し替える必要があります。さらに、古いページの回収や、変更内容の周知など、付随する作業も発生します。
特に困るのが、更新のタイミングがずれてしまう問題です。一部の社員が古いマニュアルを使い続けてしまうことで、業務の手順にばらつきが生じる可能性があります。また、急な修正が必要になった場合、すぐには対応できないケースもあります。
このように、紙のマニュアルの更新作業は、想像以上に多くの時間と労力を必要とします。業務効率化を目指すマニュアルが、かえって業務の負担となってしまうのです。
検索がしにくい
紙のマニュアルで特に困るのが、必要な情報をすぐに見つけられない点です。ページ数が多くなればなるほど、目的の箇所を探し出すのに時間がかかってしまいます。
例えば、急なトラブル対応で特定の手順を確認したい場合。目次から該当ページを探し、さらにその中から必要な項目を見つけ出す必要があります。電子マニュアルのようなキーワード検索ができないため、この作業に余計な時間を取られてしまうのです。
特に新人社員にとって、この問題は深刻です。マニュアルの構成に慣れていない段階では、どこに何が書いてあるのかを把握するのも一苦労。結局、「人に聞いた方が早い」と考えてしまい、せっかく作ったマニュアルが活かされなくなってしまいます。
このように、検索性の低さは、業務効率の低下だけでなく、マニュアル自体の活用度を下げてしまう要因にもなります。情報へのアクセスのしやすさは、現代のビジネスにおいて重要な要素なのです。
電子マニュアルを作成する手順
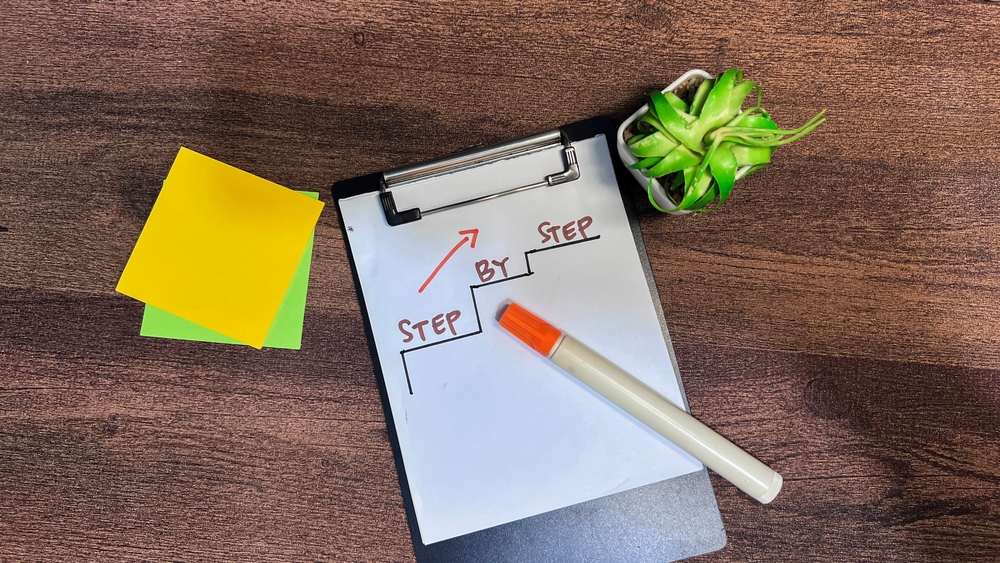
現代のビジネス環境では、スピードと効率が求められるケースが多いため、電子マニュアルの導入を検討する企業が増えています。では、効果的な電子マニュアルを作成するには、具体的にどのような手順で進めればよいのでしょうか。
紙のマニュアルの良さも取り入れながら、実践的で活用される電子マニュアルを作るためのポイントを、順を追って解説していきます。
- ステップ1 マニュアル化が必要な業務を洗い出す
- ステップ2 利用するツールを決める
- ステップ3 マニュアル作成の担当者を決める
- ステップ4 マニュアルの骨組みを作る
- ステップ5 骨組みをもとに肉付けする
- ステップ6 組織内で運用する
- ステップ7 改善を重ねる
ステップ1 マニュアル化が必要な業務を洗い出す
電子マニュアルを作成するために、最初にマニュアル化が必要な業務の洗い出しをしましょう。ただやみくもに作成を始めるのではなく、計画的なアプローチが重要です。
まずは、社内の業務を主要なカテゴリーに分類し、リストアップしていきます。例えば、「営業関連」「経理関連」「人事関連」といった具合です。その中から、標準化が必要な作業や、よくミスが起きる工程を特定していきます。
次に、マニュアル作成の優先順位を決めます。この際、現場の意見を積極的に集めることが大切です。「この作業のやり方が人によってバラバラ」「新人教育に時間がかかりすぎる」といった課題が、優先度を判断する重要な指標となります。
また、マニュアル作成の目的と目標を、関係者で明確に共有することも忘れずに。「何のために電子マニュアルを作るのか」という認識が揃っていれば、より実用的なマニュアルが作れるのです。
ステップ2 利用するツールを決める
電子マニュアルの作成において、使用するツールの選択は非常に重要なポイントです。組織の規模や、作成したいマニュアルの形式、閲覧方法などによって、最適なツールは変わってきます。
例えば、シンプルな手順書であればワープロソフトで十分かもしれません。しかし、動画や画像を多用したい場合や、スマートフォンでの閲覧を重視する場合は、専用のマニュアル作成ツールの導入を検討する必要があります。
ツールの選択時に重要なのは、
- コンテンツで扱う素材が何か(テキストが中心、動画や画像も多用するなど)
- どんなデバイスで閲覧するのか(パソコンのみ、タブレットやスマホも活用など)
- どんな業務をマニュアル化するのか
といった点です。現場での使用シーンを具体的にイメージしながら、必要な機能を洗い出していきましょう。
また、将来的な拡張性も考慮に入れることが大切です。業務の変化や組織の成長に合わせて、柔軟に対応できるツールを選択すれば、長期的な運用がスムーズになります。
ステップ3 マニュアル作成の担当者を決める
電子マニュアル作成を成功させるには、適切な担当者の選定と役割分担が欠かせません。誰がどの部分を担当するのか、チェック体制をどうするのかなど、明確な体制づくりが重要です。
まず決めるべきなのは、各マニュアルの作成担当者です。実際の業務に精通している人が担当すれば、より実践的な内容になります。ただし、マニュアル作成のスキルも必要なため、必要に応じてサポート体制を整えることも検討しましょう。
次に、内容をチェックする担当者を決めます。業務の正確性はもちろん、わかりやすさや表現の統一性なども確認が必要です。複数の目で見ることで、より質の高いマニュアルが作れます。
また、動画マニュアルを作成する場合は、出演者の選定も重要です。話し方がわかりやすく、適切なペースで作業を説明できる人材を選びましょう。
ステップ4 マニュアルの骨組みを作る
電子マニュアルの作成では、最初から詳細な内容を書き始めるのではなく、まずは全体の骨組み作りが重要です。この段階でしっかりと設計することで、よりわかりやすく、使いやすい電子マニュアルが完成します。
具体的には、章立てや見出しのレベル分けから始めましょう。例えば、「1.基本操作」「2.日常業務の手順」「3.トラブル対応」といった具合です。その際、実際の業務の流れに沿った構成にすることで、使う人が直感的に必要な情報にたどり着けます。
また、電子マニュアルならではの特徴を活かした構成も考えましょう。検索のしやすさ、リンクによるページ間の移動、動画や画像の効果的な配置など。これらを念頭に置いた骨組み作りが大切です。
この段階で現場の意見を取り入れることも効果的です。実際に使う人の視点に立てば、より実用的な構成が見えてきます。
ステップ5 骨組みをもとに肉付けする
骨組みを作成したら、いよいよ具体的な内容を肉付けしていきます。この段階で大切なのは、「初めて見る人でも理解できる」という視点を持つことです。当たり前すぎて説明を省いてしまいがちな部分こそ、丁寧な解説が必要かもしれません。
特に効果的なのが、文章だけでなく、視覚的な要素を活用すること。手順を説明する際は、実際の画面のスクリーンショットや、作業の様子を撮影した写真を積極的に取り入れましょう。動画による説明も、電子マニュアルならではの強みです。
また、専門用語や略語は極力避け、平易な言葉で表現することを心がけます。どうしても使用する必要がある場合は、用語集を設けるなどの工夫が効果的です。
このように、文字、画像、動画をバランスよく組み合わせることで、よりわかりやすく、実践的な電子マニュアルが完成します。
ステップ6 組織内で運用する
せっかく作成した電子マニュアルも、実際に活用されなければ意味がありません。作成後の運用方法をしっかりと計画し、組織への定着を図ることが重要です。
まず大切なのが、マニュアルの存在と使い方の周知です。単にメールで案内するだけでなく、実際の操作方法を説明する研修会を開催したり、部署ごとに担当者を決めてサポート体制を整えたりすることで、スムーズな導入が可能になります。
また、マニュアルへのアクセス方法を簡単にすることも重要です。社内ポータルサイトのトップページにリンクを設置したり、よく使うページをブックマークできるようにしたりと、ちょっとした工夫が活用度を大きく左右します。
さらに、使用状況をモニタリングし、どのページがよく見られているか、検索ワードは何か?などを分析することで、より使いやすいマニュアルへと改善できます。
ステップ7 改善を重ねる
マニュアルは作成して終わりではなく、業務の変化や改善に合わせて、定期的な見直しと更新が欠かせません。一般的には、半年から1年に1度の見直しがおすすめです。
見直しの際は、次のポイントに注目しましょう。
- 内容が現在の業務手順と合っているかどうか
- わかりにくい説明や、よく質問がくる箇所はないか
- 新しい事例や注意点を追加する必要はないか
また、現場からのフィードバックを積極的に集めることも重要です。実際に使っている人の声こそが、マニュアルを改善する最大のヒントになります。「ここがわかりづらい」「こんな機能があったら便利」といった意見を、しっかりと取り入れていきましょう。
電子マニュアルを作成する5つのポイント

ここまで電子マニュアルの作成手順を詳しく見てきましたが、実際の作成時には、以下の5つのポイントを押さえる必要があります。
- 手順を細かく区切って明確にする
- 検索しやすいようにする
- 画像や動画を活用する
- 編集が簡単なツールを選ぶ
- クラウドで運用する
これらのポイントは、電子マニュアルの使いやすさを大きく左右する要素となります。例えば、手順の明確な区分けは理解のしやすさにつながり、検索機能の充実は業務効率の向上に直結します。
5つのポイントは、作成開始前のチェックリストとしても活用できます。一つずつ具体的に見ていきましょう。
手順を細かく区切って明確にする
電子マニュアルを作る際、最も重要なのは「手順の明確化」です。業務の流れを細かく区切り、それぞれのステップをわかりやすく説明することで、誰が読んでも同じように作業できるマニュアルが完成します。
例えば、「データを入力する」という作業1つとっても、「①システムにログインする」「②該当画面を開く」「③必要項目を入力する」といった具合に、できるだけ細かく分解します。当たり前と思える動作でも、省略せずに記載することが大切です。
また、作業の目的や、その手順が必要な理由も併せて説明すると、より理解が深まります。単なる作業の羅列ではなく、「なぜそうするのか」を理解することで、応用力も身につきやすくなります。
検索しやすいようにする
電子マニュアルの大きな強みは、必要な情報をすぐに見つけられる点です。この特徴を最大限に活かすため、検索のしやすさにこだわることが重要です。
具体的には、適切な見出しやタグの設定、キーワード検索への対応などが効果的です。例えば、よく検索されそうな用語や、現場でよく使う表現をタグとして登録しておくと、より素早く目的の情報にたどり着けます。
また、関連情報へのリンクも効果的に配置しましょう。「詳しくはこちら」といった形で関連ページへのリンクを張っておくと、必要に応じて詳細な情報まで確認できます。現場の作業を止めることなく、スムーズな情報アクセスが可能になるのです。
画像や動画を活用する
電子マニュアルならではの特徴を活かすなら、画像や動画による視覚的な説明は外せません。「百聞は一見にしかず」という言葉通り、適切な視覚情報があることで、理解度は大きく向上します。
例えば、操作手順の説明では、各ステップの画面キャプチャを掲載。複雑な作業の解説には、実際の動作を撮影した動画を活用。注意点の説明には、具体的な事例の写真を使用するなど、目的に応じた使い分けが効果的です。
ただし、むやみに視覚情報を増やすのは逆効果でしょう。本当に必要な場面を見極め、適切なサイズと画質で提供することが重要です。文章による説明と視覚情報のバランスを意識しましょう。
編集が簡単なツールを選ぶ
電子マニュアルは、業務の変更や改善に応じて、こまめな更新が必要です。そのため、誰でも簡単に編集できる環境を整えることが、継続的な運用の鍵となります。
特に重要なのは、専門知識がなくても更新作業を行えるツールの選択です。HTMLやプログラミングの知識が必要なものは避け、直感的な操作で編集可能なものを選びましょう。例えば、ワープロソフトのような感覚で編集できるツールなら、現場の担当者でも気軽に更新作業に取り組めます。
また、変更履歴の管理機能や、複数人での同時編集機能なども、運用をスムーズにする重要な要素です。更新作業の負担が少ないほど、電子マニュアルは最新の状態を保ちやすくなります。
クラウドで運用する
電子マニュアルの運用では、クラウドの活用が大きな効果を発揮します。従来のようにデータを各端末に保存する方式では、最新版の管理や共有に手間がかかってしまいます。
クラウドを利用することで、全社員が常に最新のマニュアルにアクセスできます。更新があった際も、サーバー上のデータを書き換えるだけで完了。各端末での更新作業は不要です。また、更新履歴の管理や、アクセス権限の設定なども容易になります。
セキュリティ面でも、クラウドは有効です。データの暗号化や、アクセスログの管理により、機密情報の漏洩リスクを低減できます。社外からの安全なアクセスも可能となり、テレワーク時の活用もスムーズです。
電子マニュアル作成ツールを選ぶポイント

電子マニュアルの作成ツールを選ぶときは、以下の3つがポイントになります。
- 作成のしやすさ
- 閲覧のしやすさ
- 活用を促す機能
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
作成のしやすさ
電子マニュアルの作成ツールを選ぶ際、まず重要なのが作成のしやすさです。使いやすいツールを選ぶことで、効率的にマニュアルを作成できます。
最も基本となるのが、テンプレートの活用です。用意されたテンプレートに沿って入力するだけで、見やすい電子マニュアルが完成します。専門的なスキルがなくても、整った体裁のマニュアルを作れるのが特徴です。
また、画像や動画を簡単に挿入できる機能も大切です。手順を視覚的に伝えることで、よりわかりやすいマニュアルになります。充実した編集機能があれば、多様な表現方法を駆使して、より効果的なマニュアルを作成できます。
さらに、更新・修正のしやすさも重要です。マニュアルは常に最新の情報を提供する必要があるため、迅速かつ容易に編集が行える機能が不可欠。レイアウトを気にすることなく、内容を手軽に更新できるツールを選びましょう。
閲覧のしやすさ
マニュアルは作るだけでなく、使う人が快適に閲覧できることも重要です。ここでは、閲覧のしやすさを決める要素を見ていきましょう。
まず欠かせないのが、充実した検索機能です。必要な情報をすぐに見つけられることは、業務効率を大きく左右します。タイトルや本文の検索はもちろん、タグ設定による絞り込みなども便利な機能です。
また、マルチデバイス対応も重要なポイントです。パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットでも快適に閲覧できることで、場所を選ばず必要な情報にアクセスが可能になります。特に現場での作業中、確認する際に役立ちます。
さらに、閲覧権限の設定機能も欠かせません。部署や役職に応じて、必要なマニュアルだけを表示できれば、関係のない情報に惑わされることなく、効率的な情報アクセスが可能になります。
活用を促す機能
どんなに優れた電子マニュアルを作っても、使われなければ宝の持ち腐れです。電子マニュアルの活用を促進するために、以下のような機能が搭載されているかどうかも見ておく必要があります。
- 利用状況の追跡機能
- 閲覧数やPV数、よく使われる検索ワードなどのデータを分析できると、マニュアルの改善に役立ちます。どのページがよく見られているか、どんな情報が求められているかを把握することで、より使い勝手の良いマニュアルへと進化させられます。
- 評価やフィードバック機能
- 使う側からの意見や感想を集められると、マニュアルの品質向上につながります。
- QRコード出力機能
- 現場の機器や設備の近くにQRコードを掲示しておけば、すぐに関連マニュアルにアクセス可能。特に外国人スタッフが多い職場では、言葉の壁を超えて必要な情報に導くことができます。
このように、活用状況の把握から具体的な利用促進まで、さまざまな機能を活用することで、より効果的なマニュアル運用が可能になります。
電子マニュアルの作成におすすめのツール4選

電子マニュアル作成ツールを選ぶポイントについて見てきました。それでは、実際にどんなツールがあるのでしょうか。ここでは、作成のしやすさ、閲覧性、活用促進機能などの観点から、おすすめの4つのツールをご紹介します。
- DocBase
- Googleドキュメント/スプレッドシート
- Word/Excel/Powerpoint
- Dropbox Paper
DocBase
【DocBaseの特徴】
- 画像のペイントモード
- 柔軟な公開範囲設定
- 豊富な検索機能
- 誰でも使えるシンプルな編集機能
- メモの外部公開機能
DocBaseは、社内の情報共有をサポートする多機能ツールです。マニュアルはもちろん、社内wiki、ナレッジ共有、議事録まで、あらゆる文書管理がこれ1つで実現できます。画像編集機能、柔軟な公開範囲設定、高度な検索機能、シンプルな編集機能、外部公開機能を備え、マニュアル作成の効率化と、マニュアルの活用を促進します。
画像編集機能により、画像編集ソフトを使わずにDocBase内で直接、矢印、テキスト、モザイクなどの加工が可能。画像編集と文書作成をワンストップで完結させ、手順書などのマニュアル作成を大幅に効率化します。
柔軟な公開範囲設定では、グループ機能を利用して、作成したマニュアルを特定のチームメンバーのみに公開したり、複数のグループに公開したりと、情報を見せる範囲を細かく調整できます。
また、高度な検索機能により、キーワード、グループ、タグなど、さまざまな条件でマニュアルを検索可能です。PDFやExcelなどの添付ファイルの内容も検索対象となるため、必要な情報を迅速に見つけ出し、活用できます。
シンプルな編集機能は、マークダウンとリッチテキストの両形式に対応し、それらを同時に使えるハイブリッドエディターも搭載しているため、デジタルツールに不慣れなメンバーでも容易にマニュアルの作成・編集に参加でき、チーム全体の知識として蓄積・活用を促進します。
さらに、メモの外部公開機能を利用すれば、DocBaseを利用していない社外のメンバーにもマニュアルを共有可能です。共有時にはパスワードを設定できるため、セキュリティに配慮した情報共有が可能です。
【DocBaseの費用・料金プラン】
| 無料トライアル | スターター | ベーシック | レギュラー | ビジネス | |
| 料金 | 0円 | 990円/月 | 4,950円/月 | 9,900円/月 | 21,450円/月 |
| ユーザー数 | 無制限 | 3人 | 10人 | 30人 | 100人 |
| ストレージ | 無制限 | 3GB | 10GB | 30GB | 100GB |
【公式サイト】
Googleドキュメント/スプレッドシート
Googleのオンラインツールである、Googleドキュメント/スプレッドシートは、電子マニュアル作成の入門に最適です。無料で15GBまで利用でき、Microsoft Office製品に似た操作感で、初めての方でもすぐに使いこなせるでしょう。
直感的な操作で文書作成、表挿入、画像配置が可能。特に、複数人で同時に編集できる共同編集機能は使い勝手がよく、部門間の連携によるマニュアル作成・チェックがスムーズに行えます。
コメント機能による議論や修正依頼、変更履歴機能による編集内容の追跡も容易です。作成したマニュアルはリンク共有で配布でき、権限設定による編集・閲覧制限も可能。
さらに、スマートフォンやタブレットからのアクセス、オフライン編集機能、自動保存機能など、利便性にも優れています。
Googleドキュメント/スプレッドシートは、使い慣れた環境で手軽に電子マニュアルを作成したい場合に、最適な選択肢となるでしょう。
Word/Excel/PowerPoint
より手軽なのが、Microsoft Office(Word/Excel/PowerPoint)の活用です。 社内にライセンスがあれば、追加費用なしで使い慣れた環境を活かせます。クラウド版のOffice 365であれば、Googleオンラインツール同様の同時編集も可能です。
作りたいマニュアルの種類に応じて、最適なツールを選択できます。文章主体のマニュアルにはWordが適しており、目次自動生成やスタイル一括適用など、文書作成に便利な機能が充実しています。手順や規則をテーブル化したい場合はExcelが便利で、条件付き書式による重要項目の強調表示が可能です。視覚的な説明が必要なマニュアルにはPowerPointが最適で、アニメーション機能によるステップバイステップの説明が効果的です。
長年の実績と充実した編集機能を持ち、テンプレート活用で統一感のあるマニュアルを効率的に作成できます。PDF変換も容易で、完成したマニュアルのスムーズな共有も可能です。
Microsoft Officeは多くの人が使い慣れたツールであり、豊富なオンラインヘルプやコミュニティの情報も活用できるため、迷うことなく電子マニュアル作成に取り組めます。
【Office 365の費用・料金プラン】
| Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | Microsoft 365 Apps for business | |
| 価格 | ¥899 | ¥1,874 | ¥3,298 | ¥1,236 |
※: 価格はユーザー/月相当、税別、年払い、年間サブスクリプション – 自動更新です。
【公式サイト】
https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/microsoft-365-business
Dropbox Paper
電子マニュアルの新しい選択肢として、Dropbox Paperも見逃せません。2GBまでなら無料で使える上に、一部動画も組み込めるので、よりわかりやすいマニュアルが作れます。
複数で同時に編集できる機能があり、チームでの作業がとてもスムーズです。特に、@メンション機能を使えば、特定のメンバーにタスクを割り当てたり、確認を依頼したりとう使い方も可能。また、コメントやステッカーを使って、楽しみながらコミュニケーションを取れるのも特徴です。
テキスト入力や書式設定はもちろん、チェックリストの作成も簡単です。作ったマニュアルは「招待」ボタンで簡単に共有でき、ワンクリックでPDFにも変換可能。
マニュアル以外にも、会議の記録や計画表など、さまざまな文書作成にも使えます。クラウド上に自動保存されるので、データの紛失も心配ありません。困ったときは、充実したコミュニティやサポートを利用できる点も安心です。
シンプルな操作性と便利な機能を兼ね備えた、電子マニュアル作成ツールといえるでしょう。
【Dropbox Businessの費用・料金プラン】
| Essentials | Business | Business Plus | Enterprise | |
| 料金 | 2,000円/月 | 1人1,500円/月 | 1人2,400円/月 | 要相談 |
| 人数 | 1人 | 3人~ | 3人~ | 要相談 |
| ストレージ | 3TB | 9TB~ | 15TB~ | 要相談 |
| サービス | 最大 100 GB のファイル転送180 日以内に削除されたファイルの復元ファイル エンゲージメントの追跡署名依頼の件数が無制限PDF 編集動画の録画、レビュー、編集 | 最大 100 GB のファイル転送180 日以内に削除されたファイルの復元ファイル エンゲージメントの追跡署名依頼の件数が無制限PDF 編集動画の録画、レビュー、編集管理者の設定共有されたコンテンツの把握 | 最大 250 GB のファイル転送1 年以内に削除されたファイルの復元ファイル エンゲージメントの追跡署名依頼の件数が無制限PDF 編集動画の録画、レビュー、編集管理者役割の階層化の設定不審なアクティビティのアラートコンプライアンスのトラッキング | 最大 250 GB のファイル転送エンタープライズ レベルのセキュリティ ツールと可視性ツールクラス最高のセキュリティ ソリューションとの連携専任のエキスパートによるパーソナライズされたライブ サポート |
【公式サイト】
DocBaseを活用して電子マニュアルを作成しよう

この記事では、電子マニュアルの基本的な考え方から具体的な作成方法、おすすめツールまで幅広く解説してきました。
作成にあたっては、「手順の明確化」「検索性の向上」「視覚情報の活用」など、いくつかの重要なポイントがあります。また、作って終わりではなく、定期的な見直しと改善により、さらに実用的なマニュアルへと進化させていくことが大切です。
電子マニュアルの導入を検討されている方は、まず自社の課題や目的を明確にし、それに合わせて適切なツールを選びましょう。すぐにでも始められる第一歩として、まずは小規模な業務から電子マニュアル化に取り組んでみてはいかがでしょうか。
DocBaseは電子マニュアル作成にもおすすめの情報共有ツールです。電子マニュアルの作成や共有を簡単に行う機能が搭載されており、誰でも操作に苦労せず利用することができます。無料のお試し期間(クレジットカードの登録不要)が提供されているので、実際に操作をしながら導入を検討いただけます。
DocBaseにおける電子マニュアル活用事例
| 企業名 | 活用内容 | 効果 | 事例ページ |
| 株式会社アールキューブ | ・社内マニュアル、顧客情報、人事情報、コピー機の使い方など、ほぼ全ての情報を集約し、「アールキューブ版ウィキペディア」として活用。 ・結婚式場情報を共有し、経験のない社員でもノウハウを共有可能。 ・業務マニュアル (ネットの繋ぎ方、招待状の作り方) や外部パートナーとの共有マニュアルとしても活用。 |
情報の一元化と検索性の向上による業務効率化。DocBaseなしでは業務が回らないほど重要なツールに。 | アールキューブ版ウィキペディアをDocBaseで作成 〜検索すればなんでも分かる |
| オイシックス・ラ・大地株式会社 | ・社内ルールや便利ツールのリンク集「ここみて」を作成し、組織図や各種依頼書、システム周りの設定方法などを掲載。 ・ヘルプデスク担当者がよく来る問い合わせをDocBaseに上げ、同様の問い合わせにはそのURLを送付。 |
情報へのアクセスの容易化。ヘルプデスク担当者の負担軽減。 | 会議のペーパーレス化が進んで、とても楽になりましたオイシックス・ラ・大地株式会社様 |
| 医療法人 風林会 | ・人事課内でDocBaseをメインにマニュアル作成。 ・DocBaseを見れば業務を進められるように、業務の情報を全て掲載し、検索すればノウハウがわかる状態に。 ・DocBaseの使い方や採用・人材管理ツールの使い方、過去の採用活動の進捗や対策、振り返りなどを共有。 |
新人教育にかかる時間を大幅に削減。チーム内で知識レベルの統一。 | 新人スタッフへの100通超の業務連絡メールを削減「全国にスタッフがいる会社におすすめです」 | DocBase ナレッジ共有・情報共有ツール |
| 大垣ケーブルテレビ | ・顧客サポートに関するノウハウの属人化を解消するため、DocBaseを導入し、障害対応の手順などを全社で共有できるようにマニュアルを作成。 ・覚えるのが難しい機器の設定マニュアルなども作成し、必要な時に見れるように。 |
全社員が障害対応できるように。新人でも不具合対応ができるように。属人化の解消と、顧客対応力の向上。 | 属人化していたノウハウを全社で共有し、誰でも顧客サポートができるチームへ大垣ケーブルテレビ様 |
| 株式会社人機一体 | ・ワープロのような「書類」ではなく「情報」を蓄積したいというニーズからDocBaseを導入し、業務上のルールなどを事務の担当者がDocBaseに記録。 ・複数人での共有のしやすさ、Markdown形式での記述、そしてPDFへの書き出しの綺麗さなどが重要な要素。 |
DocBaseがないと回らないほど、情報共有において重要な要素となっている。 | 共有できて、ワープロでもエディターでもない、いいところを狙っているツール株式会社人機一体 金岡克弥様 |





