ナレッジマネジメントとは? 必要な要素や成功事例・ツールを詳しく解説
最終更新日:2025年2月26日
ビジネスシーンで時折、耳にする「ナレッジマネジメント」。ナレッジマネジメントは、企業内の貴重な知識やノウハウを効率的に共有・活用できるようになる仕組みを示します。例えば、ベテラン社員の商談テクニックを体系化して新人教育に活用したり、部門をまたいだ業務改善のアイデアを共有したりするといったケースがナレッジマネジメントにあたります。本記事では、ナレッジマネジメントの基本概念から具体的な導入方法、さらには最新のツール情報まで、実践的な知見を詳しく解説します。業務効率化や人材育成、組織開発にお悩みのの方はぜひご一読ください。
この記事を読んでわかること
- ナレッジマネジメントの概要や必要な要素
- ナレッジマネジメントの手法
- 導入方法やツール、成功事例
目次
ナレッジマネジメントとは
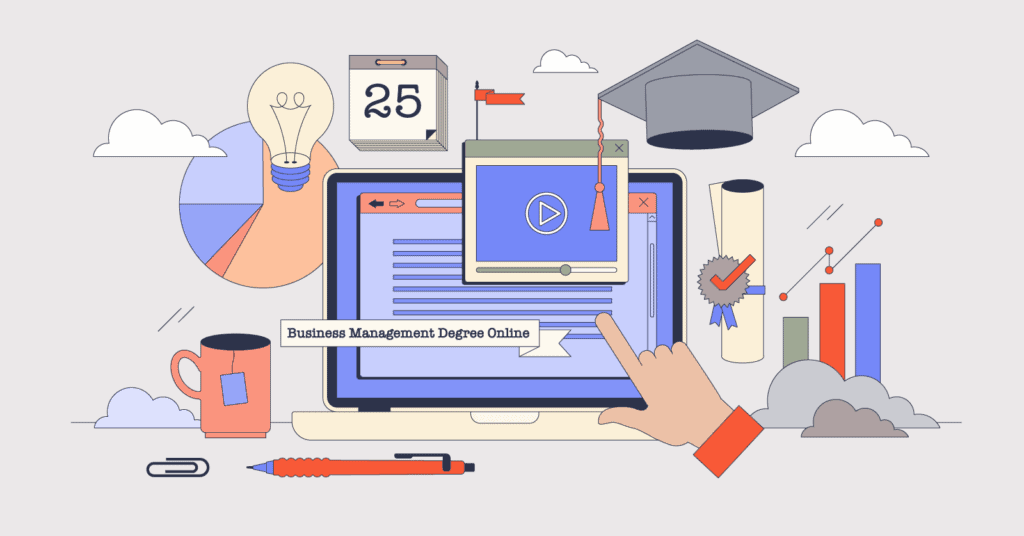
ナレッジマネジメントとは、個人の持つ業務知識やスキルを組織全体で共有し、活用する仕組みです。
1990年代に一橋大学大学院の野中郁次郎教授が提唱したナレッジマネジメントは、日本発の経営理論として世界中に広がりました。企業の中には、毎日の業務から生まれる多くの知見が眠っています。例えば、営業担当者が培った商談のコツ、カスタマーサポートの対応事例、技術者の製品改良のアイデアなどです。
これらの知見を組織全体で共有すると、業務の効率が上がり、新しいアイデアが生まれやすくなります。具体的には、営業チームの成功事例を共有することで、新人でも早く成果を出せるようになったり、製品開発チームの気づきを活かして、より使いやすい商品が生まれたりします。
現在では、世界の大手企業の多くがナレッジマネジメントを導入しています。個人の経験を組織の財産として活用することで、企業の成長スピードが加速するからです。昨今ではデジタル技術の進歩により、知識共有の手段が増えたため、ナレッジマネジメントの効果はより高まっています。
ナレッジマネジメントは、単なる情報共有の仕組みではありません。組織の知恵を集めて新しい価値を生み出す、現代のビジネスに欠かせない経営手法でもあります。
ナレッジマネジメントの理解に必要な4つの要素

ナレッジマネジメントを理解する上では、以下の4つを押さえておくといいでしょう。
- 暗黙知→形式知へ
- SECIモデル
- 「場」
- 知的資産
それぞれについて、具体的に解説していきます。
暗黙知→形式知へ
ナレッジマネジメントで重要なのが、「暗黙知」と「形式知」という2つの知識の形態です。
暗黙知とは、ベテラン社員が持つ経験則や、熟練した技能者の手作業のコツなど、言葉で説明しにくい知識のことです。例えば、優秀な営業担当者が持つ商談の進め方や、熟練した整備士が持つ機械の調整方法などが該当します。
一方の形式知とは、誰でも理解できるように文章や図表で表現された知識です。業務マニュアルや、会議の議事録、商品カタログなどがこれに当たります。
この暗黙知を形式知に変換することが、ナレッジマネジメントを活用する目的となります。具体的には、ベテラン社員の暗黙知を若手社員に伝えるため、作業手順をステップごとに細かく文書化したり、写真や動画で記録したりする取り組みです。
野球のコーチングを例に考えると、「もっと振り抜け」という抽象的な指示ではなく、「バットのグリップはここを握り、肘の角度はこうする」といった具体的な説明に置き換えることです。
このように暗黙知を形式知に変換することで、個人の経験やノウハウを組織全体で共有できるようになり、業務の効率化や品質の向上につながります。さらに、共有された知識を基に、新しいアイデアや改善策が生まれやすくなるのです。
SECIモデル
組織の知識はどのように生まれ、広がっていくのでしょうか。ナレッジマネジメントでは、この過程をSECI(セキ)モデルとして体系化しています。
最初のステップは「共同化」です。これは、チームメンバーが実務を通して経験を共有する段階です。例えば、新入社員が先輩社員の仕事ぶりを間近で見て学んだり、現場で一緒に作業したりする場面がこれに当たります。
次に「表出化」のステップがあります。ここでは、経験から得た気づきや発見を、誰にでもわかる形で表現します。具体的には、業務の手順書を作成したり、成功事例をレポートにまとめたりする活動です。
三つ目は「連結化」です。表現された知識を組み合わせて、新しい知識を生み出します。部署をまたいだプロジェクトで異なる視点を組み合わせたり、過去の事例を分析して新しいマニュアルを作成したりする過程です。
最後は「内面化」です。形式化された知識を実践を通じて身につけ、自分のものにします。マニュアルを読んで実際に作業してみたり、他部門の成功事例を自分の業務に応用したりする段階です。
このサイクルを繰り返すことで、組織の知識は螺旋状に発展していきます。重要なのは、これら4つのステップをバランスよく実施することです。SECIモデルを上手に活用することで、組織全体の知識レベルが継続的に向上していきます。
「場」
ナレッジマネジメントにおいて、知識が生まれ、共有される環境を「場」と呼びます。これは単なる物理的な空間だけでなく、人々が交流し、アイデアを交換する機会も含みます。
「場」には、様々な形態があります。対面での活動としては、顧客との商談、部門間のミーティング、現場での作業などがあります。また、デジタル上では、社内SNS、電子掲示板、データベースなどが「場」として機能します。
例えば、病院における「場」を考えてみましょう。診察室では医師と患者の対話から診療ノウハウが蓄積され、カンファレンスルームでは医療スタッフ間で治療方針が検討されます。電子カルテシステムも重要な「場」として、患者情報や治療記録を共有します。
ただし、「場」があるだけでは十分とはいえません。マニュアルだけを読んでも実践力は身につきにくいものです。重要なのは、その「場」で実際に経験を積み、他者と意見を交わしながら、知識を自分のものにしていくプロセスです。
効果的な「場」づくりのポイントは、以下の3つです。
1. 参加者が自由に意見を出せる雰囲気作り
2. 定期的な対話の機会の設定
3. デジタルツールの適切な活用
これらのポイントを意識して、「場」を整備し活用することで、組織内の知識は活発に循環し、新しい価値の創造につながっていきます。
知的資産
企業の競争力を支える「知的資産」もナレッジマネジメントの1つです。知的資産は、特許などの知的財産権だけでなく、組織に蓄積された様々な無形の資産を指します。
知的資産には多様な形態があります。例えば、社員一人一人の専門知識やスキル、部門間の連携体制、取引先との信頼関係、ブランドイメージなどです。これらは財務諸表には現れませんが、企業の成長を支える重要な要素です。
具体的な例を挙げてみましょう。熟練技術者の製造ノウハウ、営業部門が築いた顧客データベース、長年の実績で培われた企業評価、独自の人材育成プログラムなど、これらはすべて知的資産です。
経営者にとって重要なのは、自社の知的資産を把握し、戦略的に活用することです。これを「知的資産経営」と呼びます。たとえば、ベテラン社員のノウハウを若手に伝承するプログラムを作ったり、顧客との関係性を新商品開発に活かしたりする取り組みがこれに当たります。
知的資産は、日々の業務の中で生まれ、蓄積されていきます。知的資産を意識的に発見し、育て、活用することで、企業の持続的な成長が実現できるのです。特に現代のビジネス環境では、このような目に見えない資産の価値が、ますます重要になっています。
ナレッジマネジメント4つの手法
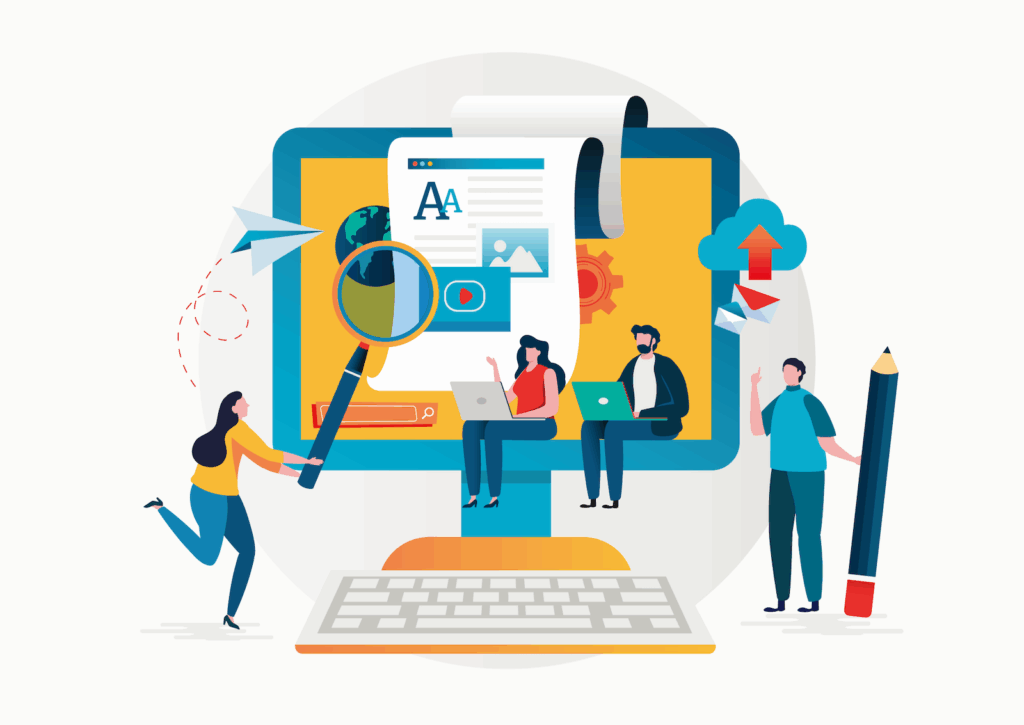
ナレッジマネジメントは、以下の4つの手法に分けられます。
- ベストプラクティス型
- 顧客知識共有型
- 専門知識共有型
- 経営資本・戦略策定型
それぞれについて具体的に解説していきます。
ベストプラクティス型
会社の成長に欠かせないのが、優秀な社員の持つ知見やノウハウを組織全体で共有することです。これを実現するのが「ベストプラクティス型」のナレッジマネジメントです。
優秀な営業社員が実践する効果的な商談の進め方や、顧客との信頼関係を築くヒアリング手法を明文化します。例えば、商談時の話題の順序、顧客の反応に応じた対応方法など、具体的な行動を記録します。
このように蓄積された実践的なノウハウは、新人からベテランまで誰もが活用できます。マニュアルには記載されていない実務での工夫点を共有することで、社員全体のスキルアップにつながります。
さらに、共有された知見をもとに各社員が業務に取り組むことで、新たな発見が生まれます。この発見を再び共有することで、組織のナレッジが継続的に増えていきます。
顧客知識共有型
顧客サービスの質を高めるために、顧客情報の一元管理も重要です。顧客知識共有型のナレッジマネジメントでは、個人情報から対応履歴まで、散在する情報を一箇所に集約します。
営業部門での商談内容、コールセンターでの問い合わせ対応、アフターサービスの記録など、部門を超えたナレッジが共有されれば、顧客とのコミュニケーションに齟齬が生じることもありません。例えば、営業担当者が提案した内容を、サポート担当者も正確に把握できます。
また、過去のトラブル対応事例を共有することで、同様の問題が発生した際に迅速な解決が可能になります。担当者不在時でも他のスタッフが適切な対応を取れるため、顧客満足度が向上します。
さらに、担当者の退職時にも詳細な引き継ぎ資料として活用できるため、業務の継続性が保たれます。顧客との信頼関係を長期的に維持するためにも、顧客知識共有型のナレッジマネジメントは重要です。
専門知識共有型
組織内に存在する専門的な知見を効率的に活用するには、専門知識共有型のナレッジマネジメントがあります。この手法では、社内の専門知識を体系的に整理し、必要な時にすぐ取り出せる状態にします。
具体的には、製品仕様書、技術資料、社内規定などの専門情報を一元管理します。また、各分野のエキスパート社員との連携体制を整備することで、専門的な課題が発生した際に素早く解決策を見出せます。
特に効果的なのが、顧客からの問い合わせ対応です。製品やサービスに関する質問とその回答を整理しておくことで、どの担当者でも正確な情報提供が可能になります。顧客対応の待ち時間が短縮され、サービス品質が向上します。
さらに、専門知識共有型のナレッジマネジメントは、新入社員の教育にも活用できます。体系化された専門知識を新入社員が学習することで、早期の成長につながります。
経営資本・戦略策定型
企業の持続的な成長には、社内外の知的資産を戦略的に活用することが不可欠です。経営資本・戦略策定型のナレッジマネジメントは、分散している知見を収集し、収益向上につなげる手法です。
この手法の特徴は、社内の技術やノウハウだけでなく、他社の成功事例も積極的に取り入れる点です。例えば、自社の製造技術と他社の販売戦略を組み合わせることで、独自の市場価値を創出できます。
また、業界内の成功事例を分析することで、自社の業務プロセスの改善点が見えてきます。その気付きを経営戦略に反映させることで、競争力を高められます。
蓄積した知的資産を経営判断に活用することで、的確な意思決定が可能になります。こうした経営資本・戦略策定型のナレッジマネジメントにより、市場環境の変化にも柔軟に対応できる組織を作ることができます。
ナレッジマネジメントの導入方法

ナレッジマネジメントを導入する際には、配慮すべき以下のポイントがあります。
- ナレッジマネジメントの目的を明確にする
- 共有したい情報をまとめる
- 目的にあったナレッジマネジメントツールを選定する
- 定期的に見直す
それぞれについて、具体的に解説していきます。
ナレッジマネジメントの目的を明確にする
ナレッジマネジメントを効果的に導入するには、まず目的を明確にすることが重要です。単に社内情報を集めるだけでは、業務改善には結びつきません。
導入の目的は具体的な数値目標として設定します。例えば「顧客対応時間を30%削減する」「新人の業務習得期間を3カ月短縮する」といった明確な指標を定めます。
また、この取り組みによって得られるメリットを全社員に伝えることも大切です。営業部門では商談成約率の向上、製造部門では不良品率の低下など、部門ごとの具体的なメリットを示します。
このようにナレッジマネジメントの目的と効果を明確にすることで、社員一人ひとりが「自分の仕事がよくなる」と納得感が得られます。その結果、情報共有への積極的な参加が期待でき、組織全体の底上げにつながります。
共有したい情報をまとめる
ナレッジマネジメントを成功させるには、共有すべき情報を適切に選別することが重要です。ただ情報を集めるだけでは、かえって業務効率を下げる結果になりかねません。
まず、現場の課題を丁寧に洗い出します。例えば「新人が商品説明で躓く」「クレーム対応に時間がかかる」といった具体的な問題点を特定します。この課題に対して、どんな情報があれば解決できるのかを検討します。
また、情報の優先順位も明確にします。即座に活用できる実践的な内容を優先的に共有し、理論的な内容は補足情報として位置づけます。
さらに、不要な情報の集約を防ぐため、共有基準を設定します。社員は迷わず必要な情報を共有でき、情報の質も保てます。
目的にあったナレッジマネジメントツールを選定する
ナレッジマネジメントの効果を最大限に引き出すには、適切なツール選びが重要です。紙のファイルやエクセル表では、情報の検索性や共有範囲に制限があり、せっかくの知見を活かしきれません。
最近は目的別に特化した多様なナレッジマネジメントツールが提供されています。例えば、営業情報共有には顧客管理機能が充実したもの、技術情報共有にはデータベース機能が優れたものといった具合です。
費用面では、利用人数や機能に応じて柔軟な料金プランを選べます。必要な機能だけを使用することで、無駄なコストを抑えられます。
多くのナレッジマネジメントツールは無料トライアル期間を設けています。実際の業務で使用してみて、検索のしやすさや入力の手間を確認することをお勧めします。使い勝手の良さは長期的な活用に直結します。
定期的に見直す
ナレッジマネジメントは、仕組みを構築しただけでは十分な成果は得られません。効果を最大化するには、定期的な見直しと改善が必要です。
具体的には、毎月の活用状況を確認します。例えば、共有された情報の質、アクセス数、実際の業務改善事例などを数値化して評価します。情報が古くなっていないか、必要な知見が不足していないかもチェックします。
また、ユーザーである社員からフィードバックを収集します。「検索しづらい」「入力の手間が多い」といった声は、システムの改善に活かします。
発見された課題は優先順位をつけて改善を進めます。小さな改善の積み重ねで、より使いやすく、より効果的なナレッジマネジメントへと進化させることができます。
ナレッジマネジメントを導入するメリット

ナレッジマネジメントを導入するメリットは、以下のようなものが挙げられます。
- 業務効率化
- 人材育成の効率化
- コスト削減
- 売上アップ
- 社員の離職率低下の防止
それぞれについて、具体的に紹介していきます。
業務効率化
企業内で蓄積された知識やノウハウを共有する仕組みであるナレッジマネジメントは、業務の効率化に大きな効果をもたらします。
企業には、業務のエキスパートとして活躍する従業員がいます。この従業員たちの持つ専門知識や業務の進め方を組織全体で共有することで、業務の進行スピードが向上します。
具体的な効果は、たとえば営業部門での成約率向上に表れます。経験豊富な営業担当者のセールストークのポイントを文書化し、新人社員と共有することで、営業成績の底上げにつながります。さらに、システム開発や財務など、専門性の高い業務でも、手順や注意点を共有することで、担当者が不在でも業務を滞りなく進められます。
ナレッジマネジメントを導入すると、業務の効率化だけでなく、仕事の質も向上します。個人の持つ優れたスキルを全体で共有することで、ミスの防止や作業時間の短縮が実現できます。
人材育成の効率化
企業における人材育成は、時間とコストがかかる重要な経営課題です。ナレッジマネジメントを活用すると、この人材育成を効率的に進められます。
一般的な企業では、新入社員が入社するたびに、上司や先輩社員が基礎から教育を行います。この方法では、教える側の負担が大きく、教える内容にもばらつきが生じます。
ナレッジマネジメントを導入すると、業務に必要な知識やスキルを体系的に整理できます。例えば、経理部門なら決算業務の手順書、営業部門なら商談の進め方といった実践的な知識を文書化します。
こうした取り組みにより、教育担当者は基礎的な説明に時間を取られることなく、個別の課題に集中できます。また、従業員は必要な時に必要な知識にアクセスできるため、自主的な学習も促進されます。
結果として、社員全体の業務スキルが向上し、会社全体の生産性アップにつながります。
コスト削減
経営課題の1つであるコスト削減。ナレッジマネジメントは、この課題解決に直接的な効果をもたらします。
企業内の知識やノウハウを共有し、業務の効率化が進むと、具体的な数字として表れる成果が出てきます。最も分かりやすい効果は、作業時間の短縮です。
従来なら3時間かかっていた業務が2時間で終わる、週に一度の定例会議が月一回で済むなど、時間の節約につながります。この時間短縮は、残業時間の削減という形で経費削減に直結します。
さらに、残業が減ることで、オフィスの電気代や空調費といった光熱費も抑えられます。また、社員の健康管理の面からも、残業削減は重要な意味を持ちます。
ナレッジマネジメントによる業務効率化は、経費削減と働き方改革の両方を実現する有効な手段となります。
売上アップ
ナレッジマネジメントの真の目的は、単なる知識共有ではありません。最終的なゴールは、企業の売上向上です。
多くの企業では、ナレッジマネジメントを「社内の知識を共有する仕組み」と捉えがちです。しかし、その本質は「売上を高める戦略的な取り組み」です。
例を見てみましょう。営業部門では、優秀な営業担当の商談プロセスを分析し、成功パターンを見出します。このパターンを他の営業メンバーと共有することで、チーム全体の受注率が向上します。
また、新人教育においても、体系化された教育プログラムにより、即戦力の育成が可能になります。営業力が強化され、売上増加につながります。
ナレッジマネジメントを導入しなければ、将来の利益機会を逃してしまう可能性が生まれます。企業の成長戦略としても、ナレッジマネジメントの活用は重要です。
社員の離職率低下の防止
企業における人材の定着は、組織の安定と成長に不可欠です。ナレッジマネジメントは、社員の離職率低下に貢献する有効な手段として注目されています。
その理由は、まず、拠点や部署を超えた情報共有を促進し、組織全体の一体感を醸成する点にあります。各部門が持つ知識やノウハウを共有することで、社員は自らの仕事が組織全体に貢献していることを実感しやすくなり、帰属意識が高まります。
また、新入社員にとっては、過去の成功事例や先輩社員の知識に容易にアクセスできるため、早期に業務を習得し、成長を実感できる環境が提供されます。質問しやすい環境を整備することで、不安や疑問を解消し、安心して業務に取り組むことができます。
さらに、ナレッジ共有を通して、社員は自身の貢献を可視化し、自己肯定感を高めることができます。これらの要素が複合的に作用することで、社員のエンゲージメントが向上し、結果として離職率の低下に繋がります。組織の一体感を高め、社員の定着を図るために、ナレッジマネジメントを戦略的に導入・活用することが重要です。
ナレッジマネジメントの成功事例

企業はナレッジマネジメントをどのように実践しているのでしょうか。ここでは以下の事例についてご紹介します。
- 富士フイルムビジネスイノベーション
- NTT東日本法人営業本部
- 国土交通省
富士フイルムビジネスイノベーション
ナレッジマネジメントの成功事例として、富士フイルムビジネスイノベーションの「何でも相談センター」が注目されています。
この取り組みの特徴は、社員からの業務相談に対して、必ずダイレクトな回答を提供する点です。相談内容を部署間で転送することなく、センターが責任を持って解決策を提示します。
例えば、営業担当者が商談で行き詰まった際、センターに相談すると具体的なアドバイスがもらえます。技術的な質問には専門家の意見を、契約に関する疑問には法務部門の見解を、迅速に提供します。
この仕組みにより、2つの効果が生まれました。1つは、問題解決までの時間が大幅に短縮されたこと。もう1つは、相談内容とその解決策が社内の知的財産として蓄積されていくことです。
結果として、業務の質が向上し、社員の成長にもつながっています。
NTT東日本法人営業本部
NTT東日本法人営業本部では、リアルとバーチャルを組み合わせた独自のナレッジマネジメント環境を構築しています。
オフィス空間は、目的別に4つのゾーンに分かれています。通常業務を行う「ベースゾーン」、アイデア創出のための「クリエイティブゾーン」、集中作業のための「コンセントレーションゾーン」、そして休息のための「リフレッシュゾーン」です。
デジタル面では、社員全員が個人ホームページを持ち、日々の業務で得た知見を共有します。各部署もホームページを運営し、組織的な知識の蓄積を進めています。
この2つの取り組みにより、部署を超えた活発な交流が生まれ、新たな価値創造につながっています。社員間の知識共有も進み、業務効率が大幅に向上しました。
物理的な空間とデジタルツールを融合させた先進的な取り組みとして、多くの企業の参考になるでしょう。
国土交通省
行政機関におけるナレッジマネジメントの実践例として、国土交通省の防災ナレッジ共有システムが注目を集めています。
災害発生時には、迅速かつ的確な判断と行動が求められます。しかし、職員の防災対応経験には個人差があり、これまでは統一された対応が難しい状況でした。
この課題を解決するため、国土交通省はイントラネット用ブログツールを活用した知識共有システムを導入しました。このシステムでは、過去の災害対応事例や、ベテラン職員の経験則が分かりやすく整理されています。
職員は必要な時に必要な情報にアクセスでき、防災対応のノウハウを効率的に学べます。新任職員でも、システムに蓄積された知識を活用することで、適切な対応が可能になります。
この取り組みは、行政機関におけるナレッジマネジメントの有効性を示す好例といえるでしょう。
ナレッジマネジメントツールを導入する注意点

ナレッジマネジメントを推進するには、ツールを導入するのもおすすめです。ナレッジマネジメントツールを導入する際には、以下の点に注意しましょう。
- 使用する目的を明確にする
- 実際に社員が操作性を確認する
- ナレッジを提供したくなる仕組みを作る
- ナレッジマネジメントを定着させる
それぞれについて、次から具体的に解説していきます。
使用する目的を明確にする
組織の成長に欠かせないナレッジマネジメント。その導入には明確な目標設定が必要です。単にツールを入れるだけでは、社内の知識共有は進みません。大切なのは、このシステムを通じて何を実現したいのかを明確にすることです。
例えば、新人研修の効率化や、営業ノウハウの蓄積、部門間の情報共有促進など、具体的な目標を定めましょう。こうした取り組みで、社員一人ひとりがナレッジマネジメントの意義を理解し、自分に関係する取り組みとして認識できます。
また、経営陣は導入による具体的な効果を示すことで、社員の積極的な参加を促せます。「月間の問い合わせ対応時間が20%削減された」といった数値目標を設定すれば、社員の意欲も高まります。
目的と効果を組織全体で共有することで、ナレッジマネジメントツールの導入は形だけの取り組みではなく、実効性のある取り組みへと進化していきます。
ナレッジマネジメントツールの導入目的の例
| 目的 | 詳細 |
| 1. 知識・情報の共有と活用促進 | |
| 属人化の解消 | 特定の担当者しか知らない業務知識やノウハウを可視化し、共有することで、担当者が不在の場合でも業務を円滑に進められるようにする。 |
| 情報へのアクセス向上 | 必要な情報を迅速かつ容易に探し出せるようにすることで、業務効率を向上させ、意思決定を迅速化する。 |
| 知識の再利用 | 過去の成功事例や失敗事例を共有し、類似の課題が発生した場合に、過去の知識を有効活用することで、効率的な問題解決を促進する。 |
| 組織全体の学習能力向上 | 個人やチームの知識を組織全体で共有し、学び合う文化を醸成することで、組織全体の知識レベルと競争力を高める。 |
| 暗黙知の形式知化 | 個人の経験や勘に基づいた暗黙知を、形式知として文書化・共有することで、組織全体の知識資産として活用できるようにする。 |
| 2. コミュニケーションとコラボレーションの促進 | |
| 部門間連携の強化 | 異なる部門間で情報を共有し、意見交換を活発化することで、組織全体の連携を強化し、一体感を醸成する。 |
| プロジェクトチームの円滑な運営 | プロジェクトに関する情報を一元管理し、進捗状況や課題を共有することで、プロジェクトを円滑に進める。 |
| リモートワーク・分散型チームでの連携 | 場所に依存しない情報共有とコミュニケーションを実現し、リモートワークや分散型チームでの連携を円滑にする。 |
| ナレッジワーカー同士の交流促進 | 各自の専門知識や経験を共有し、互いに刺激し合うことで、新たなアイデアやイノベーションを生み出す。 |
| 3. 業務効率化と生産性向上 | |
| 業務プロセスの標準化 | ベストプラクティスを共有し、業務プロセスを標準化することで、業務効率を向上させ、属人化による品質のばらつきを抑える。 |
| 問い合わせ対応の効率化 | よくある質問とその回答をナレッジとして蓄積し、社員が自己解決できる範囲を広げることで、問い合わせ対応にかかる時間と手間を削減する。 |
| 新人教育の効率化 | 新入社員が業務に必要な知識を迅速に習得できるよう、研修資料やマニュアルなどを一元管理し、教育コストを削減する。 |
| 情報探索時間の短縮 | 必要な情報を迅速に探し出せるようにすることで、情報探索にかかる時間を短縮し、業務効率を向上させる。 |
| 4. 組織の競争力強化 | |
| 変化への迅速な対応 | 常に最新の情報を共有し、変化の兆候を早期に捉えることで、市場の変化に迅速に対応できる組織を作る。 |
| イノベーションの創出 | 異なる分野の知識やアイデアを組み合わせることで、新たな製品やサービス、ビジネスモデルを創出する。 |
| 顧客満足度向上 | 顧客からのフィードバックを分析し、製品やサービスの改善に役立てることで、顧客満足度を向上させる。 |
| 組織の知的資産の最大化 | 組織が持つ知識を最大限に活用し、企業の競争優位性を高める。 |
| 5. その他の目的 | |
| 従業員エンゲージメントの向上 | 知識共有を通じて、従業員の成長を促し、貢献意欲を高めることで、エンゲージメントを向上させる。 |
| 組織文化の醸成 | 知識を共有し、互いに学び合う文化を醸成することで、オープンで協力的な組織文化を育む。 |
| コンプライアンス遵守 | 法律や規制に関する情報を共有し、従業員のコンプライアンス意識を高める。 |
| リスク管理 | 過去のトラブル事例を共有し、リスクを早期に発見し、未然に防ぐ体制を構築する。 |
実際に社員が操作性を確認する
効果的なナレッジマネジメントの実現には、社員が日常的に使いたくなるツールの選定が重要です。画面構成が複雑だったり、データの入力に時間がかかったりするツールは、いずれ使われなくなってしまいます。
ナレッジマネジメントツール選びのポイントは、実際に使う社員の意見を取り入れることです。多くのナレッジマネジメントツールが無料トライアル期間を設けているため、導入前に複数の部署で試用することをお勧めします。営業部門では外出先からの入力のしやすさ、管理部門では検索機能の使い勝手など、部署ごとの業務特性に合わせた評価が必要です。
また、社員のITスキルレベルも考慮に入れましょう。20代のデジタルネイティブ世代と50代のベテラン社員では、望ましい操作性が異なります。世代を超えて使いこなせるナレッジマネジメントツールを選ぶことで、全社的な活用が進みます。
トライアル期間中は、実際の業務データを使った検証を行い、社員からのフィードバックを丁寧に集めることが、適切なナレッジマネジメントツール選定につながります。
ナレッジマネジメントツールの操作性に関する評価ポイント
| カテゴリ | 評価ポイント | 詳細 |
| 1. インターフェースの分かりやすさ | 直感的なデザイン | メニューやボタンの配置が論理的で、初めて使う人でも迷わず操作できるか。アイコンが意味を理解しやすく、視覚的に操作をサポートしているか。デザインがシンプルで、情報過多になっていないか。 |
| レスポンシブデザイン | PC、タブレット、スマートフォンなど、異なるデバイスで快適に表示・操作できるか。画面サイズに合わせてレイアウトが適切に調整されるか。 | |
| 多言語対応 | グローバル展開している企業や、多国籍のメンバーがいるチームで利用する場合、対応言語の種類と質は重要。 | |
| 2. コンテンツの作成・編集のしやすさ | エディターの使いやすさ | テキストの装飾(太字、斜体、リストなど)が簡単に行えるか。画像の挿入や動画の埋め込みがスムーズに行えるか。- 表や図の作成が直感的か。テンプレート機能が充実しているか(記事の形式を統一できるか)。 |
| バージョン管理機能 | 過去の編集履歴を確認できるか。- 誤った編集を元に戻せるか。複数人で同時に編集する場合、競合を避ける仕組みがあるか。 | |
| ドラッグ&ドロップ操作 | ファイルやフォルダのアップロード、記事の並び替えなどがドラッグ&ドロップで簡単に行える。 | |
| プレビュー機能 | 編集中のコンテンツがどのように表示されるか、リアルタイムで確認できるか。 | |
| 3. ナレッジの検索・閲覧のしやすさ | 検索機能 | キーワード検索、タグ検索、カテゴリ検索など、多様な検索方法に対応しているか。検索結果が精度高く、関連性の高い情報が上位に表示されるか。- 検索対象を絞り込む機能があるか(期間、作成者など)。全文検索に対応しているか(ドキュメント内のテキストも検索できるか)。 |
| 閲覧性 | 記事の構造が分かりやすく、必要な情報にすぐアクセスできるか。関連情報をリンクで辿れるか。- コンテンツの表示速度は快適か。 | |
| フィルタリング機能 | カテゴリ、タグ、作成者などで絞り込んでコンテンツを表示できるか。 | |
| お気に入り機能 | よく見るコンテンツを保存しておけるか。 |
ナレッジを提供したくなる仕組みを作る
企業の貴重なナレッジは、多くの場合、第一線で活躍する優秀な社員が持っています。しかし、彼らは日々の業務で多忙を極め、知識やノウハウの共有に時間を割くことが難しい状況です。
このハードルを下げるには、具体的な施策が必要です。例えば、移動時間を活用できるようタブレット端末を支給し、移動や待ち時間にナレッジを入力できる環境を整備します。また、ナレッジ共有を評価項目に組み込み、人事評価制度に反映させることも効果的です。
特に重要なのは、成果主義一辺倒の評価から脱却することです。売上や利益だけでなく、後輩の育成やチーム全体の生産性向上にも目を向けた評価基準を設けましょう。
さらに、ナレッジマネジメントをリードする専任の担当者を配置し、定期的な情報発信や優れた投稿の表彰制度を設けることで、社員の積極的な参加を促せます。
ナレッジマネジメントを定着させる
優れたナレッジマネジメントツールも、実際に活用されなければ意味がありません。定着化のカギは、導入前から運用後までの一貫した支援体制を整えることです。以下に具体的な例を紹介します。
導入前
- 現状把握と目標設定:
- 今のナレッジ共有の問題点や課題を洗い出す。
- ナレッジマネジメントで達成したい目標を具体的に決める。
- 戦略と準備:
- どんなナレッジを、どう共有するかの方針を決める。
- 担当者を決めて、予算を確保する。
- 使うシステムを選び、導入計画を立てる。
導入時
- システム導入とルール決め:
- システムを導入し、初期設定を行う。
- ナレッジ登録や利用に関するルールを作る。
- 従業員への教育(実践重視):
- 全社員向けの基本操作研修を実施: 単なる機能説明ではなく、実際の業務データを使った実践的な内容で理解度を高める。
- 部署ごとの活用事例を共有: 具体的な業務改善につながる使い方を提案する場を設ける。
運用時
- 運用とサポート:
- システムの利用状況をチェックし、問題があれば対応する。
- ナレッジ登録を促し、古くなった情報を更新する。
- 専任のナレッジマネジメント推進担当者を配置: 日常的な質問や相談に対応できる体制を作り、社員の不安を解消する。
- 効果測定と改善:
- 目標が達成できているかを確認し、改善点を見つけて修正する。
- 定期的なフォローアップを実施: 月1回のナレッジ活用報告会を開催し、優れた活用事例を共有する。
ポイント
- 段階的な導入: 小さく始めて、徐々に拡大していく。
- 従業員の巻き込み: 現場の意見を聞きながら進める。
- 継続的な改善: 運用しながら、常に改善を繰り返す。
- 実践的な研修: 実際の業務データを使った研修で理解度を高める。
- サポート体制: 専任担当者の配置と定期的な報告会で利用を促進する。
ナレッジマネジメントに有効なツール

現在ナレッジマネジメントツールは数多く存在します。そこでここでは、おすすめのナレッジマネジメントに有効なツールを6つご紹介します。特徴や価格面などを参考に、自社に見合ったツールを検討してください。
- DocBase
- flouu
- QuickSolution
- esa
- Knowledge Explorer
- NotePM
DocBase
【DocBaseの特徴】
- 導入件数1万件以上
- 業界初ハイブリッドエディターで、マークダウンとリッチテキスト両方利用可能
- マルチデバイスや外部ツール連携に対応可能
- 直感的な操作感で利用に迷わない
- ISO27001の認証取得済
- 優れたコストパフォーマンス
DocBaseは、チームのナレッジを効率的に一元管理・共有するナレッジマネジメントツールです。社内Wikiだけでなく、マニュアルや設計書、日報などの作成機能も付いており、さまざまな情報を作成・共有できます。
マークダウンとリッチテキストのハイブリッドエディターを採用しています。また、マルチデバイスにも対応済みであり、PCやスマートフォン、タブレットのいずれからでも利用可能です。操作も直感的にできるため、初めて操作する人でも、マニュアルが手離せないという可能性は低いでしょう。
セキュリティ性も高く、ISO27001の認証を取得済であるため、安心して利用できます。その一方でコスト面はリーズナブルに設定されており、ひとりあたり214円で情報共有ツールを導入可能です。また、30日間の無料トライアルもあるため、ぜひ導入前に利用し、使用感を確かめてみてください。
【DocBaseの費用・料金プラン】
| 無料トライアル | スターター | ベーシック | レギュラー | ビジネス | |
| 料金 | 0円 | 990円/月 | 4,950円/月 | 9,900円/月 | 21,450円/月 |
| ユーザー数 | 無制限 | 3人 | 10人 | 30人 | 100人 |
| ストレージ | 無制限 | 3GB | 10GB | 30GB | 100GB |
flouu
【flouuの特徴】
- AWSを利用した高いセキュリティ
- ISO27001の認証取得
- さまざまなサービスとの連携が可能
flouuは、チーム内の情報共有を支援するツールですが、議事録作成にも利用できます。リアルタイムでの編集やコメントが可能で、会議中にその場で議事録を完成させられるでしょう。
音声を用いた議事録作成はできませんが、多くの参加者のメモや実際の会議資料を活用して議事録を作成します。手間がかかるのは仕方ない側面はありますが、さまざまなサービスと連携できるため、議事録作成の手間を削減します。
【flouuの料金プラン】
| 基本料金 | |
| 料金 | 660円/月※1ユーザーあたり |
| ユーザー数 | 無制限 |
| ストレージ | 10GB |
※別途「セキュリティオプション」「OCRオプション」を追加可能
QuickSolution
【QuickSolutionの特徴】
- 社内ファイルサーバからクラウドまで社内外の情報を横断検索
- 複雑な日本語や画像内の文字情報も検索可能
- 高速・高精度な検索+ChatGPT連携で欲しい情報にすぐアクセス
QuickSolutionは、社内情報を横断検索できる企業内検索システムです。ファイルサーバーからクラウドまで、様々な形式のファイルの中身を、アクセス権限を考慮して一括検索。複雑な日本語や画像内の文字も、セマンティック検索や画像OCRで読み取り、高速・高精度に検索します。
ChatGPT連携で欲しい情報にすぐアクセスでき、純国産ならではの安心サポートも魅力。AI搭載で、利用するほど検索精度が向上します。情報検索の無駄をなくし、業務効率化を支援します。
【QuickSolutionの費用・料金プラン】
QuickSolutionの価格は、サーバーライセンス で、利用ユーザー数には依存せず、ライセンスの種類とモデル(検索対象データの規模)に応じて価格が決まります。ライセンス価格は、250万円(税抜)〜 となります。
esa
【esaの特徴】
- 「情報を育てる」がコンセプト
- 入力補助機能で作成をサポート
- 各種外部ツールとの連携も可能
- 最長2か月の無料利用が可能
esaは「情報を育てる」がコンセプトの社内Wikiツールです。ナレッジ共有ツールとしても利用できます。コンテンツは完成してから公開するものではなく、途中でも公開してしまい、完成まで皆でブラッシュアップすれば良いというのがesaの考え方です。
社内Wikiとして利用できる一方、コミュニケーション性も高く、チャット機能などを利用したやり取りも可能です。社内Wikiだけでなく、カジュアルにやり取りできる環境もツールに求めたい場合にピッタリです。
【esaの費用・料金プラン】
| 無料 | 通常 | |
| 料金 | 無料 | 1ユーザー500円/月 |
| 期間 | チーム作成月から2か月後の月末まで | 無料期間終了後~ |
Knowledge Explorer
【Knowledge Explorerの特徴】
- AIが参考資料をプッシュ通知でお知らせ
- 類似テーマ検索機能
- AI を活用した検索機能
Knowledge Explorerは、AIで社内情報活用を促進するナレッジマネジメント支援システムです。特徴は、①AIが作成中の文書を解析し、参考資料をプッシュ通知する機能、②キーワードなしで類似テーマの文書を検索できる機能、③文書内の重要語をAIが判断し、関連知識を提示する機能の3点です。従来のシステムのように情報共有だけでなく、ユーザーの「気づき」を促し、知識の獲得・処理を支援します。これにより、業務効率化やナレッジの利活用を促進し、企業全体の成長を支えます。
【Knowledge Explorerの費用・料金プラン】
要お問い合わせ
NotePM
【NotePMの特徴】
- 社内Wikiや社内FAQとして活用可能
- 利用状況を分析レポートから把握できる
- 全文検索やダッシュボードカスタマイズなどさまざまな機能が搭載されている
- セキュリティ性が高く、医療機関や金融機関に導入実績有り
NotePMは、社内の情報共有やナレッジ管理を効率的に行える社内Wikiツールです。マニュアル作成や社内FAQ作成ツールとしても、利用できます。
テンプレート機能や下書き機能、ダッシュボードカスタマイズ機能など、ツール利用側に魅力的な機能が多数搭載されており、ストレスフリーに情報共有が可能です。加えて、コメント機能やいいね機能などSNSに似た機能も有しているため、コミュニケーション促進の効果も見込めます。
【NotePMの費用・料金プラン】
| プラン8 | プラン15 | プラン25 | プラン50 | プラン100 | プラン200~ | |
| 料金 | 5,280円/月 | 9,900円/月 | 16,500円/月 | 33,000円/月 | 66,000円/月 | 132,000円/月 |
| ユーザー数 | 8人まで | 15人まで | 25人まで | 50人まで | 100人まで | 200人まで |
| ストレージ | 80GB | 150GB | 250GB | 500GB | 1TB | 2TB |
ナレッジマネジメントを利用して業務効率化を図ろう

ナレッジマネジメントは、組織の知識やノウハウを戦略的に活用し、企業価値を高める重要な経営手法です。ナレッジマネジメント導入により、業務効率化、人材育成の促進、コスト削減、売上向上など、具体的な成果が期待できます。
成功のポイントは、目的の明確化、適切なナレッジマネジメントツール選定、社員の積極的な参加を促す仕組みづくりにあります。最新のナレッジマネジメントツールを活用し、部門を超えた知識共有を実現することで、組織全体の生産性向上が図れます。
特に重要なのは、単なる情報共有の場としてではなく、組織の知恵を集めて新しい価値を創造するプラットフォームとして活用することです。
DocBaseはナレッジマネジメントにおすすめのツールです。誰でも簡単に作成、編集、共有でき、ファイルサーバーや社内WIkiの代わりとして利用いただけます。無料でお試し可能ですので、ぜひご検討ください。
DocBaseの導入によるナレッジマネジメント事例
| 企業名 | 活用方法 | 効果 | 事例URL |
| 株式会社アールキューブ | 「アールキューブ版ウィキペディア」として活用。提携会場DB、施行報告書、パートナー情報を記録。 | 全員が同じクオリティのサービスを提供可能に。 | 詳しく見る |
| 株式会社オイシックス・ラ・大地 | 情報の一本化。議事録や資料をDocBaseにのみ投稿。 | 欲しい情報が見つかるようになった。 | 詳しく見る |
| 株式会社モバイルファクトリー | WikiよりもDocBaseを使い、情報を共有。 | 投稿数が4倍に増加。 | 詳しく見る |
| 株式会社インフラトップ | DocBaseへの投稿を評価制度に組み込み。 | 社員の投稿が促進。 | 詳しく見る |
| 株式会社キュア・アップ | DocBaseを「メモ」と呼び、気軽に書ける雰囲気に。 | 投稿数が増加。 | 詳しく見る |
| 株式会社サイバーエージェント宣伝本部 | 議事録をDocBaseで管理。 | 検索性が向上。 | 詳しく見る |





