情報整理で仕事効率UP!デジタル時代に必須の誰でもできる簡単整理術
最終更新日:2025年4月4日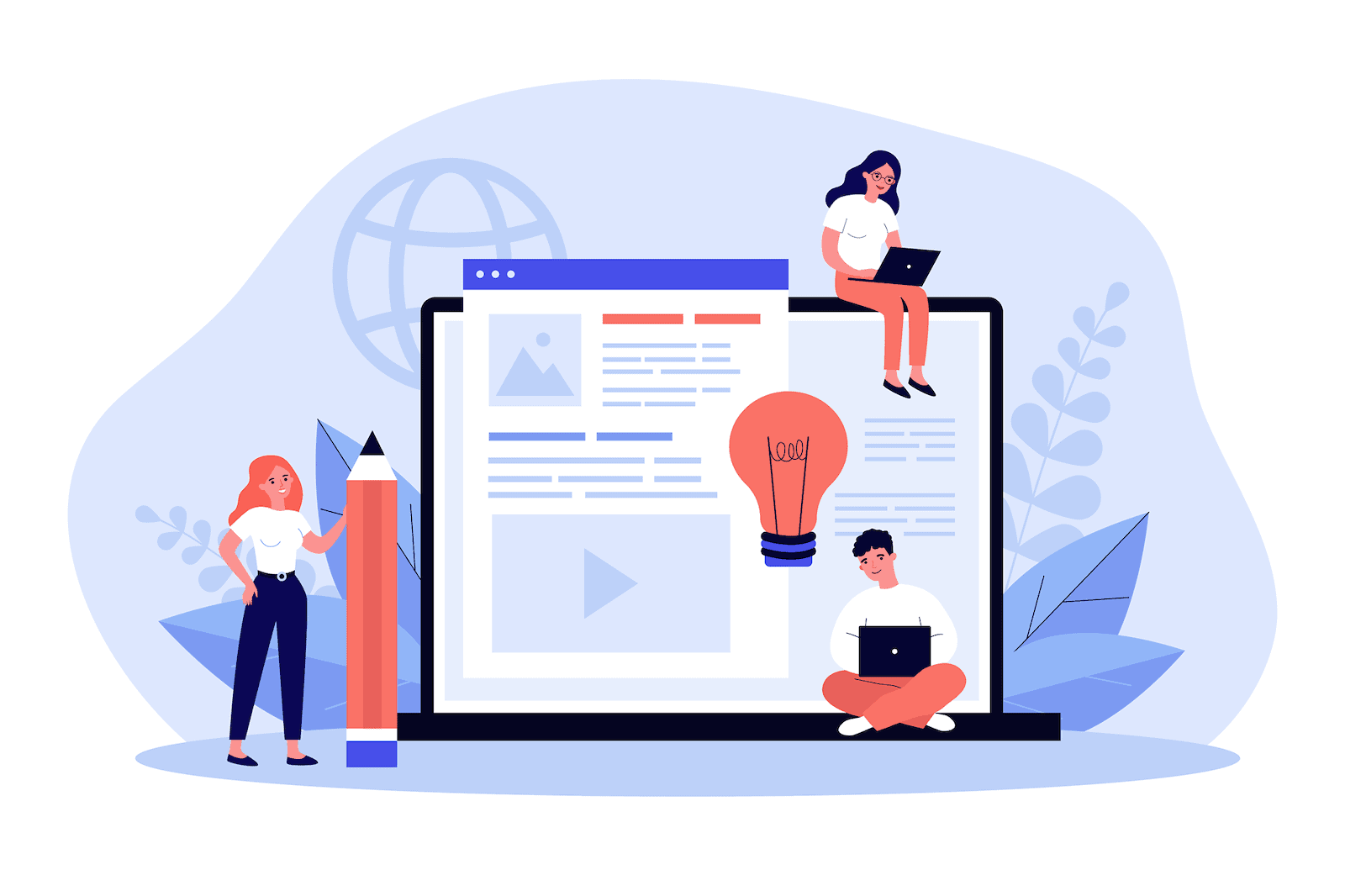
「この資料はどこにあったっけ… …」「同じような情報がいろいろなところに散らばっている… …」。デジタル時代の今、私たちはたくさんの情報に囲まれて仕事をしています。メール、書類、メモ、データなど重要な情報が整理されていないと、必要な時にすぐ情報が取り出せず、貴重な時間を無駄にしてしまいがちです。
そんな状況を解決するのが情報整理のノウハウ。この記事では、情報整理の基本から実践的なテクニックまで、わかりやすくお伝えします。
情報が整理されれば、あなたの仕事は確実にスピードアップできるはずです。また、情報を整理することで、チームの生産性も向上します。必要な情報がすぐに見つかり、知識が効率的に共有され、新しいアイデアも生まれやすくなります。この記事で情報整理の第一歩を踏み出し、あなたの職場で実践できるノウハウを見つけてください!
【この記事を読んでわかること】
- 情報整理とは、散在する資料やデータを一元化し、活用しやすい形で共有して、社員全体の理解と情報活用を促進すること
- 情報整理のメリットは、情報の価値を高めて業務の効率化や生産性向上を実現し、社内の情報を誰もが活用できる資産に変えられること
- 効果的な情報整理には、目的を明確にして目的別に情報を分類することが重要。活用方法を考えた上で、ルールを統一する
- 情報整理を効果的に行うためには、ロジックツリーの使用、社員からのフィードバック収集および適切なツールの活用が重要
目次
情報整理とは?

情報整理とは、集めた情報を使いやすい形に整えることです。例えば、企業の中には研修の資料やマニュアルなど、たくさんの大切な情報があります。これらがバラバラな状態で保管されていると、必要な時にすぐに見つけられず、とても不便です。
整理された情報は、自分の理解を深めるだけでなく、周りの人にも伝えやすくなります。また、整理して新たな気づきが生まれることもあります。特に企業では、情報の整理がスムーズな業務のために欠かせません。
しかし、多くの企業では貴重な情報が紙やパソコンの中に散らばったままになっています。せっかくの情報も、整理されていないと宝の持ち腐れになってしまうのです。
情報整理は、企業の成長に必要不可欠な取り組みといえます。まずは手元にある情報を見直し、整理することから始めてみましょう。
情報整理するメリットとは?

情報整理を行うメリットには、以下のような点が挙げられます。ここではそれぞれについて詳しく解説していきます。
- 必要な情報を資産化できる
- 業務引き継ぎが簡単になる
- 業務効率が上がる
必要な情報を資産化できる
情報を集めるのは簡単ですが、それを生かすことは意外と難しいものです。せっかく集めた情報も、整理されていないと、使いづらい状態になってしまいます。
では、そもそもなぜ情報整理が大切なのでしょうか?それは、整理された情報が企業の大切な「資産」となるからです。きちんと整理された情報は、必要な時にすぐに取り出せて、誰でも使える状態になります。
現代は情報があふれる時代です。ネットで検索すれば、すぐにたくさんの情報が手に入ります。でも、ただ集めるだけでは意味がありません。本当に必要な情報を選び、整理することで、初めて価値が生まれるのです。
整理された情報が増えれば増えるほど、企業の価値も高まっていきます。それは、その情報を使って新しい価値を生み出せるからです。
情報整理は、単なる片付けではありません。企業の未来を支える大切な投資なのです。
業務引き継ぎが簡単になる
「前任者が辞めてしまって、仕事のやり方がわからない……」。こんな経験はありませんか?多くの企業で、マニュアルや手順書はあるものの、それぞれの社員がバラバラに保管していて、なかなか見つからないということがよくあります。
特に困るのが、引き継ぎの時です。前任者の持っていた知識やノウハウが上手く伝わらないまま、後任者が一からやり方を学ばなければならない……。これでは時間もかかるし、効率も悪くなってしまいます。
こうした「仕事のやり方を1人だけが知っている状態」を解決するのが、情報整理の役割でもあります。部署やチームの大切な情報を、みんなが使える形にまとめることで、誰でも必要な時に必要な情報を見つけられるようになります。
整理された情報があれば、新しく担当になった人も早く仕事を覚えることができます。引き継ぎもスムーズになり、業務の質も保ちやすくなるのです。
情報整理は、チームの力を高める大切な取り組みです。みんなで協力して、使いやすい情報の整理を目指していきましょう。
業務効率が上がる
仕事をしていて「必要な情報がすぐに見つからない」「たくさんの情報の中から何を使えばいいかわからない」と感じることはありませんか?こうした悩みを解決してくれるのも、情報整理です。
情報を整理する過程で、大切な発見があります。それは「本当に必要な情報」と「そうでない情報」が見えてくることです。不要な情報を整理して、必要なものだけを残すと、仕事がグッとスムーズになります。
例えば、探し物をするときを想像してみてください。きれいに整理された引き出しなら、すぐに欲しいものが見つかりますよね。情報も同じです。整理されていれば、必要な時にすぐに情報が見つけられて、仕事の効率もグンとアップします。
実は情報整理を行うだけでも、仕事の進め方が良くなっていきます。なぜなら、整理することで「何が必要で、何が不要か」が明確になるからです。
まずは身近な情報から整理を始めてみましょう。きっと、仕事がもっと楽しくなるはずです。
効果的な情報整理の方法とは?

ただ漠然と情報整理を行っても効果は見込めません。そこで、知っておくと役に立つ効果的な情報整理の方法を4つ紹介します。
- 情報整理する目的を明確にする
- 情報取得の範囲を決めて分類する
- 情報整理後のイメージを書き出しておく
- 整理のルールを統一する
情報整理する目的を明確にする
「とりあえず情報を集めて整理してみよう」——。こんな風に始めても、なかなかうまくいきません。情報整理を成功させるコツは、まず「なぜ整理するのか」という目的をはっきりさせることです。
目的が明確になれば、どんな情報を集めればいいのか、自然と見えてきます。例えば「部署内で知識を共有したい」という目的なら、みんなが使える形で情報整理することを考えます。「特定の業務に役立てたい」なら、その業務に関連する情報を重点的に集めることになります。
また、目的がはっきりしていれば、情報の重要度も判断しやすくなります。「これは今すぐ必要な情報」「これは後で使う可能性がある情報」というように、優先順位をつけられるようになるのです。
整理の目的を決めることは、地図を手に入れるようなものです。目的地がわかれば、そこまでの道筋も見えてきます。
情報整理を始める前に、まずは「なぜ整理するのか」をチームで話し合ってみましょう。きっと、より良い情報整理への第一歩となるはずです。
情報取得の範囲を決めて分類する
企業には、顧客データ、営業資料、社内の手順書などさまざまな情報があふれています。これらをごちゃ混ぜにしていては、必要な時に情報をすぐ見つけられません。そこで大切になるのが、情報の分類です。
分類のコツは、まず範囲を決めることです。例えば「お客様に関する情報」「業務の手順に関する情報」といった具合です。そして、それぞれの分類に合わせてフォルダを作り、情報を整理していきます。
ここで気をつけたいのは、情報が多すぎると探すのに時間がかかってしまうこと。「本当に必要?」と自問しながら、不要な情報は整理対象から外しましょう。
分類することで、どんな情報があるのか、全体が見えやすくなります。引き出しにラベルを貼るように、情報の居場所がはっきりしてきます。
初めは少し手間に感じるかもしれません。でも、情報がきちんと分類されれば、みんなが使いやすく、仕事もスムーズになります。
情報整理後のイメージを書き出しておく
家を建てるときにまず設計図を描くように、情報整理にも全体像を描く必要があります。「情報を整理した後、どんな状態にしたいか」という完成イメージを最初に描くことで、整理がぐっとスムーズになります。
全体像が見えていないまま情報整理を始めると、途中でやり直しが必要になったり、使いづらい状態になったりします。そこで大切なのが、最終的な活用方法から逆算して考えることです。
例えば「誰でも3クリック以内に必要な情報が見つかる」「部署ごとに関連情報がまとまっている」といった具体的なイメージを書き出してみましょう。どんなカテゴリ分けが必要か、どんなフォルダ構成にすべきかが見えてきます。完成イメージを共有すれば、チームのみんなで同じ目標に向かって進めることもできます。
情報整理を始める前に、少し時間をかけて設計図を描いてみましょう。きっと、より良い情報整理への道しるべとなるはずです。
情報整理のイメージの例
- 「タグ付け・メタデータの活用」: 文書やファイルに適切なタグやメタデータを付与することで、検索性を向上させる。(例:プロジェクト名、担当者、作成日、関連部署などを付与)
- 「アクセス権限の明確化」: 情報へのアクセス権限を明確にすることで、必要な情報にスムーズにアクセスできるようにする。(例:部署内は全員アクセス可能、機密情報は特定のメンバーのみアクセス可能)
- 「情報の鮮度管理」: 情報が常に最新の状態に保たれるように、定期的な見直しと更新を行う。(例:半年に一度、部署内のドキュメントを見直し、不要なものは削除、古い情報は更新)
- 「情報の一元管理」: 複数の場所に散在している情報を、一箇所に集約して管理する。(例:プロジェクトに関する情報を、プロジェクト管理ツールに集約)
- 「情報の階層化」: 情報を整理しやすいように、適切な階層構造で分類する。(例:プロジェクト > フェーズ > タスク > ドキュメント)
- 「テンプレートの活用」: 定型的な情報(議事録、報告書など)は、テンプレートを活用することで、情報の形式を統一する。
- 「情報の可視化」: 情報をグラフや図表などで可視化することで、理解を促進する。(例:売上データをグラフ化し、進捗状況を把握しやすくする)
- 「情報のオーナーシップの明確化」: 各情報について、責任を持つ担当者を明確にする。(例:ドキュメントの更新担当者を明記する)
整理のルールを統一する
情報整理で大切なのは、誰が見てもわかりやすい「共通のルール」です。ファイルの名前の付け方や保存場所がバラバラでは、せっかく整理しても混乱を招いてしまいます。
例えば「【2024年1月】営業報告書」「【20240115】議事録」のように、日付や種類が一目でわかる名前を付ければ、中身を開かなくても概要がわかります。こうしたルールを決めておくことで、誰が情報を追加しても同じ基準で整理できます。
特に気をつけたいのは、いつの情報なのかがわかるようにすること。「先月の資料はどこ?」「去年のデータはある?」といった探し物に、すぐに対応できるようになります。
ルール作りは、交通ルールのようなもの。みんなが同じルールに従うと、情報の流れがスムーズになります。最初は慣れるまで少し時間がかかるかもしれませんが、続けることで大きな効果を生み出します。
情報整理のコツとは?

情報整理を上手に実践していくにあたっては、以下のようなコツを知っておくと、よりスムーズになります。
- ロジックツリーを使う
- 社員からフィードバックを受ける
- ツールを活用する
それぞれについて具体的に解説していきます。
ロジックツリーを使う
たくさんの情報が複雑に絡み合っているとき、どうやって整理すればいいのでしょうか? そんな時に役立つのが「ロジックツリー」という方法です。
ロジックツリーは、情報を木の枝のように分けていく整理法です。例えば「営業力アップ」という目標があれば、その下に「商品知識」「接客スキル」「市場理解」といった要素を枝分かれさせていきます。
この方法の良いところは、情報同士のつながりが見えやすくなること。それぞれの情報がどんな関係にあるのか、全体像を把握しやすくなります。特に、大小さまざまな情報が混在している時に効果を発揮します。
また、ロジックツリーは他の人との共有にも便利です。図で表現されているので、「この情報とあの情報はこんな風につながっている」と、直感的に理解できます。
複雑に見える情報も、枝分かれさせて整理すれば、すっきりとわかりやすくなります。まずは身近な課題で、ロジックツリーを試してみましょう。新しい気づきが得られるはずです。
社員からフィードバックを受ける
情報整理は、1人で完結する作業ではありません。整理された情報を実際に使うのは、チームのメンバーたち。だからこそ、使う人の声を聞くことが大切です。
例えば「この分類だと探しにくい」「もっと簡単なファイル名の付け方があるのでは」といった意見は、とても貴重です。実際に使ってみて初めて気づく課題もたくさんあるものです。
フィードバックをもらうことで、情報整理の質は着実に上がっていきます。「ここが使いづらい」という声は、より良い整理方法を考えるきっかけになります。また、「こうすれば便利」というアイデアは、新しい改善につながります。
大切なのは、批判を恐れないこと。むしろ、改善点を指摘してもらえたら、情報整理を進化させるチャンスです。
まずは、チームの中で気軽に意見を言い合える雰囲気を作りましょう。みんなの知恵を集めることで、より使いやすい情報整理が実現できるはずです。
ツールを活用する
情報整理は大切な作業ですが、全てを手作業で行うのは大変です。そこで役立つのが、情報整理のためのツール。上手に活用することで、作業がグッと楽になります。
ツールを選ぶときは、いくつかのポイントに注意しましょう。まず、そのツールが自分たちの目的に合っているか。次に、予算の範囲内で導入できるか。そして、タグやフォルダでの管理機能があるか。さらに重要なのが、チームのみんなが使いやすいかどうかです。
便利なツールを使えば、情報の保管場所やファイル名の付け方などを、いちいちルール化しなくても大丈夫。決められた手順に従うだけで、情報が整理された状態で保存できます。
でも、ツールはあくまでも道具。大切なのは、チームに合った使い方を見つけること。最初は基本的な機能から始めて、少しずつ使いこなしていくのがおすすめです。
情報整理を効率的に進めるために、ぜひツールの力も借りてみましょう。整理作業がスムーズになるはずです。
情報整理ならDocBaseにおまかせ

情報整理は、デジタル時代を生き抜くための重要なスキルです。本記事で紹介した方法を実践すると、散らばっている情報を価値ある資産へと変えることができます。
情報整理の効果は、単なる整理整頓にとどまりません。必要な情報にすぐアクセスでき、業務効率が向上し、チーム全体の生産性も高まります。また、きちんと整理された情報は、スムーズな引き継ぎや知識共有を可能にし、組織の成長を支える基盤となります。
情報整理は特別な才能がなくても、誰でも始められます。まずは目的を明確にし、分類方法を決め、ルールを統一することから始めましょう。必要に応じて情報整理のツールも活用し、チームからのフィードバックを取り入れながら、より良い方法を見つけていけばいいのです。
情報整理ならDocBaseがおすすめです。DocBaseは情報共有ツールとして、情報整理に役立つさまざまな機能と特徴を備えています。無料トライアルもご用意していますので、実際に利用しながら導入を検討いただけます。
DocBaseにおける情報整理に役立つ特徴・機能
| 機能 | 特徴 | |
| 基本的な機能 | 多様な編集モード | マークダウン、リッチテキスト、ハイブリッドエディターが利用可能。デジタルツールが得意でない人も使いやすい |
| 同時編集機能 | 複数人で同時にメモを編集できるため、議事録作成やアイデア出しに便利 | |
| 情報の再利用 | 差し込み機能で他のメモを簡単に参照でき、効率的なドキュメント作成が可能 | |
| 文書管理 | 柔軟な公開範囲設定 | グループ機能でメモの公開範囲を限定し、複数のグループに公開できる |
| 豊富な検索機能 | キーワード、グループ、タグなどで検索可能で、添付ファイル内も検索対象 | |
| タグ機能 | メモにタグ付けができ、タグの編集・統合も可能 | |
| スター機能 | 重要なメモに目印を付けてアクセスしやすくできる | |
| メモのピン留め | 重要なメモをグループメモ一覧の上位に表示できる | |
| セキュリティ機能 | シングルサインオン | Azure Active Directoryなど、SAML2.0に対応しているIDプロバイダーを利用できる |
| 2段階認証 | パスワードに加えてセキュリティコードで認証 | |
| アクセス制限 | DocBaseにアクセスできるIPを制限可能 | |
| 操作履歴 | メンバーの操作履歴ログをCSV形式でダウンロード可能 | |
| データの暗号化 | メモや個人情報は暗号化され、チームごとに暗号化されている | |
| その他の特徴 | マルチデバイス対応 | スマートフォンやタブレットからも閲覧・編集可能 |
| 外部サービス連携 | SlackやChatworkなど、さまざまなサービスと連携可能 | |
| テンプレート | 日報や議事録などのフォーマットをテンプレートとして登録可能 | |
| 画像編集機能 | 画像に矢印やテキスト、モザイクなどを配置できる | |
| ファイルアップロード | PDFやZIPなど、多様な形式のファイルをアップロード可能 |





