ペーパーレス化に必要なツール・システムの選び方は?特徴や導入事例を紹介
最終更新日:2025年3月5日
「ペーパーレス化に取り組みたいけれど、どのツールを選べばいいか分からない……」そんな悩みを抱える企業が増えています。実はペーパーレス化ツールは、目的や用途によって大きく異なります。
オンラインストレージ、ビジネスチャット、Web会議など、さまざまなツールが登場していますが、自社に最適なものを見極めることが成功の鍵となります。
この記事では、各種ツールの特徴や選び方のポイント、さらに導入のメリット・デメリットまで、企業のペーパーレス化を実現するために必要な情報を詳しく解説します。
【この記事を読んでわかること】
- ペーパーレス化とは具体的に何を指すか
- ペーパーレス化を実現するツールのタイプ別の特徴
- ペーパーレス化を実現するツールのメリットとデメリット
- ツール導入時に注意すべきポイントと具体的な導入成功事例
目次
業務のペーパーレス化とは
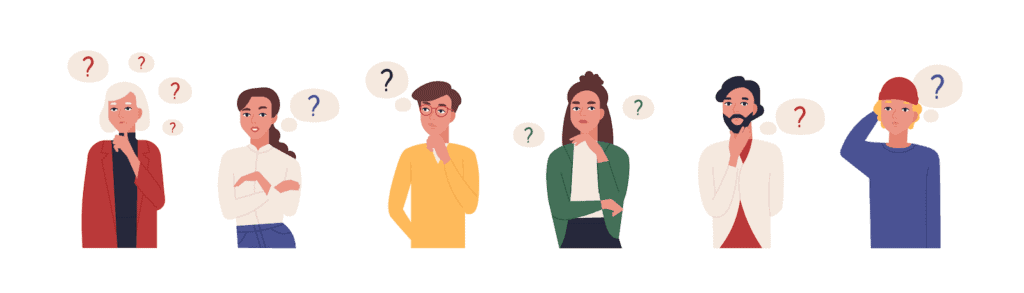
ペーパーレス化とは、業務の効率化を目的として、紙の書類をデータとして保存・管理・活用することです。
近年は電子帳簿保存法やe-文書法の整備により、データ保存された書類の法的な効力が認められるようになりました。そのため企業は、安心してペーパーレス化を進められます。
ペーパーレス化のメリットは3つあります。1つ目は、データでの文書管理により検索性が高まり、情報共有がスムーズになること。2つ目は、場所を問わずにアクセス可能なため、テレワークなどの柔軟な働き方に対応できること。3つ目は、紙の使用量を減らして環境保全に貢献できることです。
ペーパーレス化を進めるには、まず自社の課題を明確にすることが大切です。例えば契約業務の効率化なら電子契約ツール、社内文書の管理なら文書管理ツールというように、目的に応じて適切なツールを選びましょう。
導入に際しては、使いやすさやセキュリティ機能、既存システムとの連携性も重要な選定ポイントとなります。複数のツールを比較検討し、自社に最適なものを見つけることをおすすめします。
業務のペーパーレス化を進める主要ツール
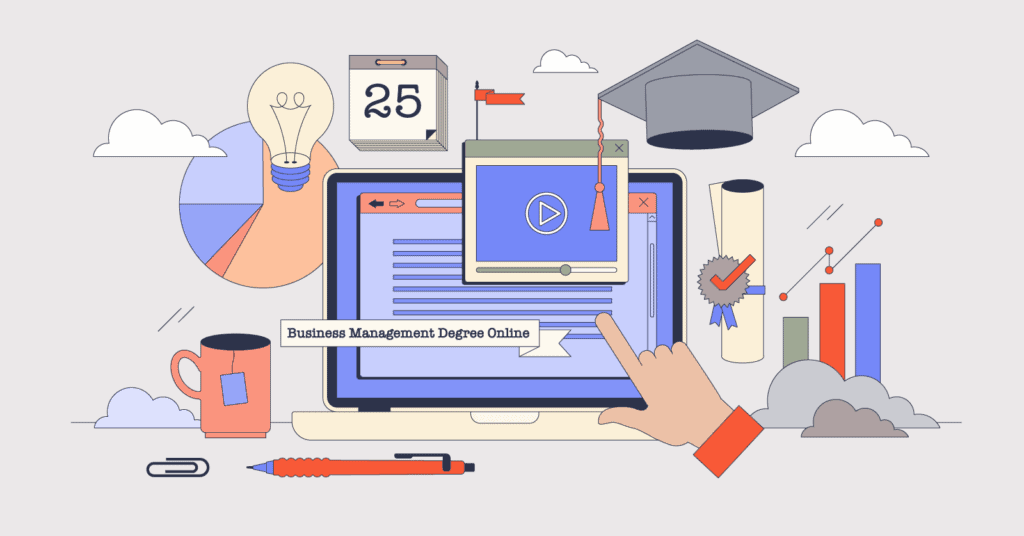
業務のペーパーレス化を促進するツールには、さまざまなタイプのものがあります。ここでは主要な以下のツールについて、具体的に解説していきます。
- オンラインストレージツール
- ビジネスチャットツール
- Web会議ツール
- ナレッジ共有ツール
- 文書管理ツール
- 勤怠管理ツール
- 電子契約ツール
- 請求書受領ツール
- ワークフローツール
オンラインストレージツール
インターネット上にデータを保管できるオンラインストレージは、ペーパーレス化の基盤となるツールです。
オンラインストレージの特徴は、場所を選ばないアクセス性にあります。インターネット環境があれば、外出先からでも必要な文書をすぐに取り出せます。また、データはクラウド上に保存されるため、パソコンの故障や災害による情報損失のリスクも軽減できます。
文書管理においても優れた機能を備えています。ファイル名やタグによる検索機能により、膨大な文書の中から目的のものをすぐに見つけ出せます。さらに、自動バックアップ機能により、データの保護も万全です。
セキュリティ面では、アクセス権限の設定により情報漏えいを防止できます。部署や役職に応じて閲覧可能な文書を制限することで、機密情報の適切な管理も可能です。
導入時は、ストレージ容量や同時接続数、料金プランを確認しましょう。また、社内のセキュリティポリシーに合致しているかも重要なポイントです。使い勝手の良さと安全性のバランスがとれたオンラインストレージツールを選ぶことで、業務効率の向上につながります。
ビジネスチャットツール
ビジネスチャットツールは、社内のコミュニケーションをデジタル化し、情報共有を円滑にするツールです。
電話やメールと比べて即時性が高く、気軽にやりとりができるのが特徴です。送受信した内容は全て記録として残るため、後から内容を確認することも簡単です。部署やプロジェクトごとにグループを作成して、必要な情報を必要なメンバーと共有できます。
多くのビジネスチャットツールには、基本的なメッセージ機能に加えて便利な機能が備わっています。例えば、タスク管理機能でプロジェクトの進捗を把握したり、ファイル共有機能で資料を共有したり、ビデオ通話機能で遠隔会議を開いたりすることができます。
業務用ツールなので、私用のチャットツールと使い分けることで、仕事とプライベートの区別も明確になります。特にテレワークが増えている昨今では、離れた場所にいるメンバー同士のコミュニケーションツールとして重宝されています。
導入時は、社員数や必要な機能、既存システムとの連携性を考慮してツールを選びましょう。使いやすさを重視しながら、情報セキュリティにも配慮したビジネスチャットツール選びが大切です。
Web会議ツール
Web会議ツールは、インターネットを通じて顔を見ながらコミュニケーションができるツールです。
このツールの最大の特徴は、場所を問わず会議に参加できる点です。パソコンやスマートフォン、タブレットなど、インターネットに接続可能な端末があれば、どこからでも参加できます。このため、テレワークやリモート商談との相性が抜群です。
多くのWeb会議ツールには、会議をより効率的に進めるための機能が搭載されています。画面共有機能を使えば、資料を参加者全員で閲覧しながら議論を進められます。会議の録画機能により、欠席者への共有や議事録作成も簡単になります。
さらに、会議資料をデジタル化して共有すれば、完全にペーパーレス化した会議が実現できます。そのため資料の印刷コストや保管スペースの削減、環境負荷の低減にもつながります。
導入時は、参加人数の上限、画質や音質の品質、セキュリティ機能を確認しましょう。社内の通信環境や利用者のITリテラシーも考慮に入れ、最適なツールを選択することが重要です。
ナレッジ共有ツール
ナレッジ共有ツールは、社内の知識やノウハウをデジタル化して共有・蓄積できる、組織の成長に欠かせないツールです。
ナレッジ共有ツールの特徴は、従業員が持つ業務知識を簡単に記録・共有できる点にあります。紙のマニュアルと違い、内容の更新や追記が容易で、常に最新の情報を保つことが可能です。また、検索機能により必要な情報にすぐにアクセス可能なため、業務効率が大幅に向上します。
ナレッジ共有は、組織が抱えるさまざまな課題を解決します。例えば、特定の社員だけが持つ知識を共有することで業務の属人化を防げます。新入社員の教育にも活用でき、若手社員の早期戦力化にも役立ちます。
進捗管理機能を活用すれば、直接顔を合わせなくても各従業員の業務状況を把握できます。テレワーク環境でも、チーム全体の業務進行を円滑に進められます。
導入時は、使いやすいインターフェース、情報の整理・分類機能、アクセス権限の設定機能を重視しましょう。社員全員が積極的に活用できるツールを選ぶことで、組織全体の生産性向上につながります。
文書管理ツール
文書管理ツールは、紙の文書をデジタル化して一元管理する、ペーパーレス化の核となるツールです。
このツールの導入により、保管スペースの問題が解決します。キャビネットやファイルボックスに収められた大量の紙文書を、データとしてコンパクトに保管できます。さらに、文書の検索や取り出しにかかる時間も大幅に短縮するため、業務効率が向上します。
また、文書へのアクセスがオンラインで可能になるため、情報共有が容易です。必要な文書を探すために書庫まで足を運んだり、複数の部署間でコピーをやり取りしたりする手間がなくなります。
2022年に施行された改正電子帳簿保存法にも対応可能な文書管理ツールも多く登場しています。法令要件を満たした形で帳票類を電子保存できるため、コンプライアンス面でも安心です。
導入時は、文書の検索性、アクセス権限の設定機能、セキュリティ対策を確認しましょう。また、既存の業務システムとの連携性も重要なポイントです。自社の文書管理ニーズに合った機能を持つツールを選択することで、業務改革を効果的に進められます。
勤怠管理ツール
勤怠管理ツールは、社員の出退勤から残業時間、休暇取得までを一括管理できる、人事労務のデジタル化に不可欠なツールです。
勤怠管理ツールの特徴は、場所を問わない勤怠報告が可能な点にあります。パソコンやスマートフォンから出退勤の打刻ができるため、テレワーク中の社員も正確な勤務時間を記録することが可能です。管理者側も、社員の勤務状況をリアルタイムで把握できます。
労働時間管理の面でも優れた機能を備えています。残業時間の自動計算や上限アラート機能により、労働基準法で定められた時間を超えないよう管理できます。有給休暇の取得状況も自動で集計されるため、取得促進に向けた施策も立てやすくなります。
さらに、給与計算システムと連携させることで、経理担当者の業務負担を軽減できます。勤務時間や残業代の計算が自動化され、給与計算の正確性も向上します。
導入時は、自社の勤務形態への対応力、操作性、他システムとの連携性を確認しましょう。働き方改革に対応し、かつ使いやすいツールを選ぶことで、人事労務管理の効率化を実現できます。
電子契約ツール
電子契約ツールは、契約書の作成から締結、保管までをオンラインで完結できる、ビジネスプロセスの改善に貢献するツールです。
電子契約ツールの最大の特徴は、紙の契約書に特有の手間を省けることにあります。印刷や押印、郵送といった作業が不要になり、契約締結までの時間を大幅に短縮できます。収入印紙も不要となるため、コスト削減にもつながります。
契約書の管理面でも効率化が図れます。締結済みの契約書はデータとして保管され、必要な時にすぐ取り出せます。また、メールやリンクでの共有が可能なため、関係者間での情報共有もスムーズです。
セキュリティ面も考慮されています。電子署名技術により、契約書の改ざんや成りすましを防止できます。さらに、契約締結時の本人確認や意思確認も確実に行えます。
導入時は、電子署名の法的効力、セキュリティ機能、利用料金体系を確認しましょう。テレワーク環境でも確実に契約業務を進められる、使いやすい電子契約ツールを選ぶことが重要です。
請求書受領ツール
請求書受領ツールは、紙の請求書をデータ化し処理を自動化する、経理部門のデジタル化に欠かせないツールです。
請求書受領ツールの導入により、請求書処理の手間が大幅に削減されます。受領した請求書は自動でデータ化され、金額や取引先情報の手入力が不要になります。そのため転記ミスなどのヒューマンエラーも防止できます。
2022年に施行された改正電子帳簿保存法への対応も可能です。特にクラウド型のツールは、法改正に合わせて自動的にアップデートされるため、常に最新の法令要件を満たした状態で運用できます。
経理部門のテレワーク化も実現できます。請求書データにオンラインでアクセスして、自宅からでも通常通りの業務が可能です。また、承認フローもデジタル化されるため、決裁者が外出先からでも処理を進められます。
導入時は、OCR精度、会計システムとの連携性、保存データの検索機能を確認しましょう。経理部門の業務効率を高め、かつコンプライアンスも確保できる請求書受領ツールを選択することが重要です。
ワークフローツール
ワークフローツールは、社内の申請・承認作業をオンラインで完結させる、業務のデジタル化に重要なツールです。
ワークフローツールの特徴は、申請から承認までの一連の流れをデジタル化できる点にあります。書式の作成から申請・承認・保管までを全てオンラインで行えるため、紙の資料を回覧する必要がありません。そのため決裁にかかる時間を大幅に短縮できます。
承認プロセスの可視化も実現します。申請書類が今どの段階にあるか、誰の承認待ちなのかが一目でわかります。また、処理が滞っている案件には自動で催促メールを送れるため、業務の遅延を防げます。
場所を問わない処理も可能です。外出先やテレワーク中でも、スマートフォンやタブレットから申請・承認作業ができます。急ぎの決裁も、移動中や出張先で処理が可能で、業務の停滞を防げます。
導入時は、カスタマイズ性、操作性、他システムとの連携を確認しましょう。自社の決裁フローに合わせやすく、社員が使いやすいワークフローツールを選ぶことで、業務改革を効果的に進められます。
ペーパーレス化推進のメリット

ペーパーレス化を推進するメリットは数多くありますが、ここではペーパレス化ツールを利用して得られるメリットについて具体的に解説していきます。
メリットは主に以下の点が挙げられます。
- 業務の効率化が期待できる
- リモートワークなどに対応しやすい
- コスト削減につながる
- 災害時に対応しやすい
- セキュリティ性が高い
業務の効率化が期待できる
ペーパーレス化ツールを導入すると、今まで手作業で行っていた資料の印刷、配布、回収などの作業が不要になります。ここから生み出された時間を他に振り分けて、営業活動やマーケティング施策の立案など、より付加価値の高い業務に充てることができます。
実際に導入した企業からは「会議の準備時間が削減された」「社員の残業時間が減少した」といった声が寄せられています。このように、ペーパーレス化ツールは、業務効率化を通じて働き方改革の実現を強力に後押しします。
リモートワークなどに対応しやすい
ペーパーレス化ツールは、働く場所の制約を取り除きます。具体例として、自宅のパソコンやタブレットから必要な書類にアクセスでき、社内の重要な会議にもオンラインで参加できます。
柔軟な働き方により、出張中のホテルや新幹線の中でも業務の継続が可能です。また、フリーアドレス制を採用している企業では、社員が好きな席で仕事をしながら、必要な書類を即座に確認できます。
実際の事例では、営業担当者が取引先との商談後、その場で契約書の確認や修正が可能になり、契約締結までの期間が短縮されたといったケースがあります。
さらに、育児や介護と仕事の両立を目指す社員も、自宅で業務を進められるため、仕事と私生活のバランスが取りやすくなります。育児からの復帰率の向上、介護による離職者の減少といったメリットが挙げられます。
このように、ペーパーレス化ツールは、場所や時間の制約から社員を解放し、より効率的で充実した働き方を実現します。
コスト削減につながる
ペーパーレス化ツールは、企業の経費削減に大きく貢献します。紙の書類を使用するとなると印刷用紙代やプリンターのトナー代、文書保管用キャビネットのレンタル料などがかかります。これらの経費は、ペーパーレス化によって大幅に削減が可能です。
さらに、社員の作業時間短縮による人件費の削減効果も見逃せません。書類の整理・保管・検索にかかる時間が減少し、残業代を抑制することが可能です。
加えて、紙の廃棄処理費用も不要になります。機密文書の処理には費用がかかりますが、この支出も削減できます。
このように、ペーパーレス化ツールは、直接的な経費だけでなく、間接的なコストの削減にも効果を発揮します。
災害時に対応しやすい
ペーパーレス化ツールは、自然災害から企業の重要データを守ります。日本では地震が多く発生し、台風や豪雨による水害も増加傾向にあります。そういった災害での書類水没による被害リスクを低減できます。
紙の書類は一度被災すると復元が困難です。2011年の東日本大震災では、津波で流された契約書や帳簿の再発行に時間を要し、事業再開の大きな障害となりました。
ペーパーレス化ツールでは、データをクラウド上に保存するため、オフィスが被災しても即座にデータを復元できます。仮に事務所が浸水被害を受けても、翌日から別拠点で通常業務を再開することも可能です。
ペーパーレス化ツールにはバックアップ機能もあるので、データの永続的な保管もできます。このように、ペーパーレス化ツールは、災害大国である日本の企業にとって、事業継続の重要な基盤となります。
セキュリティ性が高い
紙の資料を使っていることによる情報漏えい事故では、置き忘れや紛失が主な原因とされています。
ペーパーレス化ツールでは、部署別・役職別・プロジェクト別など、必要な人だけがデータへアクセス可能な権限を細かく設定することで、置き忘れや紛失といったリスクを低減できます。また、データの閲覧履歴も記録されるため、情報の取り扱いを正確に把握できます。
さらに、データの暗号化機能により、万が一の情報流出時でも内容は保護されます。遠隔操作でデータを削除する機能も搭載され、紛失したデバイスからの情報漏えいを防止します。
このように、ペーパーレス化ツールは、従来の紙媒体では実現できなかった高度なセキュリティ対策を提供します。
ペーパーレス化推進のデメリット

ペーパーレス化にはいくつかのデメリットもあります。ペーパーレス化を進めるにあたっては、デメリットも把握しておくと良いでしょう。
デメリットには以下のようなものが挙げられます。以降から具体的に解説していきます。
- ツールの浸透に時間がかかるケースがある
- 導入にはコストがかかる
- システム障害や回線速度遅延などに影響を受ける
ツールの浸透に時間がかかるケースがある
ペーパーレス化ツールの導入には、社内浸透の難しさという課題があります。企業の導入においては、ツール導入から3か月経過しても利用が浸透しないケースも報告されています。
特に、これまでExcelなどの基本的なソフトウェアしか使用していない社員は、新しいツールの操作に不安を感じることが多いようです。
この課題を解決するには、段階的な準備が重要です。具体的には、導入前に詳細な操作マニュアルを整備し、部署ごとの少人数制の研修を実施します。また、各部署にペーパーレス化ツールに詳しい担当者を配置して、日常的な疑問にすぐ対応できる体制を整えます。
導入に成功した企業では、研修期間を設け、定期的にフォローアップミーティングを実施するといった施策を実践しています。このような丁寧なサポート体制により、全社的な活用が実現します。
導入にはコストがかかる
ペーパーレス化ツールの導入には、計画的な投資が必要です。一般的な初期費用としてライセンス料、デバイス購入費、セットアップ費用が発生します。
さらに、紙の資料をデータ化する作業も必要です。過去の契約書や請求書など重要書類のスキャン作業にも工数がかかる点は考慮しておきましょう。また、社員研修や業務フローの見直しにも時間を要します。
ただし、これらの投資は将来的な経費削減につながります。投資回収についても、「1年から2年で回収する」といったように、ある程度は見積もっておくといいでしょう。ツール選定時には、自社の規模や業務内容に合わせた費用対効果の試算が重要となります。
システム障害や回線速度遅延などに影響を受ける
ペーパーレス化ツールは、ネットワーク環境に依存するという特徴があります。企業のネットワークトラブルや、それに対する復旧作業がどうしても発生してしまいます。
具体的なトラブル事例として、Web会議中の画面フリーズや音声の途切れ、クラウド上の資料にアクセスできない状況が挙げられます。複数拠点を接続した会議での通信障害の発生などもあるでしょう。
これらの課題に対応するための対策も必要です。まず、オフライン時でも閲覧できるよう、必要な資料をローカル環境に保存しておきます。また、通信回線を複数用意し、主回線に不具合が生じた際の予備として確保します。
さらに、大容量データの同期は業務時間外に設定するなど、システム負荷を分散させる工夫も効果的です。このような備えにより、安定したペーパーレス環境を実現できます。
ペーパーレス化ツールを導入する際のポイント
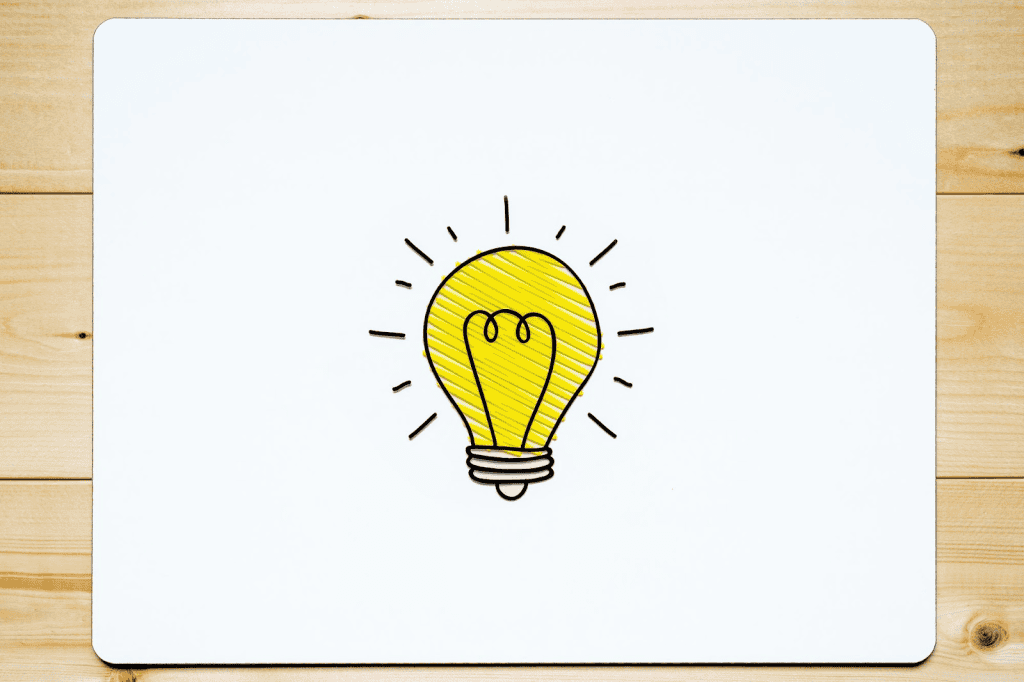
ペーパーレス化ツールを導入する際には、以下のようなポイントを理解しておくのをおすすめします。
- データに対する現状を把握し導入目的を明確にする
- ツールの必要性を導入前に周知しておく
- ツールは自社に合ったものを選ぶ
- 導入は段階を踏んで少しずつ行う
それぞれについて詳しく解説していきます。
データに対する現状を把握し導入目的を明確にする
ペーパーレス化ツールの導入では、まず現状把握が不可欠です。ツール導入に失敗した企業の多くが、事前の現状分析を十分に行っていなかったという話も耳にします。
具体的な分析項目として、紙の使用量、保管コスト、業務プロセスの可視化が重要です。例えば、「月間5万枚の紙を使用し、承認プロセスに平均3日を要している」といったように、月間の印刷枚数、書類の保管スペース、資料作成から承認までの時間などを数値化します。
次に、明確な導入目的を設定します。「紙の使用量を半減させる」「承認時間を1日以内にする」など、具体的な数値目標を立てます。さらに、業務プロセス自体の見直しも重要です。単にツールを導入するだけでなく、不要な承認工程の削減など、業務改善と組み合わせることで効果が高まります。
ツールの必要性を導入前に周知しておく
ペーパーレス化ツールの導入成功には、全社的な理解と協力が欠かせません。社内の理解が不十分なまま導入を進めてしまった結果、利用が停滞してしまう可能性もあるからです。
効果的な周知方法として、まず経営層への説明が重要です。具体的な数字を示し、「年間コスト250万円削減」「営業利益率2%向上」など、経営指標の改善効果を明確に伝えます。
一方、現場社員には、具体的な業務改善効果を示します。「資料作成時間が1日あたり45分短縮」「在宅勤務が週3日可能に」など、個人レベルのメリットをわかりやすく説明します。
導入を成功させるために、部署ごとの説明会を開催し、質疑応答の時間を十分に設けるといった施策も必要でしょう。また、若手社員による推進チームを結成し、現場の声を取り入れながら進める例もあります。
スムーズなペーパーレス化ツールの導入には、丁寧な合意形成が欠かせません。
ツールは自社に合ったものを選ぶ
ペーパーレス化ツールは、市場に数多く存在し、機能や価格帯が大きく異なります。そのため、自社に適したツール選定が重要です。
選定の基準として、まずは操作性を重視します。画面の切り替えが3回以内で目的の作業ができる、検索機能で5秒以内に必要な文書が見つかるなど、具体的な使いやすさを確認します。
次に、必要な機能を見極めます。例えば、月間の契約書作成が10件程度の企業に、年間100万円の電子署名機能は過剰です。反対に、日々100件の請求書処理がある企業には、OCR機能は必須となります。
多くのツールは2週間程度の無料トライアルを提供しています。実際の業務で使用感を確認し、社員の評価を集めることで、適切な選定が可能です。価格は月額500円から5万円といった具合で幅広いため、利用頻度と効果を考慮した投資判断が必要です。
導入は段階を踏んで少しずつ行う

ペーパーレス化ツールの導入を検討する際、全社一斉導入は避けましょう。業務への影響や社員のデジタルツールに対する習熟度の差により、円滑な運用の妨げとなるためです。
代わりに、以下の3つのステップによる段階的な導入をおすすめします。
まず、ペーパーレス化の優先度が高い資料を選定します。毎月更新する営業マニュアルや、部署間で共有する会議資料から始めることで、具体的な業務改善効果を実感できます。
次に、ITリテラシーの高い部署や社員をパイロットユーザーとして選びます。日常的にPCを使用する経理部門や、デジタルツールに長けた若手社員から導入することで、初期の混乱を最小限に抑えられます。
最後に、パイロットユーザーの成功事例を活用し、他部署への展開を進めます。導入過程で得られた知見を生かすことで、全社展開をスムーズに実現できます。
こういったアプローチにより、確実な成果を積み重ねながら、全社的なデジタル化を実現できます。
ツールの導入成功事例:オイシックス・ラ・大地株式会社
食品宅配サービス大手のオイシックス・ラ・大地株式会社は、ナレッジ管理ツール「DocBase」の導入により、社内のペーパーレス化を実現しました。
同社は導入以前、情報の分散化のほか、過去資料の検索が困難だったり、会議資料の印刷負担があったりなど、さまざまな業務が非効率な状況に置かれていました。特に、共有フォルダ、個人PC、紙媒体など情報の保管場所が多岐にわたり、必要な情報の検索に多くの時間を要していたといいます。
また、社内での知識共有が不十分で業務の属人化が進行。経験の浅い社員が先輩社員にその都度確認する必要があり、教育にかかる時間的コストも課題となっていました。
DocBase導入後、特に顕著な改善が見られたのが会議運営です。これまで毎回印刷が必要だった週次進捗会議の資料が、「基本的にDocBaseを見る」という新しい運用方式に変更され、印刷業務が撤廃されました。また、会議前の事前メモ共有により、定例ミーティングの所要時間が半減するなど、具体的な業務効率化も実現しています。
さらに、過去の会議資料やナレッジの一元管理が可能となり、情報へのアクセシビリティが大幅に向上。社内の情報共有基盤として機能しはじめています。
事例を読む(会議のペーパーレス化が進んで、とても楽になりました/オイシックス・ラ・大地株式会社様)
自社に合ったツールを導入してペーパーレス化を進めよう

ペーパーレス化ツールは、業務効率化や働き方改革を実現する重要な手段です。オンラインストレージやビジネスチャット、Web会議、文書管理など、目的に応じた多様なツールが存在します。
導入時は、自社の課題を明確にし、業務プロセスや必要機能を精査することが重要です。また、社内への丁寧な周知と段階的な導入により、スムーズな移行が可能になります。
メリットとして、業務効率化、リモートワーク対応、コスト削減、災害対策、セキュリティ向上が挙げられます。一方で、ツールの浸透に時間がかかることや初期投資が必要なことにも留意が必要です。
成功の鍵は、現状分析に基づく適切なツール選定と、全社的な理解・協力の獲得にあります。自社の規模や業務特性に合わせて最適なツールを選び、計画的に導入を進めることで、効果的なペーパーレス化を実現できます。
DocBaseは、ペーパレス化を促進するツールとして活用いただけます。具体的なメリットは以下のようなものが挙げられます。
- 紙資料の削減: 従来は印刷していた資料をDocBaseで共有することで、ペーパーレス化が実現できます
- 保存情報の利便性: DocBaseに保存された情報は、過去の資料を確認する際にも便利です
- 効率的な情報共有: DocBaseにより、情報を一か所に集約し、チーム全体で共有できるようになります
DocBaseは直感的な操作が特徴で、無料トライアルも利用できます。ぜひ導入をご検討ください。





