【2025年版】失敗しない情報整理ツールの選び方とおすすめ8選
最終更新日:2025年5月21日
ビジネスでは、知識や経験を重ねるほど、扱う情報量が増えていきます。この膨大な情報を効率的に管理するため、多くの企業が情報整理ツールの導入を検討しています。しかし、市場には多種多様な情報整理ツールが存在し、自社に合った選択が難しいと感じられる方もいるでしょう。
本記事では、情報整理ツールの概要と選び方について解説します。情報整理ツールとは、PC内の大量の情報を整理・管理するためのソフトウェアです。主に5種類(情報共有、チャット、プロジェクト・タスク管理、社内Wiki、ファイル・文書資料管理)に分類されます。
これらの情報整理ツールは、効率的な整理・整頓やスムーズな情報共有など、さまざまなメリットをもたらします。しかし、導入の際は、機能、操作性、検索のしやすさなどを慎重に吟味する必要があります。
自社に最適な情報整理ツールを見つけて、情報管理の効率化を実現しましょう。
【この記事を読んでわかること】
- 情報整理ツールとは、PC内の多くの情報を整理して管理するためのもの
- 情報整理ツールは、情報共有ツール、チャットツール、プロジェクト・タスク管理ツール、社内Wikiツール、ファイル・文書資料管理ツールの5種類に分けられる
- 効率的な整理・整頓、スムーズな情報共有などのメリットがある
- 情報整理ツール選びは、機能、操作性、検索しやすさがポイント
目次
情報整理ツールとは?
情報整理ツールは、デジタル時代の必須アイテムです。PC内の膨大な情報を効率的に管理・活用できるように設計されています。
現在、市場には多種多様な情報整理ツールが存在し、その機能は多岐にわたります。全方位的な機能を備えた総合的なものから、特定の機能に特化したシンプルなものまで、多くの選択肢が存在します。
基本的な機能としては、ドキュメントの作成・共有・管理があります。これらの機能により、情報の収集から活用までをシームレスにサポートします。単なる情報整理だけでなく、業務マニュアルや議事録の作成など、情報を形にする過程からツールが活用されることも多く、業務のあらゆる場面で役立ちます。
しかし、ツールごとに搭載機能が大きく異なるため、選定には慎重さが求められます。自社のニーズを明確にし、最適なツールを見つけることが、効果的な情報整理の鍵となります。導入を検討する際は、自社の業務フローや情報管理のニーズを深く分析し、最適な情報整理ツールを選択しましょう。
情報整理ツールの種類

情報管理ツールは、主に5つのカテゴリーに分類されます。それぞれに特徴があり、企業の需要に応じて選択することが重要です。
1. 情報共有ツール:
情報ツールは、ドキュメントやナレッジの共有に特化しています。業務マニュアルや議事録、商談記録など、さまざまな情報を一か所に集約し、チーム全体で共有できます。
2. チャットツール:
リアルタイムのコミュニケーションを促進します。1対1のやりとりだけでなく、部署やプロジェクト単位でのグループチャットも可能です。
3. プロジェクト・タスク管理ツール:
業務の進捗を可視化し、チームの生産性を向上させます。タスクの割り当てや期限管理が容易になります。
4. 社内Wikiツール:
組織の知識を集約し、誰でも編集可能な形で共有します。時間が経っても情報が流れることなく、ナレッジの蓄積が可能です。
5. ファイル・文書資料管理ツール:
さまざまな形式のファイルを一元管理します。クラウドベースで運用することで、いつでもどこからでもアクセスが可能になります。
これらの情報整理ツールを組み合わせることで、より効果的な情報管理が実現できます。自社の業務プロセスや情報フローを分析し、最適な組み合わせを見つけることが重要です。それぞれについて詳しくご紹介していきます。
情報共有ツール
情報共有ツールは、企業内の知識を管理することにおいて中心的な役割を果たします。
情報共有ツールでは、テキストベースのノートやドキュメントを通じて情報を管理し、共有することができます。マニュアル、議事録、日報、商談報告書など、多様な種類の情報を一か所にまとめて管理できるため、あらゆる業界で活用可能です。
情報共有ツールの強みは、アクセス性にあります。作成したノートやドキュメントに簡単にアクセスでき、必要な情報をクリック1つで即座に取り出せます。さらに、すでに蓄積されているナレッジの利用傾向を分析する機能を持つものもあり、どんなナレッジにニーズがあるのかを把握する際にも役立ちます。
「増え続ける情報を効率的に整理し、迅速にアクセスしたい」といった要望を満たすには、タグ付け機能や検索機能が搭載されている情報共有ツールを選ぶことが重要です。
情報共有ツールは、企業の知識管理を効率化し、情報の有効活用を促進します。ただし、導入にあたっては、ユーザーの利用習慣や組織の文化に合わせたカスタマイズが重要です。適切に活用することで、組織全体の生産性向上につながるでしょう。情報共有の必要性やメリットは?情報共有の具体的な方法や成功の秘訣も紹介!では、こうした情報共有ツールの活用方法についてより詳しく解説しています。
チャットツール
チャットツールは、いまやビジネスコミュニケーションに欠かせません。
チャットツールの最大の魅力は、会話形式で気軽に情報をやりとりできる点です。1対1のコミュニケーションだけでなく、部署やチームごとのグループチャットも可能で、情報共有の幅が大きく広がります。
電子メールと比較すると、リアルタイムで自然なコミュニケーションが可能です。この気軽さが、社内のコミュニケーションを活性化し、情報の流れを円滑にします。
特に、リモートワークや営業などで外勤が多い職場では、チャットツールの利用が便利です。対面でのコミュニケーションが難しい状況でも、リアルタイムで情報を共有し、チームの連携を維持できます。
一方で、チャットツールにも課題があります。会話が流れやすいため、重要な情報を後から探すのに手間がかかる可能性があります。この問題に対処するため、検索機能や情報のピン留め機能を備えたツールが多くあります。
チャットツールを効果的に活用するには、使用ルールの策定が重要です。例えば、重要な決定事項は別途文書化するなど、情報の管理方法を明確にしておくことで、チャットツールの利点を最大限に引き出せます。
適切に運用されたチャットツールは、組織のコミュニケーションを大幅に改善し、業務効率の向上につながります。自社の働き方に合わせて、最適なチャットツールを選択し、活用していくことが重要です。社内コミュニケーションツールとは?メリットや選定時のポイントも解説では、チャットツールを含む社内コミュニケーションツールの詳細な検討方法を解説しています。
プロジェクト・タスク管理ツール
プロジェクト・タスク管理ツールは、チームの業務効率を飛躍的に向上させる強力なアイテムです。
プロジェクト・タスク管理ツールは、業務の進捗状況の可視化に優れています。チームメンバーにタスクを割り当て、その進行状況が一目で確認できます。プロジェクト全体の進捗が明確になり、遅延や問題点を早期に発見して対処することが可能になるのです。
多くのプロジェクト・タスク管理ツールでは、タスクと関連資料を紐付けて管理する機能も提供しています。この機能により、必要な情報にすぐにアクセスでき、作業効率が大幅に向上します。従来のように、別のストレージツールに保存された資料を探す手間が省けるのです。
さらに、高度なプロジェクト・タスク管理ツールでは、タスクの依存関係の設定や、自動リマインダー機能なども備えており、複雑なプロジェクト・タスク管理をサポートします。
ただし、導入の際は注意点もあります。プロジェクト・タスク管理ツールには、個人向けとチーム向けのものがあるため、選択時には自社の需要に合ったものを選ぶ必要があります。チーム全体の業務を管理するには、協働機能やコミュニケーション機能が充実したプロジェクト・タスク管理ツールが適しています。
プロジェクト・タスク管理ツールを適切に選択して活用することで、チームの生産性を大幅に向上させて、プロジェクトの成功確率を高めます。自社の業務フローや組織構造を考慮し、最適なプロジェクト・タスク管理ツールを選びましょう。
社内Wikiツール
社内Wikiツールは、組織の知識を集約し、共有するための強力なプラットフォームです。
社内Wikiツールは、ウィキペディアの概念を企業内に適用したものです。Webブラウザから直接ページの追加・編集・更新が可能で、社内の情報を効率的に管理できます。
社内Wikiツールの最大の特徴は、情報の蓄積と共有の容易さです。従来のメールやチャットでは、時間が経つと情報が流れてしまう課題がありましたが、社内Wikiツールではナレッジを逐次ストックできます。重要な情報やノウハウが失われることなく、組織全体で共有できます。
また、社内Wikiツールには、高いメンテナンス性もメリットとして挙げられます。特定の管理者に依存せず、全従業員が自由に編集できるため、情報を常に最新の状態に保つことができます。これは、急速に変化するビジネス環境において重要な特徴です。
ただし、社内Wikiツールの効果的な運用にはいくつかの注意点があります。まず、初期段階で基本的なコンテンツを準備することが重要です。また、情報の構造化やカテゴリー分けなど、使いやすい環境を整えることも成功の鍵となります。
社内Wikiツールは、組織の知的資産を効果的に管理し、イノベーションを促進する強力なツールとなります。適切に導入・運用することで、情報のオープン化と知識の共有が進み、組織全体の生産性向上につながるでしょう。ナレッジマネジメントとは?おすすめツール10選【効果・メリット・導入・運用】では、社内Wikiツールを含むナレッジマネジメントの包括的な方法論について詳しく解説しています。
ファイル・文書資料管理ツール
ファイル・文書資料管理ツールは、企業内の多様なデジタルコンテンツを一元管理するための重要なソリューションです。
ファイル・文書資料管理ツールでは、社内のファイル情報をオンラインで包括的に管理します。PDF、Excel、Word、動画ファイルなど、さまざまな形式のデータを一か所で管理できる点が大きな特徴です。
クラウドベースで運用されることが多いファイル・文書資料管理ツールは、インターネット環境さえあれば、時間や場所を問わずアクセスが可能です。リモートワークやグローバルな業務展開にも柔軟に対応できます。
また、多くのファイル・文書資料管理ツールではバージョン管理機能が搭載されており、ファイルの変更履歴を追跡したり、以前のバージョンに戻したりすることが容易です。これは、チームでの協働作業や品質管理において有用な機能です。
一方で、利用にあたってはいくつかの注意も必要です。ファイル形式以外の情報管理には適していない場合があり、また、ファイルの編集時に一度ローカルにダウンロードする必要があるファイル・文書資料管理ツールもあります。
さらに、ファイル数が増えすぎると情報整理が難しくなる可能性があるため、効果的なフォルダ構造の設計や、強力な検索機能の活用が重要になります。
ファイル・文書資料管理ツールは、適切に運用することで、企業の情報資産を効率的に管理し、活用するための強力な基盤となります。自社のニーズや業務フローを考慮し、最適なファイル・文書資料管理ツールを選択することが成功への鍵となるでしょう。
情報整理ツールを使う3つのメリット

情報整理ツールは、情報の整理・管理、検索、共有を効率化し、業務効率を向上させます。重複情報の防止、データの可視化、タスク管理の円滑化など、さまざまなメリットがあり、組織全体の活性化に貢献します。
ここでは以下の点について具体的に紹介していきます。
- 情報を効率的に整理・管理できる
- 情報共有しやすくなる
- 社外からも情報にアクセスできる
情報を効率的に整理・管理できる
情報整理ツールは膨大な量の情報を効率的に整理・管理できます。例えば、名刺管理機能を持つ情報整理ツールでは、紙の名刺をスキャンし、自動的にデジタル化して検索可能なデータベースに変換します。数百枚の名刺から必要な連絡先を瞬時に見つけ出すことが可能になります。
また、情報整理ツールは重複データの削減にも貢献します。適切なツールを使用することで、同じ情報が複数の場所に保存されるという問題を防ぎ、データの一貫性を保つことができます。これは、誤った情報に基づく意思決定のリスクを大幅に軽減します。
さらに、多くの情報整理ツールには高度な検索機能が搭載されています。全文検索や条件検索など、精度の高い検索機能により、必要な情報に素早くアクセスすることが可能になります。これは時間の節約だけでなく、蓄積された情報の有効活用にもつながります。
情報整理ツールを効果的に活用することで、企業は情報資産を最大限に活用し、競争力を高められます。ただし、ツールの選択と導入には慎重な検討が必要であり、自社の業務プロセスやニーズに適したソリューションを選ぶことが重要です。
情報共有しやすくなる
情報整理ツールの導入は、単なる情報の整理だけでなく、効果的な情報共有を促進する重要な役割を果たします。
多くの企業では、情報共有の重要性は認識されていますが、適切なツールがない場合、その共有方法や共有頻度が社員個人の判断に委ねられがちです。情報整理ツールを導入することで、全社員が同じプラットフォーム上で情報を共有できるようになり、情報の分散や孤立が防げます。
情報整理ツールの多くは、リアルタイムでの情報更新機能を備えています。最新の情報が即座に全社員に共有され、情報の鮮度が保たれます。また、アクセス権限の細かい設定が可能なため、必要な情報を必要な人に適切に共有しつつ、セキュリティも維持することができます。
さらに、情報整理ツールは部門を越えた情報共有を促進します。従来の縦割り組織では難しかった部門横断的な情報共有が容易になり、イノベーションの促進や問題解決の効率化につながります。
使いやすい情報整理ツールを導入することで、社員の情報共有への抵抗が減り、日常的な情報共有が習慣化されやすくなります。これは組織全体の知識管理と生産性の向上につながります。
ただし、情報整理ツールの導入だけでなく、情報共有を促進する企業文化の醸成も同時に進めることが、成功の鍵となります。適切な情報整理ツールを選択し、それを活用する組織文化を構築することにより、企業は情報の力を最大限に引き出して組織全体を活性化させられるでしょう。
社外からも情報にアクセスできる
クラウドベースの情報整理ツールの導入は、場所や時間の制約を超えた情報アクセスを可能にし、ビジネスの効率性と柔軟性を大幅に向上させます。
クラウドベースの利点は、時間と場所を問わないアクセス性です。クラウド上で情報を管理することで、インターネット接続さえあれば、オフィス内外を問わず、いつでもどこでも必要な情報にアクセスできます。出張先や在宅勤務時でも、シームレスに業務を継続することが可能になります。
さらに、多くのクラウドベースの情報整理ツールは、スマートフォンやタブレットに対応しています。PCが使用できない移動中や外出先でも、必要な情報を確認したり、更新したりすることができます。この機能は、特に営業職や現場作業が多い業種で利便性を発揮します。
また、クラウドベースの情報整理ツールを使用することで、「報告のためだけに会社へ戻る」といった非効率な移動時間を削減できます。必要な情報をその場で確認し、報告や意思決定を行うことができるため、業務のスピードアップにつながります。
その他にも、リアルタイムの情報共有が可能になることで、チームの連携が強化されます。複数の社員が同時に同じ情報にアクセスし、リアルタイムで更新や共有を行うことができるため、情報の鮮度が保たれ、意思決定のスピードが向上します。
クラウドベースの情報整理ツールの導入により、企業は従来の業務の枠を超えた柔軟な働き方を実現し、生産性と競争力を高めることができます。ただし、セキュリティ面での配慮も重要で、適切なセキュリティ対策を講じることが不可欠です。
情報整理ツールの選び方

情報整理ツールを選ぶ際は、目的・ニーズを明確化し、必要な機能、導入・運用コスト、操作性などを比較検討しましょう。無料トライアルやレビューも参考に、自社に最適なツールを見つけることが重要です。以下の視点から具体的にご紹介していきます。
- 過不足のない機能か
- 操作性は高いか
- 情報を検索しやすいか
過不足のない機能か
情報整理ツールを選択する際には、自社のニーズと業務プロセスに合致した機能が搭載されているものを選ぶことが極めて重要です。
そのために、「情報整理ツールで何をするか」「何のために情報整理ツールを導入するか」を明確にすることが最初のステップです。例えば、複数人での同時編集やリアルタイムの情報共有が必要なのか、それとも単純なファイル保管が主な目的なのかを明確にします。
次に、現在の情報管理方法の問題点を洗い出します。例えば、Excelで情報管理をする場合「複数人で同時編集ができない」「さまざまなデータを一か所に集めて一元管理するのが難しい」などの課題があります。そのため、これらの課題を解決できる情報整理ツールを探すことが重要です。
さらに、将来的な拡張性も考慮に入れることも大事です。企業の成長に伴い、情報量や利用者数が増加しても対応できる情報整理ツールを選びます。
セキュリティ機能も忘れてはいけません。特に機密情報を扱う場合は、アクセス権限の設定やデータの暗号化など、セキュリティ機能が充実しているかを確認します。
最後に、他のツールとの連携性も重要です。既存の業務システムやツールとの連携が可能かどうかを確認し、シームレスな情報の流れを実現するための情報整理ツールを選びましょう。
操作性は高いか
全社的な導入の成功率を左右する要因として、操作性も重要です。複雑な操作が必要な情報整理ツールを導入してしまうと、一部の技術に精通した社員のみが使いこなせるといった結果となり、全社的な導入が困難になります。シンプルで直感的な操作性を持つ情報整理ツールを選ぶことで、全社員が効果的に利用できる可能性が高まります。
また、使いやすい情報整理ツールであれば、社員が自発的に情報を共有する機会が増えます。操作に戸惑いがあると、情報共有自体が避けられてしまう可能性があります。これは、組織全体の情報流通を妨げる要因となります。
さらに、操作が簡単な情報整理ツールは、情報の入力や検索にかかる時間を最小限に抑えることができます。社員は本来の業務により多くの時間を割くことができ、生産性の向上につながります。
学習コストの観点からも、操作性は重要です。直感的な操作性を持つツールは、導入時の研修にかかる時間とコストを削減できます。また、新入社員や異動してきた社員も短期間で使いこなせるようになります。
選択の際の具体的なポイントとしては、インターフェースの分かりやすさ、必要な操作ステップ数、カスタマイズ性、モバイル対応、ヘルプ機能の充実度などが挙げられます。また、既存ツールの操作感との類似性も、導入のしやすさに影響します。
最終的には、可能な限り実際に試用期間を設けて、社員の反応を見ることが重要です。使いやすさは主観的な面もあるため、実際の利用者の声を聞くことが最適な情報整理ツール選択につながります。
情報を検索しやすいか
情報整理ツールの選択において、検索機能の充実度は極めて重要な要素です。業務を続けるにつれて情報量は増加し、適切な検索機能がなければ必要な情報を見つけ出すのが困難になります。以下に、検索機能の重要性と、選択時に注目すべきポイントを詳しく説明します。
1. 全文検索:
ドキュメントの本文全体を検索対象とする機能です。ファイル名やタイトルだけでなく、内容に基づいて必要な情報を見つけることができます。曖昧な記憶からでも関連文書を探し出せる可能性が高まります。
2. 絞り込み検索:
日付、作成者、ファイル形式など、複数の条件を組み合わせて検索結果を絞り込む機能です。大量の情報の中から、より正確に目的の情報にたどり着くことができます。
3. キーワードハイライト:
検索結果や文書内で、検索キーワードをハイライト表示する機能です。関連部分を素早く見つけることができ、文書の内容を効率的に確認できます。
4. メタデータ検索:
ファイルに付与されたタグやカテゴリなどのメタデータを用いて検索できる機能です。文書の内容だけでなく、文書の属性に基づいた検索が可能になります。
5. 類義語検索:
入力したキーワードの類義語も含めて検索する機能です。検索の網羅性が高まり、より多くの関連情報を見つけることができます。
6. 検索速度:
大量のデータの中から瞬時に結果を表示できる処理速度も重要です。検索に時間がかかると、ツールの使用頻度が低下する可能性があります。
7. 検索結果の並べ替え:
関連度や日付など、さまざまな基準で検索結果を並べ替えられる機能です。目的の情報により早くたどり着けます。
これらの検索機能が充実していることで、情報の蓄積量が増えても、必要な情報に素早くアクセスできます。結果として、情報の有効活用が促進され、業務効率の向上につながります。
情報整理ツールを選択する際は、これらの機能の有無や性能を比較し、自社のニーズに最も適したものを選ぶことが重要です。また、実際に試用してみて、検索の使い勝手を確認するのもおすすめします。適切な検索機能を持つ情報整理ツールを選択することで、組織の情報管理が大幅に改善され、生産性の向上につながるでしょう。
情報整理ツールを最大限活用するためのポイント:業種別効果と選び方
情報整理ツールは業種や企業規模によって最適な活用方法や得られる効果が異なります。ここでは実際の導入企業18社の事例から分析した業種別効果と、成功のための選び方のポイントをまとめています。
業種別の効果最大化ポイント
様々な業種で情報整理ツールはどのような効果をもたらしているのでしょうか。下記のヒートマップをご覧ください。

※ 本表は18社の導入事例分析から抽出した効果データをもとに作成しています
このヒートマップから、業種ごとに特に効果的な活用領域が見えてきます:
- IT・開発業界では情報検索時間の削減(★★★★★)に最も効果があります。いい生活株式会社では「開発ドキュメントの検索時間が2日から3時間に短縮された」という成果を上げています。技術情報の検索性向上に重点を置くことで、開発効率を大幅に高められます。
- 医療・介護業界では属人化解消と標準化(★★★★★)で特に高い効果を発揮します。医療法人風林会では「10院舎間のマニュアルが統一され、患者対応の品質が均一化された」という成果があります。多拠点で統一された品質を実現するのに最適です。
- 製造業ではマニュアル作成効率化(★★★★★)で優れた成果が出ています。大和財託株式会社では「作業手順書の作成・更新時間が1週間から2日に短縮された」と報告されています。特に画像付きマニュアルの作成が容易になることで、現場の生産性向上につながります。
- 小売・EC業界ではコミュニケーション効率化(★★★★★)に優れた効果があります。株式会社cocoでは「顧客対応の問い合わせメールが月100通削減された」という具体的な数値効果が出ています。顧客対応ナレッジの共有に特に力を入れると効果的です。
こうした業種ごとの特性を理解することで、自社に最適な情報整理ツールの選定と活用方法が見えてきます。
情報整理ツールを選ぶ際の4つのポイント
情報整理ツールを選ぶ際には、以下の4つのポイントをチェックすることで、自社にとって最適なツール選びができます。
1. 使いやすさの確認
情報整理ツールは全社で活用してこそ効果を発揮します。ITに詳しくないスタッフでも直感的に使えるシンプルなインターフェースかどうかをチェックしましょう。
実際に株式会社cocoでは「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」ほどシンプルなツールを選んだことで、全社での活用率が高まりました。使いやすさは、導入後の定着率に直結する重要な要素です。
2. 共有のしやすさの評価
整理した情報は、共有しておくことで別の場面で活用可能な状態になり、資産化できます。情報共有に手間がかかると、情報共有が活発化せず、せっかく整理した情報を有効活用できません。
スカパーJSAT株式会社では、技術情報の共有がスムーズになったことで「技術ドキュメントの作成時間が約50%短縮」される効果がありました。特に部署間や拠点間での情報共有がしやすいかどうかをチェックすることが重要です。
3. 検索機能の充実度
情報整理ツールを使うメリットは、情報を検索しやすくなる点です。業務マニュアル・請求書・納品書・議事録など、あらゆる情報を電子化することで、必要なときにパソコンで簡単に検索可能です。ツールによっては、全文検索やタグ検索といった機能も搭載されているため、より効率的に必要な情報を見つけられます。
いい生活株式会社では「情報がわかる人に聞かないといけない状態から、情報を自分で見つけられる状態に変わりました」と報告しており、高性能な検索機能が業務効率化に大きく貢献しています。
4. 業種に合った機能の有無
上記のヒートマップでも明らかなように、業種によって特に効果的な機能が異なります。自社の業種でどのような機能が特に重要かを考慮し、その機能が充実したツールを選ぶことが成功への近道です。
例えば製造業であれば画像編集機能の充実したツール、医療業界であればマニュアル管理機能の充実したツールというように、業種特性に合った機能を重視しましょう。
成功のための導入・活用ステップ
情報整理ツールの導入を成功させるためには、以下のステップを意識することが効果的です:
- 現状分析と目標設定: 自社の情報管理の課題を明確にし、ツール導入で達成したい目標を設定
- 段階的な導入: 一部のチームや部署での試験導入から始め、成功事例を作ってから全社展開へ
- 定期的な活用状況の確認: 導入後も定期的に活用状況をチェックし、必要に応じて運用方法を調整
- 使いこなすための工夫:
- 標準的な情報の命名規則やタグ付けルールを決める
- 定期的に情報をアップデートする担当者や頻度を決める
- 成功事例を社内で共有し、活用のヒントを提供する
いい生活株式会社では「情報を自分で見つけられる状態」を実現するため、情報の標準的な分類方法と検索キーワードの命名規則を決めることで、効果を最大化しています。
企業規模に合わせた活用ポイント
企業規模によっても、情報整理ツールの最適な活用方法は異なります:
【10〜50人規模】
小規模企業では、情報の属人化防止に特に効果を発揮します。創業メンバーの暗黙知を形式化し、全員がアクセスできる状態を作ることで、組織の成長をスムーズにします。
【50〜100人規模】
中規模企業では、部署間の情報共有やプロジェクト管理に活用するのが効果的です。部署の壁を越えた情報共有により、組織のサイロ化を防ぎ、コラボレーションを促進します。
【100人以上】
大規模組織では、情報の統一管理とセキュリティのバランスが重要です。複数拠点間での情報共有と、適切なアクセス権限設定を両立させることで、安全かつ効率的な情報管理を実現します。
※ 本セクションは18社の導入事例分析から抽出したデータをもとに作成しています。詳細な個別事例については、導入事例ページをご参照ください。
おすすめの情報整理ツール8選
情報整理ツールは、単なる情報管理ツールではなく、企業のDX化を推進し、競争力を強化するための重要なインフラと言えるでしょう。こうした視点に基づいてツールを選び、情報共有を促進することで、企業全体の効率性と生産性の向上が実現します。
ここでは、おすすめの情報整理ツールを紹介していきます。
- DocBase
- Notion
- OneNote
- DropBox
- Slack
- Helpfeel Cosense(旧Scrapbox)
- Google Keep
- Trello
DocBase
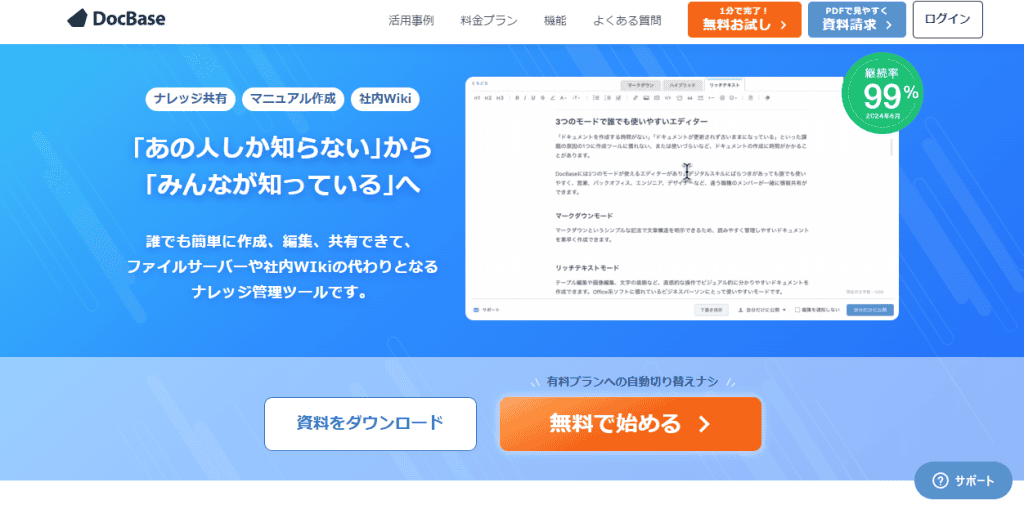
【DocBaseの特徴】
- マークダウンとリッチテキストに対応したハイブリッドエディター
- 画像ペイントモード:画像に矢印やテキスト、モザイクなどを直接配置
- 同時編集機能
- タグ機能
- 豊富な検索機能
ocBaseはナレッジ管理ツールとして誰でも使いやすい設計が特徴です。画像に直接注釈を加えられる画像ペイント機能や、複数人での同時編集が可能なリアルタイム編集機能により、チーム全体での情報共有をスムーズに行えます。
また、差し込み機能を使えば他のメモを簡単に参照でき、「知識の再利用」が容易になります。セキュリティ面でも高い評価を受けており、10,000社以上の導入実績があります。
⚡ ツール基本情報
💰 予算:スターター990円/月〜、ユーザー数無制限プランあり、30日間無料トライアル可能
🖥️ 使いやすさ:マークダウンとリッチテキスト両対応、ハイブリッドエディター搭載
🔧 用途:📝 マニュアル作成、💡 ナレッジ共有、📋 議事録作成
🔒 セキュリティ:ISO27001認証、2段階認証、グループ別アクセス権限設定
👥 運用負荷:専任管理者不要、タグとグループで整理可能
【DocBaseの料金プラン】
| 無料トライアル | スターター | ベーシック | レギュラー | ビジネス | |
| 料金 | 0円 | 990円/月 | 4,950円/月 | 9,900円/月 | 21,450円/月 |
| ユーザー数 | 無制限 | 3人 | 10人 | 30人 | 100人 |
| ストレージ | 無制限 | 3GB | 10GB | 30GB | 100GB |
Notion
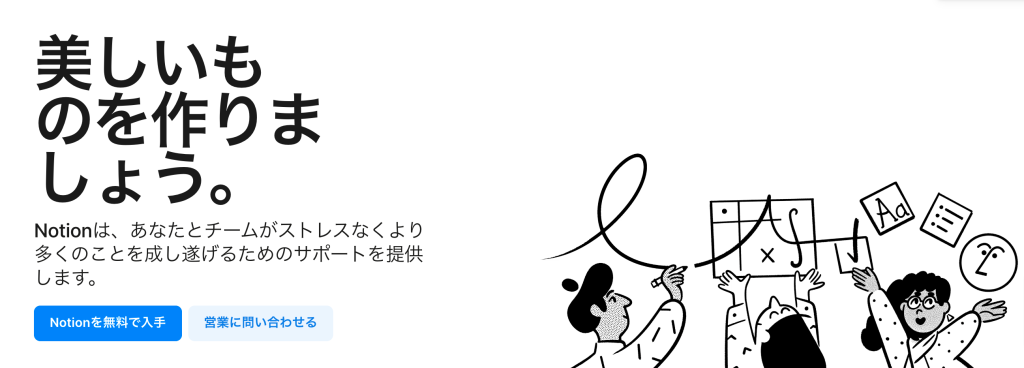
【Notionの特徴】
- 自由度と柔軟性が高い
- オールインワンのワークスペースを構築できる
- 豊富なテンプレートで即作成可能
Notionは、情報管理ツールだけでなく、文書作成やデータベース作成、プロジェクト管理などを搭載したツールです。カスタマイズの自由度が高く、自社に合わせてツールを作り変えられるため、業種や業務を問わず導入できる点が魅力です。
無料で提供されているテンプレートがあるため、多機能ながら操作に迷うリスクも抑えられています。使い勝手の良い多機能型ツールをお探しの場合は、検討してみてください。
⚡ ツール基本情報
💰 予算:無料プランあり、Plus 1,650円/ユーザー/月、ビジネス 2,500円/ユーザー/月
🖥️ 使いやすさ:ブロックベースのフレキシブルなインターフェース
🔧 用途:📊 データベース機能、📋 プロジェクト管理、🗂️ 個人の情報整理
🔒 セキュリティ:SOC 2 Type 2認証、データ暗号化
👥 運用負荷:テンプレート活用でスムーズな導入が可能
【Notionの料金プラン】
| 無料 | プラスプラン | 企業向けプラン | |
| 料金料金(月額/1ユーザーあたり) | 無料 | 1ユーザー1,650円 | 1ユーザー2,500円 |
| 人数 | ~10名 | 11名~ | ~250名 |
※251名以上の場合は要問い合わせ
OneNote

【OneNoteの特徴】
- スタイラスによる手書き入力と柔軟な思考整理
- 多様なメディアの組み合わせと情報整理機能
- 教育現場での活用と複数デバイス間での同期
OneNoteは、マイクロソフトが提供する多機能なデジタルノートアプリケーションです。iPadやSurfaceでのスタイラス入力(ペン型装置での入力)に対応し、柔軟な思考整理が可能です。情報整理、ノートシール(分類および優先順位付けする手法)、インク機能、メディアの組み合わせ、Web Clipper、共有機能など、多彩な機能を備えています。教育現場での活用も進んでおり、授業計画の整理や学習支援に役立ちます。
Microsoft 365のサブスクリプションに含まれ、モバイルアプリも提供されているため、さまざまなデバイスで利用できます。あらゆるファイルをノートに貼り付けられる点も特徴的で、ユーザーのニーズに幅広く対応する柔軟性の高いツールです。
⚡ ツール基本情報
💰 予算:Microsoft 365に含まれる(個人向け無料版あり)
🖥️ 使いやすさ:Officeアプリと連携したノート作成環境
🔧 用途:📝 メモ作成、🖼️ 画像付きノート、✏️ 手書き入力対応
🔒 セキュリティ:Microsoftアカウント認証、セクション保護オプション
👥 運用負荷:ノートブック、セクション、ページの階層構造で情報を整理
【OneNoteの料金プラン】
| 費用 | Personal | Family |
| 料金 | ¥14,900/年 | ¥21,000/年 |
| 人数 | 1人 | 最大6人 |
DropBox

【DropBoxの特徴】
- データ復元機能と外部ツールとの連携
- 多様なファイルの一元管理と全デバイス同期
- 充実したセキュリティ機能と柔軟な料金プラン
Dropboxは、個人やビジネス向けのオールインワンプラットフォームです。ファイルの保存・共有、PDF編集、ビデオ共有、電子署名など、多様な機能を1つのツールで提供します。データ復元機能により、誤削除や編集ミスに対応可能です。外部ツールとの連携も特徴的で、タスク管理やチャットツールと組み合わせて使用できます。
さまざまなファイルを一元管理でき、全デバイスでのファイル同期により、常に最新情報にアクセスできます。セキュリティ機能も充実しており、ファイルの復元やパスワード保護、閲覧履歴の確認が可能です。個人向けとビジネス向けの複数のプランを提供し、ユーザーのニーズに合わせた選択ができます。
⚡ ツール基本情報
💰 予算:Standard 1,500円/ユーザー/月〜
🖥️ 使いやすさ:ファイル同期とクラウドストレージの統合
🔧 用途:📁 ファイル共有、💾 大容量データ管理、🔄 バージョン管理
🔒 セキュリティ:AES 256bit暗号化、高度なセキュリティ機能、HIPAA準拠
👥 運用負荷:チーム共有フォルダ、選択的同期で効率的に管理
【Dropboxの料金プラン】
| プラン | Basic | Plus | Business | Essentials | Business Plus | Enterprise |
| 料金料金(月額/1ユーザーあたり) | 無料 | 1,500円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,880円 | 要問い合わせ |
Slack

【Slackの特徴】
- フリープランでも利用可能な個人・グループチャット機能
- 画面共有機能付きの音声・ビデオ通話機能
- チャンネルでの関連情報のまとめ管理機能
Slackは、効率的な情報共有とコミュニケーションを実現するビジネスチャットツールです。フリープランでも個人やグループチャットが利用可能で、柔軟な情報共有が可能です。また、画面共有機能付きの音声・ビデオ通話機能を搭載しており、フリープランでは一対一の通話が可能です。
チャンネル機能では、関連ページの追加やフォルダ作成ができ、関連情報をまとめて管理できます。これにより、個人でもチームでも円滑な情報共有が実現できます。Slackは、多様なコミュニケーション手段を提供することで、ビジネスの効率化と生産性向上をサポートします。
⚡ ツール基本情報
💰 予算:無料プランあり、Pro 1,050円/ユーザー/月、ビジネス+ 1,800円/ユーザー/月
🖥️ 使いやすさ:チャットインターフェースで直感的操作
🔧 用途:💬 リアルタイムコミュニケーション、⚡ チーム連携、🔌 アプリ連携
🔒 セキュリティ:GDPR準拠、データ暗号化、エンタープライズ向けセキュリティ
👥 運用負荷:チャンネル設計で情報を整理、検索機能で過去情報にアクセス
【Slackの料金プラン】
| プロ | ビジネスプラス | Enterprise Grid | |
| 料金(/年払い月額・1人あたり) | 925円 | 1,600円 | 要見積もり |
| ユーザー数 | – | – | – |
| ストレージ | – | – | – |
HelpfeelCosense(旧Scrapbox)

【HelpfeelCosenseの特徴】
- AI搭載の意図予測検索による最適な回答提示
- VOC分析機能による顧客ニーズや課題の把握
- 問い合わせ削減と顧客満足度向上の両立
HelpfeelCosenseは、AIと特許技術を活用した検索型FAQシステムです。企業のウェブサイトやアプリにFAQページを構築し、顧客の自己解決を促進することで、カスタマーサポート部門の負担を軽減します。意図予測検索、AIによるFAQドラフト自動生成、VOC分析機能などを備えており、問い合わせ削減と顧客満足度向上を実現します。
さらに、問い合わせフォーム、進化系チャットボットUI(ユーザーインターフェース)、PDF検索機能も提供しています。導入企業では、問い合わせ件数の大幅削減や顧客ニーズの把握、業務効率化などの成果があったと報告されています。Helpfeelは、デジタル化が進む顧客対応の中心的ツールとして活用されています。
⚡ ツール基本情報
💰 予算:無料プランあり、PERSONAL 無料、BUSINESS 1,100円/ユーザー/月、ENTERPRISE 要問い合わせ
🖥️ 使いやすさ:インライン編集方式でページ間リンクが容易、直感的な操作性
🔧 用途:🔍 FAQ・ヘルプセンター構築、💡 ナレッジベース作成、📊 VOC(顧客の声)分析
🔒 セキュリティ:AES-256bit暗号化、プライベートプロジェクト機能、アクセス制限設定
👥 運用負荷:AI搭載の意図予測検索による回答提示機能で運用コスト削減
【HelpfeelCosenseの料金プラン】
| プラン | PERSONAL | BUSINESS | BUSINESS ENTERPRISE |
| 料金(月額/1ユーザーあたり) | 無料 | 1,100円 | 要見積 |
Google Keep
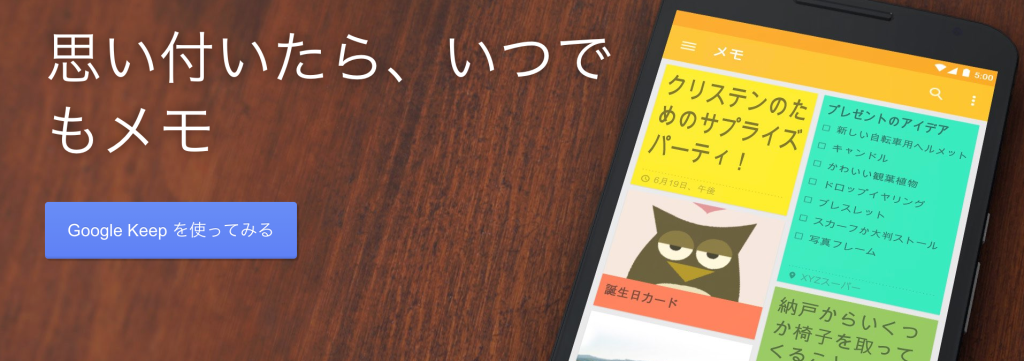
【Google Keepの特徴】
- 簡単な操作で音声入力や手書き入力が可能
- Gmailユーザー間での容易なメモ共有
- Googleドライブとの連携によるドキュメント化機能
Google Keepは、Googleが提供する無料の情報整理ツールです。シンプルな操作でメモ作成が可能で、スマートフォンの音声入力や手書き入力にも対応しています。Gmailアカウントを持つユーザー間でメモの共有が容易にでき、外出先でのアクセスも可能なため、リモートワーカーや移動の多い職種の人々に適しています。
Googleドライブとの連携により、メモをGoogleドキュメント化することもできます。基本機能は無料で利用可能ですが、有料プランではセキュリティの強化と高度な検索機能が追加されます。直感的な操作性と柔軟な利用方法により、幅広いユーザーに支持されています。
Trello

【Trelloの特徴】
- 付箋形式の直感的なタスク管理
- 豊富なテンプレートによる作業効率化
- リマインダー機能によるスケジュール管理とタスクもれ防止
Trelloは、直感的な操作が特徴のプロジェクト管理ツールです。タスクを付箋形式で管理でき、貼り付けや剥がしたりする感覚で操作が可能で、タスクのステータスを一目で把握できます。豊富なテンプレートが用意されており、作業時間の短縮や効率化に貢献します。リマインダー機能を使用して期限設定ができ、スケジュール管理やタスクもれの防止に役立ちます。
ボード、リスト、カードという基本要素で構成され、視覚的なレイアウトでチーム全体の進捗状況を共有できます。自動化機能やPower-Ups(アドオン)による機能拡張も可能で、さまざまな業界や用途に対応できる柔軟性を持っています。
【Trelloの料金プラン】
| プラン | Standard | Premium | Enterprise |
| 料金(月額/1ユーザーあたり) | $6 | $12.50 | $17.50 |
自社に必要な機能を備えた情報整理ツールを選ぼう

情報共有、ファイル管理、チャットなど、情報整理ツールにはさまざまな種類がありますが、用途特化型のツールでは運用中に機能不足に陥る可能性もあります。そこで、自社に必要な機能が網羅され、かつシンプルで使いやすいツールを選ぶことが重要です。誰でも直感的に操作できれば、社内への浸透もスムーズに進み、情報共有の効率化が期待できます。
DocBaseは、ナレッジ共有、会議のペーパーレス化、コミュニケーション活性化など、さまざまな場面で活用できる情報整理ツールです。社員が気軽にメモを作成・共有できる文化を構築し、タグ付けやグループ機能で情報を効率的に管理することで、情報へのアクセス性向上、意思決定の迅速化、社内文化の醸成に貢献します。さらに、社外メンバーとの情報共有や他のツールとの連携も可能で、DX化を促進する強力なツールとして活用できます。無料トライアルもご用意していますので、ぜひご検討ください。
参考情報と編集ポリシー
データ出典: 本記事の効果データと業種別分析は、DocBase公式サイトに掲載されている複数の導入事例とインタビュー内容を分析したものです。
ツール情報: 各ツールの機能・料金情報は、各公式サイトの最新情報を参照しています。
編集ポリシー: 本記事はDocBase開発元が作成していますが、各ツールの特徴や機能について可能な限り客観的で公正な情報提供を心がけています。当社の視点に基づく部分がありますが、読者の皆様に役立つ情報提供を第一に考えて作成しています。





