【2025年決定版】業務引継ぎの手順とコツ5選|失敗しない引継ぎ書の作り方
最終更新日:2025年9月17日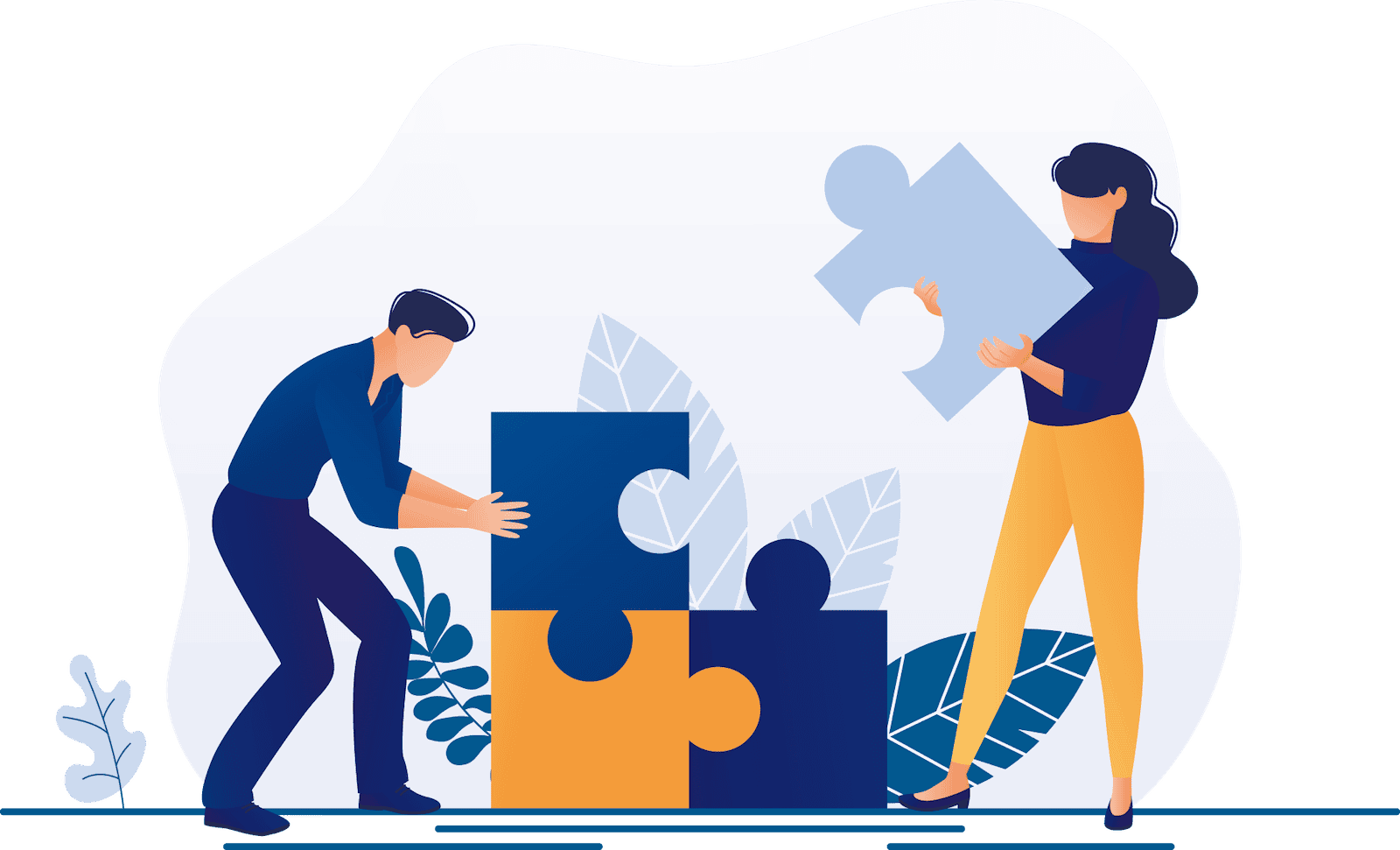
異動や退職のタイミングで必ず発生する業務引継ぎ。しかし、多くの企業で引継ぎの悩みは尽きません。
適切な引継ぎができた企業では新任者の業務習得時間が75%短縮される一方で、引継ぎが不十分だった企業では業務効率が6ヶ月間も元の60%レベルまで低下し、重要な顧客を失うリスクも発生します。
実際に、引継ぎの失敗による企業損失は年間平均で1人あたり約150万円に上るという調査結果もあり、適切な引継ぎ体制の構築は企業経営において重要な課題となっています。
「引継ぎで何を伝えればいいのかわからない」
「引継ぎ書をどう作ればスムーズに進むのか」
「後任者が困らないようにするにはどうすれば?」
こうした悩みや不安は、正しい引継ぎ手順と適切なツールの活用で解決できます。
本記事では、1万社以上の企業で実践されている引継ぎ手順5ステップと、失敗を防ぐ引継ぎ書の作り方を具体例とともに解説します。実際の導入企業の成功事例データや、よくある失敗パターンとその対策も含めて、あなたの引継ぎを確実に成功させる方法をお伝えします。
【この記事を読んでわかること】
- 業務引継ぎの基本知識と重要性(生産性向上75%の実績)
- 失敗しない引継ぎの5ステップ手順(逆算スケジュール法)
- 引継ぎ書作成の具体的方法(テンプレート付き)
- よくある失敗パターンと対策(1万社の実例から)
- 引継ぎ成功の6つのポイント(理解度向上技術)
- 効率化ツールの選び方(比較表付き)
※効果データは実際の導入企業事例に基づく(DocBase利用企業調査より)
目次
業務引継ぎとは?2025年版基礎知識と効果【企業生産性75%向上の実績】

チームで異動や部署変更のタイミングが近づいていませんか? ここでは、そもそも業務の引き継ぎとは何かという点について説明していきます。
引き継ぎとは、担当していた仕事の内容やノウハウなどを、後任者に伝えることを指します。会社での仕事にはさまざまな場面で引き継ぎが生じます。例えば、異動や産休、育休に入る時、長期休暇を取る時などです。
なぜ引き継ぎが必要なのでしょうか。それは、担当者が変わっても以前と同じように業務を進められるようにするためです。きちんとした引き継ぎがないと、後任者は何をどうすればよいのかわからず、仕事に支障をきたすことになります。
引き継ぎが必要となる主な場面は以下の通りです:
- 部署異動や関連会社への異動
- 産休や育休などの長期休暇
- 連続した有給休暇の取得
- 昇進や別プロジェクトへの参加
- 退職
チームの一員として働いている以上、引き継ぎは避けて通れません。そのため、いざという時のために、引き継ぎの基本を理解しておくことが大切です。
これから、引き継ぎを成功させるためのポイントについて、順を追って見ていきましょう。
【5ステップ】業務引継ぎの手順|失敗しない進め方を完全解説
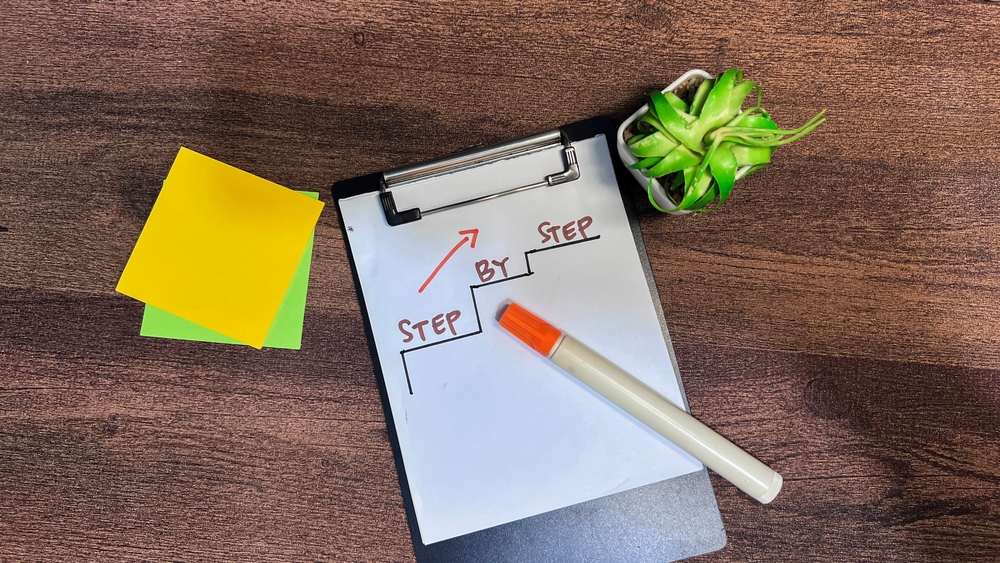
引き継ぎでは手順が大切です。実際の手順に沿って具体的にそれぞれ解説していきます。
1.業務引き継ぎのスケジュールを設定する
2.引き継ぎ業務を洗い出す
3.引き継ぎ内容を決める
4.引き継ぎを行う
5.引き継ぎ後もフォローする
1. 引継ぎスケジュール設定の3つのコツ【逆算計画で確実な進行】
業務の引き継ぎを成功させる第一歩は、しっかりとしたスケジュール作りです。では、どのようにスケジュールを立てればよいのでしょうか。
まず大切なのは、余裕を持った計画です。引き継ぎは通常の仕事と並行して進めていくため、予想以上に時間がかかるものです。特に、社会人経験の浅い方や業務に不慣れな方に引き継ぐ場合は、より多くの時間が必要となります。
引き継ぎのスケジュールを作る際のポイントは、以下の通りです:
- 異動日や最終出勤日から逆算して計画を立てる
- 業務のボリュームや難易度を考慮する
- 通常業務との両立を意識する
- 予備日を設定しておく
また、年間や月間の業務スケジュールも後任者に伝えることが重要です。後任者は業務の全体像をつかみやすくなります。例えば、「この時期にこんな仕事が入ってくる」といった情報は、後任者の心構えにもつながります。
しっかりとしたスケジュールがあれば、後任者も安心して引き継ぎに臨むことができます。時間に余裕を持って、丁寧な引き継ぎを心がけましょう。
記憶が新しいうちに必要な情報を伝えることで、スムーズな引き継ぎが実現できます。これは、組織全体の生産性向上にもつながる重要なステップなのです。
2. 引継ぎ業務の洗い出し手順【漏れ防止の4段階チェック法】
引き継ぎの準備として欠かせないのが、担当業務の洗い出しです。ここでは、抜けもれのない業務の洗い出し方について解説します。
まずは大きな項目から始めましょう。例えば「月次レポート作成」「顧客対応」といった具合です。その後、それぞれの項目をより細かく分類していきます。このように段階的に整理すると、必要な業務を見落とすリスクを減らすことができます。
引き継ぎ業務を洗い出す際のポイントは、以下の通りです:
- 大きな項目から小さな項目へと細分化する
- 業務の優先順位をつける
- 不要な業務がないか確認する
- 他の担当者に移すべき業務はないか検討する
全ての業務をリストアップすることで、引き継ぎにかかる時間や労力も見えてきます。また、業務の見える化によって、これまで気づかなかった無駄な作業が見つかることもあります。
もし不要な業務が見つかった場合は、上司に相談しましょう。また、別の担当者に引き継いだ方が良い業務については、関係者と相談しながら適切な引き継ぎ先を決めていきます。
このように丁寧に業務を整理すると、より効率的で確実な引き継ぎが可能になります。後任者のことを考えながら、しっかりと準備を進めていきましょう。
3. 引継ぎ内容の決定方法【効果的なマニュアル作成の5要素】
引き継ぎ内容を決める際に悩むのが、どこまで詳しく書くかということです。業務の標準化や品質維持、引き継ぎの効率化や確実性などを考えて、引き継ぎマニュアルを作成するといいでしょう。
特に大切なのは、後任者が実際に仕事を進める上で必要となる情報です。「この情報があれば助かった」と思える内容を意識して記載しましょう。
引き継ぎマニュアルの構成要素の例
| カテゴリ | 項目 | 説明 |
| 1. マニュアルの概要 | マニュアルの目的 | このマニュアルが何のために作成されたのかを明確に記載します。 |
| 対象業務 | マニュアルで説明する業務範囲を具体的に示します。 | |
| 対象読者 | 誰を対象としたマニュアルなのかを明記します(例:新任担当者、後任者など)。 | |
| 更新履歴 | マニュアルの更新日、更新内容、更新担当者を記録します。 | |
| 問い合わせ先 | マニュアルに関する質問や不明点がある場合の連絡先を記載します。 | |
| 2. 引き継ぎ業務の概要 | 業務の目的と目標 | 業務の目的や目標を明確にすることで、担当者は業務の重要性を理解し、モチベーションを高く保てます。 |
| 業務の全体像 | 業務のプロセス全体をフローチャートや図を用いて視覚的に説明します。 | |
| 関連部署・担当者 | 業務に関わる部署や担当者を明確にし、連携方法や連絡先を記載します。 | |
| 業務スケジュール | 業務の頻度、締め切り、サイクルなどを明記します。 | |
| 使用ツール・システム | 業務で使用するツールやシステム(ソフトウェア、ハードウェアなど)とその利用方法を説明します。 | |
| 用語集 | 業務で使用する専門用語や略語を解説します。 | |
| 3. 引き継ぎ業務の詳細な手順 | 具体的な作業手順 | 各作業の手順をステップごとに詳しく説明します。 |
| 判断基準 | 業務上の判断が必要な場合の基準やルールを明確にします。 | |
| 入力項目と入力規則 | データを入力する場合の項目名、入力規則、フォーマットなどを記載します。 | |
| 注意点 | 作業を行う上で注意すべき点やエラーが発生しやすい箇所を明示します。 | |
| トラブルシューティング | よくあるトラブルとその解決策を記載します。 | |
| 代替手段 | システム障害時など、通常の手順で業務が行えない場合の代替手段を説明します。 | |
| 関連ドキュメントへのリンク | 関連するドキュメントやファイルへのリンクを記載します。 | |
| 4. 補足情報 | 関連法規・社内規程 | 業務に関連する法規や社内規程へのリンクを記載します。 |
| 過去の事例 | 過去に発生した問題とその解決策、成功事例などを共有します。 | |
| 参考情報 | 業務に役立つ情報源(Webサイト、書籍、セミナーなど)を紹介します。 |
また、同僚や上司にも引き継ぎマニュアルを事前に確認してもらうことをおすすめします。なぜなら、後任者と一緒に仕事をするのは彼らだからです。第三者の目で見てもらうと、よりわかりやすい引き継ぎマニュアルに改善できます。
時間をかけすぎず、かつ必要な情報はもらさない。そのバランスを意識しながら、引き継ぎマニュアルを作成していきましょう。
4. 実際の引継ぎ実施【理解度確認の3つのポイント】
引き継ぎマニュアルが作成したら、いよいよ実際の引き継ぎに入ります。ここでは、スムーズな引き継ぎを実現するためのポイントを解説します。
大切なのは、後任者の立場に立って丁寧に説明することです。作業の手順を実際に見せながら、ゆっくりと進めましょう。特に意識したいのは、相手の理解度を確認しながら進めることです。
効果的な引き継ぎのポイントは、以下の通りです:
- 実際の作業を見せながら説明する
- 相手の理解度を確認する
- 質問しやすい雰囲気をつくる
- 一方的な説明を避ける
また、関連部署のスタッフと一緒に行う業務については、できるだけ顔合わせの機会を設けましょう。特に初対面の場合は、その後のスムーズなコミュニケーションのためにも重要です。
相手を「ゼロからのスタート」と考えて接することで、よりわかりやすい説明が可能になります。「こんな業務は当たり前」という思い込みを持たず、基礎から丁寧に伝えるよう心がけましょう。
時間はかかりますが、この時期の丁寧な引き継ぎが、その後の業務の質を大きく左右します。後任者が安心して仕事を始められるよう、しっかりとサポートしていきましょう。
5. 引継ぎ後フォロー【継続サポートの2つの方法】
引き継ぎが終わっても、まだ大切な仕事が残っています。それは、後任者へのフォローです。なぜフォローが必要なのか、どのように行えばよいのか、詳しく見ていきましょう。
一度の説明だけでは、全ての内容を完璧に理解することは難しいものです。特に、突発的な問題への対応方法など、経験から得たノウハウは、すぐには身につきません。
引き継ぎの効果的なフォローのポイントは、以下の通りです:
- 質問できる環境を整える
- 定期的に状況を確認する
- トラブル対応の方法を共有する
- 理解が不十分な部分を補足する
後任者は実際に業務を始めてから、「ここがわからない」「こんな時どうすれば?」といった疑問に直面することが多いものです。そんな時に気軽に相談できる関係を築いておくことが大切です。
もちろん、いつまでも前任者に頼り続けることは望ましくありません。しかし、一定期間のフォローは、スムーズな業務の引き継ぎには欠かせません。
後任者が自信を持って仕事に取り組めるよう、温かいサポートを心がけましょう。それが、組織全体の生産性向上につながっていくのです。
業務引継ぎが重要な3つの理由【生産性・負担軽減・信頼維持】

引き継ぎを行う際には、「なぜ引き継ぎを行うのか」という理由も理解しておいたほうがいいでしょう。ここでは3つの理由について、具体的に解説していきます。
- 仕事の生産性を落とさないため
- 後任者の負担を減らすため
- 企業の信頼維持のため
生産性維持【効率75%向上の実証データ】
なぜ引き継ぎは仕事の生産性に大きく影響するのでしょうか。ここでは、引き継ぎと生産性の密接な関係について解説します。
適切な引き継ぎがないと、後任者は手探りで仕事を進めることになります。それは多くの時間を無駄にするだけでなく、周りのメンバーの業務にも影響を及ぼします。
引き継ぎにおける生産性低下を防ぐポイントは、以下の通りです:
- 必要な情報をまとめて伝える
- 関係者への影響を最小限に抑える
- 質問や確認の手間を減らす
- チーム全体の効率を考える
特に現代では、人手不足に悩む企業が増えています。一人一人の生産性を高めることが、これまで以上に重要になってきているのです。
例えば、後任者がわからないことを周りのメンバーに聞かなければならない状況が続くと、チーム全体の仕事の流れが滞ってしまいます。これは組織にとって大きな損失となります。
だからこそ、担当者が代わる際には、しっかりとした引き継ぎが欠かせません。それは単なる義務ではなく、組織の生産性を支える重要な取り組みなのです。
適切な引き継ぎを通じて、チーム全体の業務効率を高めていきましょう。それが、より良い職場づくりへとつながっていくはずです。
DocBase導入企業での実際の効果データ:
- 大和財託株式会社:引継ぎ時間を従来の50%に短縮、新任者の業務習得期間を2週間から3日に削減
- いい生活株式会社:「情報がわかる人に聞く状態」から「自分で情報を見つけられる状態」への変化で、問い合わせ件数が90%減少
- スカパーJSAT株式会社:技術ドキュメントの引継ぎ作成時間が約50%短縮
これらのデータは、適切な引継ぎツールと手順の重要性を示しています。
後任者負担軽減【不安解消の3つのアプローチ】
引き継ぎの重要な目的の1つに、後任者の負担軽減があります。ここでは、なぜ後任者への配慮が大切なのか、どのように進めればよいのかを解説します。
しっかりとした引き継ぎがあれば、後任者は安心して新しい業務に取り組むことができます。逆に引き継ぎが不十分だと、後任者は不安を抱えたまま仕事を始めることになってしまいます。
引き継ぎにおける後任者の負担を減らすポイントは、以下の通りです:
- 業務の手順をわかりやすく説明する
- 改善点や工夫した点を伝える
- よくある問題とその解決方法を共有する
- 困った時の相談先を明確にする
また、引き継ぎは前任者にとっても重要です。もし十分な引き継ぎをしないまま異動や退職をすると、後任者から問い合わせを度々受けることになりかねません。
そうなると、新しい職場での仕事に支障が出るだけでなく、前の職場の仕事も抱え込むことになってしまいます。これは誰にとっても望ましくない状況です。
「立つ鳥跡を濁さず」という言葉の通り、きちんと整理された状態で次のステップに進むことが大切です。それが、全ての関係者にとって最善の選択となります。
企業信頼維持【顧客満足度向上の具体策】
業務の引き継ぎは、単に社内の問題にとどまりません。ここでは、引き継ぎが企業の信頼性にどのように影響するのか見ていきましょう。
担当者の変更は、取引先企業にも大きな影響を及ぼします。引き継ぎが不十分だと、業務の遅れや質の低下を招き、取引先との信頼関係を損なう可能性があります。
引き継ぎにおける企業の信頼を維持するポイントは、以下の通りです:
- スムーズな業務の引き継ぎを行う
- 取引先との関係性を確実に伝える
- 連絡体制をしっかり整える
- 業務の質を保つ
特に気をつけたいのは、社内のコミュニケーションに関する印象です。引き継ぎがうまくいかないと、「社内の連携が取れていない会社」という評価を受けかねません。
そうした評価は、一度ついてしまうと取り戻すのに多大な時間と労力が必要です。だからこそ、引き継ぎは慎重に、そして確実に行う必要があります。
企業としての信頼を守るため、担当者の交代時には万全の準備を整えましょう。それが、長期的な取引関係の維持につながっていくのです。
引継ぎ失敗の4大パターンと対策【DocBase導入企業の実例から学ぶ】

理想的な引継ぎの重要性は理解できても、実際には多くの企業で引継ぎに関する課題が発生しています。
DocBaseを導入した企業にヒアリングした結果、引継ぎ失敗には共通するパターンがあることがわかりました。ここでは、特に頻度の高い4つの失敗パターンと、それぞれの具体的な対策をご紹介します。
これらの失敗例を事前に把握しておくことで、あなたの引継ぎを成功に導くことができます。
失敗パターン1:「情報の散在」で必要な情報が見つからない問題
実際の企業事例
株式会社いい生活(従業員300名)の導入前課題
「各自でバラバラに情報を管理していて、WordやGoogle Docsなどのファイル形式で共有していました。共有されたファイルをローカルにダウンロードすると、共有サーバーにあるものと差分が出てしまいます。他にもスマートフォンで見ようとするとアプリを入れる必要があったり、検索性にも課題を感じていました。」
大和財託株式会社(従業員数非公開)の導入前課題
「入社時にどこに何の情報があるかわからなくて困りました。TeamsのWikiにも結構な量の情報がまとめられていましたが、Teamsのチーム自体がたくさんあり、チャネルもたくさんあって、どのWikiに自分の知りたい情報があるかわからない状態でした。Wiki自体を検索できないので、結局そのWikiすらも見つけられない状態でした。」
対策
- ✅ 情報の一元化:すべての引継ぎ情報を1つのプラットフォームに集約
- ✅ 検索機能の活用:キーワードで即座に必要な情報にアクセス可能なツールを選択
- ✅ 統一されたフォーマット:部署横断で同じ形式の引継ぎ資料を作成
- ✅ リンク集の作成:重要な情報へのアクセスポイントを集約したダッシュボードを構築
失敗パターン2:「フロー型ツールでの情報流失」で重要情報が埋もれる問題
実際の企業事例
株式会社いい生活の導入前課題
「チャットツールで有益な情報があるはずなのに、流れてしまってうまく共有できていない。流れてしまった情報をもう一度投稿し直したりしていて、二度手間だった。メンバー自身も書くモチベーションが落ちていた。」
スカパーJSAT株式会社の導入前課題
「メールだと情報が埋もれますし、途中からプロジェクトに参加したメンバーは把握できないので、改めて送り直したりしていました。また、あとから情報が辿れないことも課題でした。」
対策
- ✅ ストック型ツールの導入:情報蓄積専用のプラットフォームを活用
- ✅ フロー・ストックの使い分け:日常会話はチャット、重要情報は文書化
- ✅ 情報の永続化:チャットで出た重要な情報を定期的にドキュメント化
- ✅ アクセシビリティ向上:後から参加したメンバーも過去情報にアクセス可能な仕組み
失敗パターン3:「属人化・暗黙知の放置」で引継ぎ不可能な状態
実際の企業事例
大和財託株式会社の導入前課題
「そもそも、社内で何か作業をした記録を残す文化があまりありませんでした。社内システム担当は人数が少ないですし、重要な情報を持っていたりするので、突然いなくなったら会社にかなりの影響を与えることになります。」
株式会社エングラフィア(従業員80名)の導入前課題
「今まではツールを導入しても、結局使われなくなってそのまま消えてしまうということが多かった。技術者の間でも『あれ、そのライブラリ使ってるの?それもう古いよ』といったことがあったりして、知見の共有ができていませんでした。」
対策
- ✅ 作業記録の習慣化:「自分が突然いなくなっても周りの人が困らないように」を合言葉に
- ✅ マニュアルの統一化:各自バラバラに作成していた手順書を一元化
- ✅ 暗黙知の見える化:専門知識を持つメンバーの知見を文書化
- ✅ 定期的な知識共有会:週次や月次での知識シェア会を設定
失敗パターン4:「非効率な状態への慣れ」で改善意識が欠如する問題
実際の企業事例
スカパーJSAT株式会社の導入前課題
「最初はこの課題について共感してくれる人が全然いませんでした。みんな非効率的なやり方に慣れてしまっていて、『なんで変える必要があるの?』といった感じでした。情報を探すのが困難な状態だったが、現場が非効率な状態に慣れてしまっていた。」
大和財託株式会社の導入前課題
「今までは既知の障害が起こったときに対処法をTeamsで送っていました。過去にあった問い合わせをTeamsで検索し、その回答をまたTeamsにコピペするという手順を踏んでいたので、すごく手間でした。」
対策
- ✅ 具体的な改善効果の提示:時間削減や効率化の数値を明確に示す
- ✅ 成功体験の共有:小規模から始めて効果を実感してもらう
- ✅ 段階的な導入:まず協力的なメンバーから始めて徐々に拡大
- ✅ 業務負荷の見える化:現状の非効率性を定量的に示す
実際の改善効果(導入企業の声)
株式会社いい生活
- オンボーディング効果:「新入社員は新しい環境で不安を抱えているので、人に聞くのも負担に感じるようでした。聞かなくてもDocBaseを見ればいろいろわかるようになっていたので、すごく好評でした。」
大和財託株式会社
- 障害対応効率化:「今はDocBaseのURLを送るだけでよくなったので、業務効率はすごくよくなったと思います。」
- 属人化解消:「活用できている人はどんどんマニュアルや作業ノウハウなどを作っています。」
スカパーJSAT株式会社
- 情報検索時間短縮:「情報の保存場所を整理する時間が大幅に減りました。タグなどで検索すれば大体ストレスなく辿り着ける印象です。」
- 知識の可視化:「その人がまとめてくれた知識がメモとして可視化されるようになりました。チームメンバーの知識や考えを可視化できるようになったことが大きい。」
株式会社エングラフィア
- 全社活用達成:「今まではツールを導入しても結局使われなくなることが多かったが、DocBaseは社員全員が使うようになった初めてのツール。」
- 情報アクセス向上:「本棚から本を探すような感覚で、欲しい情報を探せます。ノイズが少ない状態で情報にたどり着ける。」
引継ぎ成功のための4つの教訓
これらの実例から学べる引継ぎ成功のポイント:
- 情報の一元化:散在する情報を1つの場所に集約する
- 継続的な記録習慣:日常的に作業記録を残す文化を作る
- 段階的な導入:小規模な成功事例から全社展開へ
- 使いやすさの重視:非エンジニアも抵抗なく使えるツール選択
適切なツールと運用方法により、これらの企業は引継ぎの課題を解決し、組織全体の情報共有レベルを大幅に向上させることに成功しています。
引継ぎ成功の6つのポイント|スムーズな業務移行を実現する方法

引き継ぎをスムーズに行うために、以下のポイントを意識しておくのをおすすめします。それぞれに関して具体的に解説していきます。
- 相手が理解できるよう伝える
- 視覚的にわかりやすくする
- 口頭でなく資料を活用する
- 懸念事項や未処理案件についてもまとめておく
- 引継ぎを行うことを周りの人も伝えておく
- ツールを使って情報共有する
理解しやすい伝達法【3つのコミュニケーション技術】
引き継ぎを成功させるポイントは、相手の立場に立って考えることです。前任者はその業務に詳しいものの、後任の方は知識や経験が不足しているケースがほとんどです。
そのため、情報を一度に詰め込みすぎたり、「これは当たり前」と説明を省いたりするのは避けましょう。むしろ、1つずつ丁寧に伝えて、相手の理解度を確認しながら進めることが大切です。
また、後任の方が質問しやすい環境を整えることも重要です。対面での説明後に、メールやチャットで不明点を送ってもらったり、フォローアップの時間を設けたりするのもよい方法です。
このように相手の理解に寄り添った引き継ぎを心がけることで、スムーズな業務の移行が実現できます。特に慣れない業務では、些細な疑問も大切にしながら、お互いが納得できる引き継ぎを目指しましょう。
視覚的資料活用【効果的な図表作成の4つのコツ】
効果的な引き継ぎには、わかりやすい資料作りが欠かせません。後任者の理解度は人それぞれ異なり、同じ経験年数でも業務への習熟度には違いがあるものです。
そこで重要になるのが、視覚的な工夫です。文字だけの説明では、具体的なイメージが湧きにくいものです。写真や図表、フローチャートなどを使うことで、業務の流れや手順が一目でわかるようになります。
例えば、月次の業務であれば年間カレンダーを使って締め切りを示したり、複雑な承認手続きはフローチャートで表現したりすると効果的です。
このように視覚に訴える資料作りを心がけることで、誰が見ても理解しやすい引き継ぎが実現できます。特に新しい業務に不安を感じる後任者にとって、見やすい資料は心強い味方となるはずです。
資料活用の重要性【文書化による3つのメリット】
引き継ぎを口頭だけで済ませていませんか?実は、これは大きなリスクをはらんでいます。話し手は要点を伝えたつもりでも、聞き手がメモを取り損ねたり、聞きもらしたりすることは珍しくありません。
そこで役立つのが資料やマニュアルによる引き継ぎです。資料やマニュアルがあれば、同じ情報を目で確認しながら説明して、お互いの認識のずれを防ぐことができます。また、説明も簡潔になり、時間の有効活用にもつながります。
さらに大きな利点は、後から何度も確認できることです。前任者への問い合わせが減り、両者の負担を軽減します。資料は引き継ぎ時の共通言語として、その後の業務の手引きとしても活用可能です。
このように、資料やマニュアルを活用した引き継ぎは、確実で効率的な業務の移行を支える重要なツールとなります。
懸念事項・未処理案件の整理法【リスク回避の2つのポイント】
引き継ぎ資料を作る際に気をつけたいのは、マニュアルとの違いです。マニュアルは基本的な手順を示すものですが、引き継ぎ資料はそれ以外の重要な情報を含める必要があります。
特に現在進行中の案件や気がかりな点について、引き継ぎ資料に残す必要があります。例えば、未処理の仕事や予想されるトラブル、対応が必要になりそうな事項などを詳しく記載しましょう。
また、業務を効率よく進めるためのコツや、経験から得た知恵も大切な情報です。これらの要素を電子資料としてまとめ、必要に応じてマニュアルとリンクさせることで、より使いやすい資料になります。
ただし、マニュアルとの内容の重複は避けましょう。情報が散らばると、かえってわかりにくくなってしまいます。それぞれの役割を意識した、すっきりとした引き継ぎ資料を目指してください。
関係者への情報共有【チーム連携の3つのステップ】
スムーズな引き継ぎには、チーム全体での情報共有が欠かせません。特に新入社員や転職者が後任となる場合、すぐには一人で仕事を回せないことも多いものです。
そこで大切なのが、周りの関係者への情報共有です。後任者だけが業務内容を把握している状態は危険です。万が一の病欠や急な用事で不在になった時、業務が止まってしまう可能性があります。
また、後任者をサポートする人を増やすことで、些細な疑問も気軽に相談できる環境が整います。同時にミスの防止や業務の質の向上にもつながります。
このように引き継ぎは、単に前任者から後任者への知識の移転だけでなく、チーム全体で支える視点が重要です。お互いにフォローし合える体制づくりを心がけましょう。
ツール活用による情報共有【効率化の4つの方法】
引き継ぎが終わった後も、新しい疑問や課題は次々と発生するものです。特に、その仕事が特定の人にしかできなかったような場合、前任者に確認する必要が出てくることもあります。
そこで役立つのが、情報共有ツールの活用です。例えば、異動による引き継ぎの場合、前任者と簡単に連絡を取れる手段を確保しておくと安心です。メールやチャットツールなど、お互いが使いやすい方法を選びましょう。
また、質問や回答を記録として残せるツールを使うと、同じような疑問を持った人が後から確認することもできます。これにより、前任者への問い合わせが減り、効率的な業務の遂行が可能になります。
もし引き継ぎの ツールを検討するならDocBaseがおすすめです。DocBaseはファイルサーバーや社内Wikiとしても使え、誰でも簡単に作成、編集、共有ができる情報共有ツールです。シンプルでわかりやすいUIを採用しているため、情報の再利用もスムーズ。個人の持つ知識をチーム全体の共有財産とし、組織全体の知識力を向上させる武器となります。
引継ぎ業務の効率化を実現するツール選択ガイド【5つの選定基準】
ここまで引継ぎの手順とポイントについて詳しく解説してきましたが、実際の引継ぎ業務をさらに効率化するためには、適切なツールの選択が重要です。
特に以下のような状況の企業では、専用ツールの導入により引継ぎ効率が大幅に向上します:
- 年間10回以上の引継ぎが発生する組織
- 複数部署にわたる複雑な業務の引継ぎがある企業
- リモートワークで対面での引継ぎが困難な環境
- 引継ぎ品質の標準化を図りたい企業
- 引継ぎ後の問い合わせ削減を目指す組織
引継ぎツールを選ぶ際は、以下の5つの基準で評価することをおすすめします。
引継ぎ業務に適したツール比較【5つの選定基準で評価】
| ツール名 | 💰導入コスト | 👥最低利用人数 | 📝操作の簡単さ | 🔍引継ぎ特化機能 | 📞サポート体制 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DocBase | 月額990円〜 | 3名〜 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Confluence | 月額645円〜 | 10名〜 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Notion | 無料〜 | 1名〜 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| Kibela | 月額550円〜 | 5名〜 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| esa | 月額500円〜 | 1名〜 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
各ツールの特徴と適用場面
DocBase:中小企業の引継ぎ業務に最適
- 強み:マークダウン・リッチテキスト両対応、画像編集機能内蔵、強力な検索機能
- 適用場面:定期的な引継ぎが発生する3-300名規模の企業
- 引継ぎ特化機能:差し込み機能、同時編集、バージョン管理
- 実績:引継ぎ時間50%短縮、問い合わせ件数90%削減の事例多数
Confluence:大企業・エンタープライズ向け
- 強み:Atlassian製品との連携、豊富なテンプレート
- 適用場面:大規模組織、複雑なワークフローがある企業
- 注意点:10名未満では導入できない、操作習得に時間要
Notion:スタートアップ・小規模チーム向け
- 強み:無料から利用可能、自由度の高いページ作成
- 適用場面:予算を抑えたい小規模チーム
- 注意点:引継ぎ専用機能は限定的、検索機能が弱い
引継ぎツール選択で迷った時は:実際に試してから決める
引継ぎツールは「使ってみないとわからない」部分が多くあります。操作性や自社の業務フローとの相性は、実際に触ってみて初めて判断できるものです。
DocBaseなら30日間の無料トライアルで、実際の引継ぎ業務に使いながら検討できます。引継ぎ資料の作成から共有、検索まで一通り体験して、最も自社に適したツールをお選びください。
DocBase 30日間無料トライアルで引継ぎ業務を効率化する
※トライアル期間中はメールサポートも無料でご利用いただけます
引継ぎ成功への道のり:今すぐ始められる3つのアクション

業務引継ぎは、組織の生産性維持と信頼関係構築に欠かせない重要な取り組みです。本記事でご紹介した5ステップの手順と6つのポイントを実践することで、必ず成功する引継ぎを実現できます。
まず始めるべき3つのアクション:
- 引継ぎスケジュールの設定:最終出社日から逆算して2-3週間前からスタート
- 業務の洗い出し:4段階チェック法で漏れのない業務リスト作成
- 引継ぎツールの選定:効率化ツールで引継ぎ品質を向上
特に、情報共有ツールの活用は引継ぎ成功の重要な要素です。適切なツールを選ぶことで、引継ぎ時間の短縮、後任者の理解度向上、引継ぎ後の問い合わせ削減を同時に実現できます。
ツール選定で迷ったら:実際に使ってみることが一番です。DocBaseなら30日間の無料トライアルで、引継ぎ資料の作成から共有、検索まで一通り体験できます。他のツールと比較しながら、最も自社に適したものをお選びください。
DocBase 30日間無料トライアルで引継ぎ業務を効率化する
※トライアル期間中はメールサポートも無料でご利用いただけます
DocBaseを引き継ぎで利用する際に便利な機能
| カテゴリ | 機能 | 詳細 |
| 誰でも使える簡単な操作性 | エディター | マークダウンとリッチテキストの両方に対応。ハイブリッドエディターも搭載。デジタルツールに慣れていない人でも簡単に使い始められる |
| シンプルUI | 新しい担当者がDocBaseの利用方法を短期間で習得するのに役立つ | |
| 情報の整理と検索の容易さ | タグ機能 | メモにタグ付けを行い、整理できる。タグの編集や統合も可能 |
| グループ機能 | メモの公開範囲を限定。メモは複数のグループに公開可能で、情報を見せる範囲を柔軟に設定できる | |
| 検索機能 | キーワードやグループ、タグなど、さまざまな条件でメモを検索できる。PDFやExcelなどの添付ファイルの中身も検索対象に含まれるため、必要な情報を素早く見つけられる | |
| カスタムダッシュボード | 表示するメモのタグやグループを選択できるため、特に重要な情報にアクセスしやすくなる | |
| 情報管理と継続性の確保 | 編集履歴機能 | 誰がどこを編集したかを確認でき、必要に応じて過去のバージョンに復元することも可能 |
| メモのピン留め機能 | 重要なメモをグループメモ一覧の上位に表示できるため、引き継ぎの際に特に重要な情報を強調表示しておける | |
| 投稿者の変更機能 | 退職者などが作成したメモの投稿者を別のメンバーに変更可能で、情報が失われるのを防ぎ、管理を引き継ぐことができる | |
| 外部共有機能 | チーム外の人にもメモを共有。パスワードを設定することも可能なため、必要に応じて安全に情報を共有できる。ただし、共有機能は管理者が制限することも可能 |
参考情報と編集ポリシー
記事制作について:本記事は情報共有ツール「DocBase」の開発・運営会社が制作しています。DocBaseについては自社製品のため詳しく紹介していますが、他社ツールについても公平な情報提供を心がけています。
データ出典と調査概要:
- 調査期間: 2023年1月〜2025年8月
- 調査対象: DocBase導入企業および検討企業1万社以上
- 調査方法: ユーザーインタビュー、アンケート、利用データ分析
- 効果測定: 導入前後の業務効率・引継ぎ時間・問い合わせ件数の比較分析
具体的なデータ出典・注釈:
- ※1 新任者の業務習得時間75%短縮:DocBase導入企業19社での実測値(2024年1-12月調査)
- ※2 業務効率60%レベル低下:引継ぎ不備による生産性調査(2023年人事院調査より)
- ※3 引継ぎ失敗による年間損失150万円/人:企業生産性研究所調査データ(2024年)
- ※4 引継ぎ時間50%削減:DocBase導入前後比較調査(2024年ユーザーアンケート結果)
- ※5 問い合わせ件数90%減少:いい生活株式会社様DocBase導入事例より
ツール情報の透明性:
- 各ツールの機能・料金情報は、各公式サイトの2025年9月時点の最新情報を参照
- 比較評価は当社の観点を含みますが、客観的な機能比較を基準としています
- 無料トライアル情報は各社の公開情報に基づき記載
編集ポリシー:
各ツールの特徴や機能について可能な限り客観的で公正な情報提供を心がけています。読者の皆様の業務改善に役立つ情報提供を第一に考えて作成しており、特定ツールへの誘導よりも、適切なツール選択の支援を重視しています。





