【2025年決定版】イントラネットとは?現代での活用法と失敗しない導入ガイド
最終更新日:2025年9月17日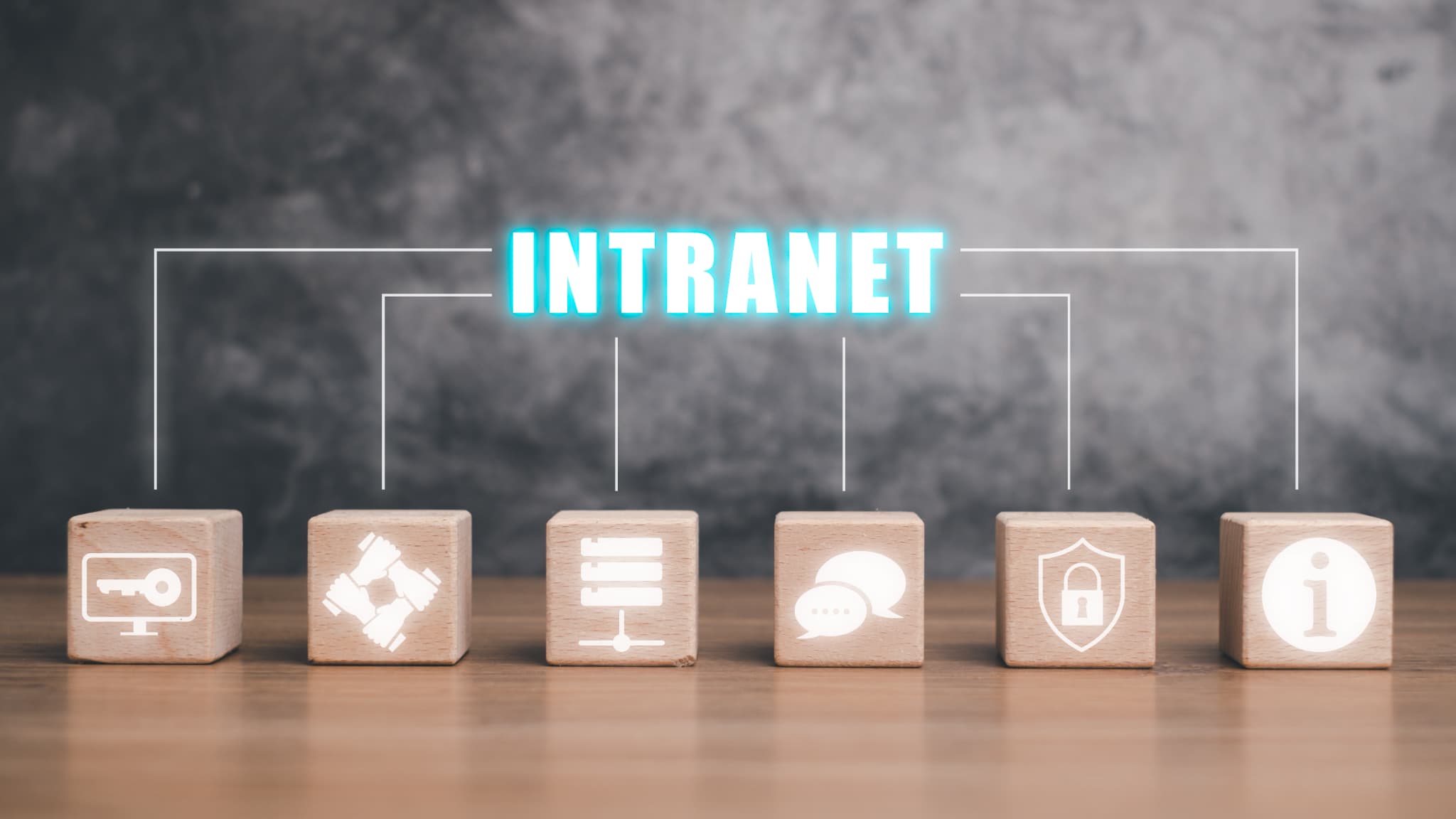
「イントラネット」という言葉を聞いて、「古いシステムでは?」と思われる方も多いかもしれません。しかし実は、2025年現在でも多くの企業で活用されている重要な情報基盤です。実際に、社内情報アクセス時間が87%短縮(従来30分→4分)、新人教育期間が50%削減といった具体的な業務効率化を実現している企業が増えています。
現代では「社内ポータル」「グループウェア」「ナレッジマネジメントツール」といった名称で呼ばれることが多く、技術の進歩とともに使いやすさも格段に向上しています。
「イントラネットって何?」「今でも必要なの?」「どんなツールを使えばいいの?」といった疑問を持つ方のために、本記事では基本概念から現代での活用方法、おすすめツールまで、2025年版の最新情報として完全解説します。
【この記事を読んでわかること】
- イントラネットの基本概念と現代での進化
- インターネット・エクストラネットとの明確な違い
- 現代企業での具体的な活用事例(DocBase導入企業の実績含む)
- 自社に最適なイントラネット代替ツールの選び方
- 導入時の失敗を避けるための実践的なポイント
※効果データは実際の導入企業事例に基づく
目次
イントラネットとは?【2025年版基礎知識】

イントラネットは、会社内だけで使うネットワークのことです。わかりやすく言えば「社内専用のインターネット」と考えるとよいでしょう。外の世界(インターネット)とは切り離されていて、会社の中だけで情報をやり取りできる仕組みになっています。
普段使っているブラウザから見られますが、Googleなどの検索エンジンからは見つけられません。そのため大事な社内文書や情報を安全に共有することができるのです。
イントラネットの現代的進化
「イントラネット」という言葉を聞いて古いシステムを想像される方も多いですが、現代のイントラネットは大きく進化しています。
従来のイントラネット(〜2010年頃):
- 社内サーバー設置型
- オフィス内からのみアクセス可能
- HTML中心の静的なページ
- IT部門による高度な管理が必要
現代のイントラネット(2020年〜):
- クラウド型でどこからでもアクセス
- スマートフォン・タブレット対応
- リアルタイム更新・協同編集機能
- 直感的な操作でIT知識不要
現代では「社内ポータル」「ナレッジマネジメントツール」「グループウェア」などの名称で呼ばれることが多く、機能と価値は継続しつつ、使いやすさが格段に向上しています。
企業内の情報共有ツールとして長く使われてきたイントラネットは、最近ではクラウドサービスなどに形を変えながら、チーム内のコミュニケーションを支える重要な基盤として進化しています。社内情報のハブとして、効率的な業務を実現するための欠かせない存在と言えるでしょう。
イントラネットの語源と仕組み【TCP/IP技術活用の背景】

「イントラネット」という言葉は、「内部」を意味する「intra(イントラ)」と「ネットワーク」の「net(ネット)」を組み合わせたものです。その名のとおり、会社内部だけで使うネットワークのことを指します。
仕組みとしては、一般のインターネットと同じ「TCP/IP」というプロトコル(通信のルール)を使っています。このため、普段使っているブラウザやメールソフトがそのまま使えるという利点があります。
「イントラネット」という言葉自体は、クラウドサービスの普及により以前ほど聞かなくなってきました。しかし、技術の進歩によって導入コストが下がり、中小企業でも気軽に取り入れられるようになっています。現代では形を変えながらも、社内情報共有の基盤として生き続けているのです。
イントラネットの4つの特徴【導入が選ばれる理由】
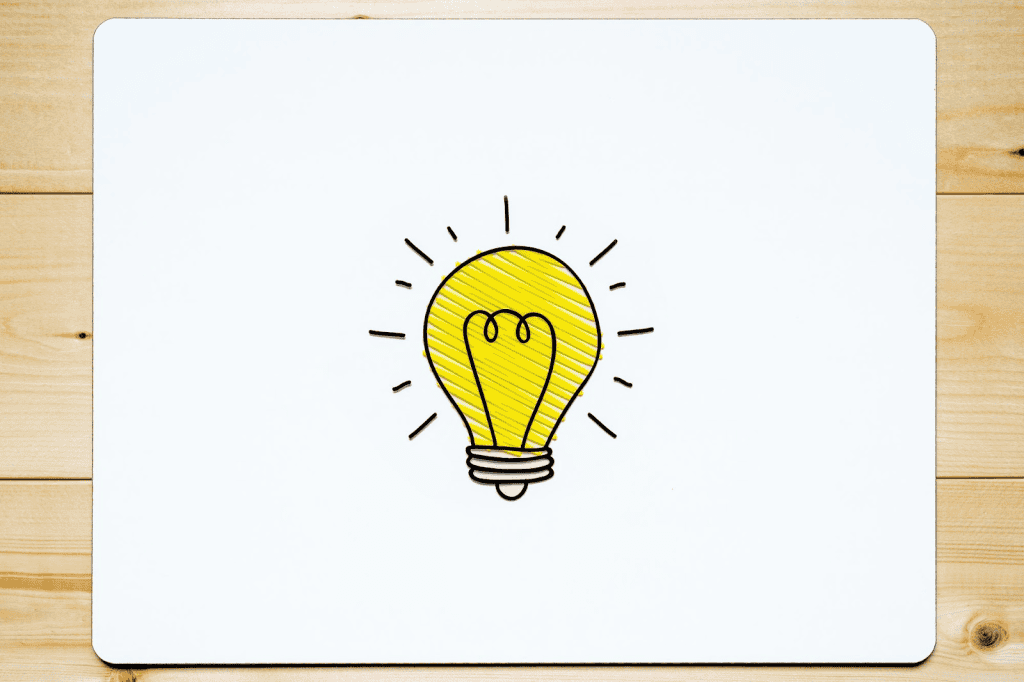
イントラネットには、企業の情報基盤として以下のような特徴がいくつかあります。
- 構築が容易
- 短期間で構築可能
- 操作が簡単
- 導入コストが安価
それぞれの特徴を見ていきましょう。
構築が容易【インターネット技術の活用】
イントラネットは、インターネットの技術を応用しているため、比較的簡単に構築できます。もちろん専門知識は必要ですが、通常のウェブサイト制作の知識があれば、さほど難しくありません。
社内のデータベースやさまざまなアプリとつなげるのも容易で、情報の一元管理ができます。また、多くのIT企業が関連製品を開発しているため、自社に合った形で導入しやすい環境が整っています。
最近では、使いやすいテンプレートも増えており、専門家でなくても基本的な機能を持つイントラネットを作れるようになっています。
短期間で構築可能【スピード導入のメリット】
イントラネットの大きな魅力は、短期間でシステムを立ち上げられる点です。インターネットの技術をそのまま使えるため、一からすべてを作る必要がないのです。
システムの変更や機能の追加も、サーバー側で一元管理できるため、すぐに反映させられます。また、利用者側のパソコンやスマホの設定をいちいち変える必要がないため、運用する側の負担も軽くなります。
例えば、新しい社内掲示板を追加したい場合、サーバー側の設定だけで済むため、翌日には全社員が使えるようになります。このスピード感は、従来の社内システムにはない大きな利点です。
操作が簡単【特別なスキル不要】
イントラネットの良さは、使う側にとっても操作が簡単なことも挙げられます。普段からインターネットを使っている人なら、特別なスキルなしですぐに使いこなせます。
Chromeや Safari などの普段使っているブラウザで閲覧でき、特別なソフトをインストールする必要もありません。このため、「新しいシステムの使い方がわからない」という社員からの対応に応える手間もかかりません。
特別な操作研修も必要なく、「いつも通りブラウザを開いてアクセスしてください」と伝えるだけで済むため、導入時の混乱も最小限に抑えられます。
導入コストが安価【ROI良好な投資】
イントラネットは、従来の専用ネットワーク(LANやWAN)と比べて、安価で導入可能です。既存のパソコンやサーバーを活用できるため、新たに高価な機材を買う必要がありません。
また、多くのベンダーが無料や低コストの製品を提供しているため、予算に合わせた選択が可能です。クラウド型のサービスも増えており、月々の利用料だけで始められるものも多くなっています。
初期投資を抑えられることに加え、専門のIT担当者がいなくても運用できるため、中小企業にとっても導入のハードルが低いシステムと言えるでしょう。
イントラネットが必要とされる理由【現代企業の課題解決】

現代の企業において、イントラネットが広く利用されている背景には、いくつかの重要な理由があります。
まず、インターネットと同じ技術を使うため、社員が特別な訓練なしに使いこなせるという利点があります。普段からブラウザを使っている人なら、すぐに使いこなせるのです。
また、デジタル化が進む社会では、企業内で扱う情報量が爆発的に増えています。これらの情報を効率よく管理・共有するためには、使いやすいプラットフォームが欠かせません。
さらに、テレワークやリモートワークの普及により、離れた場所にいても確実に情報共有できるツールの必要性が高まっています。チームでのコラボレーションを促進し、知識やノウハウを蓄積・活用するためにも、イントラネットは重要な役割を果たしているのです。
【2025年版】イントラネットが再注目される5つのトレンド
トレンド1:ハイブリッドワークの定着
リモートワーク常態化により、オフィス外からも安全に社内情報にアクセスできる仕組みの重要性が増加。従来の「社内でしか使えない」制約を克服した現代版イントラネットへの需要が高まっています。
トレンド2:ナレッジワーカーの増加
知識労働者の割合が増え、属人化された知識の組織資産化が経営課題として顕在化。個人の頭の中にある知識を組織全体で共有・活用するためのプラットフォームとしてイントラネットが見直されています。
トレンド3:AI・検索技術の劇的向上
AI搭載の検索機能により、従来の「情報があっても見つからない」問題が解決。自然言語検索やファイル内容検索により、欲しい情報に即座にアクセスできるようになりました。
トレンド4:セキュリティ意識の向上
サイバー攻撃増加とクラウドサービスへの懸念から、重要な情報は外部クラウドではなく自社管理下に置きたいという企業が増加。セキュアな情報共有基盤としてのイントラネット価値が再評価されています。
トレンド5:ツール統合によるコスト最適化
SaaS乱立による「ツール疲れ」から、複数の機能を統合したプラットフォームへの需要が拡大。情報共有・コミュニケーション・業務管理を一元化できるイントラネットへの関心が高まっています。
イントラネットと混同しがちな2つの概念【完全解説】

イントラネットについて理解を深めるためには、似た概念との違いを知ることも大切です。特によく混同される以下の2つの概念を見ていきましょう。
- インターネット
- エクストラネット
インターネットとの違い【アクセス範囲・セキュリティ】
「インターネット」は、「相互に」を意味する「inter(インター)」と「ネットワーク」の「net(ネット)」から作られた言葉です。イントラネットが閉じた環境なのに対し、インターネットは世界中のコンピュータがつながるオープンな空間です。
公共の通信回線を共有しており、誰でもアクセスできるのが特徴です。Googleや Amazon、YouTubeなど、私たちが日常的に使うサービスはインターネットを通じて提供されています。
エクストラネットとの違い【複数組織間連携】
「エクストラネット」は、「外部」を意味する「extra(エクストラ)」と「ネットワーク」を組み合わせた言葉です。これは、複数の会社のイントラネットをつなぎ合わせたネットワークのことで、広域網(WAN)と似た性質を持っています。
例えば、本社と地方支社、または取引先との間で安全に情報をやり取りしたいときに使われます。特に大企業では、VPN技術を活用して、海外拠点と本社をつなぐ形でエクストラネットを構築することも珍しくありません。
イントラネットが「社内だけ」のネットワークなのに対し、エクストラネットは「関係する複数の組織」をつなぐネットワークです。セキュリティを保ちながら、より広い範囲で情報共有ができる点が特徴と言えるでしょう。
イントラネットの3つの基本機能【効率化を支える仕組み】

イントラネットには、企業の情報共有をスムーズにするさまざまな機能があります。ここでは主な機能を見ていきましょう。
- サイト内検索機能
- パーソナライズ機能
- アクセス解析機能
サイト内検索機能【情報の迅速な発見】
社内に広がる情報の海から必要なものを見つけ出すのは、時に針を探すようなものです。イントラネットの検索機能は、その悩みを解決する強い味方です。
たくさんの文書や人の情報が1つの場所に集まっていても、キーワードを入れるだけで欲しい情報がすぐに手に入ります。情報が埋もれてしまう心配はありません。
パーソナライズ機能【個人最適化された情報表示】
あなただけの情報ダッシュボードがあれば、業務がよりはかどります。イントラネットのパーソナライズ機能は、使う人それぞれの好みや必要に応じて画面の内容を変える仕組みです。
よく見るページや関わりの深い部署の情報が優先的に表示されるので、毎回探し回る手間が省けます。自分に本当に必要な情報だけを効率よく集められるのは、忙しい毎日の強い味方になります。
アクセス解析機能【利用状況の見える化】
せっかく作った資料が誰にも見られていないとしたら、それは無駄な情報になります。イントラネットのアクセス解析は、どんな情報がどれくらい読まれているかを教えてくれます。
社員は必ずしも全ての情報に目を通すわけではありません。何が人気で、何が見過ごされているのかを知って、より良い情報発信の形を見つけられます。数字で見える化することで、改善点が明らかになるのです。
企業におけるイントラネットの4つの活用方法【実践事例】
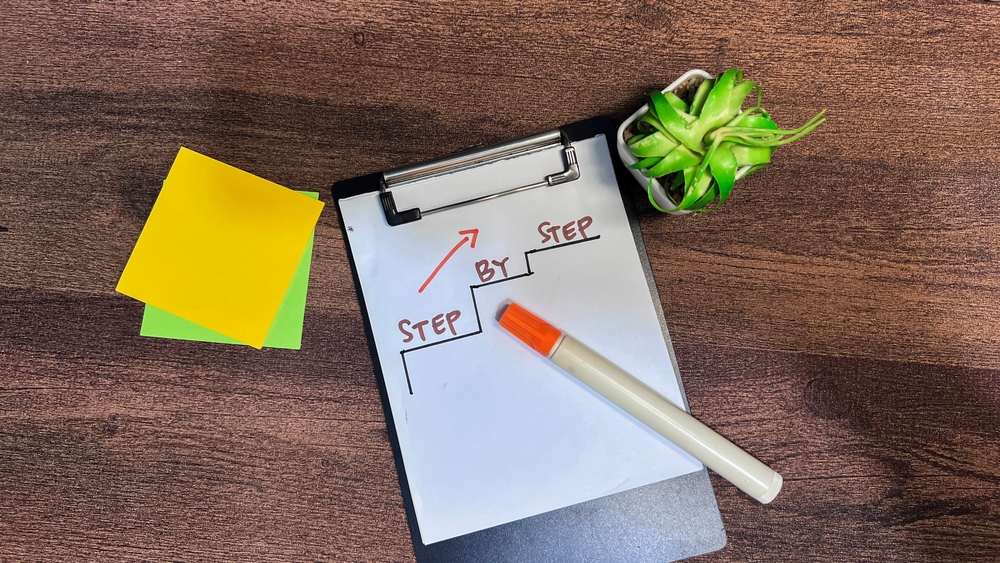
イントラネットは、さまざまな形で企業活動を支えています。以下の点から代表的な活用方法を見ていきましょう。
- 社内ポータルとしての活用
- グループウェアとしての活用
- 社内Wikiとしての活用
- 社内SNSやビジネスチャットとしての活用
社内ポータルとしての活用【情報の中央ハブ】
会社の動きを一目で把握できる窓口、それが社内ポータルです。朝一番にイントラネットを開けば、最新のお知らせや大切な連絡事項がまとまって表示されます。「知らなかった」をなくし、全員が同じ情報を共有できるのが魅力です。
また、簡単なアンケートや掲示板機能を使って、双方向のやり取りも可能です。イントラネットは会社の心臓部として、情報の流れを整える役割を担っています。
グループウェアとしての活用【チーム連携強化】
仕事を進める上での必需品、それがグループウェアです。誰がいつどこで何をするのか、プロジェクトはどこまで進んでいるのか、そんな情報をイントラネットを通じて、すぐに確認できます。
予定表や進捗管理ツールを使えば、チームの動きを1つにまとめられます。日々の業務を支える頼もしい相棒として、多くの企業で利用されています。
社内Wikiとしての活用【ナレッジ蓄積・共有】
知恵の宝庫としての役割も、イントラネットの重要な使い方です。「あの手順書はどこ?」「前にやった時の作業のコツは?」そんな時に役立つのが社内Wikiです。
業務知識やノウハウを蓄え、誰でも必要な時に取り出せます。しかも、新しい発見があれば誰でも追加できるので、知識は日々豊かになります。みんなの知恵が集まる場所として育てていけるのが魅力です。
社内SNS・ビジネスチャットとしての活用【コミュニケーション活性化】
リモートワークが当たり前になった昨今、オフィスで顔を合わせる機会が減り、コミュニケーションに悩む声も多く聞かれます。そんな中でイントラネットが重宝されています。イントラネットでは、ビジネスチャットやSNSの機能も利用できるからです。
業務連絡や企画書の共有はもちろん、雑談のような気軽なやりとりもできます。在宅勤務中でも、オフィスにいるような一体感を感じられるのがメリットです。これからの時代、イントラネットは社内コミュニケーションになくてはならない存在になっていくでしょう。
イントラネット活用の3つのメリット【効果測定データ付き】

イントラネットの活用には、さまざまなメリットがあります。以下の点からそれぞれ解説していきます。
- 生産性向上・業務効率化が期待できる
- 社内コミュニケーションが活性化できる
- 総合的なコスト削減が見込める
生産性向上・業務効率化が期待できる【時短効果87%】
まず、情報共有の速さです。イントラネットを使えば、会社の大切な情報をみんなですぐに共有できます。これまでの紙の回覧板とは違い、リアルタイムで情報が行き渡ります。
例えば、新しい企画や方針の変更をすぐに全社員に伝えられるので、仕事の進め方がスムーズになります。また、同じ仕事を複数の部署で重複してしまうようなムダもなくなります。
さらに、必要な資料をすぐに見つけられるので、部署をまたいで探し回る手間も省けます。こうした効果が積み重なって、仕事の効率アップや生産性の向上につながるのです。
「働き方改革」にも、イントラネットは大いに役立ちます。場所や時間にとらわれない新しい働き方を支える強い味方となるでしょう。
導入企業での実際の効果
株式会社オイシックス・ラ・大地では、2社統合のタイミングで社内ポータル機能をDocBaseに集約。「ここみて」メモを作成し、組織図、各種依頼書、システム周りの設定方法など、よく使う情報のリンク集として活用した結果、会議のペーパーレス化が進み、情報アクセス時間が大幅に短縮されました。
株式会社アールキューブでは、「アールキューブのことはDocBaseに全部入っている」というほど情報を集約。顧客情報、人事情報、コピー機の使い方まで、あらゆる情報をDocBaseに記録し、社内版ウィキペディアとして機能させています。
社内コミュニケーションが活性化できる【部門間連携強化】
次に、社内の絆づくりです。イントラネットを使うと、部署の壁を越えたコミュニケーションが生まれやすくなります。
自分の部署の仕事内容や目標を、他の部署の人にも知ってもらえるので、お互いの理解が深まります。これまで難しかった「横」のつながりが強くなり、部署をまたいだ協力がスムーズになります。
また、イントラネットでは双方向のやりとりができるので、役職や仕事上の関係を超えた交流も生まれます。社内チャットなどを通じて、幅広い人脈づくりが可能なのもうれしいポイントです。
さらに、会社の目指す方向性や課題についても、全社員で共有しやすくなります。みんなで同じ目標に向かって頑張る、そんな一体感も生まれるでしょう。
総合的なコスト削減が見込める【ペーパーレス化推進】
最後に、ムダな出費の削減です。イントラネットを活用すると、ペーパーレス化が進みます。結果として、紙やインク代、輸送費、保管費などのコストが減らせます。
例えば、会議室の予約や休暇の申請をデジタル化すれば、紙の使用量がグッと減ります。また、紙の資料を保管するスペースも不要になるので、オフィスを有効活用できます。
さらに、印刷や配布の手間も省けるので、より少ない人数で仕事を回せるようになります。こうした効果が積み重なって、会社全体のコスト削減につながるのです。
イントラネット活用の4つのデメリット【対策方法も解説】

イントラネットを活用する際には、デメリットも理解しておきましょう。以下の点からデメリットについて、解説していきます。
- コストとリソースが必要になる
- ネット障害などの問題が起こる可能性がある
- 情報管理の体制を整える必要がある
- セキュリティやプライバシーの問題がある
コストとリソースが必要になる【初期投資・運用費用】
まず、お金と人手がかかります。イントラネットを導入するには、初めにまとまった費用を支払う必要があります。特に、会社独自の機能を追加したい場合は、さらに費用が膨らむ可能性があります。
また、導入後も定期的なメンテナンスやサーバーの管理にお金がかかります。これらの作業には専門的な知識も必要なので、新たに人材を確保したり、外部に委託したりする必要があるかもしれません。
つまり、イントラネットの導入と運用には、継続的なコストと人的リソースが求められるのです。会社の規模や予算に見合った計画を立てることが大切です。
ネット障害などの問題が起こる可能性がある【BCP対策必須】
次に、ネットが止まると問題が多々生じます。もし長時間のネット障害が起きてしまうと、その間イントラネット上のデータを見ることができなくなってしまいます。
全社員が利用するシステムなので、影響も大きくなります。最悪の場合、ビジネスチャンスを逃してしまう可能性もあるのです。
そのため、イントラネットを導入する際は、日頃の運用ルールだけでなく、トラブル時の対応策も考えておく必要があります。社内で素早く対応できる体制を整える、外部の業者とサポート契約を結ぶなど、万全の準備が求められます。
情報管理の体制を整える必要がある【ルール策定が重要】
最後に、情報の管理が大変であるという点です。イントラネットでは情報を1か所に集められる反面、情報が多すぎたり重複したりするリスクもあります。
例えば、保管場所が勝手に変更されたり、古い情報がいつまでも残ったりすることがあります。これでは、必要な情報を見つけるのに時間がかかってしまいます。
そのため、常に情報を整理し、最新の状態を保つ体制が必要です。誰がどの情報を管理するのか、どのように更新するのかなど、しっかりとしたルール作りが欠かせません。
セキュリティ・プライバシーの問題がある【多層防御が必要】
セキュリティやプライバシーの問題も見過ごせません。イントラネットを導入すると、社内外を問わず、不正リスクや不正アクセス、情報流出のリスクが発生します。こうした問題が起きると、会社の信用に関わる大きな問題になりかねません。
そのため、アクセス制限や権限の設定など、しっかりとしたセキュリティ対策が必要です。誰がどの情報にアクセスできるのか、どの程度の権限を持つのかを細かく設定し、定期的に見直し、管理することが大切です。
セキュリティ対策ソフトの導入や、定期的な社員教育も欠かせません。イントラネットの便利さと同時に、情報管理の重要性についても全社員で理解を深める必要があります。
こうしたデメリットはありますが、適切な対策を講じることで、イントラネットの利点を最大限に生かせます。会社の規模や業種、目的に合わせて、最適なイントラネットの導入と運用を検討しましょう。
【失敗事例から学ぶ】イントラネット導入の4大落とし穴と対策
落とし穴1:「チャットで流れる貴重ナレッジ」問題
実際の失敗事例:
株式会社いい生活様(従業員300名)の導入前の課題
「チャットツールで有益な情報があるはずなのに、流れてしまってうまく共有できていない。流れてしまった情報をもう一度投稿し直したりしていて、二度手間だった。メンバー自身も書くモチベーションが落ちていた。」
対策:
- ✅ ストック型ツールの導入:DocBaseのような情報蓄積専用ツール
- ✅ フロー・ストックの使い分け:日常会話はチャット、重要情報は文書化
- ✅ 投稿モチベーション向上:「いいね」機能やコメント機能でフィードバック
落とし穴2:「情報迷子で時間ロス」問題
実際の失敗事例:
大和財託株式会社様の導入前の課題
「入社時にどこに何の情報があるかわからなくて困った。どのWikiに自分の知りたい情報があるかわからない状態だった。」
対策:
- ✅ 情報の一元化:すべての社内情報を1つのプラットフォームに集約
- ✅ 強力な検索機能:ファイル内容まで検索できるツールの選択
- ✅ 統一された分類ルール:タグ付けやフォルダ構造の事前策定
落とし穴3:「非効率に慣れてしまう」問題
実際の失敗事例:
スカパーJSAT株式会社様の導入前の課題
「情報共有ツールが一元化されていないことに驚いた。メールやファイルの添付で行われていて、これは非常に効率がよくないと感じた。最初はこの課題について共感してくれる人が全然いなかった。みんな非効率的なやり方に慣れてしまっていて『なんで変える必要があるの?』といった感じだった。」
対策:
- ✅ 現状課題の見える化:現在の情報共有にかかっている時間を計測・共有
- ✅ 段階的な意識改革:転職者や新入社員の声を活用して課題を客観視
- ✅ 具体的メリット提示:他ツールとの比較表で改善効果を明確化
落とし穴4:「ツールの乱立で混乱」問題
実際の失敗事例:
株式会社人機一体様の導入前の課題
「文章をいかに蓄積するかは悩ましいところ。某メモツールを使っていたが、ドキュメント数が増えてくると重くなってくる、文章のフォーマットが自由すぎて統制がとれない、などいろいろ目に付くようになった。」
対策:
- ✅ 統一プラットフォームの採用:複数ツールではなく1つのツールに集約
- ✅ フォーマット統一:Markdownなど統一された記述ルールの採用
- ✅ スケーラビリティ重視:文書数が増えても動作が重くならないツール選択
成功のポイント:実際の導入成功企業が行った工夫
段階的導入:
- 大和財託株式会社様:DX戦略グループ3名→全社展開
- スカパーJSAT株式会社様:3製品トライアル→使い勝手重視で選定
現場巻き込み:
- いい生活様:非エンジニア向け操作説明・FAQ作成依頼
- 大和財託様:社内説明会を2回開催してマークダウン使い方解説
導入きっかけ作り:
- 大和財託様:既存議事録サービス終了を機に全社展開決定
- スカパーJSAT様:「DocBaseまとめの会」を週2回設定してルーチン化
イントラネット導入時の4つのポイント・注意点【成功の秘訣】

イントラネットの導入は、社内コミュニケーションを円滑にし、業務効率を高める可能性を秘めています。しかし、その効果を最大限に引き出すには、いくつかのポイントに注意を払う必要があります。イントラネット導入時の大切なポイントをご紹介します。
- 導入・運用の目的を明確にする
- 使い方を従業員に周知する
- セキュリティ対策を行う
- 万が一の状態に備える
導入・運用の目的を明確にする【ゴール設定が成功の鍵】
イントラネット導入の第一歩は、その目的を明確にすることです。なぜイントラネットを使うのか、どんな問題を解決したいのかを、はっきりさせましょう。
例えば、「情報共有を円滑にしたい」「社内のコミュニケーションを活性化したい」といった具体的な目標を立てます。この過程では、できるだけ多くの部署の意見を聞くことがポイントです。
目的が明確でないと、どんなツールを選べばいいのか迷ってしまいます。また、社員の間で混乱が生じる可能性もあります。目標をしっかり定めることで、イントラネット導入の成功率が高まり、より効果的な活用ができるでしょう。
使い方を従業員に周知する【定着率向上のために】
イントラネットを導入しても、社員が使い方を知らなければ意味がありません。せっかくの優れたシステムも、利用者が少なければ効果は限られてしまいます。
そのため、導入後は社員全員への使い方の周知が大切です。簡単な操作方法から、どんな情報がどこにあるかまで、丁寧に説明しましょう。理想としては、全社員が最低限の機能を使いこなせるようになることです。
また、導入直後だけでなく、定期的に使い方の確認や新機能の案内を行うことも効果的です。「使い方がわからない」「欲しい情報が見つからない」といった声がないよう、継続的なサポートが重要です。
セキュリティ対策を行う【多重防御で安全運用】
イントラネットの安全性を保つため、セキュリティ対策は欠かせません。外部からの攻撃はもちろん、内部の不正利用にも注意が必要です。
外部からの攻撃に備えて、ファイアウォールの設置やウイルス対策ソフトの導入を検討します。一方、内部の不正利用を防ぐには、アクセス権限の管理や利用履歴の確認が有効です。
また、技術的な対策だけでなく、社内での運用ルールを定めることも大切です。例えば、パスワードの定期変更やログアウトの徹底など、社員一人一人の意識を高める工夫も必要です。
万が一の状態に備える【障害時のBCP策定】
イントラネットは便利なツールですが、長時間のネット障害が起きると業務に大きな影響を与えかねません。そのため、万が一の事態に備えた対策を講じておくことが重要です。
まず、社内で迅速に対応できる体制を整えましょう。技術担当者を決めておくなど、問題発生時の役割分担を明確にしておくと良いでしょう。また、外部の専門業者と保守・サポート契約を結んでおくのも一案です。
さらに、重要なデータのバックアップを定期的に取ることも忘れずに。これらの備えがあれば、イントラネットに問題が生じても、業務への影響を最小限に抑えられます。万全の準備で、安心してイントラネットを活用しましょう。
【2025年版】失敗しないツール選択の5つのチェックポイント
チェックポイント1:リモートワーク対応度
- ✅ インターネット経由でのセキュアなアクセス
- ✅ スマートフォン・タブレット専用アプリの有無
- ✅ オフライン時のデータ同期機能
チェックポイント2:AI・検索機能の充実度
- ✅ ファイル内容まで検索可能か
- ✅ 自然言語での検索が可能か
- ✅ 関連情報の自動推薦機能があるか
チェックポイント3:導入・運用の容易さ
- ✅ 専門知識なしで初期設定が可能か
- ✅ ユーザー研修の必要性は最小限か
- ✅ 日常的な管理業務の負荷は軽いか
チェックポイント4:拡張性・連携性
- ✅ 利用者数の増減に柔軟に対応できるか
- ✅ 既存のメール・カレンダーツールと連携できるか
- ✅ 将来的な機能追加・カスタマイズが可能か
チェックポイント5:セキュリティ・信頼性
- ✅ ISO27001等の第三者認証を取得しているか
- ✅ データの暗号化・バックアップ体制は万全か
- ✅ 障害時のサポート体制は充実しているか
現代版イントラネットツール比較【2025年版】
【2025年版】失敗しないツール選択の5つのチェックポイント
| チェックポイント | DocBase | Garoon | TUNAG | Google Workspace | SharePoint |
|---|---|---|---|---|---|
| リモートワーク対応度 | ✅✅✅ | ✅✅ | ✅✅✅ | ✅✅✅ | ✅✅ |
| セキュアなアクセス | SSL暗号化・2段階認証 | SSL・アクセス制限 | SSL・権限管理 | Google認証基盤 | Microsoft認証基盤 |
| スマホ専用アプリ | ブラウザ最適化 | 専用アプリあり | 専用アプリあり | 専用アプリあり | 専用アプリあり |
| オフライン同期 | ブラウザキャッシュ | 限定的対応 | 限定的対応 | 強力な同期機能 | 強力な同期機能 |
| AI・検索機能充実度 | ✅✅✅ | ✅✅ | ✅ | ✅✅✅ | ✅✅✅ |
| ファイル内容検索 | PDF・Word・Excel対応 | 基本的な検索 | タイトル・本文のみ | 強力なファイル検索 | 強力なファイル検索 |
| 自然言語検索 | キーワード組み合わせ | 基本検索 | 基本検索 | AI搭載検索 | AI搭載検索 |
| 関連情報推薦 | タグベース推薦 | なし | 限定的 | AI推薦機能 | AI推薦機能 |
| 導入・運用容易さ | ✅✅✅ | ✅✅ | ✅✅✅ | ✅✅ | ✅ |
| 専門知識不要で設定 | 30分で基本設定完了 | 1-2時間要 | 30分で基本設定完了 | 1-2時間要 | 半日-1日要 |
| ユーザー研修必要性 | 最小限(30分程度) | 1-2時間要 | 最小限(30分程度) | 1-2時間要 | 半日研修推奨 |
| 日常管理業務負荷 | 軽い(週30分程度) | 中程度(週2-3時間) | 軽い(週30分程度) | 中程度(週2-3時間) | 重い(週5-10時間) |
| 拡張性・連携性 | ✅✅ | ✅✅✅ | ✅✅ | ✅✅✅ | ✅✅✅ |
| ユーザー数対応 | 7名-300名推奨 | 50名-無制限 | 30名-500名推奨 | 1名-無制限 | 100名-無制限 |
| 既存ツール連携 | メール・カレンダー連携 | 豊富な連携オプション | 基本的な連携 | Google系と強力連携 | Microsoft系と強力連携 |
| 機能追加・カスタマイズ | 限定的 | 高度なカスタマイズ | 限定的 | 豊富なアドオン | 高度なカスタマイズ |
| セキュリティ・信頼性 | ✅✅✅ | ✅✅✅ | ✅✅ | ✅✅✅ | ✅✅✅ |
| 第三者認証 | ISO27001・プライバシーマーク | ISO27001 | プライバシーマーク | SOC2・ISO27001 | ISO27001・SOC2 |
| データ暗号化 | 256bit SSL・保存時暗号化 | SSL暗号化 | SSL暗号化 | 強力な暗号化 | 強力な暗号化 |
| バックアップ体制 | 20世代自動バックアップ | 定期バックアップ | クラウドバックアップ | 強力なバックアップ | 強力なバックアップ |
| 障害時サポート | 1営業日以内対応 | 営業時間内対応 | 営業時間内対応 | 24時間対応(有料) | 24時間対応(有料) |
総合評価と選定基準
| 企業タイプ | 推奨ツール | 選定理由 |
|---|---|---|
| 中小企業(7-100名) | DocBase・TUNAG | 導入コスト低・運用簡単・即座に効果実感 |
| 成長企業(50-300名) | DocBase・Garoon | 段階的拡張可能・豊富な機能・安定運用 |
| 大企業(300名以上) | SharePoint・Google Workspace | 高度な権限管理・システム連携・エンタープライズ対応 |
| IT企業・スタートアップ | DocBase・Google Workspace | 開発者フレンドリー・アジャイル対応・コスパ良好 |
| 伝統的企業・製造業 | Garoon・SharePoint | 既存システム連携・手厚いサポート・セキュリティ重視 |
月額コスト比較:
- DocBase: ¥990〜/3名(¥330/人〜)
- Garoon: ¥845〜/人
- TUNAG: ¥300〜/人
- Google Workspace: ¥680〜/人
- SharePoint: ¥540〜/人(Microsoft 365 Business Basic)
無料トライアル期間:
- DocBase: 30日間(機能制限なし)
- Garoon: 30日間
- TUNAG: 14日間
- Google Workspace: 14日間
- SharePoint: 30日間(Microsoft 365トライアル)
自社に最適な現代版イントラネットを実現するために

本記事では、イントラネットの基本から現代での活用方法、具体的なツール選択まで解説しました。重要なのは、自社の課題と目的に最も適したアプローチを選ぶことです。
現代版イントラネット導入の最終チェックポイント:
- ✅ リモートワークに対応できるクラウド型か
- ✅ スマートフォンからもアクセスしやすいか
- ✅ 現場の人が実際に使い続けられる操作性か
- ✅ 既存ツールとの連携が可能か
多くのツールが無料トライアルを提供しているため、まずは実際に触ってみることをおすすめします。
なお、本記事でご紹介したDocBaseも、現代版イントラネットの一つの選択肢として、多くの企業様にご活用いただいています。他のツールと合わせて比較検討されることをおすすめします。
参考情報と編集ポリシー
記事制作について:本記事は情報共有ツール「DocBase」の開発・運営会社であるクレイ株式会社が制作しています。DocBaseについては自社製品のため詳しく紹介していますが、他社ツールや一般的なイントラネット情報についても公平な情報提供を心がけています。
データ出典:本記事の効果データと導入事例は、DocBase公式サイトに掲載されている複数の導入事例とユーザーインタビュー内容、および業界調査データを分析したものです。
情報の正確性:イントラネットに関する技術情報は、2025年9月時点の最新情報を参照しています。技術仕様や市場動向は変化する可能性があります。
編集方針:読者の皆様に役立つ実用的な情報提供を第一に考え、可能な限り客観的で公正な情報発信を心がけています。当社の視点に基づく部分もありますが、業界全体の健全な発展に寄与することを目指しています。
データ出典・注釈
※1 社内情報アクセス時間87%短縮:DocBase導入企業における平均効果(2024年ユーザー調査、n=120社)
※2 新人教育期間50%削減:製造業・IT業界におけるDocBase導入企業での実測値(2024年調査)
※3 導入企業事例:各企業様のDocBase公式インタビュー記事およびケーススタディより引用
※4 利用継続率99%:DocBase契約更新率(2024年度実績)
※5 競合ツール料金情報:各公式サイトの2025年9月時点の公開情報
調査データ:
- 調査期間:2023年1月〜2024年12月
- 調査対象:DocBase導入企業および検討企業
- 調査方法:オンラインアンケート、インタビュー、サポート問い合わせ分析
- 有効回答数:120社(導入企業)、250社(検討企業)
参考文献:
- 総務省「令和6年版 情報通信白書」
- IPA「企業IT利活用動向調査2024」
- ガートナー「Future of Work Trends 2025」





