働き方改革に有効なICTツールとは?各ツールの特徴・メリットを紹介
最終更新日:2025年3月5日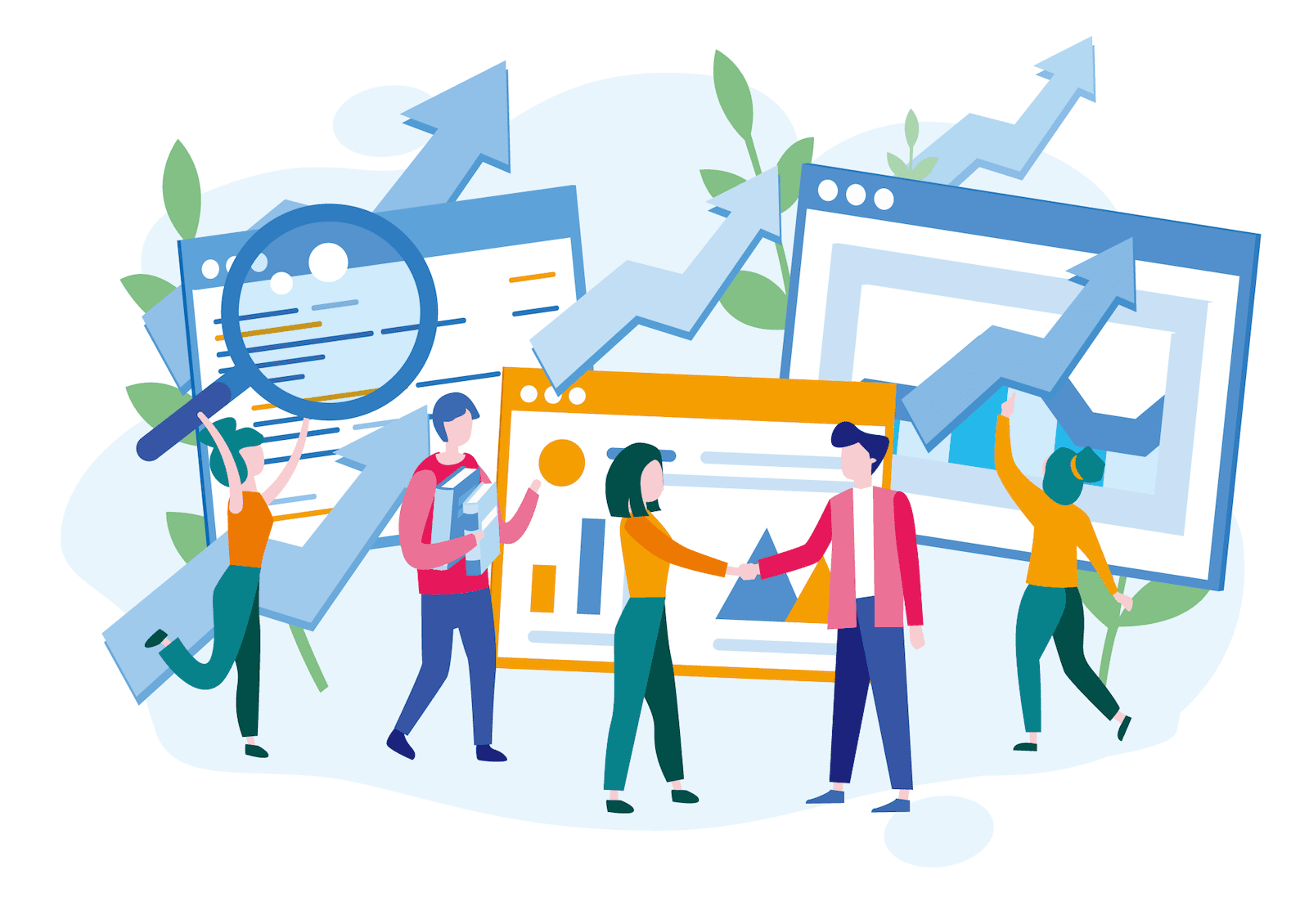
ICTツールの導入により、業務効率化や働き方改革への対応がスピーディーに進むと言われていますが、具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。本記事では、ICTツールの種類や特徴を詳しく紹介するとともに、効率的な活用方法をわかりやすく解説します。
働き方改革の要点となる残業時間の削減や有給休暇の取得率向上、フレックスタイム制、テレワークなど、さまざまな課題に対応できるICTツールの活用法も合わせて説明。自社に合った最適なツールを選び、確実に定着させるためのポイントもご紹介します。ICTツールを通じて、業務の生産性向上と働き方改革の両立を実現しましょう。
【この記事を読んでわかること】
- ICTツールとは、情報通信技術を活用するシステム・アプリケーション・デバイスを指す
- 主な例としては、ビジネスチャットツール、Web会議ツール、ナレッジ共有ツールなどがある
- 労働時間などの管理やテレワークの体制作りなど、働き方改革にも役立つ
- 社員のITリテラシーに合うICTツールを選び、定着を促す体制作りが大切
目次
ICTツールとは?

「ICTツール」という言葉を耳にする機会が増えてきました。働き方改革やテレワークの普及で、多くの企業が導入を検討していますが、具体的にどんなものなのかピンとこない方も多いのではないでしょうか。
ICTは「Information and Communication Technology(情報通信技術)」の略です。私たちが普段使っているメールやSNSも、実はICTツールの1つ。ビジネスでは、これらのICTツールをベースにした情報共有システムや、プロジェクト管理ツールなど、より専門的なものを含めて、幅広く活用されています。
ICTツールで大切なのは、「Communication(コミュニケーション)」の部分。人と人、人とコンピューターをつなぐ技術としてチームワークを支える重要な役割を果たし、デジタル化時代の必須アイテムと見なされています。
ICTツールの種類

ICTツールには、さまざまな種類が存在します。ここでは以下のツールについて、それぞれ具体的に解説していきます。
- ビジネスチャットツール
- Web会議ツール
- ナレッジ共有ツール
- 在籍管理ツール
- 仮想デスクトップツール
- 勤怠管理ツール
- 電子黒板ツール
- スマートフォンの内線電話化ツール
- 電子決済ツール
- ファイル共有ツール
ビジネスチャットツール
ビジネスチャットツールとは、従来のメールよりも手軽に、しかしながら個人向けチャットよりもしっかりとした機能を持つ、ビジネス専用のコミュニケーションツールです。今では、オフィスワークの効率化に欠かせません。
例えば、急ぎの連絡はメッセージで、大切な資料は添付ファイルで、プロジェクトごとの話し合いは専用のスレッドでというように、目的に応じて使い分けることで、スムーズな情報共有が可能になります。
特にテレワーク環境では、ビジネスチャットツールが役立ちます。離れた場所にいても、簡単な確認から本格的な打ち合わせまで、まるでオフィスにいるような感覚でコミュニケーションを取ることができます。チームの一体感を保ちながら、業務を効率的に進められる点が、多くの企業から支持されている理由です。
Web会議ツール
場所や距離の制約を超えて、まるで同じ部屋にいるような対話を可能にするWeb会議ツール。インターネットを通じて、相手の表情を見ながら会話ができる便利なICTツールとして、いまや多くの企業で活用されています。
例えば、遠方のお客様との商談や、複数拠点をつないだミーティング、オンライン研修、採用面接など、活用シーンは実にさまざま。画面共有機能を使えば、資料を見せながら説明することも、チャット機能で補足情報を共有することも可能です。
Web会議ツールの最大のメリットは、移動にかかる時間とコストの大幅な削減です。東京・大阪間の打ち合わせも、移動することなく実施できます。また、急な確認事項が発生しても、すぐにオンラインで顔を合わせて話し合えるため、ビジネスのスピードアップにも貢献します。
これからのビジネスシーンでは、対面とオンラインをうまく組み合わせた、ハイブリッドなコミュニケーションが標準になっていくでしょう。
ナレッジ共有ツール
社内に蓄積された知識や経験を効率よく共有できないか、お悩みではありませんか?ナレッジ共有ツールは、そんな課題を解決する味方です。マニュアル作成ツールや社内Wikiなど、さまざまな形で活用できます。
このICTツールの特徴は、これまで紙の資料やファイルサーバーに散らばっていた情報を、すっきりとデジタル化できること。必要な情報をすぐに検索可能なのはもちろん、文章だけでなく動画やイラストなど、わかりやすい形式で情報を共有できます。
例えば、新入社員研修の資料や業務マニュアル、プロジェクトの記録など、社内の大切な情報を一元管理。「どこに保存したっけ?」と探す手間が省けて、欲しい情報にすぐにアクセスできます。また、テレワーク中でも必要な情報を取り出せるため、場所を問わない働き方の実現にも役立ちます。
情報共有の課題を解決し、組織の知識を効率的に活用する。それがナレッジ共有ツールのもたらすメリットです。
在籍管理ツール
テレワークやフリーアドレスが一般的になった今、「誰がどこで働いているのか」を把握することは、とても重要です。在席管理ツールは、そんな悩みを解決する便利なシステムです。
このICTツールを使えば、社員の勤務状況をリアルタイムで確認できます。例えば「今は会議中」「外出中」といった状況が一目でわかるため、スムーズなコミュニケーションが可能です。フリーアドレスオフィスでは、空き席の確認や座席の予約を行い、効率的なスペース活用も実現できます。
特に管理職の方には心強い味方です。部下の勤務状況を把握しやすくなり、適切なタイミングで指示を出せます。また、テレワーク中のメンバーの状況もわかるため、場所にとらわれない柔軟なチームマネジメントが可能になります。
働き方が多様化する中、在席管理ツールは効率的な業務運営と円滑なコミュニケーションを支える重要なツールです。
仮想デスクトップツール
「どこからでも会社のパソコン環境にアクセスしたい」「情報セキュリティを確保しながらテレワークを実現したい」。そんな願いを叶えてくれるのが、仮想デスクトップツールです。
仮想デスクトップとは、会社のパソコン環境をそのままインターネット経由で利用できる仕組み。自宅のパソコンやタブレットから、まるで会社のパソコンを使っているかのように作業が可能です。
このICTツールの魅力は、高いセキュリティ性と使いやすさの両立です。利用する端末には情報が残らないため、情報漏えいのリスクを抑えられます。また、特別な高性能パソコンを用意する必要もなく、普段使っている端末で気軽に始められます。
テレワークはもちろん、出張先での急な作業にも対応できるため、場所を選ばない柔軟な働き方を実現。育児や介護との両立が必要な社員のワークライフバランスの向上にも貢献します。
これからのビジネスシーンでは、安全性と利便性を兼ね備えた仮想デスクトップが、新しい働き方のスタンダードとなっていくかもしれません。
勤怠管理ツール
「煩雑な勤怠管理業務を、もっとシンプルに」。そんな願いを叶えてくれるのが、勤怠管理ツールです。出退勤の記録から、休暇申請、有給管理まで、労務管理に関わるさまざまな業務をデジタル化できます。
例えば、従来のタイムカードやエクセル管理から解放され、スマートフォンやパソコンで簡単に打刻が可能に。勤務時間の集計も自動で行われるため、計算ミスの心配もありません。また、有給休暇の申請や承認もオンラインで完結できるため、書類の往来による手間も省けます。
特にテレワーク環境では、このICTツールが役立ち、在宅勤務でも正確な勤務時間の記録が可能で、労働時間を適切に管理できます。さらに、有料サービスであれば、働き方改革関連法への対応なども問題ありません。
人事システムや給与計算システムとの連携も可能で、より広範な業務効率化を実現します。デジタル時代の新しい労務管理のスタンダードとして、勤怠管理ツールの重要性は今後さらに高まっていくでしょう。
電子黒板ツール
会議室のホワイトボードがデジタル進化を遂げた「電子黒板」。大型のタッチディスプレイに、カメラやスピーカー、マイクを搭載し、従来のホワイトボードの使いやすさとデジタルの利便性を組み合わせた新しいツールです。
最大の特徴は、その場にいる人もリモート参加者も、同じように書き込みや編集ができること。例えば、アイデア出しの際には、みんなで自由に書き込みながら意見を出し合えます。また、プレゼン資料を表示しながら、その場で重要なポイントの書き込みや共有も可能です。
さらに、会議で書き込んだ内容は、そのまま保存・送信できるため、議事録作成の手間も大幅に削減します。「写真を撮り忘れた」「手書きメモが読めない」といった悩みから解放されます。
これからのハイブリッドな働き方において、電子黒板は対面とリモートをつなぐ重要な架け橋となるでしょう。会議の質を高め、より創造的なコミュニケーションを実現する、これからの時代に重宝するICTツールです。
スマートフォンの内線電話化ツール
「外出先でも会社の電話を受けたい」「リモートワーク中も内線電話を使いたい」。そんな要望に応えるのが、スマートフォンの内線電話化ツールです。
このICTツールを導入すれば、スマートフォンがそのまま会社の内線電話として使えるようになります。社内の固定電話にかかってきた電話もスマートフォンで受けることができ、まるで会社にいるかのように、どこからでも電話対応が可能になります。
メリットは、場所を選ばない柔軟な電話対応ができるだけではありません。物理的な内線電話機が不要になるため、設備投資やメンテナンスのコストを抑えられます。また、在席確認やメッセージのやり取りなど、ビジネスチャットのような便利な機能も備えているツールも多くあります。
特に昨今のテレワーク環境では、このICTツールが役立ちます。自宅勤務中でも会社の電話に出られるため、お客様対応の質を落とすことなく、柔軟な働き方を実現できるのです。
これからのビジネスシーンでは、固定電話と携帯電話の垣根を越えた、新しい電話コミュニケーションが標準になっていくかもしれません。
電子決済ツール
「判子を押すために出社する」「決裁者不在で書類が止まる」。そんな悩みを解決するのが、電子決裁ツールです。交通費精算や出張申請、稟議(りんぎ)書など、これまで紙でやり取りしていた申請業務を、すべてオンラインで完結できます。
このICTツールの特徴は、スピーディーな決裁プロセスです。パソコンやスマートフォンから申請・承認が可能で、決裁者が外出中でも素早く処理できます。また、申請から承認までの履歴が自動で記録されて、データはクラウド上で安全に保管されるため、書類の紛失や保管スペースの確保に悩む必要もありません。
導入効果は数字にも表れます。紙の削減やファイリングの手間が省けることで、コストと時間の大幅な削減が可能になります。さらに、テレワーク環境でも通常通りの決裁業務が行えるため、働き方改革の推進にも貢献します。
これからのビジネスでは、スピーディーで効率的な電子決裁が当たり前になっていくでしょう。ペーパーレス化と業務効率化を同時に実現できるICTツールです。
ファイル共有ツール
「大きなファイルを送りたいけどメールに添付できない」「チームでファイルを共有したいけど、セキュリティが心配」。そんな悩みを解決するのが、ファイル共有ツールです。
このICTツールの特徴は、インターネット上の安全な保管場所(クラウドストレージ)にファイルを置き、必要な人だけがアクセスできる仕組みです。例えば、重要な企画書や大容量の動画ファイルも、簡単に共有が可能。アクセス権限も細かく設定可能で、情報漏えいの心配もありません。
特に便利なのが共同作業機能です。同じファイルを複数のメンバーで同時に編集したり、変更履歴を管理したりできます。「古いバージョンを使ってしまった」「誰かが上書きしてしまった」といったトラブルも防げます。
また、自動バックアップ機能により、大切なデータの消失も防止。パソコンの故障やうっかりミスによる削除に対しても安心です。場所を選ばずにファイルにアクセス可能で、テレワーク環境での情報共有ツールとしても利用できます。
これからのデジタルワークスペースでは、安全で効率的なファイル共有が、ますます重要になっていくでしょう。
働き方改革とは

ICTツールを有効活用するためには、働き方改革そのものを理解しておいた方がスムーズになります。働き方改革とは、2018年6月29日に可決・成立した「働き方改革関連法案(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)」のことです。
働き方改革の8つの大きなポイントを、以下で具体的に解説していきます。
- 残業時間の上限規制
- 有給5日取得の義務化
- 勤務間インターバルの努力義務
- 中小企業の割増賃金率変更
- 労働時間把握と産業医の機能強化
- 高度プロフェッショナル制度
- 3か月単位のフレックス制度導入
- 同一労働・同一賃金の原則
※:なお各省庁でも働き方改革に関する情報が見られます。
| 官公庁 | 概要 | URL |
| 内閣府 | 新しい働き方の定着に関する情報を提供 | 新しい働き方の定着|成長戦略ポータルサイト |
| 総務省 | テレワークに関する総合情報を掲載 | 総務省|ICT利活用の促進|テレワークの推進 |
| 厚生労働省 | 働き方改革特設サイト(年次有給休暇の取得促進、時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金など) | 働き方改革特設サイト |
| 内閣官房 | 霞が関働き方改革推進チームの活動内容を紹介 | 霞が関働き方改革推進チーム |
| 文部科学省 | 学校における働き方改革の取り組み、全国の事例集、チェックシートなどを公開 | 学校における働き方改革について:文部科学省 |
| 国土交通省 | 建設現場における週休2日制の推進など、働き方改革の取り組みを紹介 | 技術調査:働き方改革・建設現場の週休2日応援サイト – 国土交通省 |
残業時間の上限規制
残業時間の上限が法律で定められ、企業は確実な管理が必要となりました。月45時間、年間360時間という基準を超えると、経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。
特別な事情がある場合でも、年720時間以内、複数月で平均80時間以内、単月で100時間未満という制限が設けられています。これらの基準を超過すると、最大で6か月の懲役や30万円以下の罰金といった厳しい処分を受けることもあります。
こうした状況に対応するため、企業ではICTツールの活用が広がっています。例えば、勤怠管理システムを導入すれば、従業員の残業時間を自動で集計して、上限に近づくと警告を出すことができます。
また、業務の自動化ツールやプロジェクト管理ツールを使えば、仕事の無駄を見つけ出して、残業そのものの削減も可能です。
企業には、ICTツールを活用しながら、残業時間の適切な管理と業務の効率化を進めることが求められています。
有給5日取得の義務化
有給休暇の取得が企業の義務となり、年10日以上の有給がある従業員に対して、最低5日の取得を確実に進める必要が出てきました。これまでは従業員からの申請待ちでしたが、今は企業側に積極的に取得を促すことが求められています。
このような状況で力を発揮するのが、有給休暇管理システムです。このICTツールを使えば、従業員ごとの有給休暇の残日数や取得状況を簡単に把握できます。また、取得予定日を事前に設定して、計画的な消化を進められます。
さらに、就業規則への記載や有給休暇管理簿の3年間保存といった義務も、システムで効率的に対応できます。従業員の意向を尊重しながら、会社全体で有給休暇の取得を進められる環境が整います。
なお、この規定に違反すると30万円以下の罰則対象となるため、きちんとした管理が欠かせません。ICTツールを活用して、従業員が安心して休暇を取れる職場づくりを進めましょう。
勤務間インターバルの努力義務
従業員の健康とワーク・ライフ・バランスを守るため、勤務間インターバル制度の導入が求められています。この制度は、1日の仕事が終わってから次の出社までに、一定時間の休息を確保するものです。
厚生労働省は休息時間の目安として9時間以上を提案しています。例えば夜10時に仕事が終わった場合、翌朝は7時までは仕事を始められない仕組みです。罰則はありませんが、この努力義務に応えないと監督官庁から指導を受ける可能性があります。
シフト管理システムを導入すれば、インターバル時間を自動で計算し、基準を下回る勤務予定を組めないように設定可能です。また、勤怠管理ツールと連携させることで、実際の勤務状況も正確に把握できます。
さらに、チャットツールやビデオ会議システムを活用して早朝や深夜の会議を減らせば、インターバルの確保に自然とつながります。
ICTツールを上手に使えば、従業員の休息時間を守りながら、効率的な業務運営が可能になります。まずは自社に合ったツールを選び、健康的な職場づくりを進めましょう。
中小企業の割増賃金率変更
2023年4月から中小企業でも、月60時間を超える残業の割増賃金率が25%から50%に引き上げられました。この変更により、人件費の管理がより重要になっています。
具体的な計算例を見てみましょう。
例:製造業の中小企業(従業員50名)
A社は、従業員50名の製造業の中小企業です。これまで、従業員の残業時間は月40時間程度でしたが、繁忙期には一部の従業員が月80時間まで残業することがありました。
改正前: 月60時間を超える20時間分の残業については、25%の割増賃金が適用されていました。
改正後: 月60時間を超える20時間分の残業については、50%の割増賃金が適用されるようになりました。
これにより、A社は、月80時間残業した従業員に対して、これまでよりも多くの割増賃金を支払う必要が生じます。例えば、時給1,500円の従業員の場合、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金は、以下のようになります。
改正前: 1,500円 x 1.25 x 20時間 = 37,500円
改正後: 1,500円 x 1.50 x 20時間 = 45,000円
また深夜労働が加わると、割増賃金の計算が少し複雑になります。
こうした状況で活躍するのが給与計算システムです。残業時間に応じて自動的に正しい割増率を適用し、計算ミスを防ぐことができます。また、勤怠管理システムと連携させれば、残業時間の入力から給与計算まで一気通貫で処理が可能です。
さらに、業務効率化ツールを導入すれば、そもそもの残業時間を減らすことも可能です。例えば、定型作業の自動化や、プロジェクト管理ツールによる業務の見える化で、無駄な残業を削減できます。
中小企業こそ、ICTツールを活用して残業時間と人件費の適切な管理を進めることが大切です。
労働時間把握と産業医の機能強化
従業員の健康管理がより重要になり、管理職や裁量労働制の社員を含めた全従業員の労働時間の把握が義務づけられています。特に、月80時間を超える残業をした従業員には、その事実を通知し、産業医による面接指導の機会を設ける必要があります。
こうした管理を正確に行うため、ICTツールの活用が欠かせません。例えば、クラウド型の勤怠管理システムなら、パソコンの使用時間やスマートフォンの打刻データから、客観的な労働時間を自動で記録できます。
また、健康管理アプリと連携させることで、従業員の体調変化や疲労度も把握できます。システムが自動で警告を出してくれるため、産業医との面談が必要な従業員の見落としもありません。
さらに、オンライン診療システムを活用すれば、産業医との面談も場所を問わず実施できます。従業員は移動時間を気にせず、気軽に健康相談ができるようになります。
ICTツール活用で、従業員の労働時間と健康状態を適切に把握し、必要な対応を迅速に取ることができます。健康経営の実現に向けて、ぜひ活用を検討してください。
高度プロフェッショナル制度
年収1075万円以上の専門職を対象とする高度プロフェッショナル制度。この制度では、労働時間規制や割増賃金の規定が適用されない代わりに、従業員の健康管理が特に重要になります。
対象となるのは、金融商品開発、ディーリング、アナリスト、コンサルタント、研究開発などの業務です。これらの職種は、時間と成果が必ずしも比例しない特徴があります。
ICTツールの活用で、この制度をスムーズに運用できます。例えば、プロジェクト管理ツールで業務の進捗や成果を可視化したり、健康管理アプリで休息時間を確認したりすることが可能です。
また、ナレッジ管理システムを導入すれば、専門職の知見を組織で共有して、より効率的な業務遂行が可能になります。Web会議ツールを使えば、場所を問わず高度な専門的議論もできます。
労使委員会での制度設計から労働基準監督署への届出まで、文書管理システムで一元管理することも重要です。ICTツールを上手に活用して、専門性の高い人材が活躍できる環境を整えましょう。
3か月単位のフレックス制度導入
フレックスタイム制が進化し、3か月単位での労働時間の調整が可能になりました。例えば、繁忙期は長めに、閑散期は短めに働くなど、柔軟な働き方に対応できます。
具体的には、1か月160時間の労働時間を3か月で480時間として管理。ただし、1週間あたり50時間を超えてはいけないなど細かいルールがあり、これらを守らないと30万円以下の罰金対象となる可能性があります。
このような複雑な管理をスムーズに行うため、ICTツールの活用が欠かせません。クラウド型の勤怠管理システムを使えば、3か月の総労働時間や週単位の上限時間を自動でチェックできます。
また、シフト作成支援ツールを導入すれば、各従業員の希望も考慮しながら、法令に準拠した勤務スケジュールを組めます。スマートフォンアプリとの連携で、従業員は自分の労働時間をリアルタイムで確認できます。
さらに、労使協定の届出管理もシステム化することで、漏れのない手続きが可能です。ICTツールを活用して、柔軟で効率的な働き方を実現しましょう。
同一労働・同一賃金の原則
正社員と非正規社員の間での不合理な待遇差をなくす「同一労働同一賃金」。この制度では、職務内容やスキル・経験に応じた公平な待遇が求められ、違いがある場合は説明責任が生じます。
このような複雑な人事制度の運用には、ICTツールの活用が効果的です。人事評価システムを導入すれば、従業員の職務内容や能力を可視化し、公平な評価基準に基づいた待遇決定が可能になります。
例えば、業務の達成度や保有資格、経験年数などを点数化し、それに応じた給与体系の設計が可能です。また、タスク管理ツールと連携させることで、実際の業務内容や責任の度合いも正確に把握できます。
さらに、説明義務に対応するため、デジタル人事台帳で待遇の根拠となる情報を一元管理することも大切です。従業員から説明を求められた際に、すぐに対応できる体制を整えられます。
ICTツール活用で、雇用形態に関係なく、公平で納得性の高い人事制度を実現できます。まずは自社の状況に合わせて、必要なツールを選びましょう。
ICTツールは働き方改革にどう生かせるか

働き方改革にICTツールをどのように生かせるかについては、以下のポイントが挙げられます。
- ICTツールで労働時間・労働状態を管理
- テレワークの体制をICTツールで整える
- ICTツールで業務効率化が実現する
それぞれについて具体的に解説していきます。
ICTツールで労働時間・労働状態を管理
働き方改革を進める上でまず取り組むべきは、労働時間の適切な管理です。長時間労働の是正や有給休暇の取得率向上、時間外労働の割増賃金の正確な計算など、従業員一人一人の勤務状況を把握することが求められています。
この課題を解決するICTツールが、クラウド型の勤怠管理システムです。このシステムを導入すれば、在宅勤務やフレックスタイム制など、多様な働き方をする従業員の勤務時間も正確に記録できます。
さらに、Web会議ツールなどの遠隔コミュニケーションツールと連携させることで、より詳しい勤務状況の把握が可能になります。例えば、オンライン上での業務の進捗確認や従業員の健康状態のチェックなども、効率的に行えます。
勤怠管理システムは単なる出退勤の記録だけでなく、働き方改革で求められるさまざまな要件に対応できます。自社の状況に合わせて適切なICTツールを選び、効率的な労務管理を実現しましょう。
テレワークの体制をICTツールで整える
働き方改革の重要な施策であるテレワーク。多様で柔軟な働き方を実現するには、適切なICTツールの活用が欠かせません。
効率的なテレワークの土台となるのが、タスク管理とナレッジ共有のICTツールです。これらを導入することで、どの業務が誰によって進められているのか、その進捗状況はどうなっているのかをチーム全員が共有できます。
また、コミュニケーション面では、Web会議ツールやチャットツールが活躍します。電子黒板などと組み合わせることで、離れた場所にいても、まるでオフィスで話し合っているような自然なやり取りが可能です。会議や打ち合わせも、場所を問わずスムーズに実施できます。
これらのICTツールをうまく組み合わせることで、出社時と変わらない環境で効率的に業務を進められます。物理的な距離を感じさせない、快適なテレワーク環境を整えることが、これからの企業には求められています。
ICTツールで業務効率化が実現する
みなさんは日々の業務に追われていませんか?今、多くの企業で導入が検討されているのが、ICTツールを活用した業務効率化です。
ナレッジ共有や勤怠管理といったICTツールを導入することで、これまで手作業で行っていた業務を自動化できます。例えば、紙の申請書で行ってきた勤怠管理をシステム化すれば、入力や集計の手間が大幅に削減可能です。また、社内の情報をデータベース化することで、必要な情報へのアクセスが素早くなり、業務のスピードアップにつながります。
さらに、こうした効率化によって生まれた時間は、新しい事業の創出や従業員のスキルアップなど、より価値の高い業務に振り向けることができます。残業や休日出勤が減り、従業員一人一人の生活の質も向上します。
ICTツールは単なる業務の効率化だけでなく、企業の成長とワークライフバランスの実現という、2つの価値を同時に叶える力を持っているのです。
ICTツールを定着させるポイント

テレワークの広がりとともに、多くの企業でICTツールの導入が進んでいます。しかし、せっかく導入したICTツールが使われずに終わってしまうケースも少なくありません。
ICTツールが定着しない理由としてまず考えられるのが、自社のニーズとの不一致です。多機能だからといって、必ずしも良いとは限りません。むしろ、従業員のITスキルに合わせて、シンプルで使いやすいものを選ぶことが大切です。
また、効果が見えないからといって、次々と新しいICTツールを導入するのも避けるべきです。ICTツールの使い方に慣れるまでには時間がかかるものです。その間、社内でICTツールの活用を推進するリーダーを決めて、利用を促す体制を整えることが重要です。
ICTツールは、導入自体が目的ではありません。業務の効率化という目標に向かって組織全体で取り組む姿勢が、成功への鍵となります。
ICTツールの活用で業務効率化と働き方改革に生かせる

本記事で紹介したICTツールは、働き方改革の味方となります。チャットツールやWeb会議システムによるコミュニケーションの円滑化、勤怠管理システムによる労働時間の適切な把握、ナレッジ共有ツールを活用した業務効率化など、導入効果は多岐にわたります。
これらのICTツールは、単なる業務のデジタル化だけでなく、働き方そのものを変革する力を持っているという点にすぐれています。テレワークやフレックスタイム制など、多様な働き方を支援し、従業員一人一人のワークライフバランスの向上にも貢献します。
ただし、ICTツールの導入は慎重に進める必要があります。自社の業務内容や従業員のスキルレベルを考慮し、必要な機能を見極めましょう。また、導入後は社内での活用を促進する体制を整えて、効果が最大限発揮されるように工夫することも重要です。
ICTツールを検討されているのであれば、DocBaseがおすすめです。直感的な操作が可能で、無料トライアルもご用意。初めての方でも安心してご利用いただけます。
ICTツール活用に関連したDocBaseの活用例
| 目的 | 具体的な使い方 | 期待される効果 |
| 情報共有の一元化と効率化 | – 社内に分散した情報をDocBaseに集約 | – 必要な情報へのアクセス向上 |
| – 会議議事録、社内ルール、FAQ、業務マニュアルなどをDocBaseで共有 | – 情報の検索性向上、問い合わせ対応の効率化、会議時間の短縮 | |
| – 部署を越えた情報共有を促進 | – 組織全体の透明性と連携を強化 | |
| – リモートワークや多様な働き方を支援 | – 時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を実現 | |
| 業務の属人化解消と標準化 | – 個人のノウハウや経験をDocBaseに記録し、チーム全体で共有 | – 業務の属人化を解消 |
| – 業務手順や判断基準を明確化し、標準化 | – 業務品質の均質化と効率化を促進 | |
| – 新メンバーの教育コストを削減 | – 即戦力化を支援 | |
| コミュニケーションの活性化と組織文化の醸成 | – メモへのコメントやリアクション機能を通じて、メンバー間のコミュニケーションを促進 | – 活発な意見交換を支援 |
| – 代表や経営陣の考えや情報を共有 | – 組織全体のベクトルを合わせ、一体感を醸成 | |
| – 成功事例や失敗事例を共有 | – 学びを促進し、組織全体の成長を加速 | |
| – 感謝を伝える制度や部活動など、ユニークな取り組みを共有 | – 組織文化を醸成し、エンゲージメントを向上 |





