ファイル共有サーバーって何?メリットやデメリット、NASとの違いも解説
最終更新日:2025年3月5日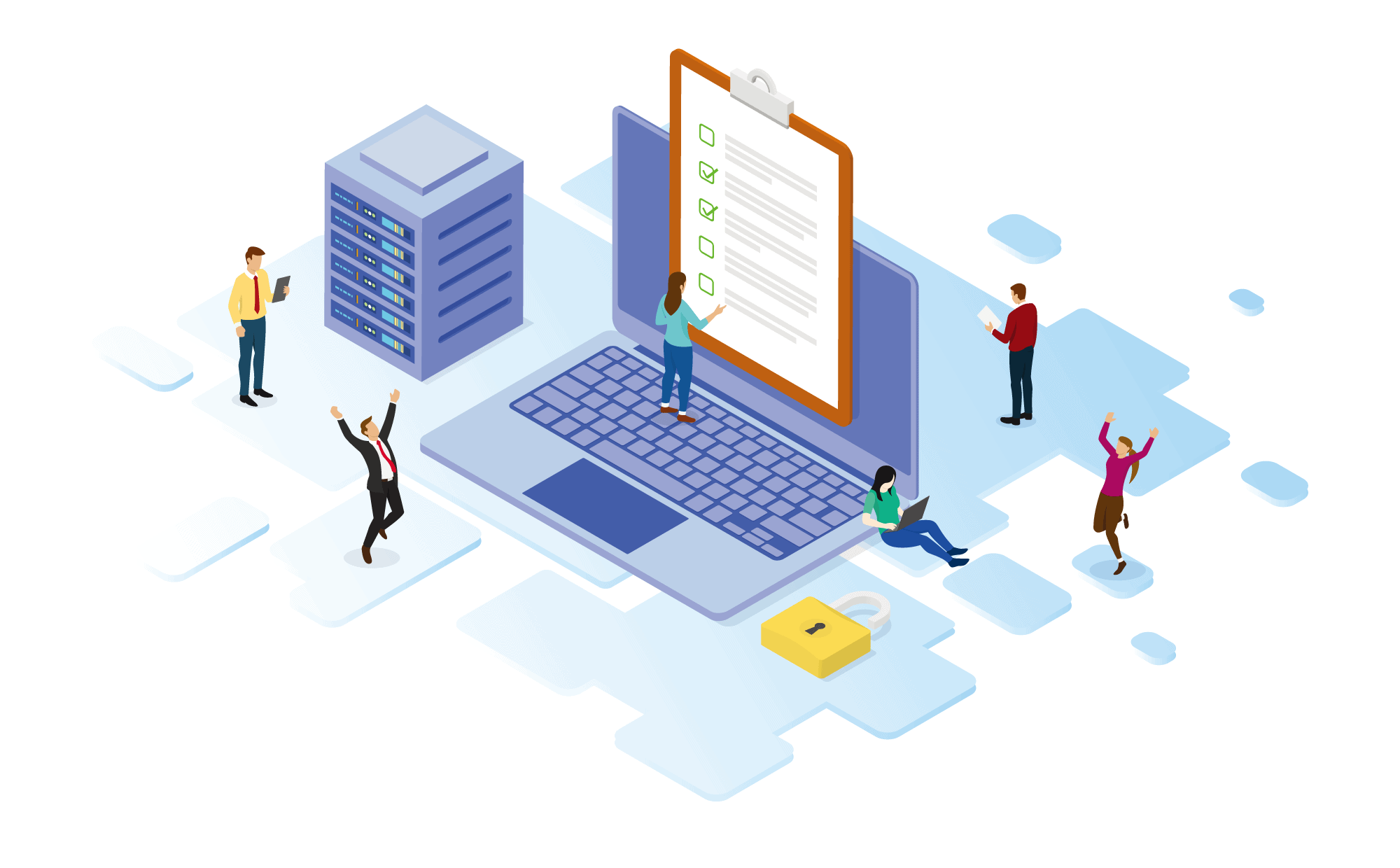
ファイル共有サーバーは、社内の重要データを一元管理し、業務効率を劇的に向上させる便利なシステムです。しかし、導入にあたっては、メリット・デメリットを十分に理解し、自社に最適なソリューションを選択する必要があります。
本記事では、ファイル共有サーバーの基本的な仕組みから、導入時の注意点、さらにはNASや他の共有方法との違いまで、実務に即した形で詳しく解説します。社内のデータ管理を改善したい方、導入を検討している方におすすめです。
【この記事を読んでわかること】
- ファイル共有サーバーの仕組みと主要な用途
- ファイル共有サーバーのメリットとデメリット
- クラウド型ファイル共有サーバーのメリットとデメリット
- クラウド型ファイル共有サーバーを選定する際のポイント
目次
ファイル共有サーバーとは

ファイル共有サーバーとは、企業のデータ管理を円滑にするネットワーク上の大容量コンピューターのことです。このサーバーは、社内の全てのパソコンからアクセス可能で、データの保存や削除を自由に行えます。
従来の企業では、社員それぞれのパソコンにデータを個別に保存し、情報共有が必要な際はメールでのファイル添付や書類の印刷を行って対応していました。この方法では、データの管理が煩雑になり、情報共有に時間がかかるという問題がありました。
そういった問題を解消するために、ファイル共有サーバーを導入することで、データの保存場所が一元化されます。例えば、営業部門で作成した提案書をサーバー上に保存すれば、他部門のメンバーも即座にその内容を確認できます。このように、社内の情報共有がスムーズになり、業務効率が大幅に向上します。
また、データを一か所で管理できるため、重要な情報の紛失リスクも軽減されます。万が一、社員のパソコンが故障しても、サーバーにデータが保存されているため、業務の継続性が保たれます。
ファイル共有サーバーは、現代のビジネスに不可欠なデータ管理基盤として、多くの企業で活用されています。
ファイル共有サーバーの用途

ファイル共有サーバーには、ビジネスを効率化する4つの主要な用途があります。それぞれの用途について、具体的なメリットを解説します。
1つ目はデータの保管・共有です。営業資料や提案書などの業務データをサーバーに保存することで、必要な時に誰でもアクセスできます。例えば、支社の担当者が本社の過去の提案資料を参照したい場合でも、即座に閲覧が可能です。
2つ目はバックアップ機能です。パソコンの故障やウイルス感染による予期せぬデータ消失を防ぎます。重要なプロジェクトデータを毎日バックアップすることで、業務の中断リスクを最小限に抑えられます。
3つ目はチームにおける共同作業の実現です。複数メンバーが同じプロジェクトに取り組む際、最新のファイルをサーバー上で共有できます。メールでのやり取りが減少し、作業効率が向上します。
4つ目はデータの一元管理です。社内のさまざまなデータを体系的に整理・保管できます。部署やプロジェクトごとにフォルダを分類することで、必要な情報へのアクセスが容易になります。
こういったファイル共有サーバーの用途から企業の情報管理が効率化され、生産性の向上につながります。
ファイル共有サーバーとNASとの違い

ファイル共有サーバーとNASは、一見似ているように見えますが、機能や用途に大きな違いがあります。NAS(Network Attached Storage)は、ネットワークに接続できる外付けハードディスクとして機能します。
NASの最大の特徴は、導入のしやすさにあります。比較的安価で、設置も簡単なため、小規模なデータ共有環境を整備したい企業に適しています。しかし、基本的な機能は保管と共有に限定されており、システム構築は利用者側で行う必要があります。
一方、ファイル共有サーバーは、より高度なデータ管理が可能です。アクセス権限の詳細な設定や、セキュリティ管理など、企業の要望に応じてカスタマイズできます。
NASには運用面での課題もあります。物理的な機器であるため、故障のリスクが存在し、ネットワークの不具合が発生した場合はデータにアクセスできなくなる可能性があります。また、アクセス権限の管理が柔軟でないため、セキュリティ面での懸念もあります。
導入に際しては、ファイル共有サーバーとNASの理解を把握し、企業規模や用途に応じて、適切な選択を行うことが重要です。
ファイル共有サーバーとNASの違い
| NAS (Network Attached Storage) | ファイル共有サーバー | |
| 主な機能 | データ保管・共有 | データ管理、アクセス制御、セキュリティ管理、カスタマイズ |
| 導入の容易さ | 簡単 (比較的安価、設置が容易) | 比較的難しい (構築に知識が必要、カスタマイズによっては費用がかかる) |
| カスタマイズ性 | 低い (基本的な機能に限定、システム構築は利用者側) | 高い (企業の要望に応じて詳細な設定が可能) |
| セキュリティ | アクセス権限管理が柔軟でないため、懸念あり | 詳細なアクセス権限設定が可能、セキュリティ管理機能が充実 |
| 運用面 | 物理的な機器であるため、故障のリスクあり。ネットワークの不具合時にアクセス不可の可能性あり | 比較的安定 (ハードウェア冗長化やバックアップ体制を構築しやすい) |
| 適した規模 | 小規模なデータ共有環境 | 中規模~大規模、セキュリティやデータ管理を重視する企業 |
| 費用 | 比較的安価 | 比較的高い (導入・構築費用、運用費用) |
【参考】ファイル共有サーバーと共有フォルダ・FTPとの違い
ファイル共有の方法には、共有フォルダやFTPサーバーなど複数の選択肢があります。それぞれの特徴と限界を理解することで、最適な方法を選択できます。
共有フォルダは、同一ネットワーク内でフォルダを共有する基本的な機能です。追加費用なく利用できるメリットがありますが、ネットワークに不具合が発生すると即座に利用不可能になります。例えば、社内LANに障害が起きた場合、保存されたデータへのアクセスが完全に遮断されてしまいます。
FTPサーバーは、FTPプロトコルを使用してファイルを送受信するシステムです。主にデータ転送に特化しており、大容量ファイルの送受信に適しています。しかし、重大な欠点としてパスワードが暗号化されないため、情報漏えいのリスクが存在します。
これに対し、ファイル共有サーバーは、データの一元管理と共有を主目的とし、高度なセキュリティ設定や権限管理が可能です。企業の重要データを扱う場合は、この方式が最も安全で効率的な選択となります。
ファイル共有サーバーのメリット

ファイル共有サーバーを利用するメリットは以下のような点が挙げられます。
- データへのアクセス性が向上して業務が効率化される
- 容量を気にせずデータ保存できる
- セキュリティ性が高い
以下から具体的に解説していきます。
データへのアクセス性が向上し業務が効率化される
社内データの共有に時間や手間がかかる……。そんな悩みを解決するのが、ファイル共有サーバーです。
個人PCでデータを管理していた場合、他のメンバーとの共有にはメールやUSBメモリが必要でした。しかし、ファイル共有サーバーを導入すれば、サーバー内のデータが更新された瞬間に、全メンバーが最新情報を確認できます。
特に効果を発揮するのが部署間でのデータ共有です。「営業部から先月の売上データを求められたけど、わざわざメールで送らなくても、保管場所を伝えるだけでOK」といった具合に、データ共有の手間が大幅に削減されます。
さらに、過去の企画書や提案書といった参考資料も、サーバー内で一元管理されているため即座に見つけられます。以前は「どこかのPCに保存してあるはずだけど……」と探し回っていた手間も省けます。
ファイル共有サーバーの導入によって、業務の無駄な中断を減らし、本来注力すべき仕事に時間を使えるようになります
容量を気にせずデータ保存できる
「PCの容量が足りない」という警告。このメッセージに頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
個人PCでデータを管理していると、保存容量の限界にいずれ直面します。その度に「古いデータを削除するか、別の場所に移動するか」という判断を迫られ、業務の中断を余儀なくされます。
ファイル共有サーバーは、この容量の問題を解決します。サーバーは膨大なデータを保存できる設計になっており、必要に応じて容量を追加することも可能です。
例えば、毎月の売上データや日々の業務報告書、製品の設計図面といった大容量のファイルも、容量を気にせずに保存できます。また、数年前の企画書や提案書も、履歴として残しておけるため、新規プロジェクトの参考資料としても活用できます。
ファイル共有サーバーによって、データ整理の手間から解放され、業務に集中できる環境が実現します。
セキュリティ性が高い
「顧客データを社外に持ち出してしまった」「USBメモリを紛失した」。このような事故は、企業の信頼を大きく損なう結果になりかねません。
ファイル共有サーバーは、データを一元管理することでこれらのリスクを防ぎます。重要データは共有サーバー内で集中管理され、個々のPCやUSBメモリにデータを保存する必要がなくなるためです。
具体的な機能として、部署やプロジェクトごとにアクセス権限を設定できます。例えば「経理部のデータは経理部員のみアクセス可能」「プロジェクトの進行状況は管理職のみ編集可能」といった具合に、細かな権限設定が可能です。
また、サーバー上のデータは定期的にバックアップされるため、PCの故障や操作ミスによるデータ消失も防げます。
ファイル共有サーバーは、情報漏えいのリスクを最小限に抑え、安全なデータ管理を実現するという重要な役割を果たしています。
ファイル共有サーバーの注意点

ファイル共有サーバーを利用するにあたっては、以下のような注意点が挙げられます。導入を検討するにあたって、あらかじめ理解しておくと良いでしょう。
- 導入に手間がかかる
- 運用にコストがかかる
- クラウド型でない場合は物理的なトラブル対策が必要
それぞれについて、以下から具体的に解説していきます。
導入に手間がかかる
ファイル共有サーバーの導入には、慎重な準備と専門的な知識が必要な作業です。
導入に必要な作業は多岐にわたります。まず、サーバー本体と搭載するOSの選定から始まり、ファイル共有システムの構築、そしてアクセス権限の設定まで、専門的な知識が求められる作業が続きます。
特に重要なのが、セキュリティ設定です。一度設定を誤れば情報漏えいのリスクが高まるため、後回しにはできません。例えば、部署ごとのアクセス権限設定や、データの暗号化といった作業は、慎重に進める必要があります。
導入後も定期的なメンテナンスが欠かせません。システムのアップデートやセキュリティパッチの適用、不要データの整理など、継続的な管理作業が発生します。
これらの作業を確実に行うには、社内に専門知識を持つ管理者を置くか、外部の専門家に委託する必要があります。ファイル共有サーバーの導入を検討する際は、この点も考慮に入れる必要があります。
運用にコストがかかる
ファイル共有サーバーの導入を含む運用には、相応の投資が必要です。規模や構成、利用状況によって大きく異なりますが、一般的に以下のような費用が発生します。
1. サーバー本体の費用
- 初期費用:
- ハードウェア購入費用: サーバー本体(CPU、メモリ、ストレージなど)、RAIDコントローラー、電源ユニットなどの購入費用
- ソフトウェアライセンス費用: サーバーOS、ファイル共有ソフトウェア、バックアップソフトウェアなどのライセンス費用
- ネットワーク機器費用: ルーター、スイッチ、ファイアウォールなどのネットワーク機器の購入費用
- ランニングコスト:
- 電気代: サーバーの稼働に必要な電気代
- 保守・メンテナンス費用: ハードウェア故障時の修理費用、定期的なメンテナンス費用、ソフトウェアのアップデート費用など
- 減価償却費: サーバーの耐用年数に応じた減価償却費
2. ストレージの費用
- 初期費用:
- ストレージ購入費用: HDDやSSDなどのストレージデバイスの購入費用
- ストレージ拡張費用: 将来的なデータ増加に対応するためのストレージ増設費用
- ランニングコスト:
- ストレージのメンテナンス費用: ストレージデバイスの故障時の修理費用、定期的なメンテナンス費用。
3. ネットワークの費用
- 初期費用:
- ネットワーク工事費用: サーバー設置場所へのネットワーク配線工事費用
- ランニングコスト:
- 回線費用: インターネット回線や専用線などの通信回線費用
- ネットワーク機器のメンテナンス費用: ルーターやスイッチなどのメンテナンス費用
4. 管理・運用の費用
- 人件費: サーバーの構築、運用、監視、障害対応を行う担当者の人件費
- 監視ツールの費用: サーバーやネットワークの状態を監視するためのツールの利用費用
- セキュリティ対策費用: セキュリティソフトの導入費用、セキュリティ対策に関するコンサルティング費用
- バックアップ費用: バックアップ用ストレージの購入費用、バックアップ作業の人件費、災害対策費用
- ファイル復旧費用: ファイルを誤って削除した場合の復旧費用
5. その他費用
- サーバーラックやUPS(無停電電源装置)の費用: サーバーを設置するためのラックや、停電対策のためのUPSの購入費用
- データセンター利用料: データセンターを利用する場合の利用料
- ソフトウェアのアップグレード費用: OSやファイル共有ソフトウェアのアップグレード費用
【具体的な費用の例】
上記の費用は、サーバーの規模や構成、利用状況によって大きく異なります。以下に、具体的な費用の例を挙げます。
| ファイルサーバーの規模 | 初期費用 | 月額ランニングコスト | 主な用途 |
| 小規模オフィス向け | 数十万円~数百万円 | 数千円~数万円 | 少人数でのファイル共有、簡易的なバックアップ |
| 中規模企業向け | 数百万円~数千万円 | 数万円~数十万円 | 部門ごとのファイル共有、部門ごとのバックアップ、アクセス権限管理 |
| 大規模企業向け | 数千万円~数億円 | 数十万円~数百万円 | 全社でのファイル共有、高度なアクセス権限管理、大規模なバックアップ、災害対策 |
ファイル共有サーバーの運用コストは、導入前にしっかりと検討し、自社のニーズに合った最適な構成を選択することが重要です。
クラウド型でない場合は物理的なトラブル対策が必要
オフィス内にファイル共有サーバーを設置する場合、日本特有の自然災害リスクへの対策が不可欠です。日本は地震大国であり、また台風による水害も頻発します。これらの自然災害は、サーバー機器に重大な被害をもたらす可能性があります。
具体的には、地震による機器の転倒や破損、水害による浸水被害、さらに災害に伴う停電によってサーバーが停止するリスクなどが存在します。最悪の場合、重要な業務データが完全に消失し、事業継続に深刻な影響を及ぼす事態も想定されます。
こういったリスクを回避するため、遠隔地のデータセンターにサーバーを設置する選択肢もあります。しかし、施設利用料、運用管理費用、さらにはネットワーク回線費用など、追加コストが発生します。また、緊急時の対応も遠隔操作に限られるため、即時対応が難しくなる場合があります。
社内にファイル共有サーバーを設置する場合は、無停電電源装置の導入や、定期的なバックアップ、耐震対策など、包括的な防災計画の策定が必要です。これらの対策にかかるコストと手間を考慮した上で、導入を検討することをおすすめします。
ファイル共有サーバーはどのような企業におすすめか?

データ管理の課題を抱える企業にとって、ファイル共有サーバーは有効な解決策となります。特に、以下のような状況にある企業では、導入による業務改善効果が期待できます。
- 事業規模の拡大に伴いデータ量が増加している企業
- 個人のPCでのデータ管理やメールでの共有では、情報の整理や検索に時間がかかり、業務効率が低下します。
- 全社的なバックアップ体制が整っていない企業
- 現在、データ保管を社員個人に任せている場合、重要データの消失リスクが高く、事業継続の観点から危険です。
- 資料の検索や共有に時間を要している企業
- 必要な資料を探すために同僚に確認が必要な状況は、明らかに業務が非効率であることを示しています。
- 部署ごとにアクセス権限を細かく設定したい企業
- 情報セキュリティの観点から、データへのアクセスを適切に制御する必要がある場合、ファイル共有サーバーの導入が有効です。
ただし、導入には一定のコストと運用体制の整備が必要です。これらの負担に見合う効果が得られるか、事前に十分な検討を行うことが重要です。
クラウド型ファイル共有サーバーについて

クラウド型ファイル共有サーバーは、インターネットを介してデータ保管・共有機能を提供するサービスです。従来型の物理サーバーと異なり、データの保管場所はサービス提供事業者が管理するデータセンターとなります。
企業は、インターネット経由でサービス事業者のデータセンターにアクセスし、必要なデータの保存や取り出しを行います。データセンターには高性能なサーバー群が設置されており、企業のデータを安全に保管します。
このサービスの特徴は、必要に応じて保存容量を柔軟に拡張できる点です。事業規模の拡大や取り扱うデータ量の増加に応じて、利用容量の追加が可能です。また、文書管理機能やワークフロー機能など、業務に必要な機能を追加することもできます。
企業側に必要なのは、インターネット環境と各端末へのソフトウェアインストールのみです。サーバー本体の購入や設置は不要となり、初期投資を抑えることができます。データセンターの運用やメンテナンスは、全てサービス事業者が担当します。
クラウド型ファイル共有サーバーのメリット

クラウド型ファイル共有サーバーを利用するメリットには、以下の点が挙げられます。
- 手間・費用面でのコストが削減できる
- 自社にサーバーを置く必要がない
- セキュリティ性が向上する
- 社内・社外を問わずアクセス可能
それぞれについて詳しく解説していきます。
手間・費用面でのコストが削減できる
クラウド型ファイル共有サーバーの導入は、企業の運用コストを大幅に削減します。具体的なコスト削減効果は以下の3つです。
- 初期導入時のコストを削減
- 物理サーバーの購入費用が不要となり、サーバールームの空調設備や無停電電源装置などの付帯設備も不要です。サービス事業者が提供する環境をそのまま利用できるため、設備投資を最小限に抑えられます。
- 運用管理の工数を削減
- サーバーの設定やセキュリティパッチの適用、システムの監視といった日常的な管理業務は、全てサービス事業者が実施します。社内のIT担当者の負担が軽減され、より戦略的な業務に時間を割り当てることができます。
- ランニングコストを削減
- サーバー機器の電力消費や空調費用が不要となり、月々の光熱費を抑制できます。また、機器の保守費用や更新費用も発生しないため、長期的な費用対効果が高くなります。
これらのコスト削減効果により、企業は本来の事業活動により多くの経営資源を投入することが可能になります。
自社にサーバーを置く必要がない
クラウド型ファイル共有サーバーは、物理的な制約から企業を解放します。具体的には、設置スペースと災害対策の2つの面で大きなメリットがあります。
設置スペースに関して、従来型のサーバー導入では、サーバールームや機器保管用のスペースを確保する必要がありました。特に都心のオフィスでは、限られた空間を有効活用する必要があるため、サーバー設置場所の確保は大きな課題でした。クラウド型では、これらの物理的スペースが不要となり、オフィススペースを本来の業務用途に活用できます。
災害対策面においては、サービス事業者が万全の体制を整えています。データセンターには、地震対策、水害対策、火災対策が施されており、24時間365日の監視体制が敷かれています。また、定期的なバックアップと複数拠点でのデータ保管により、災害時のデータ消失リスクを最小限に抑えています。
仮に災害でデータが損傷した場合でも、サービス事業者が迅速な復旧対応を行い、業務への影響を最小限に抑えられます。これにより、企業は事業継続性を高めることができます。
セキュリティ性が向上する
クラウド型ファイル共有サーバーは、専門的なセキュリティ対策により、データを強固に保護します。
最新のセキュリティ技術が常時適用され、サービス事業者は新しいサイバー攻撃手法に対する防御策を迅速に実装します。ウイルス対策、不正アクセス防止、暗号化通信など、包括的なセキュリティ対策が提供されるため、企業単独で実施するよりも高度な保護が実現できます。
情報漏えい対策も充実しています。アクセス権限の細かな設定により、部署や役職に応じた適切なデータアクセス制御が可能です。また、アクセスログの記録と監視により、不正な情報持ち出しを防止できます。これらの設定は、サービス事業者のサポートを受けながら、直感的なインターフェースで簡単に行えます。
さらに、社内システムと分離された環境でデータを保管するため、社内ネットワークへの攻撃があった場合でも、クラウド上のデータは保護されます。これにより、重要データの二重の安全性が確保されます。
社内・社外を問わずアクセス可能
クラウド型ファイル共有サーバーの最大の特長は、場所を問わずにデータにアクセス可能で、業務の柔軟性と生産性が大幅に向上することです。
インターネット環境があれば、オフィス外からでも必要なデータにアクセスできます。営業担当者が客先でプレゼン資料を表示したり、外出先で急な資料の確認が必要になった場合でも、すぐにデータを取り出せます。
特に昨今増加しているテレワークにおいて、その価値が発揮されます。在宅勤務者は、社内にあるデータに自宅からシームレスにアクセスできます。VPN接続などの複雑な設定は不要で、通常のインターネット接続だけで業務が可能です。
また、社内ネットワークに障害が発生した場合でも、業務継続が可能です。クラウド型ファイル共有サーバーのデータにアクセスできるため、ネットワーク障害や災害時でもファイル共有機能は維持されます。これにより、事業継続性が向上し、緊急時の業務停滞を防げます。
クラウド型ファイル共有サーバーのデメリット

クラウド型ファイル共有サーバーを利用する際のデメリットも把握しておきましょう。以下のようなデメリットが挙げられます。
- 利用料が毎月発生する
- カスタマイズ性はやや劣る
- 最低限の操作方法は知っておく必要がある
- データ表示に時間がかかることもある
それぞれについて具体的に解説していきます。
利用料が毎月発生する
企業がクラウド型ファイル共有サーバーを導入する際には、外部事業者が提供するサービスであるため、月額費用は必須となります。
とはいえ、クラウド型サーバーでは、データ管理やセキュリティ対策、システムの保守・運用など、通常なら専門スタッフを自社で雇用して対応する必要がある業務を全て任せることができます。
さらに、自社でサーバーを構築する場合と比較すると、初期費用を抑えられるだけでなく、機器の更新や修理費用も不要です。毎月定額のため、予算管理も容易になります。
実際の導入を検討する際は、自社の規模や業務内容に応じて、必要な機能と月額費用のバランスを確認することをおすすめめします。多くの場合、想定以上の業務効率化とコスト削減効果が期待できます。
カスタマイズ性はやや劣る
クラウド型ファイル共有サーバーのカスタマイズ性については、機能が事業者によってあらかじめ設定されているため、自社管理型と比較すると柔軟性は限定的です。
しかし、実際の業務では標準機能で十分対応できる場合がほとんどです。現代のクラウドサービスには、文書管理、バージョン管理、アクセス権限設定など、企業の基本的なニーズを満たす機能が標準で搭載されています。
また、多くのサービスでは追加のオプション機能も用意されており、業務の特性に応じて必要な機能を選択できます。例えば、電子署名機能や監査ログ機能など、専門的な要件にも対応可能です。
導入前に自社の業務フローを整理し、必要な機能を明確にすることで、最適なサービスを選択できます。特殊な業務要件がない限り、カスタマイズ性を過度に心配する必要はありません。
最低限の操作方法は知っておく必要がある
クラウド型ファイル共有サーバーを導入する際、操作方法の習得に対する不安を抱える企業は少なくありません。実際、従来のファイル管理方法とは異なる部分があり、基本的な操作方法の習得は必須となります。
特に注意が必要なのは、全社員への教育です。データの保存場所、アクセス権限の確認方法、ファイルの共有手順など、基本的な操作手順を全員が理解する必要があります。この教育には一定の時間と労力が必要です。
ただし、最近のクラウドサービスは直感的な操作性を重視して設計されています。従来使用しているWindowsやMacのファイル操作と似た画面構成を採用し、アイコンや操作ボタンもわかりやすく配置されています。
導入時は、まず管理者が基本機能を理解し、段階的に社員教育を進めることをおすすめします。
データ表示に時間がかかることもある
クラウド型ファイル共有サーバーを利用する際、データ表示の速度に関して懸念を持つ企業も多いです。インターネット経由でファイルにアクセスするため、通信環境がデータ表示速度に直接影響するためです。
特に注意が必要なのは、大容量ファイルの取り扱いです。画像データや動画ファイルなど、サイズの大きいデータを頻繁に扱う業務では、ダウンロードやアップロードに時間がかかることがあります。
また、社内のインターネット回線速度が遅い場合や、電波状態が不安定な場所での作業では、データアクセスにストレスを感じる可能性があります。複数の社員が同時にサーバーにアクセスする時間帯は、速度低下が特に起こりやすくなります。
このため、導入前に自社のネットワーク環境を確認し、必要に応じて回線速度の増強を検討することをおすすめします。また、日常的に大容量データを扱う部署がある場合は、オフラインでの作業も可能なハイブリッド型の運用を考慮するとよいでしょう。
クラウド型ファイル共有サーバー時の選定ポイント
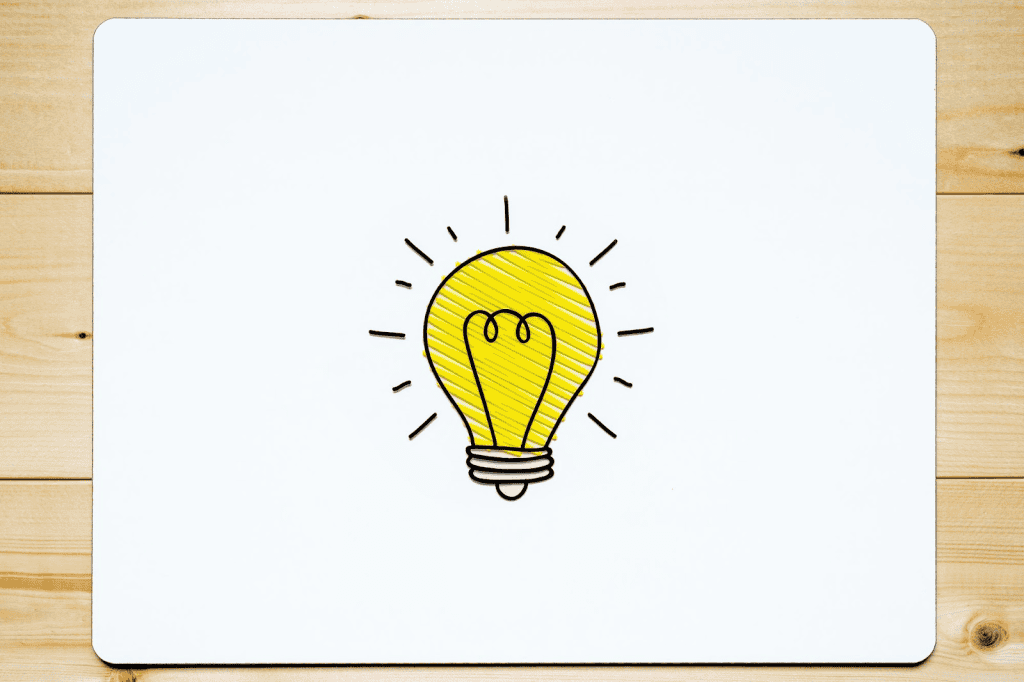
クラウド型ファイル共有サーバーの導入を成功させるには、適切な選定基準に基づいて製品を比較検討することが重要です。ここでは、主要な選定ポイントを3つ解説します。
第一のポイントは、コストの評価。月額利用料が自社の予算内に収まることは必須条件です。特に料金体系には注意が必要で、利用者数に応じて料金が変動するアカウント課金型と、定額制があります。将来の人員増加も考慮して、長期的な視点で費用を試算しましょう。
第二のポイントは、セキュリティ対策の確認です。自社のセキュリティポリシーを事前に整理し、サービス提供事業者の対策内容が要件を満たしているか精査します。データ暗号化、アクセス制御、監査ログなど、具体的な機能の有無を確認することが重要です。
第三のポイントは、必要機能の確認です。自社の利用目的を明確にして、それに合致した機能を持つサービスを選びます。例えば、同時編集機能やモバイル対応、取引先とのファイル共有機能など、業務に不可欠な機能を優先的に評価していきましょう。
ファイル共有サーバーにはさまざまなメリットがある

ファイル共有サーバーは、社内データの一元管理と業務効率化を実現するシステムです。物理型サーバーとクラウド型サーバーの両方に、それぞれのメリット・デメリットがありますが、企業規模や業務内容に応じて適切な選択をすることで、大きな効果が期待できます。
特にクラウド型のファイル共有サーバーは、初期投資を抑えながら高度なセキュリティと柔軟なアクセス環境を実現できる点でおすすめです。ただし、月額費用や通信速度などの制約も考慮する必要があります。
導入を検討する際は、自社のニーズを明確にし、コスト、セキュリティ、必要機能の3点を中心に慎重に検討しましょう。適切な選定と運用により、データ管理の効率化と業務生産性の向上を実現できます。
ファイル共有サーバーの選定に迷ったら、情報共有ツールであるDocBaseをご検討ください。DocBaseをファイル共有サーバーとして利用した場合の特徴と機能には、以下のようなものがあります。
| 特徴/機能 | 詳細 |
| ファイルアップロード | PDF、ZIP、PG, PNG, GIF, SVG、Excelなど各種形式のファイルをアップロード可能 |
| 添付ファイル内検索 | アップロードしたPDFやExcelなどの添付ファイル内のキーワード検索が可能。ファイル名だけでなく、ファイルの中身も検索できる |
| 柔軟な公開範囲設定 | グループ機能により、メモ(および添付ファイル)の公開範囲を限定できる。メモは複数のグループに公開可能で、情報を見せる範囲を柔軟に決定可能 |
| 外部共有 | チーム外の人にもメモを共有できる。パスワード設定も可能 |
| マルチデバイス対応 | スマートフォンやタブレットからも閲覧、編集が可能で、場所を選ばずに情報共有が可能 |
| 操作履歴 | 誰がいつどのような操作を行ったか、操作履歴をCSV形式でダウンロード可能。ファイルのアップロードやダウンロードに関する履歴も確認できる |
| アクセストークン管理 | チームメンバーが作成したアクセストークンの確認や有効・無効の切り替えが可能 |
| データの暗号化 | メモや個人情報など、全てのデータは暗号化されてデータベースに格納。メモに関してはチームごとに暗号化されている |
| アクセス制限 | DocBaseにアクセスできるIPアドレスを制限可能 |
| チーム管理 | チームの全てのメモと添付ファイルを一括でエクスポート可能。Markdown形式とJSON形式を選択可能 |





