ナレッジ共有は専用ツール×テンプレート使用がおすすめ!共有のポイント、流用できる他ツールも解説
最終更新日:2025年2月20日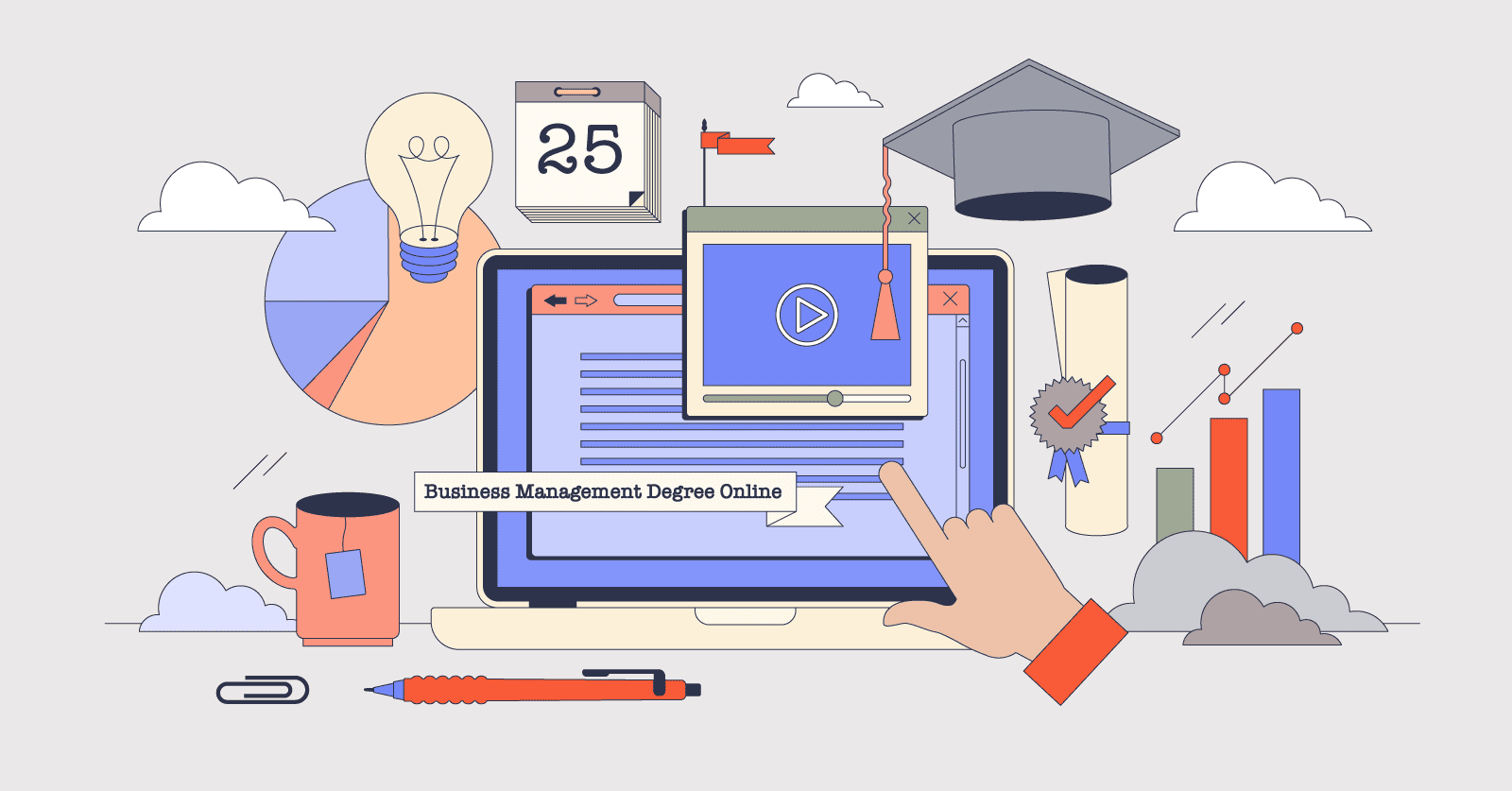
ナレッジ共有の効率化に悩んでいる企業が増えています。日々蓄積される業務知識や経験を、どのように整理し共有すれば良いのか。その解決策として注目を集めているのが、専用のナレッジ共有ツールとテンプレートの組み合わせです。適切なナレッジツールとテンプレートを活用することで、情報の整理・検索が容易になり、組織全体での知識共有が進みます。
本記事では、ナレッジ共有に最適なツールの選び方や、効果的なテンプレートの作成方法、運用のポイントまで詳しく解説します。業務効率の向上や問題解決力の強化を目指す方は、ぜひ参考にしてください。既存のエクセルを活用する方法から、最新のAIチャットボットまで、さまざまな選択肢の中から自社に合った方法を見つけましょう。
この記事を読んでわかること
- ナレッジ共有は、専用ツールのテンプレートを使用するのがおすすめ
- テンプレートを作る手順は、管理したい項目を定める、フォーマットを用意する、共有設定をする
- テンプレートによるナレッジ共有のポイントは、検索しやすい環境、作成・管理がしやすいフォーマット、必要に応じた編集者の制限、共有するナレッジの基準策定、全体への周知、効果測定
- エクセルも利用できるが、デメリットも多い
目次
ナレッジ共有のツールとテンプレート
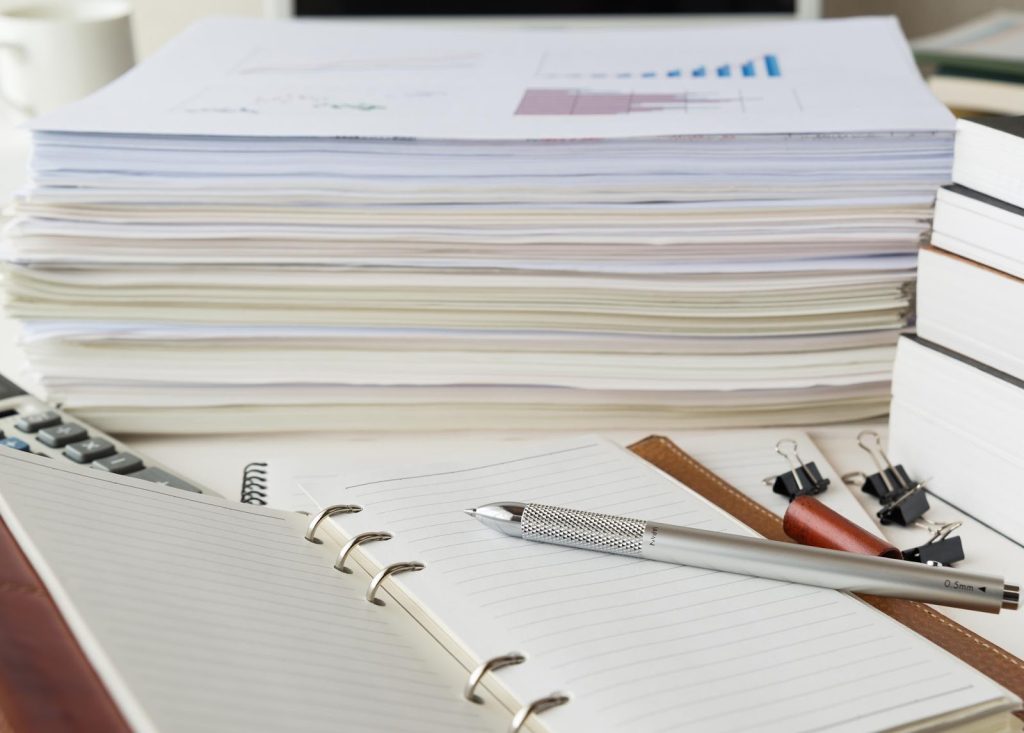
ナレッジ共有には、専用ツールに用意されているテンプレートを活用するのがおすすめです。テンプレートを使えば、形式が統一され、情報の検索性も向上します。共有する側も、受け取る側も、効率的にナレッジを活用できます。属人化を防ぎ、組織全体の知識レベルを底上げするでしょう。
ここでは以下の2点について、詳しく紹介していきます。
- ナレッジ共有はツールがおすすめ
- テンプレート化するメリット
ナレッジ共有はツールがおすすめ
ナレッジ共有を効率的に進めるなら、専用ツールの活用がおすすめです。マニュアルや社内Wiki、FAQから日報まで、幅広い用途に対応できるのが特徴です。
情報を簡単に入力できる画面構成や、整理された形で保存できる仕組みにより、誰でも迷わず使えます。また、あらかじめ用意されたテンプレートを活用すれば、統一された形式でナレッジを蓄積できます。
ナレッジツールを導入することで、組織全体で知識や経験を効率的に共有でき、業務の生産性向上につながります。
テンプレート化するメリット
テンプレートを活用したナレッジ共有は、業務の効率化に大きな効果をもたらします。
社員は定められた入力欄に記入するだけで、統一された形式のナレッジに関するドキュメントを作成できます。作成にかかる時間が短くなり、共有への抵抗感もなくなるでしょう。
また、テンプレートには必要な項目があらかじめ設定されているため、重要な情報の記入漏れを防げます。統一された形式は情報の検索性も高めるため、必要なナレッジを素早く見つけることができます。
このように、テンプレート化はナレッジ共有を成功に導く重要な要素となります。
ナレッジ共有のテンプレートを作る手順

ここでは、ナレッジ共有のテンプレートを作成する際に、どのようなことをすればいいのか、以下の手順に従って具体的に解説していきます。
- 管理したい項目を定める
- フォーマットを用意する
- 共有設定をする
管理したい項目を定める
ナレッジ共有を始める前に、まず管理する項目を明確にする必要があります。
効果的な項目例として、記入日、内容の分類、概要、担当者名、更新履歴などが挙げられます。これらの項目を設定することで、情報を整理して探しやすい環境が整います。
専用のナレッジツールを利用すると、これらの項目を自由に追加したり、不要な項目を削除したりすることが簡単にできます。チームの特性や目的に合わせて、柔軟に項目を調整できる点が大きな特徴です。
例えば、プロジェクト管理では進捗状況の項目を、技術情報の共有では難易度レベルの項目を追加するなど、場面に応じた使い分けが可能です。このようなテンプレートの柔軟性により、より実用的なナレッジ共有が実現できます。
ナレッジ共有テンプレートの項目内容例
1. 基本情報
- タイトル: ナレッジの内容を簡潔に表すタイトル。検索性も考慮してキーワードを含めると良い。
- 作成者: ナレッジを作成した担当者名。問い合わせ先を明確にする。
- 作成日/更新日: ナレッジが作成・更新された日時。情報の鮮度を把握する。
- 対象者: 誰に向けたナレッジか(例:新入社員、特定チーム、全社員など)。
- カテゴリ/タグ: ナレッジを分類するためのカテゴリやタグ。検索性を高める。
2. ナレッジの内容
- 概要: ナレッジの要点をまとめた簡単な説明。
- 背景/目的: なぜこのナレッジが必要なのか、どのような課題を解決するためのものか。
- 詳細な説明: 具体的な手順、方法、根拠など、ナレッジの内容を詳しく解説。
- 図、表、スクリーンショットなどを活用して、視覚的に分かりやすくする。
- 専門用語は分かりやすく説明するか、注釈をつける。
- 補足情報: 関連する情報へのリンク、参考資料、注意事項など。
- 事例/成功例/失敗例: 実際の事例や経験に基づいて、ナレッジの理解を深める。
- FAQ: よくある質問と回答をまとめる。
- 関連ナレッジ: このナレッジと関連する他のナレッジへのリンク。
- 注意点/リスク: ナレッジを活用する上での注意点やリスク。
- 関連ツール/システム: ナレッジを活用するために必要なツールやシステム。
3.フィードバック
- フィードバック欄: ナレッジに対する質問、コメント、改善提案などを収集する。
- 評価: ナレッジの有用性を評価するための項目(任意)。
テンプレートは、上記の項目を参考に、自社のナレッジ共有の目的や対象者に合わせて最適化してください。重要なのは、共有されたナレッジが活用され、組織全体の成長につながることです。
フォーマットを用意する
ナレッジ共有を成功させる鍵は、見やすく使いやすいフォーマットの整備にあります。
まずは必要な項目を見出しとして明確に設定します。その際、重要な見出しには太字を使い、視覚的に目立たせると効果的です。また、項目と項目の間に罫線を入れることで、情報の区切りがわかりやすくなります。
色使いも重要なポイントです。例えば、優先度の高い情報は赤色、参考情報は青色というように、色分けすることで情報の重要度が一目でわかります。
さらに、見出しレベルを活用して情報を階層化すると、全体の構造が把握しやすくなります。これにより、必要な情報への素早いアクセスが可能になり、日々の業務効率が上がります。
このように整理されたテンプレートは、新しい情報の追加や既存情報の更新をスムーズにし、継続的なナレッジ共有を支えます。
共有設定をする
ナレッジ共有の真の価値は、実際の業務での活用にあります。いくら優れた情報を蓄積しても、現場で使えなければ意味がありません。
そのため、まず明確にすべきことが2つあります。1つ目は「どのナレッジを可視化するか」、2つ目は「どのナレッジを共有すべきか」です。これらを決める際に最も大切なのは、現場の声に耳を傾けることです。
例えば、営業部門であれば成約につながった商談のポイント、製造部門であれば品質向上のためのコツなど、部門ごとに必要とされる情報は異なります。
現場からの意見を積極的に集め、実務で本当に役立つナレッジを見極めましょう。そして、集めた意見を基に共有方法を設計することで、実践的で効果的なナレッジ共有が実現できます。
ナレッジ共有をするときのポイント

ナレッジ共有をする際には、以下のポイントがあります。ここではそれぞれについて具体的に解説していきます。
- ナレッジを検索しやすい環境に整える
- ナレッジの作成・管理がしやすいフォーマットにする
- ナレッジによっては編集者を制限する
- 共有するナレッジの基準を定める
- ナレッジ共有をしたら全体に伝える
- 必ず効果測定する
ナレッジを検索しやすい環境に整える
ナレッジ共有の成功は、必要な情報にすぐにアクセスできる環境づくりにかかっています。
ここで注意したいのは、分類の数は必要最小限に抑えることです。たとえば、営業関連の情報を「商談」「提案」「契約」といった基本的な区分にとどめることで、情報を探しやすくなります。
なお細分化しすぎると、かえって使いづらいので注意しましょう。「新規商談/既存商談」「大口案件/小口案件」というように細かく分けすぎると、情報を探す際に多くの項目を確認する必要が生じます。これでは検索に時間がかかり、業務効率が下がってしまいます。
シンプルな分類構造を採用し、その代わりにキーワード検索機能を充実させることをおすすめします。誰もが素早く目的の情報にたどり着けるようになります。
ナレッジの作成・管理がしやすいフォーマットにする
効果的なナレッジ共有には、誰もが迷わず使えるフォーマットが欠かせません。
基本となるのは、入力項目を最小限に絞り、直感的に分かる配置にすることです。例えば、タイトル、概要、本文という基本的な構成に、日付や担当者名といった必須情報を加えるだけのシンプルな設計が効果的です。
このようにわかりやすい設計にすることで、新入社員から管理職まで、誰もが積極的に情報を共有できるようになります。また、統一された形式は、情報の比較や整理も容易にします。
例えば、日々の業務の気づきや、お客様からいただいた意見など、些細な情報でも共有しやすくなります。こうした小さな積み重ねが、組織全体の知恵となり、大きな価値を生み出します。
ナレッジによっては編集者を制限する
組織内のナレッジには、全員で共有すべき情報もあれば、特定の部署だけに限定すべき情報もあります。そのため、適切なアクセス管理が重要です。
例えば、経営戦略に関する情報は役員クラスのみ、新製品開発の情報は開発部門のみというように、情報の性質に応じて閲覧できる範囲を設定します。
専用のナレッジツールを使えば、部署や役職に応じて細かな権限設定が可能です。「閲覧のみ可能」「編集まで可能」といった段階的な権限付与もできます。
ただし、パスワードによる制限だけでは十分とは言えません。最近では解析ツールの進化により、簡単なパスワードが突破されるリスクもあります。そのため、重要度の高い情報には、より強固なセキュリティ対策を併用することをおすすめします。
ナレッジツールにおけるセキュリティ機能の例
1. アクセス制御
- 認証: パスワード、多要素認証(MFA)、シングルサインオン(SSO)。
- 権限設定: 役割ごとのアクセス権限(閲覧、編集、削除など)。
- 制限: IPアドレス、時間帯によるアクセス制限。
- ログ: アクセス状況の記録。
2. データ保護
- 暗号化: 通信と保存時のデータ暗号化。
- バックアップ: 定期的な自動バックアップ。
- 削除: 安全なデータ削除機能。
- 制限: ファイルアップロード制限(形式、サイズ)。
3. ツール自体のセキュリティ
- アップデート: ソフトウェアの自動アップデート。
- 診断: 脆弱性診断ツール。
- ログ: ツールの操作ログ。
- API: APIアクセスのセキュリティ強化。
4. その他
- 二段階認証: パスワードに加え、追加の認証要素。
- パスワードポリシー: 強固なパスワードルール。
- レポート: アクセス状況のレポート機能。
共有するナレッジの基準を定める
ナレッジ共有を始める際、まず決めるべきは「何を共有するか」という基準です。
共有すべき情報には幅広い種類があります。例えば、電話応対の基本手順、提案書の作成方法、商品知識、トラブル対応事例など、日々の業務に直結する実践的な情報が該当します。
しかし、むやみに情報を増やすことは避けましょう。データが多すぎると、かえって必要な情報を見つけにくくなります。また、更新や管理も難しくなり、古い情報が残り続けるリスクも高まります。
そのため、「このナレッジは誰にとって、どんな場面で役立つのか」という視点で取捨選択することが大切です。まずは部門やチームで特に重要度の高い情報から共有を始め、徐々に範囲を広げていくのがおすすめです。
ナレッジ共有をしたら全体に伝える
効果的なナレッジ共有には、情報の周知徹底が不可欠です。どれだけ質の高いナレッジをまとめても、それが社内で共有されなければ、その価値は半減してしまいます。
ナレッジ共有の周知方法には、組織の規模や文化、利用するツールによってさまざまなアプローチが考えられます。以下に、効果的な周知方法の例を具体的にご紹介します。
ナレッジ共有における周知の例
1. 社内コミュニケーションツールを活用した周知
- 社内チャットツール:
- 専用チャンネルの作成: ナレッジ共有に関する情報を集約する専用チャンネルを作成し、新着情報や更新情報を定期的に発信する。
- メンション機能: 特定のチームや担当者にナレッジ共有を促す際に、メンション機能を活用する。
- Botの活用: 新着ナレッジを自動的に通知するBotを導入する。
- 社内SNS:
- グループの作成: ナレッジ共有に関するグループを作成し、メンバー間で活発な情報交換を促す。
- ハッシュタグの活用: ナレッジのテーマごとにハッシュタグを設定し、検索性を高める。
- いいねやコメント機能: ナレッジに対する反応を可視化し、共有を促進する。
- 社内ポータルサイト:
- トップページへの掲載: 新着ナレッジや重要な情報をトップページに掲載し、視認性を高める。
- ナレッジ共有ページへのリンク: ナレッジ共有ツールへのリンクを分かりやすい場所に掲載する。
- 新着情報の更新: 定期的に新着情報を更新し、サイトの活性化を図る。
2. メールを活用した周知
- メールマガジン: ナレッジ共有に関するメールマガジンを定期的に配信し、新着情報や活用事例を紹介する。
- 部門別/チーム別メール: 特定の部門やチームに向けて、関連性の高いナレッジをメールで周知する。
- 新入社員向けメール: 新入社員向けに、ナレッジ共有の仕組みや利用方法をメールで案内する。
3. 口頭や対面での周知
- 朝礼/全体会議での紹介: 全体会議や朝礼の場で、ナレッジ共有の重要性やメリットを紹介する。
- チームミーティングでの共有: チームミーティングで、特定のナレッジを共有し、意見交換を行う。
- 勉強会/ワークショップの開催: ナレッジ共有に関する勉強会やワークショップを開催し、利用方法を実践的に学ぶ機会を提供する。
- 個別説明: 新入社員やナレッジ共有ツールを使い慣れていない社員向けに、個別に説明を行う。
4. イベントやキャンペーンの実施
- ナレッジ共有コンテスト: ナレッジの質や量を競うコンテストを開催し、モチベーションを高める。
- ナレッジ共有アワード: 優れたナレッジを共有した人を表彰し、称賛する。
- ナレッジ共有キャンペーン: 一定期間に集中的にナレッジ共有を促進するキャンペーンを実施する。
こうした取り組みを継続することで、ナレッジが社内全体に浸透し、業務効率の向上や問題解決力の強化につながります。まずは自社の実情に合わせた周知方法を選び、実践してみましょう。
必ず効果測定する
ナレッジ共有の仕組みを導入する際は、効果測定が重要です。定量的な指標と定性的な指標から、取り組みの成果を把握することで、改善点を見出せます。効果測定の方法は多岐にわたりますが、ここでは具体的な例をいくつか紹介します。
1. 定量的な指標による効果測定
- ナレッジの登録数/更新数:
- 期間ごとのナレッジ登録数や更新数をカウントし、活動の活発度を測る。
- 部門別やチーム別で比較し、活動の偏りや課題を把握する。
- ナレッジの閲覧数/ダウンロード数:
- ナレッジの閲覧数やダウンロード数をカウントし、ニーズのあるナレッジを把握する。
- 人気のナレッジを分析し、コンテンツの改善に役立てる。
- ナレッジの検索回数:
- ナレッジの検索回数をカウントし、利用頻度を把握する。
- 検索キーワードを分析し、ナレッジの分類やタグ付けの改善に役立てる。
- ナレッジの利用頻度:
- 特定の期間内にナレッジが利用された回数を計測し、利用状況を把握する。
- どのナレッジがよく利用されているか、どのナレッジが利用されていないかを分析する。
- ナレッジ共有ツールの利用時間:
- ナレッジ共有ツールの利用時間を計測し、利用状況を把握する。
- 利用時間の変化を追跡し、キャンペーンや周知活動の効果を測定する。
- 業務効率の向上:
- ナレッジ共有によって、業務にかかる時間やコストがどれだけ削減できたかを測定する。
- 具体的な業務プロセスを分析し、削減効果を数値化する。
- 例えば、問い合わせ対応時間の短縮、新人教育期間の短縮などが考えられる。
- エラー率の低下:
- ナレッジ共有によって、業務上のエラー発生率がどれだけ低下したかを測定する。
- エラー発生の原因を分析し、ナレッジの改善や不足部分の補完に役立てる。
- コスト削減効果:
- ナレッジ共有によって、研修費用、外部コンサルタント費用、印刷コストなどがどれだけ削減できたかを測定する。
- 具体的なコスト項目を洗い出し、削減効果を数値化する。
2. 定性的な指標による効果測定
- アンケート調査:
- ナレッジ共有の満足度、有用性、改善点などをアンケートで収集する。
- 従業員のナレッジ共有に対する意識や行動の変化を把握する。
- 自由記述式の質問を設け、具体的な意見や要望を収集する。
- インタビュー調査:
- 特定の従業員にインタビューを行い、ナレッジ共有の利用状況や課題、改善点を深く掘り下げる。
- ナレッジ共有による業務上の変化や効果を具体的に聞き出す。
- グループインタビュー:
- 複数人でグループインタビューを行い、多様な意見やアイデアを収集する。
- 議論を通して、新たな課題や改善策を見つける。
- ナレッジの質評価:
- 共有されたナレッジの質を評価する。
- 正確性、網羅性、分かりやすさ、最新性などの項目で評価する。
- 評価結果をナレッジ作成者にフィードバックし、改善を促す。
- 現場の声の収集:
- 日々の業務でナレッジ共有を活用している従業員から、直接意見や要望を収集する。
- 現場の課題やニーズを把握し、ナレッジ共有の改善に役立てる。
3. 効果測定の実施サイクル
- 目標設定: 測定対象となる具体的な目標を設定する。
- 例:ナレッジ登録数〇件、閲覧数〇件、業務効率〇%向上など。
- データ収集: 定期的にデータを収集する。
- ツールから自動的にデータを収集する。
- アンケートやインタビューを実施する。
- データ分析: 収集したデータを分析し、目標達成度や課題を把握する。
- 改善策の実行: 分析結果に基づき、ナレッジ共有の仕組みやコンテンツを改善する。
- 効果測定の再実施: 改善策の実施後、再度効果測定を行い、改善効果を確認する。
- 継続的な改善: 効果測定と改善を繰り返し、継続的にナレッジ共有の質を高めていく。
上記を参考に、自社の状況に合わせて適切な効果測定の方法を検討し、ナレッジ共有の活動を効果的に推進してください。
テンプレートを活用してナレッジ共有できるツール

テンプレートを活用してナレッジ共有できるツールには、以下のツールが挙げられます。それぞれについて具体的に解説していきます。
- ナレッジマネジメントツール
- AIチャットボット
- 社内Wiki
- 社内SNS
ナレッジマネジメントツール
業務の効率化を実現するナレッジマネジメントツールは、ナレッジ共有に特化した機能を備えています。複数メンバーが同時に編集でき、タグ付けや全文検索など、情報の整理と検索を簡単にする機能が充実しています。
効果的な活用には、ナレッジ共有推進チームの存在が鍵となります。このチームが中心となり、ツールの使い方や活用事例を社内に広めることで、組織全体でのナレッジ活用が進みます。例えば、月1回の勉強会開催や、部署ごとの活用事例発表など、具体的な取り組みを通じて浸透を図ります。
ナレッジ共有ツールをお探しの方には、DocBASEがおすすめです。DocBaseでは、日報や議事録などのフォーマットをテンプレートとして登録できます。 テンプレートからメモを作成できるので、毎回同じフォーマットでメモを作成する場合に便利です。 また、テンプレートには、日付やユーザー名などの変数を挿入することができます。例えば、日報テンプレートに今日の日にちや自分の名前を自動的に入力することが可能です。
AIチャットボット
AIチャットボットは、ナレッジ共有を革新的に進化させる手法です。社員がチャット形式で質問すると、即座に必要な情報を提供してくれます。
例えば、営業担当者が「新商品の特徴は?」と質問すれば、登録済みの商品情報から最適な回答を提示します。FAQページを探し回る必要がなく、業務時間の短縮につながります。
AIを搭載したチャットボットでは、質問と回答のやり取りを学習データとして活用します。頻出する質問への回答精度が徐々に向上し、より正確な情報提供が可能になります。さらに、利用状況や回答の的確さを数値化できるため、効果測定も容易です。
社内Wiki
社内Wikiは、ブラウザから簡単に情報を更新・共有できるシステムです。部署やプロジェクトごとの専用ページを作成の上、業務に必要な情報を体系的に整理できます。
例えば、新入社員が業務で困った時、Wikiページを参照することで自己解決できます。営業マニュアルや商品仕様書、トラブル対応事例など、必要な情報がすぐに見つかるためです。
Wikiの特徴は、複数メンバーでの編集が可能な点です。誰でも最新情報を追加・更新できるため、ナレッジを常に新鮮な状態に保てます。ただし、情報の正確性を担保するため、編集権限の設定や更新ルールの策定は必須です。
社内SNS
社内SNSは、日常的なコミュニケーションからナレッジ共有にまで活用が可能な便利なツールです。投稿や返信、いいね機能など、普段使いのSNSと同じ感覚で情報共有ができます。
業務上の発見や成功体験を気軽に投稿できるため、個人の持つ暗黙知を形式知に変換しやすいのが特徴です。例えば、顧客対応での工夫点や、業務効率化のヒントなど、日々の気づきを共有できます。
活発なコミュニケーションは、部署を超えた情報共有を促進します。誰かの投稿がきっかけで新たなアイデアが生まれたり、似たような課題を抱える社員同士がつながったりと、組織の知的資産が最大限に活用されます。
エクセルを流用する方法も

インターネット上にはさまざまなナレッジ共有用のエクセルテンプレートが存在し、既存ツールのため導入を検討する人も多いでしょう。しかし、エクセルでのナレッジ共有にはメリットだけでなくデメリットも多く存在します。ここでは、エクセルテンプレート利用におけるメリットとデメリットの両面について解説します。
ナレッジ共有にエクセルを使うメリット

エクセルを活用したナレッジ共有には、導入のしやすさという大きな利点があります。多くの社員が日常的に使用しているため、新たな学習負担がなく、すぐに運用を開始できます。
例えば、顧客対応履歴や営業ノウハウをエクセルで管理する場合、基本的な入力作業から始められます。表計算機能やフィルター機能、ピボットテーブルなど、充実した機能を活用することで、データの分析や可視化も実現できます。
特に小規模なチームや、ナレッジ共有を始めたばかりの組織にとって、エクセルは最適なスタートポイントとなります。追加コストをかけずに情報共有の基盤を整備でき、運用しながら必要な改善点を見出せます。
ナレッジ共有にエクセルを使うデメリット

ナレッジ共有にエクセルを使うデメリットとしては、以下の点が挙げられます。ここではそれぞれについて具体的に解説していきます。
- 複数人で管理することが難しい
- 作り込むと管理やメンテナンスが困難になる
- データ破損やセキュリティリスクがある
複数人で管理することが難しい
エクセルでナレッジを共有する際の課題は、複数人での同時管理が困難な点です。社員それぞれがファイルを編集すると、最新版の特定が難しくなります。
例えば、営業部のAさんが午前中に更新したファイルと、企画部のBさんが午後に編集したファイルが別々に存在する状況が発生します。どちらが最新の正しい情報なのか判断できず、混乱を招くリスクがあります。
同時編集機能がないため、誰かが編集中のファイルを別の人が開いて変更すると、内容が上書きされてしまう可能性もあります。このような問題を防ぐには、編集ルールの策定や、保存場所の一元化など、厳格な運用ルールが必要です。
作り込むと管理やメンテナンスが困難になる
エクセルでナレッジを管理する際の重要な注意点は、過度な作り込みを避けることです。高度な機能を使えば使うほど、管理の手間が増加します。
例えば、マクロや複雑な関数を多用したファイルでは、エラーが発生した際の原因特定に時間がかかります。VBAプログラムの不具合を修正できる担当者が限られる場合、業務に支障をきたす恐れもあります。
また、情報量が増えるにつれて、古いデータの更新漏れや重複登録といった問題も出てきます。2年前の商品情報が更新されないまま残っていたり、同じ内容が複数箇所に記載されていたりすると、正確な情報の把握が困難になります。シンプルな構造で、誰もが更新・管理できる仕組みを目指しましょう。
データ破損やセキュリティリスクがある
エクセルによるナレッジ共有には、データの安全性に関する重大な課題があります。情報量が増加すると、ファイルの破損リスクが高まります。
例えば、3年分の営業データを蓄積したファイルが突然開けなくなる、保存時にエラーが発生して編集内容が消失するといったトラブルが起こり得ます。特に画像データを多く含むファイルは、不安定になりやすい傾向があります。
セキュリティ面でも注意が必要です。エクセルのパスワード保護は、専用ツールで解除される可能性があります。また、USBメモリでの持ち出しや、メール添付での送信も容易なため、機密情報の漏えいリスクも存在します。重要度の高いナレッジを扱う場合は、より安全性の高い専用のナレッジツールを検討すべきです。
ナレッジ共有の成功はツール選びとテンプレート活用にあり!

ナレッジ共有を成功させるには、使いやすいツールと適切なテンプレートの選択が鍵となります。情報共有ツール、ファイル管理ツール、チャットツールなど、さまざまな選択肢がありますが、自社の規模や目的に合わせて必要な機能を見極めることが重要です。
特にチェックしておきたいのは、ツールの直感的な操作性です。どんなに高機能なツールでも、使い方が複雑では現場に定着しません。シンプルでわかりやすい操作感のツールを選び、必要に応じて機能を追加していく方法がおすすめです。
まずは小規模なチームで試験的に導入し、効果を確認しながら全社展開を進めていきましょう。日々の業務効率向上と、組織全体の知識レベル向上を目指して、自社に最適なナレッジ共有の仕組みを構築してください。
DocBaseはナレッジ共有にもご利用いただけます。テンプレートが用意されており、また自前でテンプレートを作成するのも簡単です。テンプレート作成の手順が具体的に紹介されているページもご一読ください(テンプレートを使ってメモを作成 – DocBase)。無料トライアルもご用意していますので、気軽にお試しいただけます。
DocBase におけるテンプレート利用の例
| 利用シーン | 説明 |
| 新入社員向けチェックシート | 必要な項目を事前に設定し、チェックシート作成を効率化。 |
| 企画書作成 | テンプレートを活用して、企画書作成の作業効率を向上。 |
| 自己紹介作成 | 名前、ニックネーム、所属部署、趣味・特技などの項目を事前に設定し、自己紹介作成をスムーズに。 |
| 議事録作成 | テンプレートを使用し、時間を節約して効率的に議事録を作成。 |





