ナレッジベースの作り方と失敗しないためのポイントを解説
最終更新日:2025年1月24日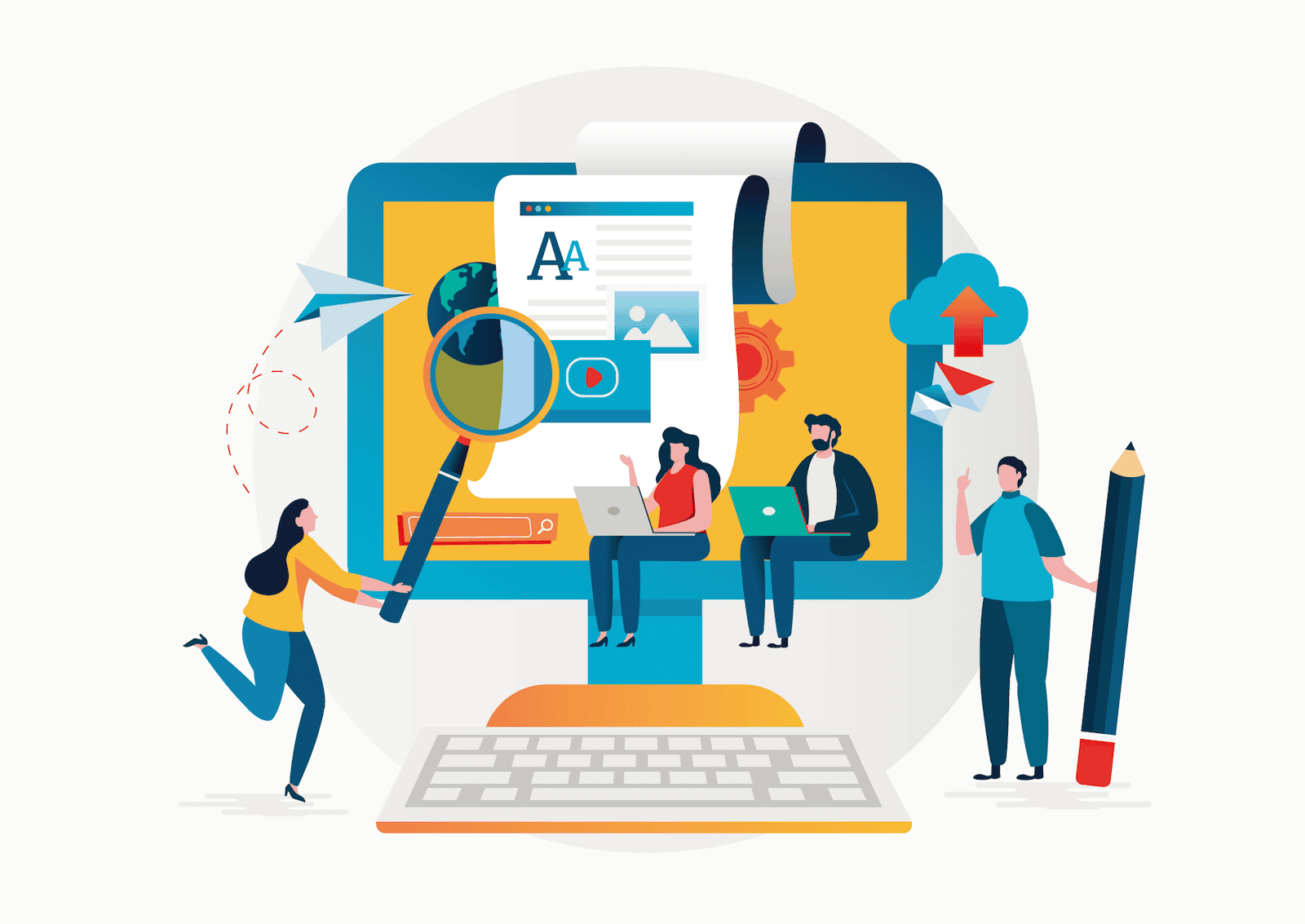
社内の知識やノウハウを効率的に共有したい。でも、どうやってナレッジベースを作ればいいのか分からない。失敗したくない。そんな悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。
この記事では、ナレッジベースの作り方として、既存ツールの活用から専用システムの導入までを具体的に解説します。情報の入力のしやすさ、検索性、セキュリティ対策など、成功のための重要なポイントもお伝えします。
これから新規にナレッジベースを作りたい方はもちろん、既存の仕組みを見直して、新たにナレッジベースを作りたい方にも役立つ内容です。ぜひ最後までお読みください。
【この記事を読んでわかること】
- ナレッジベースとは、業務の経験やノウハウを1か所にまとめたデータベースのこと
- 既存ツールと専用ツールを使用する方法があるが、それぞれメリット・デメリットがある
- 作る際のポイントとして、誰でも使いやすい、検索がしやすいなどのポイントがある
- ツール選びは、種類をよく検討して自社に適したものを選ぶ必要がある
目次
ナレッジベースの概要

ナレッジベースとは、社内の業務経験やノウハウを体系的に整理したデジタルライブラリーです。データベースに蓄積された情報は、社員全員が必要な時に必要な知識にアクセスできる状態で管理されています。
例えば、営業部門で成功した商談のポイントや、カスタマーサポートで解決した問題の対処方法など、日々の業務から得られた知見を一元管理することで、組織全体の知的資産として活用できます。
このデジタル化され、集積された知識は、企業によってはナレッジデータベースと呼ばれることもありますが、本質的な機能は同じです。社内で培われた経験を共有可能な形で保存し、企業の成長を支える基盤となります。
ナレッジベースの作り方

ナレッジベースの作り方は大きく分けて2つあります。
- 既存ツールを活用する
- 専用ツールを導入する
それぞれの方法について詳しく解説していきます。
既存ツールを活用する
業務で日常的に使用しているExcelやWordを活用して、手軽にナレッジベースを構築できます。ExcelやWordは多くの社員が操作に慣れているため、新しいスキルを習得する必要がありません。
情報を整理したファイルをクラウドストレージに保存することで、オフィスはもちろん、出張先やテレワーク中でもインターネット経由でアクセス可能です。共有設定を適切に行えば、部署や権限に応じた情報アクセスの管理も実現できます。
社内の知識を共有するために、追加の投資をせずに始められる点がメリットです。ExcelやWordなどの既存のツールを活用することで、コストを抑えながらナレッジ共有の第一歩を踏み出せます。
専用ツールを導入する
ナレッジマネジメントツールは、企業の知識共有を効率化するために開発された専用システムです。情報の登録から検索、共有設定まで、必要な機能が最初から組み込まれています。
例えば、キーワード検索や関連情報の自動リンク機能により、必要な情報へのアクセスが容易になります。また、アクセス権限の細かな設定や、更新履歴の管理など、情報セキュリティにも配慮した機能を備えています。
導入時には専門家のサポートを受けられることも多く、効果的なナレッジベースの構築をスムーズに進められます。
【作り方別】ナレッジベース構築におけるメリット・デメリット

ナレッジベースを構築する際、その作り方によってメリットとデメリットがあります。
- 既存ツールで構築するメリット・デメリット
- 専用ツールで構築するメリット・デメリット
それぞれのメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。
既存ツールで構築するメリット・デメリット
既存ツールでナレッジベースを構築する際の最大のメリットは、追加コストが発生しない点です。ExcelやWordは社員が日常的に使用しているため、新たな操作研修も不要です。
しかし、データベースの設計から共有範囲の設定まで、全てを自分たちで構築する必要があります。この作業には多大な時間と労力が必要です。また、情報量が増えると検索に時間がかかり、編集履歴の管理も煩雑になります。
特に大規模な組織では、検索性の低さや更新管理の難しさから、長期的には業務効率の低下を招く可能性があります。
専用ツールで構築するメリット・デメリット
専用ツールには、効率的な情報管理機能が標準搭載されています。キーワード検索やタグ付け、カテゴリ分類など、情報へのアクセスを容易にする機能により、社員は必要な知識を素早く見つけ出せます。
導入時には費用が発生しますが、運用サポートを受けられる点は大きな利点です。システムの不具合や使用方法の質問に対して、専門家からの支援を得られます。
長期的な視点では、業務効率の向上や知識共有の促進により、投資に見合う効果が期待できます。組織の規模が大きく、安定した運用を重視する場合は、専用ツールの導入が有効な選択肢となります。
ナレッジベースを作る際のポイント
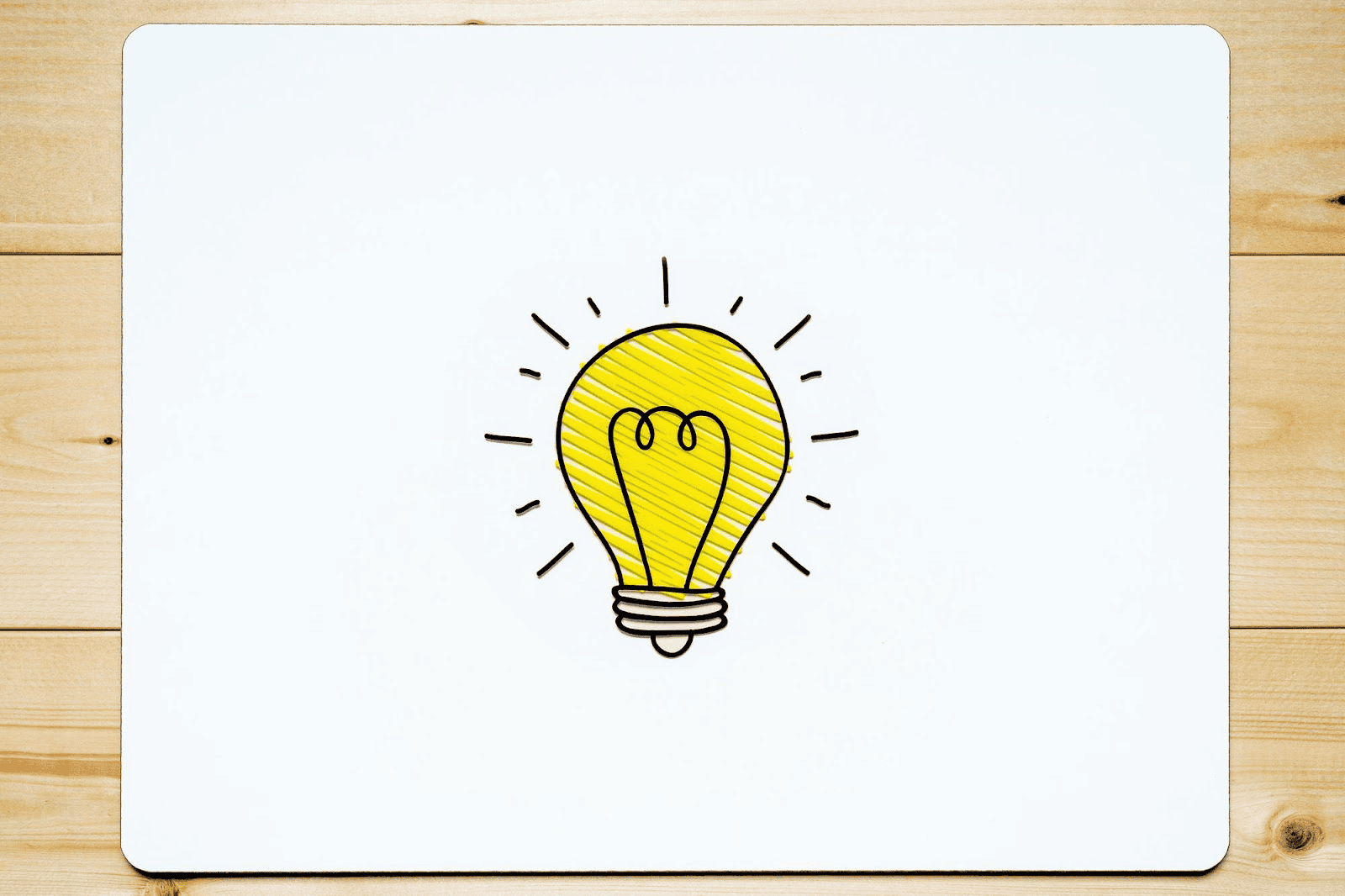
有益なナレッジベースを作る際には、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
- 誰でも使いやすいようにする
- 検索のしやすさを重要視する
- 管理しやすいツールにする
- マルチデバイス対応ツールにする
- セキュリティ対策に考慮して作る
- 小さくスタートして育てる
- 部門を横断して利用できるようにする
それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
誰でも使いやすいようにする
社内のナレッジベースは、全従業員が日常的に活用できることが重要です。システム管理者から一般社員まで、誰もが直感的に操作が可能な仕組みを整えましょう。
具体的には、マウス操作だけで情報を登録可能な画面設計や、ボタンの配置を工夫することで、ITスキルに自信のない社員でも簡単に情報を共有できます。情報共有のハードルを下げることで、より多くの社員が積極的にナレッジを蓄積し、組織全体の知識が豊かになっていきます。
またFAQページの作成も、専門知識不要で作成できるような使いやすいナレッジマネジメントツールを選びましょう。
検索のしやすさを重要視する
ナレッジベースの価値は、必要な情報に素早くアクセスできる点にあります。キーワード入力で瞬時に結果が表示される、関連情報が自動的に提案されるなど、検索機能の充実度がナレッジマネジメントツール選びの決め手となります。
特に専用ツールを導入する場合は、実際の業務シーンを想定した検索テストを行い、社員が目的の情報にたどり着けるか確認しましょう。
検索性能の高いナレッジマネジメントツールを選ぶことで、社員の情報アクセスが活発になり、ナレッジベースの活用度が向上します。
管理しやすいナレッジマネジメントツールにする
ナレッジベースの運用の成否を左右するのは、情報の更新頻度です。よって、管理者が情報を簡単に追加・更新できる仕組みが必要不可欠です。
例えば、更新作業が3クリック以内で完了する、一括更新が可能、承認フローがシンプルなど、管理者の負担を軽減する機能を重視しましょう。管理が煩雑だと情報更新が滞り、古い情報が残り続けることになります。
ナレッジマネジメントツールの選定時には必ず管理画面を確認し、日常的な運用がスムーズに行えるか検証することをお勧めします。
マルチデバイス対応ツールにする
働き方が多様化している昨今では、場所を選ばず情報にアクセスできることが重要です。PCはもちろん、スマートフォンやタブレットでも快適に閲覧可能なナレッジベースを構築しましょう。
営業担当者が商談先で製品情報を確認したり、在宅勤務中の社員がマニュアルを参照したりと、さまざまな場面で活用できます。レスポンシブデザインに対応しているナレッジマネジメントツールであれば、画面サイズに応じて最適化された状態でコンテンツが表示されます。
いつでもどこでもナレッジベースにアクセスできる環境が、社員の情報共有を促進します。
セキュリティ対策に考慮して作る
クラウド型のナレッジベースでは、情報セキュリティの確保が最重要課題です。顧客データや社内機密情報を扱うため、堅固なセキュリティ体制が求められます。
具体的には、以下のような多層的なセキュリティ対策を講じます。
- データセンターの物理的セキュリティ
- 通信の暗号化(例:TLS/SSL)
- 保存データの暗号化(例:AES-256)
- 役割ベースでのアクセス権限設定
- 多要素認証(MFA)の導入
- 操作ログの取得
これらの対策を組み合わせることで、より強固なセキュリティ体制を構築できます。サーバーの監視体制や障害対策も重要なポイントです。
ベンダーを選定する際には、セキュリティ認証の取得状況や過去のインシデント対応実績も確認することをお勧めします。
小さくスタートして育てる
完璧なナレッジベースは、一朝一夕には作れません。まずは小規模なプロジェクトチームで試験運用を始め、徐々に規模を拡大する方法が効果的です。
■試験運用のプロセス例
| ステップ | 内容 | 詳細 |
| 1. 目的と範囲設定 | 試用運用の目的と対象範囲を定める | 何を検証するか、どの部署で利用するかを具体的に決定。人数、機能を絞る。 |
| 2. チーム編成と役割 | 担当メンバーと役割を決定 | 情報システム部門、利用部署代表、ナレッジマネジメント担当者など。各メンバーの責任範囲を明確にする。 |
| 3. コンテンツ選定 | 試用運用で利用するコンテンツを選定 | 優先度の高い情報、よく参照される情報を優先。FAQ、手順書など形式を統一。最初から質にこだわりすぎず、まずは情報網羅を優先。 |
| 4. 初期設定 | ツール設定とアカウント発行 | ツール基本設定(権限、カテゴリなど)。利用者のアカウントを発行し、利用方法を説明。 |
| 5. 試用運用開始 | 実際に利用を開始し、フィードバックを収集 | 積極的に利用を促し、アンケートやコメント機能でフィードバック収集。ログを分析し、利用状況や課題を把握。 |
| 6. 課題特定と改善 | 課題を分析し、改善策を実施 | ツールの使いやすさ、コンテンツの不足、検索性の問題などを分析。改善策を検討し、ツール設定、コンテンツを修正。 |
| 7. 効果測定と評価 | 試用運用の効果を測定し、本格運用への移行を判断 | 問い合わせ件数の減少、業務効率の向上などを測定。試用運用で得られた結果を評価し、本格運用に移行するか、改善が必要か判断。 |
| 8. 本格運用準備 | 本格運用に向けて準備 | 運用ルール(コンテンツ作成・更新、権限管理など)を策定。全社向け教育研修を実施。 |
補足:
- チーム内での積極的なコミュニケーションを図る。
- 得られた知見は文書化し、本格運用へ活かす。
初期段階では情報量が限られますが、日々の業務で得られる知見を着実に蓄積していくことで、価値のある情報資産に成長していきます。将来の拡張性を考慮し、機能追加やユーザー数の増加に対応したナレッジマネジメントツールを選びましょう。段階的な展開により、運用上の課題を早期に発見し、改善することができます。
なお、スモールスタートのポイントとしては以下が挙げられます。
- 小さく始める: 最初から大規模な運用を目指さず、少人数で小さな範囲から始める。
- シンプルな機能から: 複雑な機能は後回しにし、基本的な機能に絞って運用する。
- 完璧を求めない: 最初から完璧なナレッジベースを目指すのではなく、運用しながら改善していく。
- 利用者の意見を重視: 利用者のフィードバックを積極的に収集し、改善に活かす。
- 効果測定を忘れずに: 定期的に効果を測定し、改善を繰り返す。
部門を横断して利用できるようにする
組織の知識は、部門の壁を超えて共有することでその本当の価値を生み出します。営業部門の顧客ニーズ、開発部門の技術情報、サポート部門の対応事例など、異なる視点の情報を統合することにより、新たな発見や気づきをもたらします。
各部門が持つ専門知識を共有し、相互にフィードバックできる仕組みを整えましょう。部門間のコミュニケーションを促進し、企業全体の知的資産を豊かにしていきます。
部門横断的な情報共有が、イノベーションの源泉となります。
ナレッジベース作りに利用できるツール・システムの種類

ナレッジベース作りで利用できるツールやシステムは複数存在します。それぞれにタイプや特徴、得意分野が異なります。
ナレッジベースの種類と特徴
| 種類 | 特徴 | メリット |
| データベース型 | 情報を体系的に整理・検索 | 必要な情報を即座に検索可能、意思決定に活用 |
| ヘルプデスク型 | 問い合わせ対応の効率化 | FAQを中心とした迅速な対応、サポート品質向上 |
| グループウェア型 | コミュニケーションからナレッジ蓄積 | 情報共有と知識蓄積を同時実現、業務進捗の可視化 |
| 社内Wiki型 | 社員が自由に情報投稿・編集 | 社員による知識共有促進、新入社員教育、自己解決力向上 |
| データマイニングツール型 | 情報分析による新たな価値発見 | 傾向分析、関連情報提案、効果的なナレッジ管理 |
ここではそれぞれのタイプについて、詳しく解説していきます。
データベース型|ナレッジ蓄積・共有ができる
データベース型ナレッジベースは、情報を体系的に整理し、即座に検索できる構造を持つシステムです。社内の経験やノウハウを保存し、必要な時にすぐに引き出せる仕組みを提供します。
企業の意思決定に役立つ情報を蓄積できる点が特徴です。例えば、過去の案件対応履歴や成功事例を蓄積することで、経営戦略の立案や業務改善などに役立ちます。
シンプルな構造ながら、検索機能により必要な情報に素早くアクセスできるため、日常業務での活用がしやすいツールです。
ヘルプデスク型|返答効率の向上に特化している
問い合わせ対応の効率化に特化したヘルプデスク型ナレッジベースは、FAQを中心とした情報管理システムです。頻出する質問と回答をデータベース化し、迅速な対応を実現します。
AIチャットボットによる自動応答機能を備えたものや、オペレーターが効率的に回答を検索できる仕組みを持つものまで、用途に応じて選択が可能です。
問い合わせ対応の負担を軽減し、サポート品質の向上と標準化を実現できます。
グループウェア型|コミュニケーションからナレッジに蓄積する
グループウェア型ナレッジベースは、社内コミュニケーションを通じて自然に知識が蓄積されるプラットフォームです。チャットやメッセージ機能を中心に、スケジュール管理やファイル共有も一元化できます。
日々の業務上のやり取りや課題解決のプロセスが自動的に記録され、後から参照可能な知識として残ります。カレンダーや掲示板機能と連携することで、業務の進捗も可視化されます。
グループウェア型ナレッジベースは、リアルタイムの情報共有と知識の蓄積を同時に実現できる実用的なツールです。
社内wiki型|社内ナレッジを自由に共有できる
社内Wiki型ナレッジベースは、全社員が自由に情報を投稿・編集できる掲示板のようなシステムです。業務マニュアルから社内FAQ、ベストプラクティスまで、幅広い情報を体系的に整理する場合におすすめです。
社員が自発的に知識を共有し、互いの経験から学び合える環境を構築できます。特に新入社員の教育や、部署間の知識共有に効果を発揮します。
情報を探す手間を省き、社員の自己解決力を高めることで、問い合わせ対応の工数削減にもつながります。
データマイニングツール型|情報の蓄積だけでなく分析もできる
データマイニングツール型ナレッジベースは、蓄積された情報から新たな価値を見出すシステムです。AIによる自動分析機能により、頻出キーワードの傾向や情報同士の関連性を発見できます。
例えば、よく検索されるトピックを特定して重点的に情報を充実させたり、関連する参考資料を自動的に提案したりすることが可能です。
データに基づく客観的な分析により、より効果的なナレッジ管理を実現できます。
ナレッジベースを作るなら既存ツールと専用ツールどちらが良い?

ナレッジベースの成功は、情報の更新しやすさと検索のしやすさにかかっています。専用ナレッジマネジメントツールは、これらの機能があらかじめ整備されているため、スムーズな運用が可能です。
情報の入力や更新が煩雑だと、せっかくの知識も陳腐化してしまいます。また、必要な情報にすぐにアクセスできなければ、社員の利用意欲が低下します。
業務フローに合わせて活用できる、使いやすいツールを選ぶことで、持続的なナレッジ共有が実現されます。
ナレッジベースの作り方を理解して、個々の知識を自社の資産にしよう

ナレッジベースの成功は、「使いやすさ」「検索性」「管理のしやすさ」の3つの要素にかかっています。情報共有ツールやファイル管理ツール、チャットツールなど、さまざまな選択肢がありますが、単一機能に特化したツールでは、長期的な運用で機能不足に陥る可能性があります。
重要なのは、自社の業務フローや組織規模に合わせて、必要な機能を過不足なく備えたナレッジマネジメントツールを選ぶことです。また、直感的な操作性を重視することで、社員全員が積極的に活用できる環境を整えられます。
DocBaseは機能が豊富なため、ナレッジベースを作る際の多様なニーズに合わせた使い方が可能です。無料トライアルを用意していますので、ぜひお試しください。
ナレッジベースを作る際に役立つDocBaseの特徴と機能
| 特徴 | 機能 | 説明 |
| 誰でも使える、爆速で書ける | マークダウン & リッチテキスト & ハイブリッドエディター | デジタルツールに不慣れな人でも簡単にナレッジを記述できます。マークダウンとリッチテキストを同時に使用可能です。 |
| マークダウン入力補助機能 | マークダウンの記法を知らなくても、ボタン操作で簡単に整形された文章を作成できます。 | |
| マニュアル作成をワンストップで | 画像のペイントモード | 画像編集ソフトを使わずに、DocBase上で画像に矢印、テキスト、モザイクなどを加えられます。 |
| マニュアルや手順書の作成がスムーズになります。 | ||
| みんなでメモを作りあげる | 強力な同時編集機能 | 複数人で同時に1つのメモを編集可能。 |
| 作業負担の分散、情報の取りこぼし防止、議事録作成、アイデア出しに役立ちます。 | ||
| 情報を簡単に再利用 | 差し込み機能 | ワンクリックで他のメモを参照し、内容を自分のメモに埋め込むことができます。 |
| 既存のナレッジを簡単に再利用し、効率的にドキュメントを作成できます。 | ||
| 柔軟な公開範囲設定 | グループ機能 | メモの公開範囲をグループ単位で限定できます。 |
| 特定グループへの公開、全社公開など柔軟に設定可能。メモは複数のグループに所属可能です。 | ||
| 豊富な検索機能 | キーワード・グループ・タグ検索 | 多様な条件でメモを検索できます。 |
| 添付ファイル内検索 | PDFやExcelなどの添付ファイル内も検索対象です。 | |
| テンプレート機能 | テンプレート登録 | 日報や議事録など、頻繁に作成するドキュメントのフォーマットをテンプレートとして登録できます。 |
| テンプレート利用で時間と手間を節約できます。 | ||
| 外部への共有 | 外部共有機能 | チーム以外の人にもメモを共有できます。 |
| パスワード設定 | パスワード設定でセキュリティを確保できます。 | |
| マルチデバイス対応 | スマートフォン・タブレット対応 | 外出先でもメモの閲覧・編集が可能です。 |
| 堅牢なセキュリティ | ISO 27001(ISMS)認証取得 | 情報セキュリティマネジメントシステムを確立しています。 |
| シングルサインオン & 2段階認証 | セキュリティ強化のための機能を提供しています。 | |
| 不正アクセス検知・防止、通信・データの暗号化 | 強固なセキュリティ対策が実装されています。 | |
| その他 | 編集履歴、既読メンバーの表示、チャットサービス連携 | ナレッジベース管理をより効率的に行うための機能が用意されています。 |





