古いナレッジマネジメントの特徴と問題点|刷新するための方法を解説
最終更新日:2025年1月24日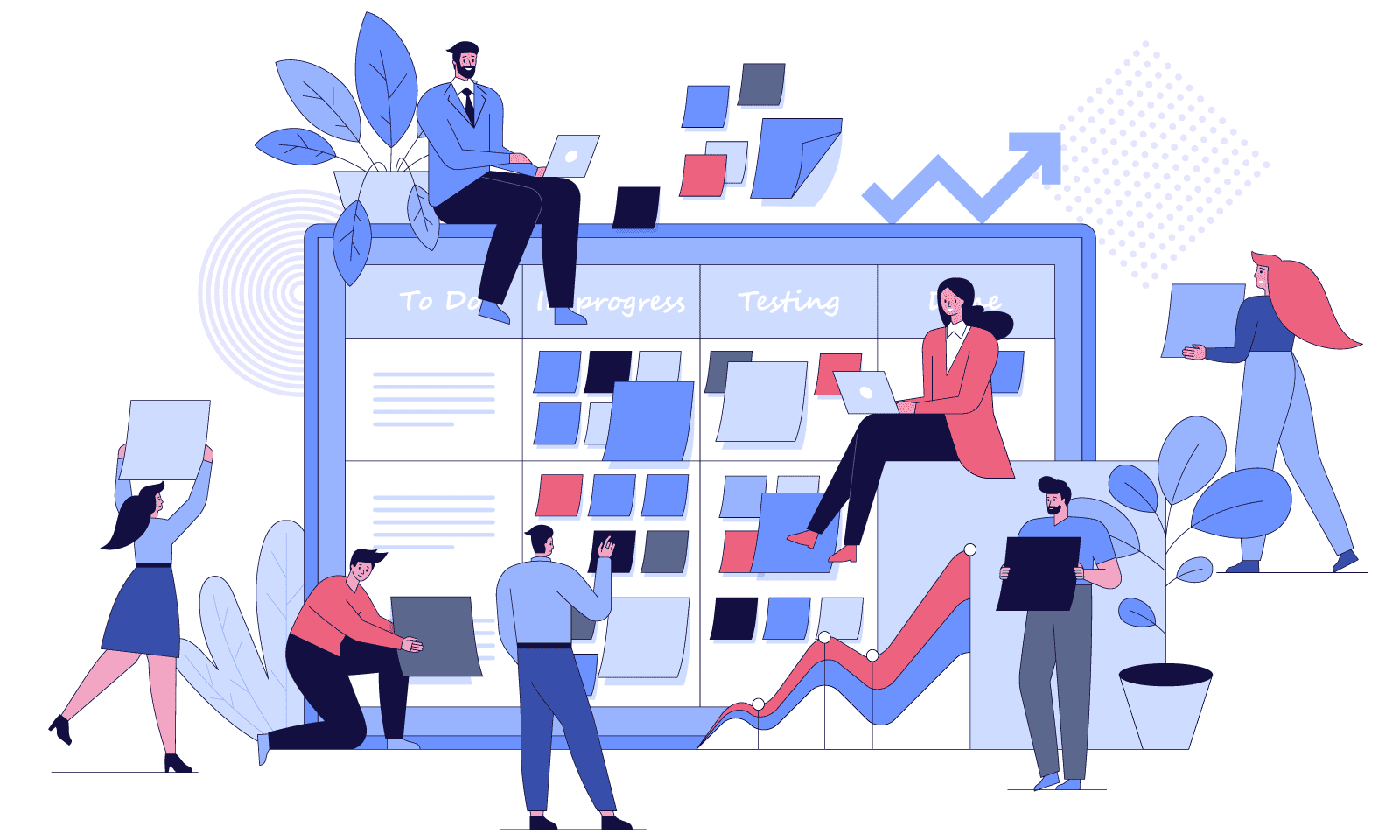
紙の資料やExcelファイルによる従来型のナレッジマネジメントでは、ビジネススピードが加速する現代の企業競争に対応できません。多くの企業で情報検索に時間を要し、部門間の知識共有が滞り、さらには情報セキュリティの課題も抱えています。
本記事では、古いナレッジマネジメントが抱える問題点を具体的に解説し、最新のテクノロジーを活用した効果的な刷新方法をご紹介します。組織の成長を加速させる新しいナレッジマネジメントの構築に向けて、まずは現状の課題を把握していきましょう。
【この記事を読んでわかること】
●ナレッジマネジメントの蓄積で、業務の属人化防止や人材育成ができるようになる
●ナレッジマネジメントツールは、精査しなければ適切な活用ができない
●ナレッジの蓄積手法として、知識資産やSECIモデルなどがある
目次
ナレッジマネジメントとは何を行うこと?

企業の成長を加速させる重要な取り組みとして、ナレッジマネジメントがあります。ナレッジマネジメントとは、社員一人一人が持つ業務上の知識やスキルを、組織全体で共有・活用する仕組みを指します。
ナレッジマネジメントで重要なのは、ベテラン社員が長年の経験で培った業務のコツや判断基準といった「暗黙知」を、誰もが理解できる「形式知」に変換することです。例えば、顧客対応における判断基準や、トラブル対応時のポイントなど、言葉では表現されていない知識を、具体的な手順やガイドラインとして文書化することです。
ナレッジマネジメントを怠ると、重要な業務知識が特定の社員に依存する「属人化」が進み、組織の業務効率が低下します。さらに、社員の退職時に貴重なノウハウが失われるリスクも高まります。企業が持続的に成長するためには、戦略的なナレッジマネジメントの構築が不可欠なのです。
新しいナレッジマネジメントを行う必要性

企業を取り巻く環境が大きく変容する中、従来型のナレッジマネジメントは機能不全に陥っています。これまでの日本企業では、終身雇用を前提とした長期的な人材育成により、自然発生的に知識やノウハウが継承されてきました。
しかし、雇用形態の多様化により、従来の育成方法は実現困難になっています。正社員、契約社員、パート社員など、さまざまな雇用形態が混在する現代では、体系的な知識共有の仕組みが不可欠です。
さらに、デジタル化やグローバル化により、ビジネス環境は日々、変化しています。競争力を維持するには、組織全体で新しい知識を素早く取り入れ、イノベーションを生み出す必要があります。
このような状況下では、従来の属人的な知識継承ではなく、組織全体で戦略的にナレッジを共有・活用できるナレッジマネジメントの仕組みの構築が急務となっています。古いナレッジマネジメントの限界を認識し、現代のビジネス環境に適応した新しいナレッジマネジメントへの移行が求められています。
古いナレッジマネジメント5つの特徴と問題点

古い体制のナレッジマネジメントには5つの特徴があります。
- 紙媒体でナレッジマネジメントを行っている
- 検索性が劣るシステムを使用している
- 部門ごとにナレッジマネジメントを行っている
- 担当者を決めずに運用している
- アクセス権限を細かく設定できないツールを使用している
これらに当てはまるナレッジマネジメントを行っている場合、刷新していく意識を持った方が良いでしょう。古いナレッジマネジメントの5つの特徴について、それぞれを詳しく解説していきます。
紙媒体でナレッジマネジメントを行っている
多くの企業で今なお紙媒体でのナレッジマネジメントが続いていますが、このアナログな方法では現代のビジネススピードに追いつけません。
例えば、営業部門で顧客対応のノウハウを紙のファイルで保管している場合、必要な情報を見つけ出すまでに平均15分以上を要します。さらに、ファイリングキャビネットやデスクの引き出しに分散して保管された書類は、探す手間だけでなく、紛失のリスクも抱えています。
最も深刻な問題は、必要なタイミングで情報にアクセスできないことです。商談中に過去の成功事例を参照したい場合や、クレーム対応で即座に過去の対処方法を確認したい場合などに、スピーディーな情報活用ができません。
この状況では、せっかく蓄積したナレッジが実務で活用されず、形骸化したナレッジマネジメントに陥ってしまいます。デジタル時代における企業競争力の維持には、紙媒体からの脱却が不可欠です。
検索性が劣るシステムを使用している
ナレッジマネジメントの真の目的は、情報の蓄積ではなく、その活用にあります。しかし、多くの企業で導入されているナレッジマネジメントのシステムは、検索機能が不十分なため、貴重な知識が眠ったままになっています。
具体的な問題として、データベースに「営業提案」と入力されている情報を「営業プレゼン」というキーワードで検索しても、該当する情報が表示されないといった例が挙げられます。また、検索結果が多すぎて必要な情報の特定に時間がかかるなど、実務での即時活用を妨げる要因となっています。
このような検索性の低さは、社員のナレッジ活用における意欲を低下させ、結果として「情報はあるのに見つけられない」「結局、一から作り直した方が早い」という非効率な状況を生み出します。
企業の競争力向上には、AIによる関連検索や、タグ付けによる多角的な検索など、現代のテクノロジーを活用した検索機能の実装が不可欠です。情報を「持っている」だけでなく、「使える」状態にすることが、ナレッジマネジメント成功の鍵となります。
部門ごとにナレッジマネジメントを行っている
現在も多くの企業で部門ごとにナレッジマネジメントを行っていますが、この方法では企業価値の最大化を実現できません。製品開発から販売、アフターサービスまで、ビジネスの成功には部門を越えた連携が不可欠だからです。
例えば、製造部門が保有する製品不具合についての情報は、営業部門の提案力向上や、開発部門の製品改良に直結する可能性があります。また、カスタマーサービス部門が把握している顧客の声は、マーケティング部門の戦略立案に重要な示唆を与えるかもしれません。
しかし、部門別のナレッジマネジメントでは、このような価値ある情報の横展開が妨げられています。結果として、各部門が似たような課題解決に個別に時間を費やしたり、他部門の成功事例を生かせなかったりする非効率が生じています。
企業全体の競争力強化には、部門の壁を超えた統合的なナレッジマネジメントが必要です。異なる視点や知識の組み合わせから、新たなビジネス機会や革新的なソリューションが生まれる可能性が広がるのです。
担当者を決めずに運用している
ナレッジマネジメントを「誰かがやっているだろう」と放置している企業が少なくありません。明確な責任者を置かずにナレッジマネジメントを運用することで、貴重な企業資産を有効活用できない事態を招いています。
具体例を挙げると、社員それぞれが思い思いに情報を登録することで、同じような内容が複数箇所に散在したり、古い情報が更新されないまま残されたりする状況が発生します。また、情報の分類方法も統一されず、必要な知識へのアクセスが困難になっています。
さらに深刻なのは、ナレッジマネジメントの質を評価・改善する機会が失われることです。現状の運用が企業にとって効果的なのか、より良い方法はないのか、という検証が行われないまま、非効率な状態が継続してしまいます。
これらの課題を解決するには、ナレッジマネジメントを主導する専任担当者の設置が不可欠です。担当者には、情報の整理・更新ルールの策定から、活用促進の施策立案、さらには運用状況の定期的な評価まで、一貫した責任を持たせることが重要です。
アクセス権限を細かく設定できないツールを使用している
多くの企業で利用されている基本的なファイル共有ツールやスプレッドシートでは、きめ細かなアクセス権限設定ができません。この制限は、企業のナレッジマネジメントに重大な問題を引き起こしています。
例えば、人事評価に関する情報や、新製品開発の機密情報など、アクセスを制限すべき重要データが、全社員に閲覧可能な状態で保管されているケースがあります。また、取引先との守秘義務が課された情報についても、適切なアクセス制御ができないため、情報漏えいのリスクにさらされています。
ナレッジは現代企業における最重要資産の1つです。部署別、職位別、プロジェクト別など、多層的なアクセス権限の設定ができないツールでは、資産となるナレッジを安全に管理することは困難です。
企業の競争力と信頼性を維持するには、アクセス権限が柔軟に設定できる専門的なナレッジマネジメントツールの導入が不可欠です。情報セキュリティと業務効率の両立を実現することで、安全かつ効果的なナレッジマネジメントが可能になります。
注目の最新ナレッジマネジメント手法

現在、ナレッジマネジメントでは以下のキーワードが注目されています。
- 知識資産
- SECIモデル
- 場(ba)
これらについて具体的に解説していきます。
知識資産
企業の競争力を高めるナレッジマネジメントでは、4種類の知識資産を適切に管理することが重要です。
第一に、業務マニュアルや規程など、組織内で日常的に使用される「恒常的知識資産」があります。第二に、ベテラン社員の対応ノウハウや過去の成功事例といった「経験的知識資産」が存在します。第三に、企業理念や行動指針などの「概念的知識資産」、第四に、業務手順書やチェックリストなどの「体系的知識資産」があります。
これらの知識資産を企業の重要な経営資源として位置づけ、計画的に継承する仕組みを構築することが不可欠です。例えば、毎月の部門会議で知識共有の時間を設定したり、四半期ごとにナレッジの棚卸しを行ったりするような具体的な施策が効果的です。
この継承の仕組みを確立できない企業では、貴重な知識資産が失われ、業務効率の低下や競争力の喪失につながります。
SECIモデル
効果的なナレッジマネジメントを実現するには、SECIモデルという4段階のプロセスが重要です。このモデルを実践することで、個人の持つ知識を組織全体の力へと転換できます。
第一段階の「共同化」では、営業同行やOJTを通じて、ベテラン社員の経験則や判断基準を若手社員が習得します。第二段階の「表出化」では、その経験則をマニュアルや報告書として文書化します。第三段階の「結合化」では、文書化された知識を分析・整理し、より実践的な業務ノウハウへと昇華させます。最終段階の「内面化」では、この実践的ノウハウを社員一人一人が習得し、自分の知識として定着させます。
このサイクルを継続的に実施することで、個人の知識は組織の知的資産となり、さらに新たな知識が生まれる好循環が生まれます。組織の持続的な成長には、このSECIモデルの確実な実践が不可欠です。
場(ba)
ナレッジマネジメントの成功には、知識が生まれ、育つ「場」の存在が不可欠です。この「場」とは、単なる物理的な空間ではなく、知識の創造・共有・活用が活発に行われる接点を指します。
具体的には、定例会議室での部門間ミーティング、オープンスペースでの即席ディスカッション、社内ポータルサイトでの情報交換など、多様な形態があります。これらの「場」では、断片的な情報が文脈と結びつき、実践的な知識へと進化していきます。
特に重要なのは、この「場」を意図的にデザインすることです。例えば、部署の壁を取り払ったオープンオフィス化や、部門横断プロジェクトの定期開催、使いやすい社内SNSの導入など、具体的な施策が必要です。
効果的な「場」のデザインにより、組織内の知識創造が活性化され、企業の競争力向上につながります。
古いナレッジマネジメントを刷新させるポイント

古いナレッジマネジメントを刷新するためには、以下の方法を取り入れていくのがお勧めです。
- ナレッジマネジメントを推進できる環境を整える
- 専用ツールの導入を検討する
- 自社に適したシステムやツールを導入する
これらについて具体的に解説していきます。
ナレッジマネジメントを推進できる環境を整える
ナレッジマネジメントの成功には、明確な目的設定と実行体制の構築が不可欠です。多くの企業が情報収集だけに注力し、その後の活用方法を具体化できていないという課題を抱えています。
まず必要なのは、企業目標達成に必要な情報を明確にすることです。例えば、営業部門では成約事例や商談ノウハウ、製造部門では不具合対応事例や改善提案といった具体的な収集対象を定めます。
次に、専任担当者の配置が重要です。担当者は情報収集の仕組み構築から、収集した情報の整理・分類、さらには全社への活用促進まで一貫して推進します。
加えて、ナレッジ共有を評価する人事制度の導入も効果的です。情報提供者への評価ポイント付与や、優秀事例の表彰制度などにより、組織全体での取り組みを活性化できます。
専用ツールの導入を検討する
ExcelやWordによるナレッジマネジメントでは、現代のビジネス環境で求められる迅速な情報活用が困難です。これらのツールでデータベースを構築すると、情報登録や必要な情報の検索に時間を要するなど、業務効率を低下させる要因になりかねません。
一方、専用ツールには画期的な機能が搭載されています。AIを活用した関連キーワード検索により、探している情報に数秒でアクセスできます。また、タグ付け機能やカテゴリ分類により、複数の視点から情報を整理・活用できます。
さらに、収集したデータの分析機能も充実しています。例えば、よく参照される情報の傾向分析や、部門間での情報共有状況の可視化など、ナレッジマネジメントの効果測定も容易です。
競争力のある組織づくりには、ナレッジマネジメントの専用ツールの導入が不可欠と言えます。
自社に適したシステムやツールを導入する
ナレッジマネジメントの成功には専用システムが必要ですが、機能過多なシステムの導入は逆効果となります。実際に、高機能システムを導入したものの、使いこなせずに活用率が低いままに留まるケースも見られます。
システム選択で重視すべきは、自社の目的達成に直結する機能です。例えば、営業力強化が目的なら、商談事例の検索機能や顧客対応ノウハウの共有機能を重視します。製品開発が焦点なら、技術情報のデータベース機能や部門間連携機能を優先します。
また、システムの導入は段階的に行うことが賢明です。まずは基本機能から始め、利用状況を見ながら機能を追加していく方法が、組織への定着を促進します。
重要なのは、システムの機能数ではなく、実際の業務における活用度合いなのです。
新しいナレッジマネジメントを実現させるシステムの選定ポイント7選

新しいナレッジマネジメントを実現させるには、以下のシステム選定のポイントを押さえることが大切です。
- 利用社員が求めるナレッジを収集・提供できる
- 誰でも直感的に使いやすい
- マルチデバイスに対応している
- スモールスタートできる
- カスタマイズし続けられる
- 自社にとって適切なコストで運用できる
- 強固なセキュリティ対策を施せる
これらについて具体的に解説していきます。
利用社員が求めるナレッジを収集・提供できる
ナレッジマネジメントシステムの成功は、利用者が必要とする情報を適切に提供できるかどうかにかかっています。例えば、営業部門では過去の商談事例や成約ノウハウ、製造部門では不具合対応や改善事例など、部門特有の情報ニーズが存在します。
また、情報量が増加すると、必要な情報を素早く見つけ出すことが課題となります。最新のシステムでは、AIが利用者の役割や過去の検索履歴から、関連性の高い情報を自動的に提示する機能を搭載しています。
さらに、情報の整理方法も重要です。部門別、製品別、顧客別など、多角的な分類方法を採用することで、さまざまな切り口からの情報検索を可能にします。
ナレッジマネジメントシステム選定では、こうした利用者視点の機能が実装されているかを重視すべきです。
誰でも直感的に使いやすい
ナレッジマネジメントシステムの成功には、直感的な操作性が不可欠です。機能が豊富でも操作が複雑なシステムは、導入後短期間で利用率が大きく低下する懸念があります。
理想的なシステムとは、新入社員でも短時間で基本操作が習得できる、直感的なインターフェースを備えたものです。日々の業務で迷うことなくスムーズに活用できます。例えば、情報入力は3クリック以内、検索結果は10秒以内に表示、ファイル添付はドラッグ&ドロップで完了するといった具合です。
システム選定時には、無料トライアル期間を活用し、実際の利用者による使用感評価を実施することが重要です。評価項目には、操作手順の分かりやすさ、レスポンスの速さ、画面レイアウトの見やすさなどを含めます。
使いやすさを重視したシステム選びが、継続的な活用を実現する鍵となります。
マルチデバイスに対応している
現代のビジネスでは、オフィス以外での情報アクセスが不可欠です。実際、営業担当者の業務時間の多くが社外となる場合もあり、スマートフォンやタブレットでのナレッジ活用が業務効率を大きく左右します。
効果的なナレッジマネジメントシステムでは、商談直後の議事録入力、移動時間中の事例検索、顧客先での提案資料の即時閲覧など、場所を選ばない情報活用が可能です。画面サイズに応じた最適化表示により、スマートフォンでも必要な情報を素早く確認できます。
特に重要なのは、デバイス間でのデータ同期です。オフィスのPCで作成した資料をスマートフォンで閲覧し、タブレットで編集するといった、シームレスな情報活用が実現できます。
モバイル対応の充実度が、ナレッジマネジメントの活用度を大きく向上させます。
スモールスタートできる
ナレッジマネジメントシステムの導入は、全社一斉ではなく、段階的に進めることが成功への近道です。全社一斉に導入した場合、システムトラブルや運用混乱により、プロジェクトが早期に停滞する可能性があります。
効果的な導入方法は、まず20人程度の小規模チームでパイロット運用を開始することです。この段階で、情報の分類方法、入力ルール、検索手順など、具体的な運用ノウハウを確立します。また、よくある質問や問題解決手順をマニュアル化し、次の展開に備えます。
パイロット運用で得られた成功事例や改善点を基に、部門単位で段階的に展開していきます。各段階での課題を確実に解決しながら進めることで、システムの定着率を高められます。
急がば回れの精神で、着実な導入を目指すことが重要です。
カスタマイズし続けられる
ビジネス環境の変化に対応するには、ナレッジマネジメントシステムも進化し続ける必要があります。特にクラウド型のナレッジマネジメントシステムは、初期投資を抑えながら、組織の成長に合わせた柔軟な拡張が可能です。
具体的なカスタマイズ例として、利用部門の追加、情報カテゴリーの細分化、検索機能の強化などが挙げられます。例えば、営業部門での成功を受けて開発部門へ展開する際も、データ容量や機能を段階的に拡張できます。
また、月額制のサービスでは、利用人数や機能を柔軟に調整可能です。50名での運用開始後、成果を確認しながら100人、200人と段階的に拡大できます。システムの使用状況に応じて、必要な機能だけを追加することも可能です。
将来の発展性を見据え、カスタマイズ性の高いナレッジマネジメントシステムを選択することが、長期的な成功につながります。
自社にとって適切なコストで運用できる
ナレッジマネジメントシステムの運用コストは、企業の成長戦略と密接に関連します。多くの場合、利用人数に応じた従量課金制を採用しています。
コスト設計では、現在の社員数だけでなく、将来の組織変更も考慮が必要です。例えば、今後3年間で社員数が1.5倍になる成長計画がある場合、増員時の追加コストを事前に試算しておくことが重要です。
また、機能面でも段階的な投資が可能なプランを選択すべきです。基本機能のみの利用から始め、活用度に応じて高度な分析機能や外部連携機能を追加できる柔軟な料金体系が理想的です。
投資対効果を見極めながら、持続可能なコスト設計を実現することが、長期的な成功への鍵となります。
強固なセキュリティ対策を施せる
ナレッジマネジメントシステムには、企業の競争力に直結する機密情報が蓄積されます。実際に、情報漏えい事件の中には、ナレッジマネジメントシステムの不適切な利用に起因するケースも見られ、セキュリティ対策は最重要課題です。
堅牢なシステムには、以下のような機能が実装されています。まず、利用者認証における多要素認証の採用。次に、アクセス権限の階層管理により、部門や役職に応じた情報アクセスの制限が可能です。さらに、データの暗号化やアクセスログの詳細記録により、不正利用の防止と追跡を実現します。
ナレッジマネジメントにおけるセキュリティ機能
| セキュリティ機能 | 説明 | 目的 |
| 認証・認可 | ||
| 多要素認証(MFA) | IDとパスワードに加え、スマホアプリや生体認証などの複数の認証要素を組み合わせることで、不正アクセスを防止します。 | アカウント乗っ取りなどによる不正ログインを防止し、システムへのアクセスを厳格化します。 |
| シングルサインオン(SSO) | 1つのIDとパスワードで複数のシステムにログインできるようにすることで、ユーザビリティを向上させつつ、アカウント管理の負担を軽減します。 | ユーザーの利便性を高めつつ、アカウント管理の一元化によりセキュリティリスクを低減します。 |
| アクセス権限の階層管理 | ユーザーの役職や部門に応じて、アクセスできる情報を制限します。不要な情報へのアクセスを制限することで、情報漏えいリスクを低減します。 | 内部関係者による不正アクセスや、誤操作による情報漏えいを防止します。 |
| データ保護 | ||
| データの暗号化(保存時・転送時) | データを暗号化することで、万が一データが漏洩した場合でも、内容を解読されるリスクを低減します。保存時だけでなく、データ転送時にも暗号化を行うことで、より強固なセキュリティを確保します。 | 情報漏えい時の被害を最小限に抑え、機密情報を守ります。 |
| データバックアップ | 定期的にデータをバックアップすることで、システム障害やデータ損失が発生した場合でも、迅速にデータを復旧させられます。バックアップデータの暗号化も重要です。 | システム障害や人為的なミスによるデータ損失を防止し、事業継続性を確保します。 |
| 監視・監査 | ||
| アクセスログの記録と監視 | ユーザーのアクセス状況、操作履歴を詳細に記録することで、不正利用や不審な動きを検知しやすくなります。ログを定期的に監視することで、早期に異常を検知し、対応できます。 | 不正アクセスや情報漏えい発生時の原因究明を迅速化し、再発防止に繋げます。 |
| セキュリティ監査 | システムのセキュリティ状態を定期的に監査することで、脆弱性を早期に発見し、対策を講じます。第三者機関による監査も有効です。 | セキュリティ上の弱点を洗い出し、情報漏えいリスクを事前に低減します。 |
| その他の機能 | ||
| IPアドレス制限 | 特定のIPアドレスからのアクセスのみ許可することで、外部からの不正アクセスを制限します。 | 外部からの不正アクセスを防止し、システムを保護します。 |
| ソフトウェアの脆弱性対策 | 常に最新のセキュリティパッチを適用し、ソフトウェアの脆弱性を解消します。定期的なアップデートはセキュリティ維持に不可欠です。 | システムの脆弱性を突いた攻撃を防ぎ、セキュリティレベルを維持します。 |
| WAF (Web Application Firewall) | Webアプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃から保護します。SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティングなどの攻撃を検知し、防御します。 | Webアプリケーションの脆弱性を突いた攻撃からシステムを保護します。 |
注意が必要なのは、無料のナレッジマネジメントシステムです。これらは便利な反面、セキュリティ基準が不明確で、重要情報の管理には適しません。
企業の知的資産を守るため、セキュリティ機能の充実度を重視したナレッジマネジメントシステム選定が不可欠です。
古いナレッジマネジメントを刷新し、個々の知識を自社の資産にしよう

ナレッジマネジメントは、企業の競争力強化に不可欠な要素ですが、その重要性を踏まえつつも、常に最新のトレンドを考慮し、効果的に実施していくことが重要です。ナレッジマネジメントツールは、「情報共有ツール」「ファイル管理ツール」「チャットツール」など種類が豊富ですが、それぞれの用途に特化したツールを導入すると、運用中に機能不足に陥るリスクがあります。自社に必要な機能を過不足なく備えたツールを選定することが、効果的なナレッジマネジメントを実現する鍵となります。
特に、誰でも直感的に操作できるシンプルなツールであれば、社内浸透をスムーズに進められます。DocBaseは豊富な機能を備えているため、多様なニーズに合わせて柔軟に活用できます。例えば、情報共有、ファイル管理、チャットツールといった個別のツールの機能をDocBaseでカバーすることも可能です。まずは無料トライアルでDocBaseの使いやすさと機能性を体感してみましょう。
ナレッジマネジメントにおけるDocBaseの特徴と機能
| 特徴 | 機能 | 概要 |
| 誰でも使える、爆速で書ける | ハイブリッドエディター | Markdownとリッチテキストを同時に使えるため、誰でも簡単に記述可能 |
| シンプルなUI | ツールの使い方を学習する時間を短縮 | |
| 情報共有の促進 | 柔軟な公開範囲設定 | グループ機能でメモの公開範囲を柔軟に設定 |
| 強力な同時編集機能 | 複数人での同時編集で負担軽減と情報共有を促進 | |
| 情報の再利用(差し込み機能) | ワンクリックで他のメモを参照し、効率的なドキュメント作成 | |
| コメント機能 | Markdown記法対応のコメント機能 | |
| グッジョブ機能 | ワンクリックで感謝を表現 | |
| メンション通知 | 特定のメンバーに通知を送信 | |
| ナレッジの蓄積と検索 | 豊富な検索機能 | キーワード、グループ、タグ、添付ファイル内も検索可能 |
| タグ機能 | タグ付けによる整理、編集、統合 | |
| スター機能 | 重要なメモへのアクセスを容易に | |
| 業務効率化 | テンプレート機能 | 定型フォーマットを登録 |
| チャットサービス連携 | 必要な情報を選択してリアルタイム通知 | |
| マルチデバイス対応 | スマートフォン、タブレットでも閲覧・編集可能 | |
| セキュリティ対策 | シングルサインオン | SAML2.0対応のIDプロバイダーを利用可能 |
| 2段階認証 | 外部アプリによる2段階認証 | |
| アクセス制限 | IPアドレスによるアクセス制限 | |
| 外部公開の制限 | チーム全体のメモ共有機能を制限 | |
| 通信の暗号化 | SSL(TLS)対応 | |
| データの暗号化 | メモや個人情報は暗号化して保存 | |
| 操作履歴 | メンバーの操作履歴をCSV形式でダウンロード |





